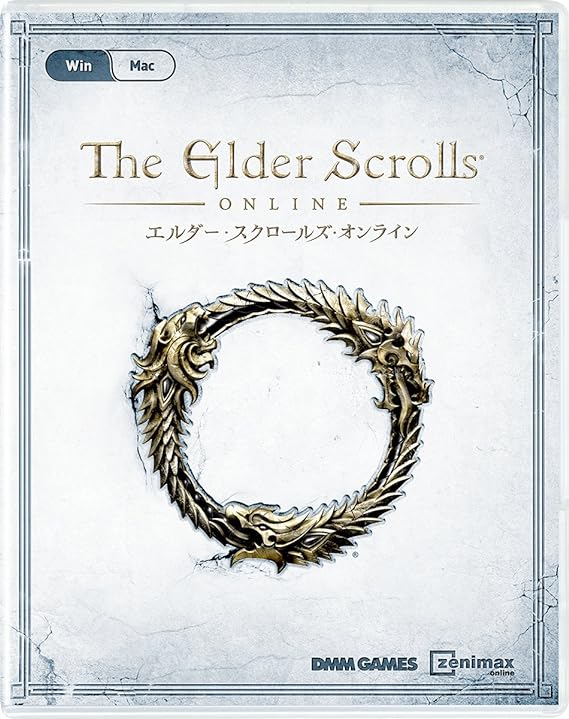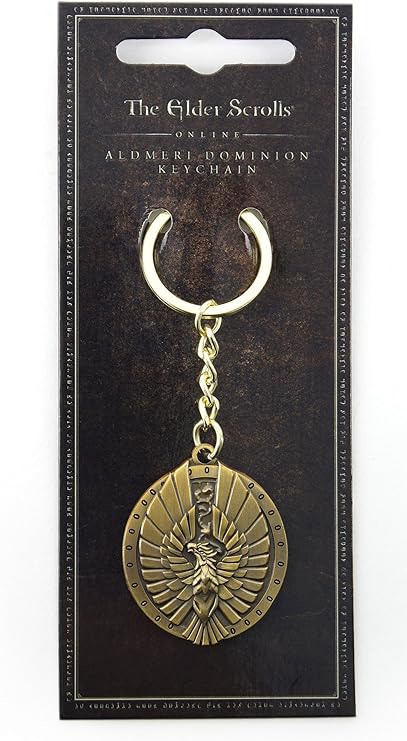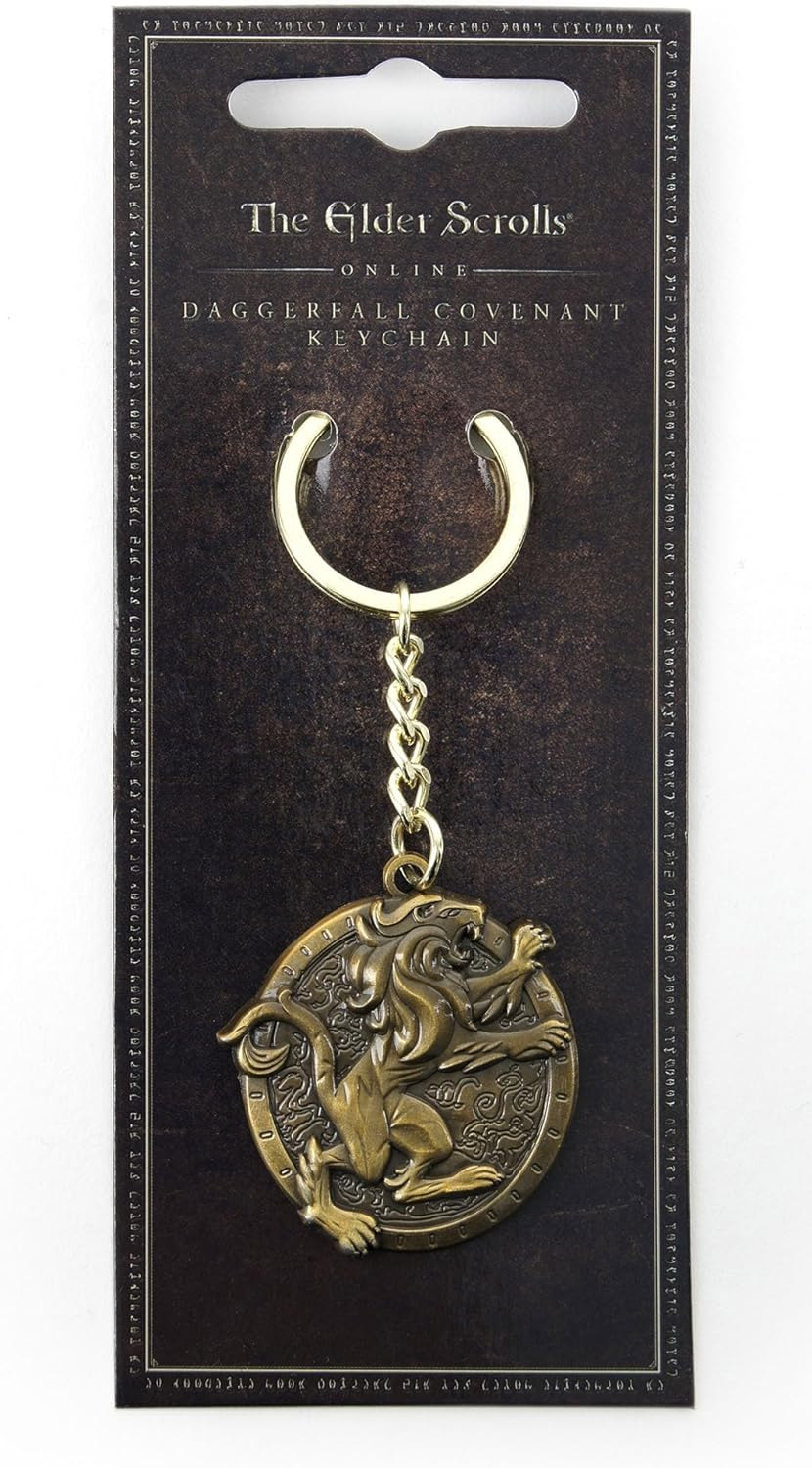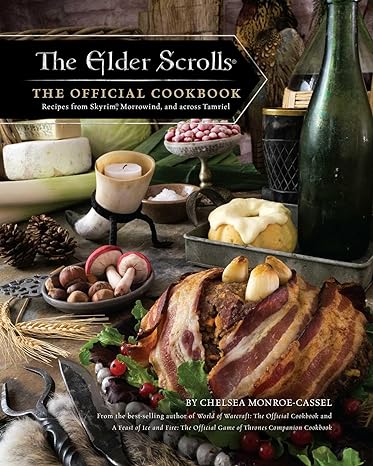ウーズ:ある寓話The Ooze: A Fable
これはヴァレンウッドに棲むウッドエルフの子供たちが、幼いころから聞かされる物語である。
かつて、この世界のものには形がありませんでした。大地の様子は定まらず、木々は硬い幹や枝や樹皮を育まず、エルフたち自身の姿も絶えず移ろい、一つにとどまらなかったのです。この渾沌が、「ウーズ」と呼ばれました。
ところが、イフレがウーズを取って命じました。イフレはまず、「緑」について語ります。「緑」とは、森とそこに生い茂る全ての植物を指します。イフレは「緑」に思い通りの形をとる力を与えました。なぜなら、それがイフレの語る最初の物語だったからです。
エルフは、イフレが語った2つめの物語でした。イフレが物語を紡ぐのに合わせ、エルフは今の姿になりました。イフレは彼らに物語を語る力を与えましたが、自分自身や「緑」の姿を変えようとしてはならないと戒めました。森の姿を変え、森を破壊することは禁じられたのです。
そのかわり、イフレはウッドエルフたちを「緑」に委ねました。雨露をしのぐ住まいと安全な道は、「緑」に頼めば与えてくれるのです。そして、彼らが尊ぶ気持ちを忘れないかぎり、「緑」は言うことを聞いてくれるのです。これを、「グリーンパクト」と呼びます。
最後に、イフレは大地を歩く生き物と川を泳ぐ生き物と空を飛ぶ生き物全てについて語りました。イフレはそれらを、生きる糧としてウッドエルフに与えたのです。彼らは植物をいっさい食べず、肉だけを食べることになりました。イフレはまた、ウッドエルフに殺されたウッドエルフは土に還ることが許されず、他の生きもの同様、食糧として消費されなければならないとも言いました。これが、「ミート・マンデイト」と呼ばれるものです。
物語が語られるたび、イフレはそれらが満足のいく形をなすよう取り計らいました。けれども、ウーズのなかにはウーズのままでいるものもありました。そこでイフレは最後の物語を語り、そうしたウーズにも目的を与えました。
「緑」の姿を変えたり「緑」を損なったりしてグリーンパクトに背いたウッドエルフは、罰として形を持たないウーズに戻されるようになりました。彼らの名前はイフレが語る物語から消され、沈黙に置き換わるのです。
ウッドエルフの間で、「緑」に愛された者はウーズに囚われた罪人を解き放つ力を持つと言われています。もっとも、そうやって解放された者たちがどこに向かい、どんな形を取るかは知られていません。
ウーズを見たことがある者は誰もいません。そこに囚われた人々の声を聞いた者もいなければ、彼ら罪人たちをこの業罰から救うことができる者に会った者もいないのです。でも、ウーズを「ただの物語」だと思うかどうかウッドエルフに尋ねれば、決まって次のような答えが返ってくるでしょう。「”ただの物語”なんてものは存在しない」と。
ウッドエルフのグルメガイド、第1章The Wood Elf Gourmet, Ch. 1
ウッドエルフなら誰しも、内側の部位ほど美味だということを知っている。他の種族は肉を調理するにしても、血が蒸発してぱさぱさになるまで火を入れるし、内臓や脳味噌は捨ててしまうが、ウッドエルフはそういった部分こそ最もジューシーで、したがって最も風味豊かであることを知っているのである。
次に紹介するのは、ヴァレンウッドのグリーンシェイド地方に伝わる名物料理である。
鹿肉の壺詰め
指で触れて柔らかくなるまで腰臀部を吊るす(5日間)。
腰臀部を中火で加熱する。その際、油を塗ると外側をカリカリにできる。肉がぱちぱち言い始めたら、火からおろす。
熱々の肉を甕か壺に入れ、出し汁とタマネギのみじん切りを加えてふたをし、そのまま2週間寝かせる。
食卓に出すときは壺の蓋を開け、肉を出し汁と一緒にそのまま皿に盛る。とても柔らかいので、ナイフで切り分ける必要はない。
この料理は4人家族がお腹を満たせる量だし、数日獲物を仕留められずにいた猟師1人を満足させるだけの量がある。
こういった名物料理は他にもたくさんあり、親から子へと伝えられるケースも少なくない。
ウッドハース:ポケットガイドWoodhearth: A Pocket Guide
ファリネスティが姿を見せなくなってから、ウッドハース以上にウッドエルフの性格と歴史を余すところなく示している都市はない。
ヴァレンウッドの南西岸に位置するウッドハースは、もともとは帝国の入植地であり、最初はつつましい街だった。その地域に点在するウッドエルフの集落との交易を促進する目的で時の皇帝が建設し、歴代の皇帝が維持してきたのである。
にぎわう港町であると同時にヴァレンウッドの自然の脅威から人々を守る砦でもあったウッドハースに対する近在のウッドエルフの反応は、好奇心と友好的態度、それに敵意が入り交ったものだった。
敵愾心の強いボズマーが防壁に攻撃を仕掛けてきたことも一度や二度ではない。その内の何度かは、強力な破壊魔法を集中的に浴びせることで、防壁の一部を崩落させることに成功している。もっとも、せっかく防壁を破壊しても、帝国軍の粘り強さと優れた装備の前に、結局は撃退されてしまうのが常だった。
やがて、ヴァレンウッドのグリーンパクト・ボズマーの間でついに和平が結ばれる。すると、ほどなくしてボズマーの集落が出現し、帝国の建築物の数を上回るようにさえなった。ウッドエルフが自分たちの住む森との間に結んでいるあの特別な関係の賜物として、ボズマーの集落の特徴である木の家や歩道が生まれたのである。
ボズマーが帝国を助ける勢力になったことで、ウッドハースの統治は徐々にウッドエルフ自身に任せられるようになって行く。樹の従士が置かれ、インペリアルの建設した区画こそさびれはしたが、全体としてウッドハースの街は栄えた。
それから一世代の内に、ウッドハースの樹の従士の評価は高まった。揺るぎない指導力を発揮し公正な裁きを行うという評価が、ウッドエルフのみならずその同盟者たちの間にも定着したのである。
この原稿を書いている現在、ウッドハースの樹の従士はファリエルであり、彼女は樹の従士としてのみならず、創設間もないアルドメリ・ドミニオンのアイレン女王の元、サルモールのメンバーとしても統治を行っている。海辺の聖域と共にヴァレンウッドの主要港の地位を保つウッドハースは、今やありとあらゆる種族が住む、種族のるつぼと言っても過言ではない。
クランマザー・アニッシの言葉パート1Words of Clan Mother Ahnissi, Pt. 1
クランマザー・アニッシから愛する娘達への言葉
パート1
アニッシは教えよう。あなたはもはや子猫ではないし、アニッシに隠しごとをすることも覚えた。だからアニッシは話そう。
初めは、オーナールとファドマイというつがいがいた。様々な局面が過ぎ、ファドマイはオーナールに、「結婚して子供を作り幸せを分かち合おう」と言った。
そして彼らの間に最初の猫、アルコシュが生まれた。オーナールは「アルコシュよ、時間を与えよう。猫のように素早く、ときにはゆっくり動くものは何だ?」と言った。
それから風のケナーシが生まれた。「ケナーシよ、お前に空を与えよう。何が風より高く飛ぶのだ?」
そして猫の目のマグルスが生まれた。「マグルスよ、お前に太陽を与えよう。何が猫の目より明るく輝くのだ?」
そして母猫のマーラが生まれた。「マーラよ、お前は愛である。何が母の愛より優るのだ?」
そして子猫のスレンダルが生まれた。「スレンダルよ、お前に慈悲を与えよう。慈悲なくしてどうしたら子猫は生き延びれるのだ?」
様々なことが起こり、オーナールとファドマイは幸せだった。
オーナールが、「もっと子供を作って幸福を分かち合うべきだ」と言った。それにファドマイも賛成した。そしてハーモーラーが生まれた。その後、ハーシーン、マールンズ、マファラ、サンジーン、シェッゴロス、他にもたくさんの子供が生まれた。
ファドマイはこう言った:
「ハーモーラーよ、お前は潮汐です。月が潮の流れを予測できるのか、それとも潮の流れが月を予測するのか、誰に分かりましょう?」
「ハーシーンよ、お前は腹を空かせた猫です。腹を空かせた猫より上手に狩りをするものは何ですか?」
「マールンズよ、お前はジャ・カジートです。子猫より破壊的なものは何ですか?」
「マファラよ。お前は一族の母です。一族の母のやり方より明かされないものは何ですか?」
「サンジーンよ、お前はスクゥーマの猫です。スクゥーマの猫より正気でないものは何ですか?」
そしてオーナールは「子供は2人で十分だ。子供が多すぎると幸せを奪われてしまう」と言った。
しかし、ケナーシはファドマイのところへ行き、「母よ、ケナーシは兄弟のアルコシュでさえも飛べないほど高い所に飛んでしまえるので寂しいです」と言った。ファドマイはケナーシを可哀そうに思い、オーナールを騙して再び身籠った。
ファドマイは月とその動きを生み出した。次に魔法の砂と豊富な森のニルニ、そして黄昏と暁のアズラーを生んだ。
最初から、ニルニとアズラーは母親の愛を奪い合った。
オーナールはファドマイが出産しているとき彼女を捕まえた。オーナールは怒った。オーナールはファドマイを打ちつけ、彼女は最後の子供を生むために深い闇の奥へと逃げた。子供たちはこの出来事を聞き、母を父の怒りから守るためにやって来た。
そしてファドマイは、最後の子供ローカジュを深い闇の中で生んだ。ローカジュの心は深い闇でいっぱいだった。ローカジュが生まれると、深い闇はその名前を知った。それがナミイラであった。
クランマザー・アニッシの言葉パート2Words of Clan Mother Ahnissi, Pt. 2
クランマザー・アニッシから愛する娘達への言葉
パート2
ファドマイは自分の死期が近いことを悟り、こう言った:
「ジャ・カージェイよ、お前にラティスを与えよう。月の側面よりしっかりとしたものは何ですか?お前の止まることのない動きは我々をオーナールの怒りから守るでしょう」そして、月は天より出てしかるべき場所に着いた。オーナールの怒りが轟き渡り深い闇は揺れたが、彼はラティスを渡ることはできなかった。
「ニルニよ、お前に素晴らしいものを残しましょう。ファドマイが今日まで子供を授かったように、お前もたくさんお子宝に恵まれるだろう」アズラーには何もないことが分かると、ニルニは笑った。
アズラーを除いてファドマイの子供たちは全員去った。ファドマイは「私のお気に入りの娘よ、お前に最も素晴らしいものをあげよう。ファドマイはお前に秘密を残します」と言って、娘に3つの事を話した。
ファドマイは「ニルニに子供がたくさんできたら、1人選んで変化させなさい。機敏で賢く、美しくし、カジートと呼ぶのです」と言った。
「カジートは最高の登り手でなければいけません。マッサーとセクンダが落ちても、ケナーシの息吹を登って月を彼らの道に戻さなくてはなりませんから」
さらに「カジートは最高の詐欺師でなければいけません。いつもオーナールの子供たちに自分の性質を隠さなくてはなりませんから」
「カジートは最高の生存者でなければいけません。ニルニが嫉妬して、砂をザラザラにし森を激しいものにし、常にニルニとの戦いで飢えるからです」
このような言葉を残してファドマイは息を引き取った。
様々な局面が過ぎ、ニルニがローカジュのもとにやって来てこう言った。「ローカジュよ、ファドマイは私にたくさん子供を生めと言いましたが、そんな場所はありません」
ローカジュは「ローカジュが子供たちのために場所を作り、お前はそこで子供を生める」と言った。しかしローカジュの心は深い闇でいっぱいだった。ローカジュは姉妹を欺き、2人はニルニとともにこの新しい地へ行くしかなかった。ファドマイの子供の多くは逃げ、星になった。ファドマイの子供の多くはニルニの歩みを安定させるために亡くなった。そして生き残った者は残り、ローカジュを罰した。
ファドマイの子供たちはローカジュの心を引き出し、ニルニの内側奥深くに隠した。彼らは「騒がしいローカジュよ、我々はお前を呪う。色々な段階をニルニと歩むように」と言った。
しかしニルニは子供を作るため、すぐにローカジュを許した。彼女は子供たちで満たされたが、お気に入りの子供、森の精は自分の姿が分からなかったので泣いた。
アズラーが来て「哀れなニルニよ、泣くのを止めなさい。アズラーからお前のために新しい子供を送ろう」ニルニは泣き止み、アズラーは月への第1の秘密を話した。2人は分かれて、アズラーを通した。アズラーは人間と野獣の狭間で悩んでいた森の精を、最高の砂漠と森へ連れて行った。アズラーはその見識で数多くの形に彼らを変えた。全ての目的に合う1つの姿にした。アズラーは彼らをカジートと名づけ第2の秘密を話し、秘密の価値を教えた。そしてアズラーはニルニの秘密の護衛者にふさわしいよう、新しいカジートを月のラティスと結びつけた。それから第3の秘密を話した。月は沼地を照らし、その光は砂糖になった。
しかしワイファーは第1の秘密の話を聞き、アズラーの後ろについて忍び込んだ。ワイファーは秘密について理解できず、アズラーの罠のことをニルニに話した。ニルニは砂漠を熱し、砂は燃えるようにジリジリした。それから森を濡らし猛毒で満たした。ニルニはワイファーに感謝し、森の精を変えさせた。ワイファーにはアズラーの巧妙な知恵はなかったので、森の精をエルフにし、2度と野獣にならないようにした。彼らをボズマーと名づけた。そのときから、彼らはもはやカジートとは同じ子供ではなくなった。
そしてワイファーは秘密の価値を理解していなかったので、息を引き取るまで第1の秘密を大声で触れまわり、ファドマイの子供たちは全員ラティスを渡れた。しかしアズラーは賢く、オーナールとローカジュの耳を塞いで、その言葉が聞こえないようにした。
グリーンパクト・ボズマーが見る幻視Visions of the Green Pact Bosmer
以下はモルヴァス・アンドリスによる4巻からなるグリーンパクト・ボズマーの研究書からの抜粋である。この研究は第一紀に3年間続けられたが、モルヴァス・アンドリスがとある弔い合戦で命を落とし、研究していたクランに貪り食われたことで途絶した。
…ファニリエルは齢100歳にして沼地の発光ガエルを食べ、上下が逆さまの樹木都市、ハートグリーンの幻影を見た。そこには逆立ちをして両手で歩くエルフたちが住んでいたという…
…「窃盗の権利」後の請求に成功した回数が200回を超える怪盗ヴァニリオンは、かつて森の真ん中に現れた木に登り、幻視を見たと言われている。
その木は葉が紫色で、ヴァニリオン自身の言葉によれば、そうした紫色の葉に囲まれて座っていると、得も言われぬかぐわしい匂いがしたという。その甘い香りを嗅いでいるうちに、ヴァニリオンは心が穏やかになり、一種陶然とした境地に入った。樹木が環状に茂る森が見えたのは、その時である。森に足を踏み入れたヴァニリオンだが、奥へと進むにつれて樹木の環は広がり、いつまでたっても森の中央にたどりつけない。
そうやって森の中をさまよううちに、ヴァニリオンはそれまでに見たこともないほど美しい霊魂に出会う。その霊魂は話す時、文章が堂々巡りをするよう、本来最後に来るべき言葉をあえて頭に置いた。「横になりましょう。おいでなさい。川のほとりで一緒に」
木の葉の強力な芳香によって恍惚境に陥っていたヴァニリオンは、枝から落ちてようやく我に返った。命に別状はなかったが、落下の衝撃で片脚を折ってしまい、盗賊家業は廃業した。ヴァニリオンはその後の人生を、葉が紫色の木を探すことに費やしたが、ついに見つけることはできなかった。
私は樹の従士に尋ねて見たことがある。パクト・ボズマーはそうした幻視を「見る」と言うが、「思い浮かべる」と表現するほうが適切ではないかと。というのも、こうした奇妙な幻影に登場する都市や森やその他の驚くべき事象が、ニルンにもオブリビオンにも実在しないことは明らかだからだ。
その樹の従士は、何やら当時流行りの発酵牛乳らしき臭い飲みものを長々とあおると、自分の足元を見つめ、それから空を見上げておもむろに答えた。「世界は自分の目で見える範囲で終わっているとあなたがたは言う。我々は違う。自分の目で見える範囲を超えたところから、世界は始まるのだ」
グリーンパクトとドミニオンThe Green Pact and the Dominion
木々が太陽に向かって伸びるように、また、月が出ている夜は出ていない夜と違う鳥たちのさえずりが聞こえるように、ヴァレンウッド生まれのウッドエルフならば誰しも(そして、ヴァレンウッド生まれでないエルフのほとんど全てが)グリーンパクトについて知っている。
グリーンパクトとは我々ウッドエルフが、大いなる物語の始まりから我々を導き、生き方を教えてくれているイフレと交わした約束である。
グリーンパクトの定めは明快だ。森を傷つけてはならない。植物由来のものは一切口にしてはならない。食べるのは肉だけにせよ。敵を征服したときには、骸が土に還るに任せず、その肉を食らうべし。無駄な殺生はこれを禁ずる。汝らウッドエルフの姿は神聖なものゆえ、獣の姿をとってはならない。
これがグリーンパクトである。この協約を守る見返りに、森——我々は「緑」と呼ぶが——は充分な食べものと雨露をしのぐ住まいを提供してくれる。森が、我々の要請に応じて自ら姿を変えてくれるのである。これは、イフレが我々ウッドエルフだけにくれた特別な贈り物だ。おかげで、我々は満ち足りた暮らしを送ってきた。
ところが今、我々は未曽有の状況に置かれている。我々の新しい盟友たち、すなわちハイエルフとカジートは、グリーンパクトを守ろうとしない。彼らは草葉と木材でこしらえた家に住み、ありとあらゆる種類の果実を食べ、ブドウから造ったワインを飲む。敵を貪り食うなど、彼らから見れば野蛮人の所業以外の何ものでもないのだ。
こういった盟友たちを、ヴァレンウッドのウッドエルフはどのように受け入れたらよいだろうか?それも、グリーンパクトを遵守しつつ、だ。これは今日多くのエルフを悩ませている問題であり、とりわけ、新たに建設されたばかりの街マーブルクに住むエルフたちの困惑は深い。我々は「緑」に対する冒涜の度合いで言えば、もっと些細な事柄をめぐって戦争をしたこともある。
一方、ドミニオン成立当時、グリーンレディとシルヴェナールがウッドエルフの利益とグリーンパクトの精神を代弁してくれたことを我々は知っている。そして今、サルモールにはウッドハースの樹の従士にして我々の力強い代弁者であるファリエルがいることを、我々は忘れてはいないのだ。
彼らはこの不確かな時代に我々が模範とすべき指導者たちだ。彼らは自らの振る舞いを通して、我々にたどるべき道を示してくれている。我々は新しい盟友たちを、ウッドエルフならではの歓待で迎え入れるべきだ。彼らに喧嘩を吹っかけてはならない。彼らから盗みを働くような真似は、慎むべきだろう(彼らの多くは「窃盗の権利」というものを正しく理解していないのだが、それはまた別の機会に論ずる)。しかし同時に、我々は自分たちの利益、そして「緑」の利益を守るためにはっきりものを言うことを、ためらうべきではない。
樹の従士たるファリエルが力強い弁舌をふるってくれたおかげで、マーブルクで使う木材の多くと草葉の全ては他からヴァレンウッドに運び込まれた。一方、街を建設する場所を作るためにおびただしい数の樹木が切り倒されなければならなかったという事実は、多くのウッドエルフにとって許しがたいことだ。ただ、ファリエルの見るところ、新たな盟友たちを受け入れることは、ヴァレンウッドを破壊するに違いない連中に対する強力な防備を構築するための第一歩なのである。
我々の意見に進んで耳を傾けようというアイレン女王の姿勢は、彼女が優れた知性の持ち主であることと、彼女がウッドエルフの民に敬意を抱いていることを示している。であれば、我々は女王の指導力を積極的に信頼することで、彼女の厚意に報いるべきであろう。
さまよえる王の伝説The Wilderking Legend
——作者不詳の口承文学を聞き書きしたもの——
歌え、ヴァレンウッド。叫べ、「緑」よ
動く者、形を与える者の物語を語れ
その名はさまよえる王
彼の目は世界に向かって突き出し
知覚するもの全てに触れる
彼は思考によって、形を与える
果たして彼はどこにいるのか
山だろうか
森だろうか
否。そこに彼はいない
なぜなら、「そこ」とは場所であり、場所には際限がある
さまよえる王に際限はない
彼は宮廷にして玉座
彼は宮廷にして玉座
彼が歩めば、踏み出した足は自身の上に落ちる
彼の足音と地響きを、誰が聞かずにいられるだろう?
彼の到来とともに大地は震える
地下から彼のホロウがせりあがる
さざ波一つない水面の儚い静けさが
極小の石つぶてで粉々に砕けるごとく
さまよえる王が通り過ぎる時、恐るべき力が伝わる
叫べ、ブランブルブリーチよ!むせび泣くがいい、影の守人よ!
さまよえる王は味方にして敵
敵にして味方なり
彼の足音を、誰が記録にとどめられるだろう?
彼が口を開いて歌う時
誰がその旋律を耳にできるだろう?
ネレイドの贈り物Gifts of the Nereids
幼い時、私は両親に連れられ、司祭たちがネレイドを崇める洞窟を訪ねた。両親は我が子もいつか司祭になれるかもしれないと、私をその聖堂に捧げたのだった。
その聖堂には、私の他に3人しか子供がいなかった。10歳になるまで、私はその3人にからかわれ続けたが、それは私の片脚がもう一方より短く、短いほうの脚を引きずって歩いていたからだ。
ある日、私たち4人は洞窟の中を走り回っていた(こうした行為は禁じられていたが、司祭たちは子供が子供らしく振る舞うのにいちいち目くじらを立てず、見て見ぬふりをしてくれることが少なくなかった)。そのとき、私は何かに蹴つまずき、顔から池に落ちてしまった。私は頭を打ち、気を失った。他の子供たちは私よりもずっと先を走っていたので、この異変に気づかなかった。
後で司祭たちに聞いたところでは、ネレイドの1人が溺れる私を助けてくれたらしい。その時私は何も憶えていないと言ったが、時間が経つにつれ、水中を浮上する感覚と、そのとき覚えた一種の戦慄に似た感覚を思い出した。それは、見てはいけない何かを見てしまった時、定命の存在が目にするには美しすぎる何かを見てしまったときに覚える感覚だった。
司祭たちは私たちにネレイドとの関わりかたを教えてくれた。私たちは「ネレイドの贈り物」という次のような文句をそらんじ、毎日繰り返し暗唱することを求められた。
ネレイドの贈り物は次の3つから成る:
姿の美しさ、
歌声の甘美さ
そして、その庇護である。
年長の子供らには、儀式を執り行う司祭たちを補佐する役目が与えられた。中央の祭壇にはネレイドに捧げる肉が運ばれる。そして年に1度、司祭の1人が洞窟の奥深くに入り、ネレイドの歌声に包まれて瞑想する。瞑想を終えて戻ってきた司祭は、預言を皆に伝えるのが常だった。
子供らは一定の年齢に達すると、聖堂に残って司祭になるか、それとも追放されるかを選ばなければならない。幼いころからずっと洞窟の中で過ごしてきた私には、他の生き方など想像することもできなかった。だから、司祭になる道を選んだ。そんな私でも、ときどき陽の光が恋しくなることがある。そしてそういう時には、もし追放を選んでいたら、自分が今頃どこにいてどんな光景を目にしていたかと、想像を巡らせずにはいられないのだ。
最も古き者:巡礼の話The Eldest: A Pilgrim’s Tale
輝かしい春。大地が雨に酔いしれ、太陽がヴァレンウッドに微笑む季節。ウッドエルフは旅に出て、齢経りたストラングラー、最も古き者のねぐらを訪ねる。そこで彼らはその年も春が訪れたことをイフレに感謝し、最も古き者の枝に囲まれて、自分たちの故郷の歴史をひもとくのである。
その後、グリーンパクト・ボズマーの主宰で、春と最も古き者を祝う盛大な宴が催される。宴は夜になっても続き、エルフたちは過去の宴や巡礼の逸話を肴に美酒を飲み交わし、佳肴に舌鼓を打つ。
宴で語られる逸話は神聖なものもあれば冒涜的なものもある。
例えばある逸話では、悪名高い戦士長に率いられた軍隊が最も古き者の住処の前で進撃を止め、住処の主に尊敬の念を示すため中に入っていく。住処から出てきた彼らは武器を捨て、そのまま立ち去った。彼らは二度と戦をしなかったという。
対照的に、こんな逸話もある。とある悪戯好きなウッドエルフが、森林マンモスの糞を挽いて粉にしたものを巡礼者たちのパンチ酒に混ぜた。そのせいで宴の参加者はみな、それまで嗅いだこともないようなすさまじい悪臭を放つ放屁に悩まされるようになる。宴が続き夜が更け、臭いがいよいよ耐えがたいものになってくるにつれ、彼らはうめき声をもらしたが、やがて鼻が慣れてしまうと、うめき声は爆笑に変わり、その笑い声が森を満たしたという。
宴で語られる逸話には、この巡礼の走りとなった男女の話もある。彼らは子供のいない老夫婦で、最も古き者を我が子のように世話したという。この2人が、初代のシルヴェナールとグリーンレディになった。
巡礼が語る逸話は他にも数多くあるが、書き留められているものは少ない。興味のある向きは春に最も古き者の住処を訪れ、逸話が語られるのを自分自身の耳で聞き、齢経りたストラングラーの姿を自分の目で拝むべきだろう。