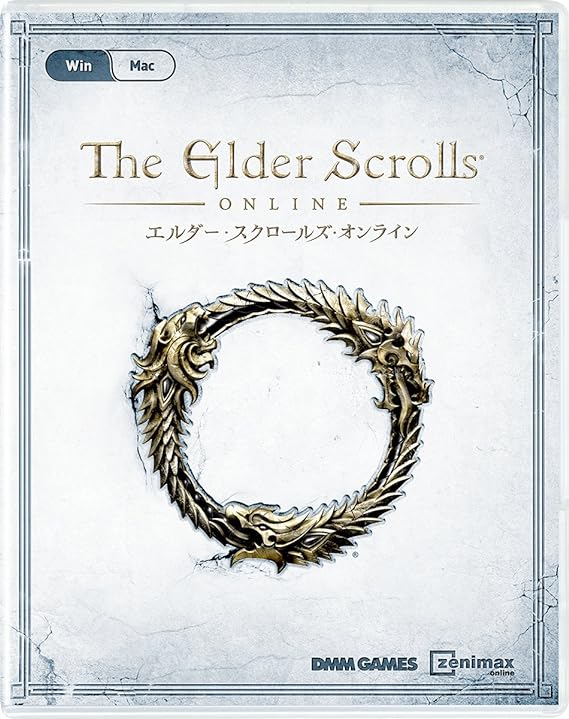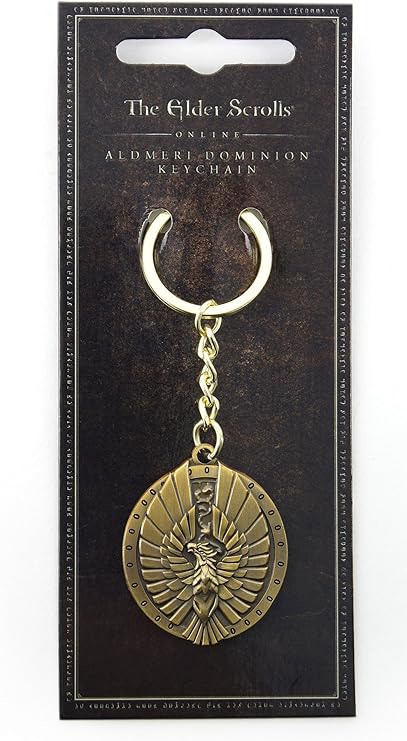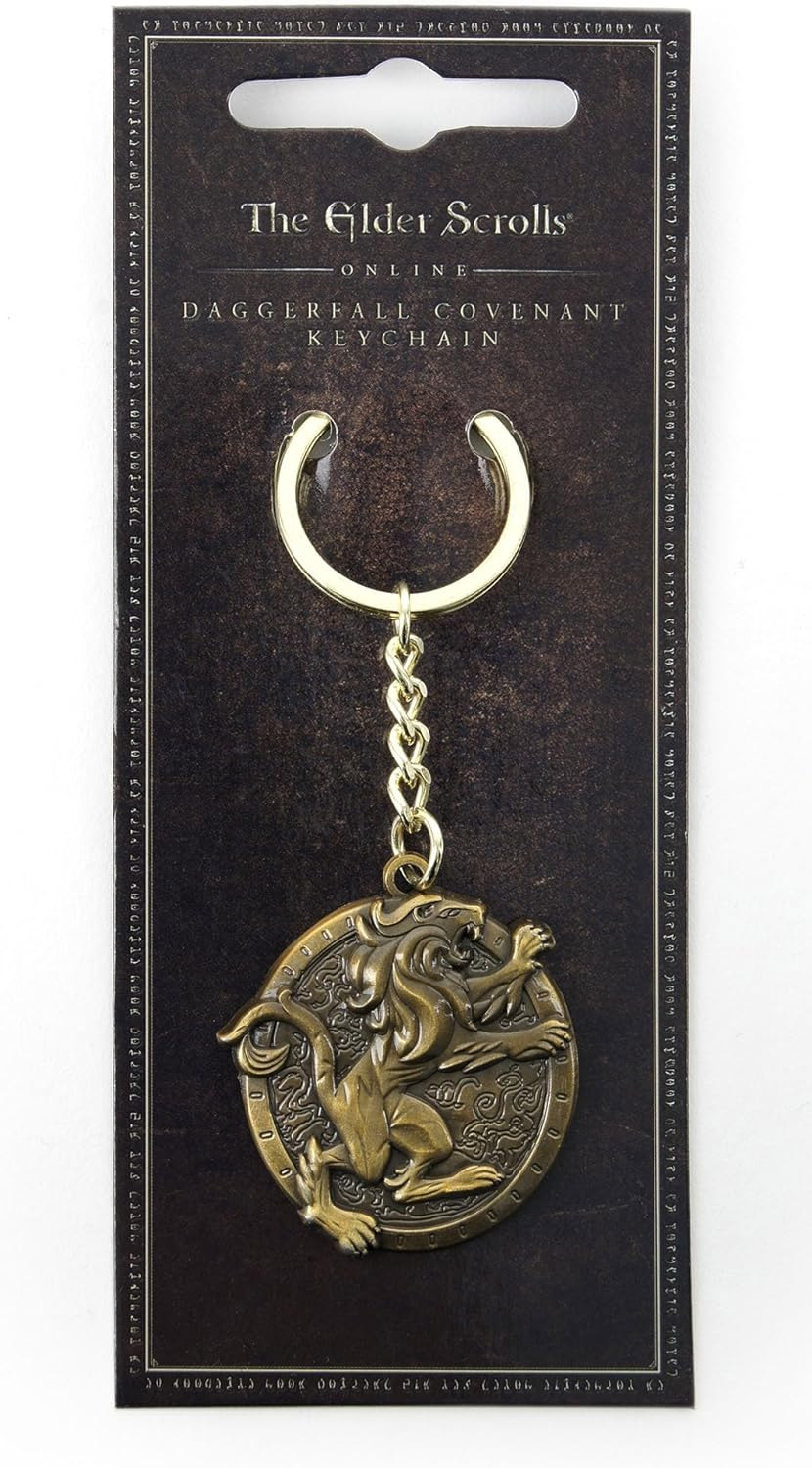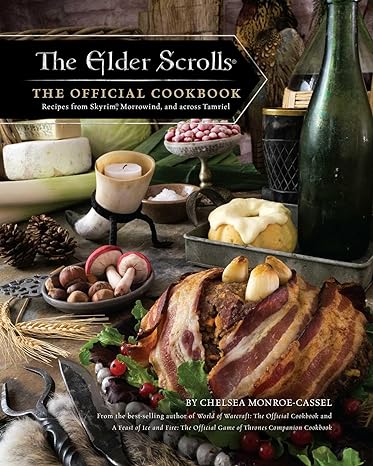アークドルイドの手紙Archdruid’s Letter
ドルイド・ウヴェン
そのクリスタルは命に代えても守れ。それを作るのにはとても苦労したのだ。お前が与えられた任務に失敗しても、これ以上クリスタルを作る機会はないだろう。人の通らない洞窟を探し、気づかれずに火山の裂け目に接近できるようにせよ。できるだけ長く、他のサークルの愚か者どもに知られずにいたい。モーナード家に我々の活動を警戒されるのはまずい。遠からず、奴らもファイアソングの力を思い知るだろう!
アークドルイド・オルレイス
アイビーヘイムへの侵入者A Trespasser in Ivyhame
グウィリム大学民俗学助教授、ザムシク・アフハラズ 著
ガレンの古代ドルイドは、いつも私を魅了してきた。研究者としての生活を通じ、私は何度もシストレス諸島を訪ね、この島の最初のドルイドたちが残していった遺跡を調査し、生きた末裔たちに話を聞いてきた。何年もの間、私は古代ドルイド王の玉座の間、アイビーヘイムについての噂を聞いてきたが、そこへ連れていってくれるようドルイドを説得できたことは一度もない。
ついに、私はそこへ行く別の手段を用意することに決めた。ヴァスティルの狩人を雇い、ガレン北東の荒野の沿岸へ案内してもらうことにしたのだ。暖かい森と切り立った丘を二日歩き、私たちは丘から海へと下っていく、絶壁に覆われた谷の頂点にまでたどり着いた。
ここで私の案内人は立ち止まり、それ以上近づくことを拒否した。「あんたをここに連れてくるだけでも、ドルイドたちの怒りを買う危険を冒しているんだ。俺はここで待つ」と言っていた。
私はただの学者だが、勇気がないわけではない。私は道を下ってアイビーヘイムの入口へと向かった。古のドルイドは王の住処として城や宮殿を建設しようとしなかった。その代わりに、ドルイド王はこの聖なる谷に君臨したのだ。もっともアイビーヘイムに王がいなくなって、もう30世紀近くも経っている。しかし神聖な雰囲気と隠された力がここには残留している。岩と自然の大聖堂だ。
私は畏敬の念に包まれつつ、もうほとんど誰にも読めないグリフに覆われた立石や、谷の壁に削りだされた、崩れかけた簡素な小屋の入口を通りすぎた。谷から海に出る場所の近くで、私は丘の内部にある大きな石の扉と、その手前に置かれたボロボロの台座を見つけた。さらなる印が扉中に張り巡らされている。そのシンボルは解読できなかったので、私は座って日記を開き、シンボルのスケッチを描き始めた。
もう少しで描き終えられると思った時、突然聞こえた声に私はぎょっとした。「やめろ!」
慌てて立ち上がると、赤褐色のローブに身を包んだ、厳格そうな髭のドルイドが私の背後に立っていた。彼の服からは灰が流れ落ち、その杖の先端には煤がくすぶって明かりを放っていた。ファイアソング・サークルのドルイドに会ったことはなかったが、目の前にいるとわかった。「後で研究するために絵を描いているだけです」と私は抗議した。
「お前は自分に属さないものを持ち去ろうとしている」と彼は応じた。「お前には値しないものを。立ち去れ、そして二度と戻ってくるな」
スケッチはもう少しで完成するところだったが、ドルイドの怒りは明らかだった。ファイアソングのドルイドが本土人と話すなどという話は聞いたことがなかった。私は自分が未知の状況にいることを知った。「わかりました、去りましょう」と私は言った。私は炭筆をしまい、向きを変えて立ち去ろうとした。
ファイアソングのドルイドは素早く大股で三歩進み、私の手から日記を奪った。彼はスケッチが描かれたページをちぎり、日記を私の足元に投げてよこした。「まだわからないのか?この印はこの地にのみ属するものだ。お前が持ち去ることは許さん!」
私にも常識はあった。私は傷ついた日記を拾い上げ、足が許す限り急いで退散した。
親愛なる読者よ、もしアイビーヘイムを訪ねる機会があったら、ぜひ行って欲しい。美しく、また神聖な場所である。しかし持ち帰るのは想い出だけにするよう、気をつけることだ。
あらゆるシーエルフに告ぐ!Calling All Sea Elves!
ガレンの自然の美を愛している?新しい人々に会うのは好き?本土から来る金払いのいい客のために、凶暴そうな笑みを作ってみせることはできる?それなら、サベージシストレスツアーにはぴったりの仕事があります!
関心と暇のあるシーエルフ船長は、ヴァスティルのジュリーン・クールセレに詳細をお尋ねください。
アルノーとリゼッテ:真実Arnoit and Lisette: The True Story
ジャコア・デュフォート 著
マダム・パジャウドはなんという人だろう。彼女は他でもない私の祖先から極めて詳細な話を聞いておきながらそれを無視し、自分の勝手な空想で恋愛物語を捏造したのだ!当時、現実に起きた悲劇に基づく明らかな警告の物語を、彼女がこのように扱ったのは唾棄すべきことだ。
私がこの文書を書くのは、マダム・パジャウドが「嵐とひまわり」の中で加えた脚色の中で最も甚だしいものを訂正するためである。以下の記述はアルノー・デュフォート(私の祖先)とリゼッテ・モーナード(彼の恋人とされる人物)との間に起きたことについて、私の両親から聞いた詳細である。私の両親は自分たちの親からその話を聞き、親はまたその親から聞いた。この悲劇が実際に起きた家族に行き着くまで遡れる話なのだ。
この物語が正確に描写されたのは、アルノーを「船大工を代表する金髪の男」と形容するところまでだ。この本はリゼッテ・モーナードをありえないほどきらびやかな存在として描いている。賢く勇敢で、騎士としての実力に優れ、愛の殉教者でもあると。彼女はそこまで完全な人間だったのか?ここから、この作品が明らかにフィクションであることがわかる。マダム・パジャウドは明白にモーナード家へ肩入れしており、それを隠そうともしていない。
一度視線を交わしたら後は手紙だけで成立する恋愛を見せられては、きっと読者も困惑したに違いない。これほど底の浅い、馬鹿げた話を聞いたことがあるだろうか?親愛なる読者よ、残念ながらリゼッテはマダム・パジャウドが描くような(あるいはマダム・パジャウド自身がそうありたいと望んだような)、勇敢で美しい人物ではない。
真実は、ナヴィール城でトーナメントを見ていた若い娘、リゼッテ・モーナードがアルノー卿に手紙を渡し、彼は親切心からそれを受け取った。リゼッテはそれから数年間アルノー卿に執着するようになり、卿がその想いに応じなかった時、不幸にも彼女はドルイドに頼ったのである。現実に使われたのはドルイドが毒を塗った剣などではなく、親切を装って手渡された、ドルイドの惚れ薬の入ったコップだった。そう、リゼッテ・モーナードは自分が魔女であることを隠し、ドルイド魔術を使ってシストレスの貴族家を破滅させようと目論んでいたのだ。ヴァスティルを見れば、今日に至るまでドルイドとモーナード家が異様なほど近い関係にあることがわかるだろう。
リゼッテはその後、魔法にかかったアルノーを説得して、彼女と共に船を盗ませた。彼女はアルノーをイフェロンに連れていき、ドルイドの儀式を行ってファイアソング山からガレンに炎の雨を降らせ、ついにガレンをドルイドの手中に収める計画を立てていたらしい。しかし、ここで何が起きたのかについては確かに議論の余地があるが、彼らの船は海賊に襲撃されたか、あるいはリゼッテが船を座礁させてしまい、海辺まで泳ごうとしていた最中にスローターフィッシュの餌食になった。いずれにせよこの話が描いているのは、敬愛された祖先が忌まわしい誘惑者の犠牲になった悲劇である。しかしどの話が真実だとしても、リゼットがふさわしい最期を迎えたことにせめてもの慰めを見出せるだろう。
しかしこの本は二人を、家臣たちの求めに共感する正当な指導者として描いている。彼らは「真実の愛」のために死に、曖昧な結末で読者を失望させている。フィクションとして見た場合でさえ、あらゆる点で面白さを欠いている!虚しく悲惨だ。こんなものは読まないほうがいいだろう。
イヴェス・グランバシェの台帳Yves Grandvache Ledger
フロレンティーノ、どうかこのメモを他の者たちに回してもらいたい。俺には時間も適正もない。真紅を愛する我らが友の相手で手一杯だからだ。
ヴァスティル
我々はここヴァスティルで通常の活動から一時的に退く。レッドブレイドとの契約は重要すぎる。営業所には警備に必要なだけのスタッフを残し、残りはファウンズ・チケット近くの発掘現場へ送るように。我々の注意がよそに向いている間、地域の誰かが変な気を起こすようなら、遺産を見つけた後に始末すればいい。
ゴンファローネ湾
現地の奴らに探らせろ。超越騎士団は仕事の機会になりそうだ。その間、ダーヴィル・ドティルへの働きかけを続けておけ。あいつは利用できる。適当な交渉材料さえ見つければいい。
フンディング港
冷眼のアルガーが機会を与えてくれたことを感謝しなければ。斥候たちが刻印の丘から戻ってきたら知らせるように。素晴らしいチャンスになるかもしれん。成り行きを見守ろう。
アバーズ・ランディング
あそこは滅茶苦茶だ。鉄の車輪ギルドは完全に暴走している。うちの者たちは退散させて、事態が落ち着くまで待たせるつもりだ。アンビに金を払って状況の報告を続けさせろ。それ以外、今のところあそこでやることはない。
ヴァスティルのドルイドの食事Druid Food of Vastyr
旅行記作家カスタス・マリウス 著
ハイ・アイルの休日ラッシュから逃れるため、私はガレンのヴァスティルの港にいるが、胃がゴロゴロと鳴っている。
私はこの街の蔓地区にある岩だらけのトンネルをさまよって、収穫したてのドルイド産品を売っている質素な屋台をいくつか見つけた。この農産物は名前だけなら他の場所にあるものと何ら変わりないが、単に香りと材料だけでも十分に特徴的である。ドルイドたちの間で、食べ物は売り物というより分け合うものであり、新鮮というよりまだ生きており、風味を強める生命力がこもっている。ハイ・アイルで長い時間を味にうるさい上流社会の仲間たちと過ごした後で、私はヴァスティルの石で覆われた街路を歩き、ストーンロアの森で摘まれたリンゴを食べてみた。最初の一口で、私は生命力が復活したように感じた。元気が出た私は、もっと食べたいと思った。
ドルイド王がキメラを創造したとかいう話に触発されたあるドルイドは、「歌う根菜」と名づけられた野菜を見せてくれた。紫の線が入ったネギと人参、ニルンルートの混合種である(ニルンルートは栽培が難しいことで悪名高いが、灰が多いシストレスの土でよく育つのだと教えられた)。彼女はこの野菜の葉の小さなサラダを提供してくれた。細切りにしてエシャロットと混ぜ、ムーンシュガーのドレッシングをかけたものだ。軽くシャキシャキした食感に加えて、夕焼けの色が耳元で鳴り響くような、強烈な風味があった。この体験はあまりに生々しく激烈だったので、私は浜辺近くの平たい岩の上に横になって、感覚が過ぎ去るのを待たねばならなかった。
そのドルイドは後でまた来て、ある根を味見してくれと言っていた。彼女はそれを午後いっぱいかけて煮込んでシチューにし、サルトリスを添えて出す予定だという。しかし私が覚悟を決めて彼女のところに戻った時は、もう夜遅くになっており、鍋は空だった。別のドルイドが私を憐れんで、砕いたオーツを加えたコンベリーの粥に取れたての蟹肉を添えたものを食べさせてくれた。こんな味の組み合わせが合うとは想像もできなかったし、実際合わなかった。それでも腹はふくれ、元気を取り戻したので、島の北にあるドルイド居留地、グリマーターンへ向かっていたグループと共に、一晩かけて歩いた。
ガレンでは春の水でさえ澄んでいるようだ。地域の住民の大半は私がこのことを言うと妙な視線を向けるが、この島のドルイド魔術が関係しているに違いない。それとも、シストレスの骨格を形成する火山岩のせいだろうか。
全体として、ヴァスティルの質素な環境はその食事にも反映されている。どこでも手に入る滋養豊かで簡素な材料が、ドルイドの手によって新たな命と風味を与えられているのである。耕作や他家受粉のプロセスについて質問すると、戸惑ったような謎めいた笑顔が返ってくる。まるでそのような秘密はドルイド仲間にしか教えられないとでも言うようだ。
だとすれば、それはそれで構わない。世界の半分がここにあるような風味の自然魔術を取り入れようとするくらいなら、私はそんな秘密はすぐさまガレンに委ね、帰る口実とするだろう。
ヴァスティルの歌Song of Vastyr
路上につま先を打ちつけても
何も恐れることはない
ダンスはいつでも大歓迎
来たれヴァスティルの街へ!
きらめく港からモーナード城まで
遠い民も近くの者も
決して友には事欠かない
来たれヴァスティルの街へ!
(コーラス)
ヴァスティル、ヴァスティル!ガレンの光り輝く宝石!
ヴァスティル、ヴァスティル!波を越えて高く!
ヴァスティル、ヴァスティル!その旋律を聞け!
ヴァスティル、ヴァスティル!歌のある街!
〈うんざりしたオルナウグ〉で飲めば
あなたの不安も消え失せる
ドルイド、貴族、観光客も歓迎しよう
来たれヴァスティルの街へ!
シストレスの美しい海岸に沿い
我らが海辺を目指して来たれ
名所を巡り、夜は踊り明かそう
来たれヴァスティルの街へ!
(コーラス)
ヴァスティル、ヴァスティル!ガレンの光り輝く宝石!
ヴァスティル、ヴァスティル!波を越えて高く!
ヴァスティル、ヴァスティル!その旋律を聞け!
ヴァスティル、ヴァスティル!歌のある街!
丈夫な壁と商人の店のため
船が埠頭を行き交う
シストレスにこれ以上の場所はない
来たれヴァスティルの街へ!
ヴァスティルの漁師歌Vastyr Fisherfolk Song
よいと引け、よいと引け
海辺が視界に入るまで
夜が朝へと変わるまで
すべての網を使いつくすまで
いったん獲物を見つけたら
それがそいつの運の尽き
俺たちの目からは逃げられない
すぐに味見をしてやろう
さあ勝負の始まりだ
船が揺れても回っても
俺たちは鉤、網、槍で
獲物を近くに巻き寄せる
よいと引け、よいと引け
海辺が視界に入るまで
夜が朝へと変わるまで
魚釣りして角笛を吹く
港じゃ行きかう人々の
視線が俺たちの品に集まる
溢れんばかりの大漁で
皆が踊って跳ね回る
その日の仕事が終わったら
踊るも遊ぶも思いのまま
宿で体を休める時の
ハチミツ酒の甘さがたまらない
よいと引け、よいと引け
再び出発するまでは
好きなように生きればいい
そうして海に出た時は
歌い騒いで帆を揚げる
それがヴァスティル漁師の生き方よ!
ヴァスティルの詩の王者The Poet-Champion of Vastyr
ディベラ司祭、チャンター・ミリウス 著
第二紀400年、最高顧問サヴィリエン・チョラックは最高顧問による統治四世紀を記念して数ヶ月にもわたる祝祭を開いた。帝都の数多くのゲームや余興のうちの一つとなったのが、詩の大会である。実力を認められた詩人たちがタムリエル中から最高顧問の宮廷で詩作をするために訪れ、その多くは有名な詩人であった。ヴァスティルからはシストレス諸島の外で無名のブレトン、ニネル・ドゥマリスという平民生まれの商人が来た。
多くの者が最高顧問に聞かせるため、壮大な叙事詩や威風高き頌歌を歌った。しかし誰もが驚いたことに、サヴィリエン・チョラックの心を揺さぶったのは、ガレンから来た無名の平民が記した言葉だった。最高顧問はニネル・ドゥマリスを詩の大会の優勝者とし、彼女に王宮での地位を進呈した。しかしニネルは辞退し、故郷をあまりにも愛しているので、永遠に離れるのは忍びないと言った。彼女はヴァスティルに戻り、長い生涯の間、数多くの美しい作品を作った。
今日ではニネル・ドゥマリスの優勝作品が、船乗りの恋人を想う女の嘆きを歌ったソネット「太陽のごとく恐れを知らず」であったことがわかっている。女がいくら愛しても、恋人がライバルである海の声に従うことを止める力は彼女にはない。それをニネルは「海鳥の笑い声、鐘の音、船長の呼び声」と印象深い手法で記している。ガレンの民によればこの偉大な詩人は若い頃、若く勇ましい船長を愛した苦い経験を基にしてこの作品を書いたという。
「太陽のごとく恐れを知らず」は有名だが、ガレンで最も愛されている詩ではない。その名誉はソネット「しなやかな妖精」に与えられる。美しいガレン島への喜ばしい讃美歌である。軽く読んだだけだと、ニネルは遊び好きの自然の霊魂について書いていると思っても無理はないだろう。しかしこの詩人はもっと巧妙である。「妖精」とは彼女の島への愛のことであり、彼女がガレンの「太陽に浸った峡谷」と「神聖なる霧」に身を任せたいという心からの想いである。この詩を口ずさめばヴァスティルのどの酒場でも、客たちは立ち上がり、胸に手を当ててあなたが言い終わるのを待つだろう。
ニネル・ドゥマリスは夕暮れの大聖堂の地下にある栄誉の地に、有名な騎士や君主たちと共に眠っている。ヴァスティルの多くの者は、栄誉を受けているのがニネルと共に眠る名士たちであり、その逆ではないと言う。
ヴァスティル包囲Siege of Vastyr
リロス・モレットの日記より。第二紀365年の日付。「群れる嵐」によるヴァスティル包囲終盤の一夜を記したもの。
* * *
昨晩炎が胸壁に降り注ぎ、それを強風が壁から散らし、屋根に振りまいた。我々は長い夜の間中働き、井戸から手桶に水を汲んで、手から手へと渡して運んだ。運の悪い建物の屋根は、我々に戦争を挑んできた「群れる嵐」艦隊のための灯となってしまった。私の家は燃やされる屈辱を免れた。何時間もかけて草ぶきの屋根に十分な水をかけておいたおかげだ。それでも城壁から街路に向かって火花が漂うたび、私は一瞬手を止めて八大神に祈った。私のアトワンと、私たちの大切な拾い子、ノム・タの無事を願った。
衛兵の呼び声が聞こえた。「群れる嵐」のシーエルフたちが我々の沿岸に船を散開させているらしい。奴らのシーメイジが風を呼び起こす呪文を止め、強風が収まったのを感じた。燃えていた家の火は再び勢いを取り戻したが、一瞬の間、手桶を運ぶ手が途中で止まった。すべては静かだった。
そして、驚くべき雷鳴と共に、ある衛兵が叫んだ。「海が退いていくぞ!」
列の中の数人は自分の持ち場を離れて、この奇妙な出来事を見ようと胸壁に駆けていった。他の者たちは手桶を丸石の地面に放り出し、封鎖されたヴァスティルの門めがけて走った。
給水部隊を指揮していた騎士はこの動きを叱責して怒鳴った。「持ち場に戻れ、街が炎に焼かれてしまうぞ!」その声で一部の者は持ち場に戻ったが、さらに多くの者たちが意を決して中心の広場から抜け出していった。最も愚かな者たちは古いドルイドのトンネルの暗闇の中へと駆けこんでいった。私は彼らの影が自分を通りすぎ、墨汁のような地下の暗闇へと消えていくのを見た。
手桶は拾われ、水で満たされたが、人数は減り、列は崩れていた。人員同士の間隔が広がったため、手桶を手渡すのにより多くの労力がかかるようになり、手の皮膚がズタズタになりそうだった。だが我々は必死に耐え、炎が東市場の屋台を飲み込むのを防ぐことができた。
上空から市民と衛兵両方の恐怖の叫び声が聞こえてきた。這うようなその金切り声は、それを引き起こした何かが迫るにつれ、より高く大きくなっていくようだった。視線を上げると、走る足音と共に胸壁から叫び声が迫って来ていた。「逃げろ」人間の洪水は叫んだ。「逃げないと、お前たちも大波に飲み込まれるぞ」。私は理解に苦しんだ。何が襲ってくるのかわからなかったからだ。しかしパニックに陥った人々が迫ってくること自体、十分に危険だった。
「大波だ、逃げろ。高い場所に行くんだ」。その声を受けて私は前進し、階段を上り、急な坂を駆けあがった。私たちが走るにつれ、波の音は大きくなっていった。聞き逃しようのない、不可能なほど高い、間延びした唸りだった。ほんの少し前まで多くの人が立っていた胸壁に、波がぶつかる音を私は聞き、感じた。波はヴァスティルの高い壁にぶつかって割れ、破壊的な水の壁となって側面を流れていった。家はその重さに砕け散った。石は固定用具から切り離され、停泊中の船でさえ目もくらむような余波を受けて突然飛び出し、港に激突した。
私の後ろを走っていた群衆がどうなったかはわからないが、背後に水の音が聞こえてこなくなるまで足を止めなかった。一番高い場所に到達してようやく、私は動きを止めた。全力で走ったため、胸が激しく上下していた。そして振り向いて、「群れる嵐」が召喚した恐るべき何かの姿を見た。
我らがヴァスティルは部分的に沈没していた。残骸が漂い、暗い水の下に沈んでいた。奇妙なことに、私の頭へ最初にはっきり浮かんだのは怒りでも哀しみでもなく、憂鬱な諦めだった。夜明けが来たら、古いドルイドのトンネルから死体を引き上げなければならないだろう。
ウミンディオルからのメモNote from Umindior
クエン
放置してすまない。だがネリのことが頭から離れない。彼女を探しに行くことにした。ドレッドセイルから抜けるよう説得してみる。彼女に遺物の場所を教えてもらえれば、この依頼を終わらせることくらいはできる。
神々の加護があれば、ここに戻ってきて合流しよう。待っていてくれ!
ウミンディオル
エメリックの裁定Emeric’s Judgment
(上級王エメリックが、ランセルの戦争の終結と大ダガーフォール・カバナントの形成、エメリック自身によるハイロックおよびその同盟国の上級王への即位を受けて発した声明の写し)
第二紀567年、新たに即位した大ダガーフォール・カバナントの上級王によって発せられた以下の簡易判決は、ランセルの戦争として知られる事態における、モーナード家の裏切りと戦争への参加、およびウェイレストとその近隣諸国の扇動に対して下されたものである。
ショーンヘルムのランセルの側につき、彼の計略を支援するために騎士と武器を送ったことにより、アヴリッペ・モーナードは即座に、かつ永久に公爵およびシストレス公爵領の管理者としての地位を奪われる。モーナード家はその領地を保持するが、諸島の管理権はデュフォート家に移され、モーナード家の指導者はそれに劣る伯爵の地位を恒久的に担うものとする。
上級王エメリックはこの判決において寛大さと慈悲を示したが、モーナード家がその誓いと義務を再び破るようなことがあれば、王はモーナード家の名も領地もニルンから完全に消し去るだろう。
さらにデュフォート家とその指導者ドノヴェン・デュフォートは、この日より公爵の地位を担い、シストレス諸島公爵領の統治権を与えられるものとする。
以上に記したことを遵守せよ。
より高き上級王、エメリック!
カエルを盗む計画Frog Stealing Plans
へレイン
助手からヴァスティルに滞在中のレッドガード商人の噂を聞いた。名前はムヌブラといい、ある特別なものを持ってハンマーフェルからはるばる来たそうよ。ドラゴンフロッグ。この男はどうやら、このカエルをビジネスパートナーか何かだと思っているみたい。信じられる?
そこで。まああなたが見てもわからないでしょうが、信じて。その獣には同じ重さの黄金に見合う価値がある。そして私には、あれをかすめ取る完璧な作戦もある。港にいる友人が、あの商人の船にいくつか穴を開けてくれる。奴が大慌てで荷物を救いだそうとしている間に、カエルを奪うの!
シストレスでドラゴンフロッグを見たことはない。そもそも他のどこでもない。だから高値で売れるはずよ。
ベルナデッテ
追伸:カエルが暴れた時のために、水を入れたバケツを用意しておいたほうがいいかな。
カソレインの夢The Dream of Kasorayn
三つの種を、一本の木の上に見た
ローワンの種、アッシュの種、オークの種
慎重に種を塵に収めた
民を導き教えるため
三本の木、九本の枝、五百枚の葉
それぞれの根に一つの季節
それぞれの種を深く眠らせよ
さすれば玉座は新たにされる
山が揺れ、種を蒔く者が目覚めし時
玉座は再び花開く
一つの選択、一つの意志、一つの縛りし言葉
すべての地に祝福か災いをもたらすだろう
カソレインの最後の夢The Final Dream of Kasorayn
三つの種を、一本の木の上に見た
ローワンの種、アッシュの種、オークの種
慎重に種を塵に収めた
民を導き教えるため
三本の木、九本の枝、五百枚の葉
それぞれの根に一つの季節
それぞれの種を深く眠らせよ
さすれば玉座は新たにされる
山が揺れ、種を蒔く者が目覚めし時
玉座は再び花開く
一つの選択、一つの意志、一つの縛りし言葉
すべての地に祝福か災いをもたらすだろう
遠い季節の末に来る
種を蒔く者を起こす日が
進んで与えられるなら、すべて良く
奪われるなら、災いが訪れる
カソレインの夢(注釈付き)The Annotated Dream of Kasorayn
グウィリム大学民俗学助教授、ザムシク・アフハラズ 著
シストレス諸島のドルイドは、タムリエルの他の地ではほぼ知られていない莫大な民間伝承の担い手である。彼らの語りは第一紀初期にまで遡る童話や歌、物語を含んでいる。おそらく最も重要なのは「カソレインの夢」と呼ばれる予言の詳細であろう。ガレンのドルイドなら誰でもこれを暗記しているが、予言の真の意味は何だろうか?筆者はささやかながら、以下のページにてこの問いの探究を試みたい。
まず、ガレンの伝達の石に記されている予言を考えよう:
三つの種を、一本の木の上に見た
ローワンの種、アッシュの種、オークの種
慎重に種を塵に収めた
民を導き教えるため
三本の木、九本の枝、五百枚の葉
それぞれの根に一つの季節
それぞれの種を深く眠らせよ
さすれば玉座は新たにされる
山が揺れ、種を蒔く者が目覚めし時
玉座は再び花開く
一つの選択、一つの意志、一つの縛りし言葉
すべての地に祝福か災いをもたらすだろう
興味深い比喩に満ちた、美しい詩のようだが、それぞれの行には秘密の言及が多く含まれている。より深い意味を探ろう。
「三つの種を一本の木の上に」はシストレスにある3つのドルイド・サークルを指している。ローワンは知恵と謙虚な奉仕、すなわちストーンロア・ドルイドの道を意味する。アッシュは神秘の力と再生を意味し、これは隠遁するファイアソング・ドルイドの象徴である。オークは当然力と勇気の象徴であり、エルダータイド・サークルを表している。最後のドルイド王カソレインはここで、3つのドルイド・サークルの確立についての言及を避けている。
ここで我々はとてもいくつかの興味深い数字が、一気に読む者に与えられていることを見出す。枝と葉、根は重要ではない。むしろ、夢の狙いは数字を見出すことだ。3×9×500、すなわち13,500である。さらに「それぞれに一つの季節」ということは、3,375年の期間になる。夢が第一紀4世紀のどこかに位置づけられるとした場合、この期間は第二紀の第6世紀末頃に終わりを迎える。確実に特定できないのは、夢がいつ記されたのか正確には知られていないからである。そして言うまでもなく、ドラゴンブレイクによって事態はさらに複雑化している。しかし、これが約束している出来事はそれほど遠くないと思われる。
第三節は予言が完了に近づいた時に注意すべき兆候と共に始まる。ここで「山」と言われているのはイフェロンの大火山、ファイアソング山である。意外なことではないだろうが、シストレスのドルイドたちはこの山にとても注目している。カソレインが「種を蒔く者」と呼んでいるのが何なのか、誰もはっきりとは知らない。第一節で言及されている種と何らかの関係があるとする学者もいる。しかし筆者はその見解に反対である。種を蒔く者はただの比喩かもしれない。
だが、我々はカソレインの夢から何を期待しているのか?ここで我々は予言の核心に迫っている。第二節と第三節の両方で言及されている玉座は、蔦の玉座のことである。ドルイドの伝説によれば、ドルイド王はガレンにある儀式の地から統治を行ったとされている。この予言は実際、新しいドルイド王の任命あるいは帰還と関係している。三千年以上の時を経て、この肩書を手にする者と。
推測ではあるが、最後の節にある「一つの選択」は新たにされた蔦の玉座を獲得する者の決断を意味しているのだろう。そして「縛りし言葉」は自然の霊魂そのものを束縛して命令する、ドルイド王の象徴と言われるものを指している可能性が高い。すべての地を祝福か災いで包むという部分の意味を解明する証拠は、筆者にはほとんど見つけられなかった。話したドルイドは議論を拒んだが、この予言は善か悪のどちらかで終わるのだろう。しかしシストレスのドルイドでさえ、カソレインの夢の真の意味については一致した見解を持っていない。
ガドからの手紙Letter from Gad
ボス、
あのふざけた海賊たちが最初の頃に力となったことはわかっていますが、奴らは発掘現場で何の役にも立ちません。ファウンズ・チケットに奴らが来なければよかったと思うくらいです。
もう何度か、酔っ払いの殴り合いのせいで作業員をヴァスティルに送り返す羽目になりました。我々の掘削がうるさすぎるというので、奴らはしょっちゅう腹を立てるんです。入口付近の波で溺れ死んだ奴までいます。海賊が腰の高さの水で溺れるなんて、呆れるばかりです。
しかもあのレッドブレイドとかいうレディは、常に監視しています。あの女には、酷く気持ちを落ち着かなくさせる雰囲気があります。気分が暗くなってくる。
あの海の犬どもを抑えておければ、もっとずっと早く財宝を発見できると思います。
ガド
ガレンの獣The Beast of Galen
エリンヒルのフラスタス 著
「カイメラ、カイメラ、カイメラ!今日は何本首がある?」
――伝統的なブレトンの庭遊び
子供の集団がカイメラ遊びをやっているのを最初に見たのは、数年前にウェイレストに旅行した時のことだった。タムリエル中の文化でよく見られる、列を作るタイプの娯楽である。私は酒場の玄関口に立って食事と楽しい歓談を待っていたが、子供たちは互いに向き合う列を2つ作っていた。子供たちはゲームの開始の合図を一斉に叫び、私は笑みを漏らした。「カイメラ」とは明らかにガレン語の「キメラ」の変形だった。先頭にいた子供は自分がどの首かを宣言した。そのグリフォンだか蛇だかの首の子供は反対側の列の子供に向かって走り、その子も同じようにした。彼らは場所を入れ替わり、列の次の子供に、自分の首を宣言する順番を譲った。それは全員の番が終わるまで続いた。
「蛇の首はシュシュシュシュって音を出せよ!」
――伝統的なブレトンの庭遊び
ガレンの深い森にあるエルダータイドの居留地に入ると、そこでは遥かに厳粛な雰囲気が私を取り巻いた。軽く雨が降る中、私は案内人に連れられていくつかの石の小屋や曲がった柱を通りすぎた。カーテンのかかった入口の向こうからは低い歌声が漏れ、出会う視線はどれも静かな軽蔑の念を込めて私を見つめた。私が研究機関と関係しておらず、案内人に多額のゴールドを支払っていなかったら、このキャンプは敵意に満ちた、むしろ危険な場所になっていただろうと確信している。私たちの先には、雲がかった空にくっきりと輪郭を表す立石がいくつか見えた。石の下には巨大な洞窟の入口が横たわっていた。その中からは低い唸り声が聞こえてきた。まるで大きな獣が発したかのような声だ。その音は深く強く、私は一瞬動きを止めた。
「ライオンの首はウオーンって鳴けよ!」
――伝統的なブレトンの庭遊び\
クラウディ・ドレッグの外にいた子供たちはまだ遊んでいたが、私は座ってグウィリム大学の敬愛する学者仲間と食事を始めた。彼女はブレトンとドルイドの伝説におけるキメラの役割について快く話してくれた。一見してわかるように、言葉それ自体が面白い。タムリエルの多様な文化の研究に従事して日の浅い学者の多くは、キメラというこの語が「チャイマー」という文化的名称の変形であると考えがちだ。チャイマーとは今日、ダンマーに先立つ伝統集団を指すために用いられる語である。実際のところダークエルフ以前の者を指すこの語の現代的用法は、「変化」を意味する遥かに古いアルトマー語変形である。そのため当然、チャイマーという文化集団を指すもう一つの一般的な言い方は「変化した者」となる。
「変化の獣」あるいは「変化した獣」を意味する語はディレニ王朝の時代に出現したとされているが、これはアレッシア以前の文書が現代になって研究されたことで生まれた推測である。その時代におけるこの語の用法については、解釈によるところがとても大きい。というのも、この名称を担うガレンの獣たちが創造されるのは、この語が第一紀初期に若いディレニの書記によって教師の手紙の中に書き記された時には、まだ数世紀も先のことだったのだから。
かなりの量の飲酒と探りを入れた後でようやく、私の食事相手はこの語自体が元来はブレトン自身を指していた可能性を認めた。実際、当時の高尚なディレニの学者たちにとって、半人半エルフを指す言葉として「キメラ」以上にふさわしいものがあっただろうか?
「グリフォンの首はクゥオオオオオって鳴くんだぞ!」
――伝統的なブレトンの庭遊び
神聖なる地の下にある石造の核へと降りていくと、周囲の壁が暖かくなっていった。明らかに、シストレスの火山の影響である。これがこの洞窟の気候を、私の目の前に立ち上がってきた巨大な獣にとって快適なものにしているのだろう。獣はこちらを向き、三対の眼が私に向けられた。獣が立ち上がると、三つの頭とその筋張った首が伸びて左右に動いた。私は首筋に冷たい針を当てられたような恐怖を感じた。すると突然、獣はよろめいた。そしてオークの木のような不動の意志を休息へと向け、唸り声をあげて暖かい大地の中に戻っていった。
キメラたちはこの地から消え去ってしまった。今では、最後のドルイド王の時代に置かれた古代の石を守るための数体が残っているだけである。キメラを作るための秘密すら忘れ去られている。案内人によれば長老の中でさえ、呪文を使ってイフレの手を導けるのは数人だけだろうということだった。私の前で眠っていた獣はその蛇の首を真っすぐ立てて、時の経過により鈍った眼で管理人を見た。そのドルイドは彼のサークルが召喚した嵐のように厳格で臆することなく、獣の脇に立ってその鼻に優しく手を置いた。私の想像かもしれないが、彼のフードの下に涙が光っているのが見えた気がする。
「カイメラ、カイメラ、カイメラ!門を抑えて石を守れ!みんな家に帰るから!」
――伝統的なブレトンの庭遊び
私たちが酒場の扉からよろよろと出てきた時、子供たちはゲームを終えていた。私たちは気持ちよく別れを済ませ、私は宿への帰り道を歩き始めた。歩きながら、私はブレトン種族の大きな物語におけるキメラの役割を思った。ドルイドたちの長期の離散と、彼らがより広い文化に刻みつけた痕跡を。キメラがその良し悪しはともかく変化を象徴しているのなら、ドルイドもまた何らかの意味で同じものを象徴しているのだろうか?そして現代の世界において、彼らはどのような役割を演じるのだろうか?
彼らは適応して生き残るのか?それともいつか、私たちはガレンのドルイドについてキメラと同じような物語を書くことになるのだろうか?いつの日か消失する、偉大なる文化の過ぎ去った一部として?
ガレンの動植物The Flora and Fauna of Galen
旅の博物学者、エリス・アグリルミルの日記より
ガレン島は自然の二面性に関する驚くべき一例である。この島は大量のひまわりが、豊かな落葉樹の森へ広がる緑の楽園だ。どんな旅人も羨む旅行先だろう。しかし溶岩だらけの無慈悲な熱帯雨林はすぐそばにあり、足を踏み入れるうかつな犠牲者を飲み込もうと待ち構えている。私はごく短時間島に入っただけだが、そこで見ただけでも心臓が凍りつきそうになった。私はできる限りメモを取った。この島を調査することで得られる知識があると思ったからだ。ここの動植物はこれまで見たもののどれにも似ておらず、未だ発見されていない秘密への手掛かりが隠されているかもしれない。まずはこの島の温暖で快適な部分について記そう。
南ガレン
私はこの島にいた時間の大半を、南ガレンの青々と茂った平原の探索に費やした。ここは広大かつ静かな土地で、引退後にここへ住むことも容易に想像できる場所だ。ゆるやかな起伏のある開けた野には、蝶や種々の野生動物が生息している。私が特に気に入ったのは、地域住民が「ファウン」と呼ぶ、一見して認知能力のある獣の集団である。タムリエル中を旅してきた私も、この諸島以外でこの生物を見たことはない。彼らは二本の後ろ足で立ち、わずかに背中を曲げている。体は長身で細身のエルフのようだが、毛皮で覆われている。頭は鹿のような大型の枝角が飾っている。
鹿を後ろ足で直立させ、両腕を与えればファウンになるだろう。彼らの行動を理解できるほどは接近できなかったが、原始的な文化を有するようだ。彼らは自然と強い結びつきを持っているようで、自然が脅かされれば守ろうとする。私はファウンが道具を使い、踊り、楽器の演奏までするところを見た。コミュニケーションを取りたいと思ったが、聞くことができたのはただの唸り声や鳴き声だった。おそらく最も興味深い点は、明らかにメスのファウンがいないことだった。彼らは私が最初に思ったよりも魔術的な存在なのか、それとも生殖の方法が伝統的なものとは異なっているのか。メスを一目から隠すのが上手いだけかもしれない。
西ガレン
さらに北や西へ進んでいくと、ゆるやかな平原は徐々に落葉樹の森へと変わっていった。温暖さにおいては劣るものの、森には息を飲むような自然美があった。私が本当に自然とつながっていると感じたのはここを散策していた時である。野生動物もこのつながりを感じているのではないだろうか。私はこの地域で「スプリガン」と呼ばれている、感覚能力を持つ植物を数多く見かけた。これまでにもタムリエルで見たことのある生物だが、ここのスプリガンのような振る舞いを私は見たことがない。通常、スプリガンは木のような存在であり、ねじれて縦長の柱のようになった根を持っている。スプリガンは根を使って地面に沿って移動し、森を傷つける者を攻撃する。ここのスプリガンは違っている。より人っぽいのだ。胴にあたる部分を形成している根は分かれて二本の足になっている。彼らは最近の侵入に応じて、より攻撃的になっているのかもしれない。スカイリムの巨人並みの大きさの、巨大なスプリガンがいるという噂も聞いている。自分では目にしていないが、そのスプリガンの怒りは小さなスプリガンよりもさらに強力なのではないだろうか。
北東ガレン
巨大スプリガンは恐ろしいかもしれないが、この島の北東で私が見かけたものに比べれば何でもない。落葉樹の森林は突然、絡みあった茨のジャングルと溶岩の川に変化した。これほどまでに居住不可能な場所は見たことがない。馬ほどに大きい蜂。マグマそのものから生まれたように見える巨大なトカゲ。この島は火山性であり、どの地形にも一定の火山活動が見られるが、このジャングルは火山に絡みつき、そこから栄養を得ているかのようだ。
地元のドルイドたちがこのような場所で生活できていることには驚愕させられる。私の飽くなき好奇心がもう少しで破滅を招くところだった。この危険な地域を住処とするあるドルイドの集落を見つけようとしたのだが、その途中で私は何かを見た。生涯を終えるまで私の記憶に付きまとうだろう。あれは蔓で作られた怪物だった。棍棒を持っており、光る眼で私を見た。あの眼は私の魂を燃やした。よそ者に対する憎しみは明らかだった。私は侵略者であり、縄張りを守ろうとしたのだ。耳をつんざくような金切り声をあげ、あの体格の獣にはありえない素早さで私に接近してきた。私は逃げた。もうあの場所には二度と戻らない。決して!
ガレンへの旅:ある学者の旅Journeys In Galen: A Scholar’s Travels
ジャン・デュシール 著
15日目
私の想いはしばしば大切なフィアンセへと向かう。彼女が分厚い毛布を屋根裏部屋から持ってきて、それにくるまって暖まる姿を思い描く。この旅は執筆中の地域の幽霊についての論文のために欠かせないものとなるだろう。間違いない。だがたとえ一日でも、彼女のそばにいられないのは辛い。
17日目
なんとかある程度の成果を得た。ブレトンはどこに旅をしても、木の霊魂の物語を話す。
論文のための文章:「祖母や宿屋にいる民、鍛冶屋に聞けば、闇の中に光る目の物語を聞かせてくれるだろう」
ガレンのドルイドたちは、闇の中の目を味方につけたらしいことがわかった。彼らによれば、緑がある場所の自然を自分たちの心に受け入れる方法を教えたという。彼らは目を「ドレイフーン」と呼ぶが、酒場やヴァスティルの市場にいた者たちは全員別の名称で呼んでいた。フォレストレイスだ。
18日目
大発見だ。ガレンの奥地を歩くだけでは、木で出来たあの怪物に出会う可能性が低いと人々は言っていた。だが強力なシストレスの酒を集中的に用いることにより、フォレストレイスを生み出す方法がいくつかあるらしいとわかった。
酒場の友人から聞いた話は、我らがグレナンブラの怪談とそっくり同じだった。
論文のための文章:「森で迷子になったある旅人が視界から消える。ドルイドたちは死者の魂を物言わぬ歩哨へ変え、彼らの古代の森を巡回させる。その恐るべき叫び声に注意せよ!」
さらに魅惑的なことに、ドルイド信仰の何らかの宗派が、「緑に服従する」ためのある儀式を記録しているらしい。このドルイドたちは野性の霊魂を自分たちの体に入らせ、レイスに変身するのだという。これは危機的な状況においてのみ行われるとのことだが、真実性には疑問が残る。
19日目
案内人と契約して、グリマーターンと呼ばれるドルイド居留地まで連れていってもらうことにした。そこではフォレストレイスの秘密の一部が、古代ドルイドの石板に保存されているらしい。この若い女性の案内人とちょっと会話しただけでも、すでに極めて興味深い話が聞けた。彼女によればレイスはドルイド王カソレインの逝去後の時期に生み出されたもので、オールウィザーと呼ばれる何かと関係しているのではないかという。不思議な話だが、調べてみる価値はありそうだ。
20日目
この森の幽霊についての真実を明らかにするのはやはり難しい。しばらくはここに留まることになるかもしれない。我が愛する人にメモを送って、ブーツの餌やりなどを頼もう。運が良ければ、キナレスの風が遠からず私を彼女の下へ連れ戻してくれるだろう。
ガレン観光案内Visitor’s Guide to Galen
エミッセ・フェアウィンド卿 著
沈む太陽のごとく美しいガレン島は、シストレス諸島の隠された宝石である。本土からの多くの訪問者はハイ・アイルより先に進まない。しかしちょっとした船旅を厭わないのなら、真の意味で忘れがたい経験によって報われるだろう。ガレンの野生の沿岸と木々の生い茂った峡谷の美しさは他で見られない。さらにこの島の自然の驚異を探検している間、神秘的なガレンのドルイドに出会えるかもしれない!
この島への訪問は古く趣のあるヴァスティル港から始まる。ここはガレンへ向かうほぼすべての船の目的地である。この街はドルイドの集落があった場所に築かれており、蔓地区や街の他の部分には今でもこの古代の村落の名残を見ることができる。ここでは最初のドルイドたちに会えるだろう。街のこの地区にいる商人や職人の多くはドルイドの信仰に従っており、旅人の好奇心にもよく順応している。
街の中央付近にある酒場〈うんざりしたオルナウグ〉は素晴らしい宿だ。燻された垂木と古い旗のある魅力的な部屋には、現地の民と船乗りが集まり活気に満ちている。それ以外にもヴァスティルで必見の場所として、港を見下ろせる美しい夜の大聖堂や、街から北の高地にある雄大なモーナード城がある。ここはガレンの管理者であるレオナード・モーナード伯爵が宮廷を開く場所である。
もちろん、ガレンまで旅をしてヴァスティルの市内に留まる者はいない。旅の疲れを癒した後は、ガイドを雇って島の残りの部分を見に行こう!
ヴァスティルの西門から北に向かい、道を進んでガレン内陸への探検を始めよう。島の中心部にある大峡谷を見下ろす吹きさらしの高い崖にそびえるのが、古代ドルイドの記念碑「伝達の石」である。この地域の伝説によれば、この石は最後のドルイド王によって立てられたもので、王の予言的な夢を保存しているという。だが眺めを見るだけでも訪ねてゆく価値はあるだろう。
伝達の石から北西に旅を続け、人里離れた壮大な西岸に向かおう。ここでは絵画のように美しいトネール城の廃墟がある。これは数百年も前に放棄された金貨男爵の居城である。ガレンの石はそれぞれに固有の物語があり、この城の廃墟も同様だ。トネールの物語はドルイド・サークルにとって神聖な地に家を立てた誇り高い王と、後に彼へ訪れたドルイドの血なまぐさい復讐の恐るべき物語である。実に興味深い!
トネール城から北に旅を続けると、北ガレンの美しい野生の丘に入っていく。ドルイドの村グリマーターンは素敵な山中の湖と、ガレンで最も標高の高い山のふもとに位置する滝に囲まれている。友好的なストーンロア・サークルのドルイドたちが住むグリマーターンは、本場ガレンにおけるドルイド文化の優れた見本を提供している…とはいえ、景色のためだけでもここは見逃せない場所である!
グリマーターンから南東へ向かうと、アメノス海峡とガレン東岸へ着く。見る者を驚かせるアイビーヘイム峡谷には絵に描いたような美しい遺跡がいくつもあり、その中には多くの立石もある。しかしこの地域で出会う可能性のあるドルイドは、グリマーターンのドルイドのように友好的ではない。アイビーヘイムは神聖な地であり、観光客は歓迎されない。さらに南下して、眺めのいいサンクレフト入江に向かうことをお勧めする。この海に面した崖の内部にある洞窟はとても美しく、訪ねてゆく価値は十分にあるだろう。
サンクレフト入江から南には、ドルイドの村トゥイニュがあるが、この一帯は避けたほうが無難である。トゥイニュは孤立を好みよそ者を嫌うエルダータイド・サークルに属しているからだ。岬沿いに伸びている道から外れないようにして、ウィンドラック・ポイントの古い砦へ歩を進めよう。ここからはガレン東に位置する火山島イフェロンを一望できる。ファイアソング山も見えるかもしれない!イフェロンの火山は日中、頻繁に煙を吐き出し、夜には暖炉のごとく明かりを放つ。
旅の最後に、ガレンの南岸沿いを西に進もう。こうしてヴァスティルの街を囲み、島の食料供給を担っている耕作地や住宅地に戻ってくることができる。遠からず、ヴァスティル東の丘の下を流れるガレン入江に到着する。この入江は海に出る船が航海するには浅すぎるが、釣りに最適であり、暖かい日には地元の人々が集まってくる。古代のドルイドが丘の下に掘ったトンネルを通り、ヴァスティルの東門から街に戻ろう。
おめでとう、読者よ!島を一巡りした今、あなたはドルイドの島、ガレンを探索したと豪語できる、希少かつ大胆な旅人の仲間入りを果たしたのだ!
キコの謎かけKiko’s Riddles
この半分は掘られた空き地の、絡まった根の影の下に眠る。火の流れが木を切り、見る者の家の南を通る
第二の欠片は手の届くところにある。西の岸から風と難破の浜辺の間。職人は鋤を手にして近づき、大釜を見て砂を返せ。
キコの最後の謎かけKiko’s Final Riddle
歌い手の道の太陽で温められた側が、宝の場所だ。船に闇のランターンを吊るし、すべての目から船を包み隠せ!
グリマーターン:ストーンロアのコミュニティGlimmertarn: A Stonelore Community
マノン・ロレイン 著
私がガレン最大のドルイド居留地グリマーターンを歩き回る許可を求めた時、ストーンロアのドルイドたちは快諾してくれた。この辺りにドルイド以外の者は少なく、この報告を読んだ者にもここへ行くことはあまり勧められない。言葉にできないほど美しい場所だが、ここは彼らの故郷であり、ドルイドの生活を体験しようと望む者のためのリゾート地ではない。
私はグリマーターンを美しい風景の断面だと考えている。十分に遠くから見れば、この牧歌的な村を構成する二つの明確に区別される色があることがわかる。底の部分から始めよう。ここには丘の中腹を貫いて流れる、渦のような小川の豊かな青がある。水は雲にまで登っているかのように見える、強大な滝から押し出されている。目を上に動かすと見えてくる第二の層は、よく茂った緑に包まれた景色である。グリマーターンはドルイドの村である以上、当然のごとく自然美に敬意を払っている。明るい木々の葉、活気ある植物、エメラルド色に輝く根の堆積が、グリマーターンの主要地区の大半を覆っている。木々はドルイドが集まる場所の大部分に守護者のごとく立っており、まるで記憶の中で永遠に根を下ろした、昔のドルイドがそこにいるかのようだ。
ガレンの豊かな野性の中に根づいているだけでなく、グリマーターンはいくつか石の建物を擁している。それらは時間の経過によって損傷しているが、真に見る価値のある建物だ。曲がりくねった階段、崖の表面へ綺麗に削りだされたトンネル、流れ続ける滝や岩だらけの断崖などだ。グリマーターンの建物は伸ばされた手のように広がり、自然の風景の中に織り込まれている。
グリマーターンには一種の階級が存在するという話を聞いた。階級という言葉は、ドルイドの生き方に慣れていない我々とは大きく違うものを意味している。富の大きさや生まれが問題ではなく、ドルイドの肩書きは獲得されるものである。志願者は見習いのドルイドであり、新しく、しばしば(常にではないが)若いドルイドである。彼らは最も経験の浅いドルイドだ。その次の地位は入門者であり、少し経験を積んでいるが、最後のドルイドの試練を通過していない者たちである。私はグリマーターンに滞在中、そうした神聖な試練をいくつか見学する機会を得た。ただし近くからではなく、かなり遠くからである。どんな試練が行われていたかはともかく、美しい光景だった。入門者が試練を通過すれば、正式にドルイドになることができる。これがグリマーターンの人口の大半を構成している。そしてもちろんアークドルイド、すなわちマスタードルイドが、基本的にコミュニティを率いている。
他のドルイド・サークルの居留地も同じような肩書きを用いて、類似の美しさを誇っていると考えていいだろう。しかし私には自分の目で見たものを書き記すことしかできない。グリマーターンは文化と美、歴史に満ち溢れた場所である。親愛なる読者のためにもっとうまく説明できないことが悔やまれる。とにかく、あなたがこれまでの人生の大半を街で過ごしてきたのなら、私の記述が新しい視点を開いてくれることを願っている。
シーエルフって何?Who Are the Sea Elves?
不明なブレトンの子供によって書かれたもの
シーエルフって何?お母さんは悪いやつだと言っていたけど、ちょっとおかしな名前だと思う。マオマーだって。妹が言おうとしたら、モー!オー!マー!っていう音になった。お母さんは僕たちがこのことを話すと嫌がるけど、お父さんは夜遅くになるとたまに物語を聞かせてくれる。
お父さんはシーエルフが大きな海の蛇に乗ること、オルグヌムという大きな怖い王様がいることを話してくれる!お父さんはその王が不死身だって言ってたけど、そんなことありえないよね?不死身じゃなくても怖そうだった。
シーエルフは怖い。お父さんの話にはたくさん血が出てくる。海の戦いも!妹は物語が怖すぎて、わんわん泣いてしまうこともある。お母さんはそういう時腹を立てる。シーエルフのことなんか話さないほうがいいし、知らないほうがいいって。でも、そんなこと言われたら余計知りたくなるじゃないか!
シーエルフって本当に何なんだろう?どんな音楽が好きなんだろう?僕や妹みたいな子供がいるんだろうか?シーエルフの船には玩具があるんだろうか。玩具がなかったらとても退屈だろう。
シーエルフは僕たちと同じものを食べるのかな?自分たちが乗る海蛇に名前を付けるのかな?僕だったら自分のにはダーセルと名づけよう。
シーエルフに聞けたらいいのに。手紙を書いて送ろうかな。シーエルフは手紙を書くのかな?船の上で手紙を受け取れるんだろうか?シーエルフに手紙を書こうとしたら、お母さんは怒るだろうけど、気になって仕方がない。シーエルフの肌は本当に青なの?きっと綺麗だろう。全員が悪人なのかな。優しい人もいるんじゃないかな。
シーロード・ナロスからの命令Orders from Sealord Nalos
ドレッドセイル艦隊の船長
船員を集合させ、ヴァスティルの街を大艦隊で襲撃する準備をせよ。捕虜たちは目立った弱点を明かしていないが、我々の数なら防衛部隊が反撃を展開する前に街を制圧できるだろう。
ファイアソング・サークルの援護には期待するな。アークドルイド・オルレイスはドルイド議会で我々が協力したことへの返礼として力を貸すと約束したが、あの女は我々の襲撃前にストーンロアの種を探したいと言っている。俺は待ちたくないし、正直言ってあの女は信用できない。
シーロード・ナロス
シストレスのワインWines of the Systres
ワインとスピリッツの愛好家にして地域情報の専門家メリニー・アグナンによる、シストレス諸島のすべての島において最も豪勢かつ独自色豊かなワインについての解説
ハイ・アイル
ハイ・アイルの気候と等級は、素晴らしいワインを発見するのにとても適している。私はハイ・アイルで低品質のワインを飲んだことがないが、以下に記すワインを探すことを勧める。これらは特に独特なワインなので、諸島を回る旅の価値を大いに高めてくれるだろう。
リーダーズライズ・レッドブレンド
ハイ・アイルで支配的な名家たちによる提携の成果であるこのレッドワインブレンドは、モーナード家のブドウ園のブドウを使い、デュフォート家の職人によって製作された樽で熟成される。このビンテージの創造は、二つの貴族の家の友好の時代を象徴するものだった。このワインは深みのあるボディと微かな温かみを持ち、夏のワインとして完璧である。デュフォート家の賓客はしばしば、ハイ・アイルのひまわり畑を見学中にこのワインを供される。
アルバトロス・カベルネ
アルバトロス騎士団の団員であるルドヴェル・ガマシェ卿は、キャンプファイアを囲んで伝説を語り聞かせる際のお供に完璧なワインを生み出した時、伝説の騎士の地位を獲得した。このワインの豊潤な風味は飲む者を香り豊かな冒険へ連れだし、騎士を目指す者は冒険の味を心に刻みつけるため、このワインをワインスキンに入れて旅に出ることで知られている。
デュフォート・シンギュラーアンバー
デュフォート家によって開発された、希少なスペシャルブレンド。ピーチやチェリーなどに由来するまろやかな舌触りと紅茶のような風味に、甘くならないハチミツが垂らされる。第二紀571年のビンテージは最も人気が高く、市場にほとんど残っていない。その年のボトルを見つけたなら、強くお勧めしよう!
揺るぎなき者のシャルドネ
揺るぎなき邸宅で、バカロ卿の慈善パーティーのために開発された。この単体で飲むためのワインは非常な人気を博したので、シストレス諸島中の宿屋に複数の樽が輸送された。驚異的にバランスの取れた味と、豊かな黄金の色合いを実現したことで知られている。
ガレン
ガレンに足を踏み入れるハイロックやシヴァリング・アイルズの貴族は少ないが、この島はそれでも素晴らしいワインを生産する。
ストーンロア・ゴラップルミード
シストレス諸島中で、ドルイドは数えきれないほどの年月、あらゆる種類の果実やベリーをフレーバーにしてワインやミードを作ってきた。しかしガレンにおいて、ストーンロア・ドルイドの強力なゴラップルミードはドルイド以外の住民の間でも人気がある。噂によるとエルダータイドのケルプミードのレシピが存在し、それはさらに美味であるとされているが、これを味わったことのあるブレトンは存在しないため、ゴラップルミードと比較することはできない。
モーナード・レッド
この濃厚なワインを味わうのは、もはやヴァスティルだけではない!モーナード家のワイン業者は芳醇で味わい深いワインを開発し、常に進化を続けている。この進化の理由はステファン・モーナードにあるとも言われている。彼はドルイドと親交が深く、モーナードのぶどう園はおかげで不当な有利を得ているとのことだ。ここまで美味しいワインができるなら、そんなことを誰が気にするだろう?
アメノス
アメノスのワインについては、できるだけ言及しない方がいい。
イフェロン
私自身は以下に記すワインのどちらも味わったことがない。ドルイドを除いて、イフェロンに足を踏み入れた者はごく少数だからだ。とはいえ、私は何人かのドルイドに話を聞く機会を得た。彼らはファイアソング山のふもとで育つぶどうのワインが極めて独特であるという点で意見の一致を見ている。
スモークスパイス・ブランデー
ワインや古い樽から蒸留された、この濃厚なアルコール飲料は煤のように黒く、加えられたスパイスによって深く豊潤な風味を得たらしい。その複雑性を理解するには、味わって飲むしかない。
アッシュ・ホワイト
煙と灰をファイアソングは歓迎している。この蒸留に使われる穀物は蒸留する前に自然に燻され、濾過され瓶に詰められる前に、島の火山の裂け目によって長く樽で熱せられるという。味は豊潤で深く、煙の匂いがするようにも思われる。賛否は分かれるかもしれないが、とても個性が強い。
シストレスの歴史:ヴァスティルSystres History: Vastyr
グウィリム大学上級講師、ヴァロナ・ヴェドラル 著
集落はドルイド王カソレインの時代以来、ガレン南端の海辺に位置している。丸石が密集した近代都市ヴァスティルの地下で行われた採掘により、ドルイドのトンネルや古代の掘っ立て小屋、ドラオイフェの儀式場、シニストラルの戦争野営地、ソードシンガーの試合場、さらにはスロードのスライム飼育場の明らかな痕跡まで見つかっている。
今日の我々が知っているこの街は、諸島最北の島の宝石のような海辺に、ほんの最近付け加えられたものだ。ゴンファローネ湾は男爵提督オロによる船舶建造の中心地としての名誉を(正当にも!)得ているが、ガレンの広大な密林は、全旗海軍の船大工たちにとって無視できない魅力を放つ宝の山だった。
何世紀も本土からの統治を受けたことで、ハイ・アイルではゴンファローネ湾の北岸から、平民が雑木林を管理する伝統的なシステムが出来上がっていた。それに対して、ガレンはドルイドのサークルたちが何世紀も費やしてその聖地としての威厳を保っていたため、実質的に手つかずの原野であった。第一紀2240年頃、男爵提督ベンドゥ・オロとその部下たちは船舶建造にさらなる力を入れた。スラスへの襲撃に備えるため、ガレンの緑野とドルイドたちが艦隊の成功に不可欠だと確信していたのだ。物資はあらゆる港から本土に届けられていたが、ガレンにある未開発の資源は無視できるものではなかった。
フォルヴス・ネルヴィロの覚え書きには、「提督のブーツは泥に浸かり、残った我々は波に乗った。ドルイドの評議会には使者を送っていたが、砂を歩く間、浜辺には誰もいなかった。彼が振り返ったので、松明の光の下でにやけた自信のありそうな顔が見えた。船長は向き直り、立ち尽くして待った。一晩中待ったように思えていたが、突然浜辺の反対側で焚火が灯された。ドルイドが来たのだ。三つのサークルが全て、数百のドルイドがいた。指導者は交渉に来たのだが、オロが勝ったことはもうわかっていた」と記されている。
全旗海軍の港と造船所として機能していた初期の時代以来、ヴァスティルではブレトンとドルイド文化が混ざりあっていた。この街は常に立石の群と八大神を崇拝するための空間が同居しており、真の道についての繊細な議論は、港沿いの酒場でも、貴族のゴシップや詩人の歌の中でもさかんに取り交わされていた。
ヴァスティルが本当の意味で自立したのは第二紀初期、モーナード家の財産が増大を始めた頃だった。中傷と賄賂、暴力によりファネ・モーナードはシストレス諸島の地方統治官の地位に上り詰めた。この一族の主な関心はハイ・アイルの豪邸やアメノスでの採掘事業だったが、一族の中の多くの者は、ファネの母ドロナのおかげで、ドルイド文化との強い結びつきを感じていた。
ドロナはウィルドと緑に深いつながりを持っていたと言われており、家族に対してドルイドのためにも一族のためにも、ヴァスティルに投資するべきだと力説したのである。
モーナードの金貨の価値が証明されたのは、数百年後に「群れる嵐」が街を襲撃した後のことである。帝国の凋落はタムリエル中に混沌を生み出した。シストレス人たちはタムリエルの民にも劣らぬ苦境にあえいだ。支配者になろうと目論む者や、王を僭称する者たちが百年の間に六度も諸島を襲撃したからである。第二紀365年におけるヴァスティルの陥落は、この島の歴史の中で最も凄惨な瞬間の一つだった。街の半分が破壊され、市民の大半は野へ追われ散り散りになった。
後のルッフェ・モーナード公爵は独裁を非難されたが、彼の祖先は再建者にして新たなヴァスティルの守護者であるとして尊敬を集めた。ベルニクは攻囲の後何十年もの間「街の母」として知られるようになった。モーナードの各領地から流れる金貨と支援物資により、街が立ち直り、世界の中に新たな地位を占められるようになったからである。ヴァスティル湾のどちらの終端にもある高い壁や、今では街の景色の中心となった広大な邸宅は、この時代の名残である。
ナハテン風邪とランセルの戦争という二つの災害の後、モーナード家は傷を癒し将来の計画を練るため、ヴァスティルへ退いた。この近代都市はハイ・アイルとドルイド、そして本土の文化のるつぼとなっている。世界中からやって来たアイデアが街の門から流れ込み、ドルイドの産品は街の壁を越えて海に出て、大陸中の顧客へと届けられる。
ヴァスティルはガレンの自然の端にあって、常に「文明的な」文化の足掛かりであり続けてきた。多くの世界、多くの文化、多くの約束を持つ街なのだ。
シストレスの歴史:補遺Systres History: Addendum
グウィリム大学上級講師ヴァロナ・ヴェドラルによって発見され翻訳された、あるドルイドによる文書
第一紀2484年のファイアソング山の噴火は、アメノス、ハイ・アイル、ガレンの主要な集落すべてを完全に破壊するか、居住不可能なレベルで損壊させた。今日でもシストレス諸島の学者や歴史家の多くは騎士や貴族の行いを扱っており、その後に続いた「緑の時代」についての我々の理解は、主に二次的な歴史資料を基にしたものである。
以下に記すのは、第一紀のストーンロアがいた場所の採掘により発見された複数のドルイド文書を、私ができる限り再構成して翻訳したものである。私とディーン・へラドレンに同行して諸島へ向かった学生たちには、これらの希少な断片の回収を助けてくれた功績を感謝したい。
最初の記述は、噴火が始まった直後に記されたもののようだ:
「今日はまた空から灰が降り注ぎ、(彼らの)骨の熱が、石が海と出会う場所へと流れた。私たちはまだ動ける者たちを集め、(解読不能)ができる(安全な場所)に移動した。私たちの中には、街の絹や船の革を身に着けた人々は追い返せと言う者もいたが、アークドルイドは聞き入れなかった。こうして私たちはファイアソング山の歌が下の大地を揺らせている間、できる限り多くの人々をかくまった」
2つ目の記述は噴火が弱まってから数ヶ月後に書かれたものらしい:
「ベリーは豊富だ。私たちの(真の道の魔術)により、木々の葉が戻り、茂みが実をつけることができた。これで私たちの枝の下に隠れる者たちも、島中の揺れに耐えて安全にしていられる。私たちはできる限りのことをタムリエルの民に教え、彼らもまたその返礼として私たちに教えを与えてくれた。ドルイド(判別不能な名前)はウェイレスト出身の男を夫として受け入れた。新しい親族を得て、私たちの絆は強くなった。この災害では多くが失われた。私たちは、これが種を蒔く者の予兆ではないかと恐れた。だが今日は、新しい命が灰の下から芽生えたようだ。緑よ、感謝します」
3つ目の記述は1年か2年後のものだ。この文書は経年による劣化が激しく、その意味の多くは同時代の作品に基づいた私の推測である。学術論文でこの文に言及する際は、その点を考慮してもらいたい:
「すべては(時間の無駄/嘘)だった。(よそ者?)は(諸島/イフレを尊敬)しない。彼らは私たちの贈り物を受け取っておきながら、(ドルイド・サークルの)目に唾を吐きかけるのだ。いつか夢は(実現?)し、私たちは世界の中に自分たちの居場所を獲得するだろう。そのことは石の中にも、我らの心と魂の中にも見えている」
参照のために言っておくが、ここに含まれている文書はすべて、元々は軽石とダークウッドを組み合わせた板に記録されていた。石には印が刻まれており、木にはこの地域のベリーブラッド・インクが使われていた。こうした遺物は要請に応じて大学の保管庫で閲覧できる。
シストレスの歴史補遺:ガレンのドルイドSystres History Addendum: The Druids of Galen
グウィリム大学上級講師、ヴァロナ・ヴェドラル 著
シストレスの歴史の本文でディーン・へラドレンが論じたとおり、ドルイドは諸島についての我々の理解を形成するために決定的な役割を果たしてきた。ガレン島はハイロックから最初の離散以来、真の道の中心であり続けてきた。口承によれば、ガレンはドルイドたちが第一紀330年に初めて上陸した場所である。
脇道にそれるが、とても学問的な題「ガレンのドルイド」は、この一般に真理とされる出来事に由来するのだろう。自分も歴史的先入観の罠に陥ったことがある学者として、このことを記すのは単にいきさつを説明するためである。
ガレン初期の時代がどのようなものだったか想像するのは難しい。ディレニに支配された本土での生活とは劇的な対照をなす、美しく感動的な体験だったことは疑いない。ついに自らの信仰を追及する自由を得て、緑の限りない優しさを与えられた最初のドルイド使節たちは、この島を楽園へ作り変えた。多くの伝説的な力の場や、深い森をさまよう独特な獣たちが現れたのは、ドルイド移住の初期の時代だった。
最後のドルイド王カソレインは、この時期の安定と成長の立役者であった。現代の記述ではドルイド王が観想的な立場の存在とされ、信者たちを遠くから見守り、どうしても必要な時を除いて介入しなかったと言われる。しかしそれでも、王は魔術と世俗の資源を大量に費やし、ドルイドたちの新たな故郷を補強した。キメラやフォレストレイス、その他のガレンの古代の石にまつわる奇妙な現象についての現代の記述を読むだけでも、そのことは明らかだろう。
ドルイド王の死は謎に満ちており、単に王は引退してシストレスの奥地に退いたと述べている記述もある。そうした記述によれば、ドルイド王は穏やかに逝去し、民には変わらず称賛され崇拝されたが、民から離れ私的な生活にいそしむことを許されていた。別の記述では、何か暴力的で忌まわしいことが王の支配を突然終わらせたことになっている。大挙してハイロックに帰還し、かつての圧制者を打ち倒すよう扇動したドルイドがいたのだろうか?文書の記録は少なく、口伝には対立する内容が多いため、確実なことは永遠にわからないかもしれない。
ドルイド王の死に続く数世紀の間、深き森は不可侵の領域だった。第一紀660年のシニストラルの襲撃は当時の物理的な記録の多くを破壊したが、ドルイドたち自身はその多くがいわゆる「レフトハンド・エルフ」の侵略を生き延びたようである。ガレンの奥地に退くことで、カソレインの子たちは侵略者に対して強力な防衛線を張ることができた。
ディーン・へラドレンは第一紀668年のファイアソング山の噴火が、何らかの仕方でレッドマウンテンの災害と関係していると示唆するが、私はドルイドたち自身がイフェロンの火山を活性化させたかもしれない証拠を見つけている。確かに爆発の際はドルイドたちも死んだが、ガレンの中心である彼らの聖地はほぼ無事だった。それが偶然ではなかったことを示す証拠は豊富にある。
ドルイドの統治評議会であるドラオイフェは、何世紀も後の全旗海軍の形成へ公的に参加することはなかったが、私はドルイドたちが海軍と船に乗ったことを示す当時の記述を複数発見した。彼らはスラスへの旅路で天候を鎮め、道案内をする役割を担ったが、大陸を沈没させるにも一定の役割を果たした可能性がある。とはいえ、それは残された乏しい資料に基づいた、私の単なる推測であることは断っておかなければならない。しかし明らかなのは、海軍の負傷者たちが男爵提督オロの帰還に際して、ドルイドの癒し手たちによる大規模な治療を受けたことである。
ドルイドの信仰とその治癒の能力は、第一紀の終わり近くに二度目のファイアソング山の噴火が起きた時、再び注目を集めた。残された地域の貴族と本土の公爵たちはシストレスの平民が飢え死にしても何とも思わなかったが、ファイアソングとエルダータイド、そしてとりわけストーンロアのサークルたちは島中に人員を展開させた。彼らは火山から飛び散った炎を消し、家を失った者のために避難所を築き、火傷を治療し、避難民たちを養うための新たな作物を育てた。
「ヴェイルテ」、「ドライ」、「ゲイテ」といったドルイドの言葉がシストレスの民の間で一般的に用いられるようになったのは、「緑の時代」として広く知られる、歴史のこの時期に由来している。これはドルイド史の中で最も活発で、協力的な時期の一つを印づけるものであり、真の道のすべての成員が自らの聖地と深き森を離れ、友人や隣人、家族たちの生存を助けた。
こうして我々は最近の歴史に行き着く。シストレス諸島の所有権がグイマルド家から、様々に姿を変えた帝国、ブレトンの金貨男爵、モーナード家へと移り変わり、現在のダガーフォール・カバナントとデュフォート家による半独立の状態へと、終わりなき変遷を遂げた時期である。これらの変化の間ずっと、ガレンのドルイドたちは古代の伝統を維持し、遠く離れた地にある黄金の会計事務所で文書が交わされたことなどほとんど気づきもしなかった。諸島を管理する貴族の大半はドラオイフェに評議会を開かせておくのを妥当とみなし、必要な時を除いて介入しなかった。特に部分的な汚名を被ったモーナード家には、ドルイド・サークルを認容してきた長い歴史がある。
実際のところ、どちらのグループもガレン島の二重の物語を象徴している。片足はしっかりと過去に根ざし、もう片足は不確定な未来の砂地を踏みしめている。
しなやかな妖精A Lissome Sprite
ガレンの詩人、ニネル・ドゥマリス 作
しなやかな妖精の軽やかな笑い声が
見守る木々を通り抜けてさまよい
秘密の喜びをたたえて、石と小川に口づけをする
それは他の者に見えぬ愛の触れあい
麗しき緑の丘の向こう、立石が
遠い昔の聖なるドルイドの夢を覚えている
この陽気な妖精は、誰にも見られずアイビーヘイムの
玉座に姿を現し、海辺に留まる
陽気な妖精の笑い声が私を呼ぶ
日々の仕事への没頭から引き出されて
私は作業を止め、自由に踊る
太陽に浸された峡谷の、聖なる霧の中で
私はガレンを歩く、独りで
森や丘、海への想いだけを胸に抱えながら
タムリエルの城への案内A Travel Guide to Tamriel Castles
アスティニア・イサウリクス 著
私がここに大いなる喜びをもってお届けするのは、旅へのはなむけであり、探検への誘いであり、普段の生活から抜け出て世界を見ることへの気軽な招きである。これはタムリエル全土の独自で恐ろしく、血と栄光に浸った主な城十選を論評したものだ。私は旅の間に、これらの魅惑的な建物であなたと出会えるかもしれない!
ウェイレスト城
おそらくタムリエルで最も有名なウェイレスト城は、第一紀の初期からストームヘヴンの中心地、すなわちブレトンの中心地に立っている。この城の最大の特徴は、街だけでなくその先の地方までも見通せる巨大な尖塔である。ガードナー家によって建設されたこの城は古典的な石造の砦として、以降数百年の間、貴族たちの家屋の基準を決定してきた。
モーナード城
シストレス諸島最北の島の街、ヴァスティルの深水港を見下ろし、広大な複数の棟を有するモーナード家の城塞は、この街の心臓であり魂であると言えるだろう。ある意味で、モーナード城こそがヴァスティルなのだ。「群れる嵐」による第一紀365年の攻囲の後、急遽再建されて出来上がったこの城は、「ヴァスティルの母」と言われたベルニク・モーナードにふさわしい記念碑でもある。彼女の遺産は広大な石壁のカーテンと、海側の丈夫な防波堤の中で存続している。
ソーン城
ソーン家の奇妙な伝統については噂が絶えないが、祖先からの家の壮麗さは否定しがたい。中央には巨大な尖塔がハーフィンガル山脈のふもとから突き出し、その同心円状の壁には、それぞれミナレットが添えられている。私は信頼できる情報筋から、一族が城の公共の空間の見学を許可しているが、朝限定であると聞いている。だから早い時間に訪れて欲しい。
アリノール宮殿
サマーセットのハイエルフには息をのむような古代建築の伝統があり、アリノール宮殿は数千年の時を遡る王族の系列を代表する。この城は複数の大きく風通しのよい部屋を基礎とし、その上に空高く伸びる尖塔が築かれている。実はそもそもこの本を書くアイデアを私に与えたのは、アルドマー評議室の巨大な窓壁だった。
エボンハート城
エボンハートの街の中心部にある城は美しくも恐ろしい古い石の建物であり、アッシュマウンテンのふもとで狩りをするクリフ・レーサーのように鎮座している。ダークエルフの宗教的恍惚とトリビュナルへの崇拝は、訪問者を困惑させるような建築上の選択を生んでいるが、その結果作られた三重尖塔の、古風ではあるが雄大な輝きは誰もが認めるだろう。
スカープ砦
オルシニウム砦とも呼ばれるこの広大な石の建物は、オーク王の権力の座である。今では廃墟となった古代都市、旧オルシニウム中心部の王宮を元として作られたこの近代建築物は、昼夜を問わず炎の輝きと笑い声、そして饗宴に満たされている。洞窟のような大広間に足を踏み入れ、この広大な空間を挟み込む巨大な石の柱を見上げる時に感じる畏敬の念は、決して忘れられないだろう。
ナヴィール城
遠く離れたハイ・アイルに立つナヴィール城から無秩序に広がる大地は、ほとんど目を疑うほどである。緑豊かな野生の花畑が、ドルイドによって世話された古代の森へと続いている。城自体は古典的なブレトン風の驚くべき建物であり、デュフォート家が居住している。私は年に二度行われるサファイアトーナメントの最中に訪れることができたが、騎士のチャンピオンに観客が送る声援の轟きを聞くことほど、血をたぎらせるものはない。
レイヴンウォッチ城
リベンスパイアー北の山脈のふもとにそびえるレイヴンウォッチ城は、このリストに載っている他の場所の壮大さに比べると、少々控えめなように見えるかもしれない。それは間違いだ!このブレトン建築の古典的な代表作は保存状態が完璧で、レイヴンウォッチ家の者たちはこの歴史的価値の高い建物を見学する際に、素晴らしいもてなしを提供してくれる。特に、城の地面の下を通る洞窟のような霊廟を探検することを勧める。
レヤウィン城
タムリエルの古代の建造の中から一番のお気に入りを選ばなければならないとしたら、私はレヤウィン城を選ぶだろう。ブラックウッドの入口にそびえるこの美しいインペリアルの建物は、壮麗な城に求めるすべてのものを備えている。頑強な円形の塔、空高くまで伸びる大広間、四方八方に広がり、街を見下ろす主砦まで通じている廊下。見事だ。このニベン下流の宝石に行く機会があったら、ぜひとも逃さないように!
ブルー・パレス
西スカイリム、ソリチュードの中心から大きなアーチを広げるブルー・パレスは、この大陸で最も独自の建物かもしれない。訪問者はとてつもない大きさの外壁を越え、広大な階段が二つある印象深い入口の間に入る。この豪勢な城は、この地域のノルドの荒々しい評判にはそぐわないように思える。しかし実際のところ、この美しさは見せかけにすぎない。ブルー・パレスは最も苛烈な攻囲にも耐えられるようになっており、帝国式の舞踏会場では貴族の美を示しつつも、戦争への備えを万全にした砦である。
以上だ!親愛なる読者たちよ、この本があなたの出発点から目的地へと向かう長旅の、ささやかな楽しみとなってくれれば幸いである。街道から離れないように。そして、キナレスがあなたの旅の無事を保証することを祈ろう!
ドルイド・セナの最後の記録Druid Senna’s Last Account
ファイアソングは私たちを殺しに来た。これはドルイド・セナの最後の記録になるかもしれない。私の最高の作品ではないかもしれないけど、死の手紙に多くは望めない。
ファイアソングが襲ってきた時、私はとっさの反応で、哀れな友人や家族と同じ運命を避けられた。私は彼らの命が消されるのを、岩陰に隠れながら見ていた。ファイアソングは私の隠れている場所にじわじわと近づいてきた。武器を抜き、炎を高く掲げて。だがとても奇妙なことが起きた。
私たちも皆知っている霊魂の塵が、谷間を越えて分厚い幕のようになって降りてきたのだ。塵はファイアソングに落ちかかり、彼らの姿は霧に包まれた影と化した。ごく短い間苦悶の声が響いた後、彼らの武器はそばに落ちた。床に倒れて深い眠りについたのかと思ったが、彼らは滝に向かって歩いていき、視界から消えた。その後彼らがどうなったのかは知らないが、不気味だった。
塵は私を囲んでおり、動物たちもそこら中を徘徊している。私は生き延びられないかもしれないが、この記録は残したい。誰かに起きたことを伝えたい。クロニクルを守らなければ。クロニクルは私たちが何者かを教えてくれるのだから。
ドルイドたちの脱出Exodus of the Druids
ストーンロア・サークルのドルイド・ローレル 著
ドルイドの教団はハイロックで生まれ、その地を愛したが、ハイロックでの生活は最終的に彼らへ耐え難いものとなった。イフレを崇拝するドルイドは第一紀330年にハイロックを去ったが、それが徐々に敵意を増すディレニ王朝に追われた結果なのか、ドルイドたちが自ら出て行ったのかは不明である。私の調査によれば、動機はどうあれドルイド王カソレインが移住の旅を計画し、ドルイドたちに船を育てさせ、それによってついに本土から脱出できたようだ。
ドルイドの伝説や口承が伝えるところによると、この海に浮かぶ船はイフレと緑による特別な贈り物であり、夢の中でドルイド王に与えられたものである。王はドルイドたちにこの船を生み出す歌を教えた。その歌はハイロックの植物や木々を、正確に決められた大きさに成長させられたのだ。残念ながら、この船を作る秘密は時の流れによって失われてしまった。
今存在する三つのサークルに分かれる以前、ドルイドの本来の共同体はどれほどの大きさだったのだろうか?私には推測しかできない。真の道を信奉する者は百万ほどもいたと主張する長老もいるが、数千だとする者もいる。いずれにせよ、ドルイド王は民をディレニから逃れさせるため多数の船からなる船団を必要とし、出発する準備が整うまでこの計画を秘密にしておく方法を考えねばならなかった。残っている物語によれば、ドルイド王は成功したことになっている。最後の戦いや危機一髪の脱出はなかった。ドルイドたちはディレニに気づかれることさえなく、ある夜、ただ姿を消したようだ。
さて、タムリエル西の広い海に出航することを想像して欲しい。当時、タムリエルの民による長い航海は行われていなかったし、海辺が見えない場所を航海する船もほとんどなかった。しかしドルイドたちは新たな故郷と呼べる場所を探そうとしていた。ドルイド王によって約束された地を。伝説によれば、ドルイド王は夢とイフレの囁きによってシストレス諸島へ導かれたが、民には王が未知の海を越えて自分たちを安全に運んでくれると信じる根拠があったのだろうか?
ハンマーや釘で作られたのではなく、生やされた奇妙な船の一団が、海辺から出航していく様を思い浮かべてもらいたい。実に異様な光景だったに違いない!ドルイド王が船団をどうやって離れ離れにならないようにしたのか、完全にはわかっていない。船を導く海図のようなものを持っていたのだろうか?確実なことは永遠にわからないかもしれないが、最近の発見が示すところ、少なくとも1隻のドルイド船が諸島にたどり着けなかった。嵐やその他の障害で遭難した船がどれだけいたのかは不明だが、たどり着けなかった船が1隻あったなら、おそらくそれ以外にも沈むか遭難するか、他の原因で姿を消した船がいたと思われる。
結果として、ドルイド船団の生き残った船はシストレス諸島の海辺にたどり着いた。最終的にドルイドたちは諸島の全土に広がったが、船団が最初に上陸したのはガレンだとされている。イフレの導きで我々はこの島々にたどり着いたのだが、ここの自然は無秩序だった。ドルイド王と民は最初の季節をかけて自然に秩序を与え、この地を維持する助けとするため霊魂を召喚した。素晴らしい時代だったに違いないのだが、とても多くの情報が失われてしまっている。
私はドルイド王カソレインの時代の生活についての探索と調査を続けるつもりだ。ドルイドの失われた歴史について、さらなる解明を試みたい。
ドルイドのモノリスThe Druid Monoliths
高名な学者にしてあらゆる文化の学徒、イグナティウス・ガレヌス 著
これはシストレス諸島のドルイドの島を旅した記録である。
私は冒険を続け、ガレン島へ流れ着いた。ここの一部しか見ることができていないが、ドルイドの大きな石の記念碑がまず目についた。彫刻とエッチングでわずかに飾られているが、意味は推測するしかない。石の柱は、どんな祠や聖堂よりも強力な何かを発していた。
こうした巨大な石を装飾する時、何をすべきだろうか。最初のモノリスにあった螺旋のパターンは肥沃の象徴だと思われる。自然が循環する性質と、季節に対するドルイドの考えを示している。円と曲線は、ほとんど官能的にも思えるほどだ。
他にもエッチングとして、環のパターンで重なり合っている同心円がある。この彫刻は、発せられる力と解釈すべきだろう。属性の力と、自然の力を組み合わせればいかに強力になるかを例示している。率直に言うと、この簡素だが意義深いデザインに秘められた情報には驚かされる。
疑問に思っていることはある。刻まれ飾られたこうした巨大な石には、メッセージが含まれているのだろうか?それとも単に美学の問題で、見たものに喜びを与えようとしているだけか?宗教的意義があるのか?話したがるドルイドを探し、強力なモノリスの意味を説明してもらわねばならない!
何人かのドルイドが、私のモノリスに対する意見を聞いてくれた。その視線からは多くのことが読み取れた。会話はかわされなかった。彼らは首を振るだけで、私が熟考するに任せた。
ドルイドがここで作りだしたのは、何とも際立って魅力的な文化だ。
ドルイドの葬式:イフレの断片Druid Funerals: A Piece of Y’ffre
エルデンルートのアレネス 著
シストレス諸島に住むドルイドがいるという話を最初に聞いた時、私は彼らに会わなくてはならないと思った。タムリエル中の他の民も私たちと同じように木々へ囲まれて生活することを好むことは知っているが、ドルイドの生き方について聞いた物語は、なぜか私の心に残っていた。最近、私はイフレから離れていると感じていた。もしかしたら、新たな視点を開くことでイフレの抱擁に戻る道を探す助けになるのではないかと思ったのだ。
ガレンへの旅は簡単だった。難しかったのはドルイドを見つけることだ。結局ある宿の主人の助けを借りて、ストーンロア・サークルのメンバーであるタイラと会うことができた。彼女は最初から親切だった。私が故郷から遠く離れて、とても居心地が悪かったことを見て取ったのかもしれない。
私は持っていたわずかな金貨を差し出して、この辺りの案内をしてもらうか、あるいは彼女の仲間たちについて話してもらおうと思った。彼女はそれを見て笑ったが、嘲る様子はなかった。ゴールドは彼女にとって使い道がないのだった。しかし彼女は、サークルの他の者たちに私を紹介すると言ってくれた。
タイラの村に入ると、大きな集まりが私の注意を引いた。彼らはいくつかの輪を作って、その中心に何かがあるようだったが、よく見えなかった。内側の輪には5人しかいなかった。その外側の輪には11人くらいだろうか。一番外の輪にはさらに多くの人がいた。儀式が行われていたのだ。私は折りの悪い時に来たのではないかとタイラに言った。
彼女は暖かく微笑んで、首を振った。長老が亡くなったので、あれはその葬式だったのだとタイラは説明した。自然死で、何も悲しむことはない。長老を失って寂しいのは確かだが、生は死と手を取り合って歩む。ありふれた感情だ。
私は葬式に出席してもいいかと尋ねた。タイラは困ったような顔を見せた。不安だったのかもしれない。彼女はガレンの外の生活についてある程度知っていたので、ドルイドの儀式を不快に思うよそ者がいることを理解していた。私は反射的に少しにやついてしまったかもしれない。ウッドエルフは外部の者を不快にさせる伝統に慣れている、と私は説明した。私が彼女に勝手な判断を押しつけることはないと。
集会に近づくと、私は言葉ではない低いハミングを聞いた。いくつかの音は重なり、輪になった人々の間を漂っていた。それはまるで森の中を吹き抜ける風のように、強くなっては弱くなっていた。
中央では、亡くなったドルイドが石板の上に裸で横たわっていたが、新鮮な枝と花びらで覆われていた。とっさに不快感を覚えたことを恥じている。彼らは生きている緑を育った場所から取り払ったのだ。だが私は自分に言い聞かせた――自分は他者の生き方を学ぶために来たのだ。私の信念を教えに来たのではない。それに、タイラには判断を押しつけないと約束したではないか。
レディンという名の女性が立ってグループに語り掛けていた。彼女は私に理解できない言語で話していたので、タイラが親切にも私のために翻訳してくれた。言葉を日記に書き記すのは失礼だと思ったので、レディンが言っていたことを私の大雑把な記憶からここに記しておく。
「死ぬのは正しいことです。死ぬとはかつて生きたということ。終わりは私たちに、いつも始まりがあることを思い出させてくれます。
歌い手は、この世界を流れている息吹で私たちを祝福することを望みました。その息吹から離れていくこと、それもまた祝福なのです。
私たちはこの世界の掟を知っています。命は命となり、それがまた命となる。だから私たちはエミルの死を受け止め、それを命へ返すことで彼を称えましょう」
という内容だった。レディンの声にはある種の確信があった。彼女はこれが物事のあり方だと知っていたのだ。
私は内側の輪のメンバーがローブからナイフを取り出すのを見た。彼らはそれぞれ、死者の体の一部分を切り取った。最初の女性は片目を、次の男性は耳を一つ。その後は、子供が足の指を1本取った。その女の子はいたずらっぽくもう一人の大人に笑いかけ、その大人も笑顔を返した。明らかに彼らの間の私的な冗談のようだった。おそらく死者の想い出と関係しているのだろう。
儀式は内側の輪が完了するまで続いた。その後は次の輪の人々が取り除く部分を選ぶ作業を始めた。私は見ていて落ち着かない気分になった。それはあまりにも親密だったからだ。死者の体から何を切り取るかという選択は明らかに、各人にとって何かを意味していた。私はとても個人的な決断を盗み見ていたのだ。
またしても、タイラは私を心配し出した。彼女は話をするために私の腕を取って連れ出した。
少しした後、彼女は庭の植物の茎を切る意味を知っているかと私に尋ねた。私は知らない理由を簡潔に説明した。彼女は多くの庭に植物を広げるための方法だと説明した。植物の一部を切り取り、新しい土に植える。うまくやれば、切った部分は根を生やし、新しい命へと育つ。
サークルの死者についても同じだと彼女は言った。当人に最も近しかった人物から始め、各人はその人個人にとって意味のある部分を選ぶ。選んだ部分は切り取って、それをどうするかは各人の自由だ。皿に乗せて外に置き、動物たちに食べさせる者もいる。木の近くの地面に埋める者もいる。あの子供は足指を乾燥させ、ペンダントとして身に着けるつもりだろうと彼女は予想した。
いずれにしても、部位は生者のもとに還る。動物は食事を得るし、木は栄養を得る。子供は祖父の想い出を抱えて笑い、森の中で遊ぶ。あの子供の選択は比較的珍しいと彼女は認めた。
それでも、サークルのメンバーは死者をどうやって自然の循環へ還すのかを自分で選択する。誰しも、歌い手への道を自分の心の中に持っているのだから…
私はそれ以来、この知恵についてずっと考えてきた。私なら自分のどの部分をイフレに捧げるだろう?もしかすると私の人生の目標は、自分のすべての部分がイフレに値するようになることなのかもしれない。
ドルイドの童話:シストレスのビーバーDruid Fables: Systres Beavers
アークドルイド・イレスによる語り 著
森の中である木が倒れ、シストレスのすべての動物が見に来ました。
それはビーバーとその連れ合いの仕業でした!まだ海水をポタポタさせながら海辺までやって来た彼らは、休む暇もなく川の隣にあった木を嚙みちぎったのです。ビーバーは確かに泳ぎがうまいことで知られていますが、ガレンに住む獣たちはずっと、わざわざアビシアンを越えてシストレスなんかに来る奴はいないだろうと思っていたのです。
「そんなに大きな音を立てる必要ある?」と鳥たちはさえずりました。
「その木を切り倒す必要はある?」とリスたちは鳴きました。
「川にダムを作る必要はあるの?」と狐は吠えました。巣が浸水したので、子狐を連れて逃げなくてはならなかったのです。
ビーバーたちはびっくりしました。「我々には皆と同じように、ここに家を作る権利がある!」と彼らは言いました。「でなきゃどうやって子供たちを食わせていくんだ?」
他の動物たちはぐうの音も出ませんでした。動物たちのほうが先にこの島に来て、この地に調和して生きてきたとはいっても、彼らは心優しかったので、せっかくここまで泳いできたビーバーたちを追いだすのは残酷だとわかっていたのです。狐は子供たちを連れて新しい巣を探し、鳥とリスは他にも住みつける木がこの島にはたくさんあると考えました。
「新しいお隣さんのために場所を空けてやらないとな」と動物たちは言いました。
時は過ぎました。シストレスに元々住んでいた動物たちはお隣さんのために場所を空けましたが、ビーバーたちは同じようにしませんでした。子供たちが成長すると、彼らは別の川で木を切り倒して自分たちの巣を作るため、出て行ってしまいました。
すると、ずっと前に出て行った二匹に何があったのか気になった他のビーバーたちがやってきました。彼らもまた森を切り崩し、どんどん大きなダムを作りました。シストレスの動物たちは、島を完全に追い出されるのではないかと心配になってきました。
するとある日、大地が揺れ始めました。ファイソング山が歌い出し、空から炎と灰が降り注ぎました。ビーバーたちの丈夫なダムでさえこの揺れには耐えられませんでした。ダムが決壊すると、強力な波が次のダムに送り出され、さらに次のダム、さらに次のダムへと続きました。かつて綺麗な水が流れていた場所に溶岩の川が流れ込み、まだビーバーたちが中にいるダムを焼き尽くし、あるいは煮えたぎる海の中に放り出しました。
生き残ったわずかなビーバーたちは、シストレスの他の動物たちに卑屈なほど親切にして残りの日々を過ごしました。でも彼らは、この諸島で最後のビーバーとなったのです。
何かを建てられるなら、いくらでも建てて構わないと思うかもしれません。でも自然の意見はいつも違います。自然が声を発するのは、時間の問題なのです。
ドルイドの童話:ファウンロードDruid Fables: Butterfly and Faun Lord
アークドルイド・イレスによる語り
昔、広大な森を支配する偉大なるファウンロードがいました。ファウンの中で一番強く大きく、誰も挑戦しようとはしませんでした。ロードは誰彼構わず、自分の力のすごさを自慢しました。ウサギは恐れ、狐は自分の草むらを踏んで通ってくる時に隠れていました。鳥でさえ、近づいてくるのを見ると木から飛び去っていきました。
ある日、ファウンロードはすべての動物を、霧の立ち込める高い山のふもとにある崖に集めました。声が動物たちの上に轟きました。
「俺はこの森で一番強い生き物だ」とファウンロードは誇り高く宣言しました。「誰も俺を倒せる奴はいない」
動物たちは全員、同意するようにうなずきました。
「俺が常にこの森を支配するんだ」とファウンロードは続けました。
別の声が割り込みました。「私も強いわよ!」
ファウンロードが振り向くと、近くに小さな蝶が浮いていました。蝶は絶えず羽をパタパタさせていました。
ファウンロードは嘲笑い、手を振って蝶々を追い払おうとしました。
「お前はこの森でも一番無力だ、消え失せろ」と王様は言いました。
「そんなことはないわ!」蝶は退きませんでした。「今すぐあなたを倒すこともできるのよ!」
何匹かの動物が笑いました。他の動物たちはその大胆さに驚きました。ファウンロードは唸り声を上げ、蹄を地面に食い込ませて蝶に向き直りました。
「ならやってみろ!ひねりつぶしてやる!」と王様は叫びました。
他の動物たちは蝶がファウンロードに向かって飛んでいくのを見て恐怖しました。ファウンロードは蝶を捕まえようとしましたが、蝶はとても素早く、羽を揺らして崖の端っこのほうへ飛んでいきました。ファウンロードは蝶を追いかけ、手を右に左に振り回してつかみ取ろうとしました。
蝶は毎回、爪をぎりぎりのところで避けました。蝶は風に乗って優雅に飛びまわり、ファウンロードをてんてこ舞いにさせました。ファウンロードはイライラして唸りました。
「こんなことで俺を倒したつもりか」とファウンロードは言いました。「単なる嫌がらせではないか!いつまで続けるつもりだ!こっちに向かってこい、虫けら!」
そこで蝶はファウンロードの鼻先に止まりました。
ファウンロードは驚いて瞬きしました。あまりに驚いたので反応できなかったのです。ファウンロードは息を吸い込み、激しいくしゃみをしました。その力がとても強かったので、崖から転げ落ちてしまいました!
蝶はファウンロードが崖から消えると同時に、何事もなく飛んで戻ってきました。動物たちは喝采をあげました。
自然は予測がつかないものです。一番小さな生き物でも巨人を倒せるのです。小さな火花が山火事を引き起こすこともあります。イフレの領域には、軽く見てよいものなどありません。強い者は決して傲慢になってはならないのです。
ドルイドの童話:誇り高きファウンDruid Fables: The Proud Faun
アークドルイド・イレスによる語り
ファウンは森で最も賢い獣でした。その蹄は素早く軽やかで、滑り落ちることも地面に足をつけることもなく、岩から岩へ飛び移ることができました。毛皮は滑らかで輝いていました。二本の角は美しく曲がり、完全な左右対称になっていました。ファウンはそういうことを全部知っていました。そして、自分の頭がいいことも知っていました。森の他の獣たちを簡単に言いくるめて、従わせられることも。そして波の上に泡が集まるように、すぐ考えをまとめられることも。
ある日、ファウンは茂みを跳ね回っている時、罠を踏んでしまいました。突然ミシッという音がして、罠が蹄に巻きつき、締めつけました。驚いたファウンは罠にかかった蹄ごと足を蹴りだし、絡まって森の地面から少し離れた位置にぶら下がってしまいました。
ファウンはもがき、力強い足で蹴りましたが、ロープはしっかり食い込んでいました。バタバタと身をよじると、ロープはファウンがとても誇りにしていた美しい巻き毛に絡みつき、引きちぎってしまいました。ファウンは宙ぶらりんになったまま、涙を懸命にこらえました。
森の動物たちの中でも一番小さく静かな蛇が、ファウンのすすり泣きの音で目を覚ましました。「ファウンさん、どうしたの?」と蛇は尋ねました。
蛇が近くにいたことに気づいていなかったファウンは、すぐ我に返りました。「別に何でもないのだ、蛇よ」。毛皮も蹄もない獣に弱みを見せるなんて、ファウンのプライドが許さなかったのです。
「空中にぶら下がっているようだけど」
「そうしたかったのだ。昼寝をしようと思ったが、地面ではゆっくり休めなかったのでね」
「足首のあたりにロープがあるけれど」
「あるに決まっている。他にどうやって自分を高く持ち上げるのだ?お前の弱い頭では理解できないだろう」
蛇はもう一度だけ尋ねてみました。「降りるのを手助けしたほうがいい?」
「助けを借りてどうなる?お前には手も蹄もないじゃないか。たとえ助けてもらおうと思っても、お前には助けられないだろう」
「そうか。それなら、私はもう行くよ」
ファウンは蛇が去っていくのを見ながら、自分のプライドと必死に戦っていました。近くに他の獣は見えないし、吊るされているおかげで目がくらみ、苦しくなっていたからです。ほとんど考えることもできませんでしたが、何かしなければなりませんでした。
「蛇よ!」ファウンは叫びました。
「何だい?」、と蛇は答えます。
「もし地面にロープの結び目が見えて、それをほどきたいのなら、我慢しなくてもいいぞ」
蛇はファウンと会った時の傲慢さを思い返しながら、意地の悪い笑みを浮かべました。「でもどうしてそんなことをするのかな?ロープの結び目をほどくなんて。あなたのお休みを邪魔したくないよ」
そして蛇はファウンから去っていきました。森で一人、空中に吊るされたままで。ちゃんと助けを求めることもできないくらい、プライドが高い自信家だったのです。
ドルイドへの不当な非難Druid Scapegoats
「嵐とひまわり」におけるドルイドへの偏見の検討
エルダータイド・サークル、ドルイド・ニヴィエンヌ 著
フィービー・パジャウドはシストレス諸島で休日を過ごす恋愛好きの読者の心に訴えるため、「事実を基にした」歴史恋愛小説を執筆した。この作品から同名の歌も生まれている。この物語の目立たないながらも否定しようのない成功は、ジャコア・デュフォートによる反論と、彼の祖先の「真実の物語」の主張を呼び起こした。この作品はフィクションであり、一度たりとも実名に言及していないにもかかわらず。興味深いことに、どちらの話でも実在するエルダータイド・サークルの名が言及されている。私がこれから論じるのはこのサークルについてである。
まず、事実を確認しよう。リゼッテ・モーナードとアルノー・デュフォートは第二紀初期にシストレスに生まれた。それは二人の一族の家系図を、ナヴィール城のトーナメントの日付と合わせれば容易に確認できる。ナヴィール城のトーナメントの記録から、リゼッテ・モーナードが確かに騎士であったこと、彼女が第二紀42年トーナメントのチャンピオンであったことがわかる。注目すべきは、物語の重要な証拠の一つが見つからない点だ。すなわち、手紙である!この恋愛の記録が隠匿されたか、破壊されたのはなぜだろうか?この点は後に検討しよう。
私はモーナード側が語る物語を聞いたことがあるが、似ているのは一族の内で語り継がれてきた点だけである。彼らの物語では、アルノーの剣に毒を塗ったのがドルイドではなく、デュフォート家の弟アンデールだった。これは一石二鳥の計画だった。高貴なるリゼッテと無能な兄を一挙に始末し、ライバルの一族を弱体化させると同時に自らの一族の中で地位を確保できるわけだ。アルノーはアメノスに送られ、そこですぐ一番高い崖を探して飛び降りた。狡猾なデュフォート家は人々に愛されたガレンの娘を堕落させ殺した、不実な悪者として描かれている。
だが、モーナード側の物語でさえ、恋人たちがドルイドの介入によって追い詰められたと主張しているのは事実だ。この点についての議論はほとんど見たことがない。あるいはジャコア・デュフォートの空想的な考えについても同様である。リゼッテ・モーナードの正体が…ドルイドなのか?魔女なのか?彼はどちらとも決めかねているようだ。いずれにせよ、この物語のそれぞれのバージョンで、ドルイドは本土のブレトンにシストレスを去るよう求める、正体不明の怪物であるという感情が込められている。
これに関する私の意見は、それの何がおかしいのか、だ。ドルイドがこの島に住んだ最初の者であることを考えれば、それほど大きな要求だろうか?確かに空想的な考えではある。だがドルイドの観点からすれば、理不尽なものではない。
また、非ドルイド文化に基づいて判断できる内容でも、この二人の悲劇の恋人たちの物語の矛盾点を明らかにできると思われる。
リゼッテとアルノーが第一子であることを考えると、一方の手で他方の嫡子が事故死したのに、この家の間で全面戦争が引き起こされなかったことになる。そんな話を本当に信じてよいだろうか?
それに二人が家系図に記されている時期に死亡したのだとすれば、彼らはどこに埋葬されたのか?
そして、最後の疑問がある。対立しているにもかかわらず、なぜ両家はドルイドが何らかの形でリゼッテとアルノーの末路に責任がある点で意見を一致させているのか?
恋人たちの観点を想像してもらいたい。公的に添い遂げる選択肢はない。シストレスから一緒に逃げることは不可能であり、ブレトンがすぐに適当な見合い結婚を用意する民族であることを考えれば、どちらかが一番財布の重い金貨男爵へ家畜のように売りに出される前に、素早く手を打たねばならなかったはずだ。
ここで認めておくが、私のエルダータイド・サークルの口承の歴史では、確かにこの恋人たちの間の手紙を運んでいるし、それ以上のこともしている。おそらく我々は彼らの結婚を執り行い、ガレンとハイ・アイルから彼らを隠したのだろう。実際、シストレスには脱出不可能とされる島が存在している。
そう、私が言っているのはアメノスだ。考えてみよう。二人の家を統合させる契約が破られることがあれば、おそらく死に帰結する。つまり、彼らは自らを良心の牢獄に閉じ込めたのだ。これは彼らの家族に強力なメッセージを送りつける、優れた計画だった。
むしろ、強力すぎたと言うべきかもしれない。
第一子が共に家族の名を拒絶し、一緒になれる島から実質的に出られないよう自らを縛ったのだ。私が非ドルイドのブレトン文化について知っていることからすれば、このような事件は間違いなく破滅的なスキャンダルであり、本土にまで届く余波を巻き起こすだろう。これは生涯の敵同士が、双方の合意の上で一つの物語を作るに至るほど強力なものである。すなわち、両家の子たちは互いの手で死に、かつドルイドが彼らを追い詰めてそうさせたという物語だ。
リゼッテとアルノーについてだが、名を捨て、本土の習慣も捨ててアメノスのドルイドとしての生を受け入れたことで、長く幸福な生涯を送ったはずだ。それほど考えられないことだろうか?
私はあり得ることだと思うが、同意してくれる人は少ないだろう。
ドレッドセイルの脅威Dreadsails: Threat to the Isles
街の警備隊長殿
これを書きたくはありませんでした。ここにいる者は皆まっとうな市民だと思っていました。当然、ドレッドセイルのような海賊どもが我々の生活に及ぼす危険を承知していると。私は間違っていました。
造船所で一日働いた後、酒場〈うんざりしたオルナウグ〉に座ってエールを飲んでいた時、ダミエン・ギニーズが大きな口を開けてこう言うのが聞こえたのです。「ドレッドセイルが欲しがっているものをくれてやったらどうだ?ヴァスティルを明け渡す。俺たちはどこでもやり直せるさ」
ヴァスティルを明け渡す?あの男は街を明け渡せば襲撃が止むとでも思っているのでしょうか?奴らが欲しいのは土地ではない。奴らが港を襲うのは、ヴァスティルに住みたいからではないのです!
ドレッドセイルに区画を渡したら、奴らは軟弱と思い、我々が諦めた証と見なすはずです。ヴァスティルの路地が奴らの手に落ちたら、もう攻撃が止むことはありません。我々が全員死に、奴らがガレンを海賊の隠れ家か何かに変えてしまうまでは。
だから何があっても、ダミエン・ギニーズのような愚か者の言葉に耳を貸してはなりません。海賊の要求に屈してはいけない。そしてモーナード家を信じ続けてください。彼らは我らの街を守り、悪党どもを追い払ってくれるのですから。
忠実なる市民、クリストフ・アリエル
ドレッドセイルへの命令Dreadsail Orders
ドレッドセイルよ!
私はお前たちに安息の地を約束した。今、我らの新たな故郷への道が目の前に開けている。私はガレンの強大なドルイドと取引した。その人物が、島で我らが要塞の確保を助けてくれる。
見返りとしてその人物は敵対するサークル、エルダータイドが所持する、ある遺物の入手を求めている。島の東岸を襲撃し、その遺物を探せ。見つからなければ、捕虜を捕えて尋問し。エルダータイドのドルイドの中に、伝承の語り部がいるはずだ。探し方を知っているだろう。
俺を失望させるな。ドルイドの遺物だけで、新たな家が手に入るんだぞ!
シーロード・ナロス
ナヴィール城の騎士The Dame of Castle Navire
船乗りたちよ、集まって耳を貸せ
激しい愛の物語を話そう
私は略奪者と戦い、極寒のスコールにも耐えた
だがナヴィールでの試合で恋に落ちた
伝令の布告を聞いて、我々は遠くから来た
山の崖から、寒い海辺から
腕を掲げ、我らが愛する人を称えた
ナヴィール城の騎士となった人を
巻きついた船の綱よりもがっしりした筋肉
「戦艦の一撃」とあだ名された右手のフック
彼女はゴンファローネの路上で孤独に育ち
一度もトーナメントで負けたことがなかった
伝令の布告を聞いて、我々は遠くから来た
山の崖から、寒い海辺から
腕を掲げ、我らが愛する人を称えた
ナヴィール城の騎士となった人を
汗でもつれた髪の毛で、彼女は剣を掲げ
その切っ先をナヴィールの騎士団長に突きつけた
「私はすべての騎士を倒し、すべての試練に打ち勝った
ハイ・アイルで一番強い者に馬上試合を挑みたい」
伝令の布告を聞いて、我々は遠くから来た
山の崖から、寒い海辺から
腕を掲げ、我らが愛する人を称えた
ナヴィール城の騎士となった人を
蹄が叩く音と声援に囲まれ、二人は激しく戦った
壊れた盾は血まみれの中庭に投げ捨てられた
老いも若きも、男たちは彼女の死を恐れた
二人は激突し、我らは全員息を止めた
この老いぼれの海賊はもうずっと
涙を流したことなんてなかったが
砂埃が収まり、彼女の姿が現れた時は
海を贈れそうなほど感激した
伝令の布告を聞いて、我々は遠くから来た
山の崖から、寒い海辺から
腕を掲げ、我らが愛する人を称えた
ナヴィール城の騎士となった人を
ナヴィール城の騎士となった人を
ネリへのメモNote to Neri
ネリ、
忙しくしているようだが、本当の任務のために少しは体力を温存しておけ。
ミナヘルはあのエロリエンとラニウィスの馬鹿どもが何をしたのか、はっきりするまで閉じ込めておきたいと言っている。奴らは古いドルイドの部屋にいる。俺たちが普段、酔いつぶれたり暴れたりした船乗りを、酔いが醒めるまで閉じ込めている場所だ。シーウィッチよりも先に、奴ら同士で殺しあわないよう見張っておけ。今は奴らに、それなりに元気なまま生きていてもらわねばならん。
ミナヘルは何だか知らんが奴らが起動させたものを元に戻すため、二人を生かしておく必要があると何度も念を押している。ミナヘルは奴らの愚かさに怒り狂ったかと思えば、急に冷静になる。そういう時は、彼女に魅力を感じるよ!普段なら恐ろしい存在なんだが。しかしドルイドが不気味な儀式をしていた場所にあった古代の遺物を使ってみようと思うなんて、相当な馬鹿だな。
それはそうと、お前の新しいおもちゃに嫉妬したほうがいいか?
モリグ
バカロ卿の日記Lord Bacaro’s Journal
〈直近の記述が以下に記されている〉
当初、ハイ・アイルとガレンでの失敗には怒りが収まらなかった。成功を確実にするためあらゆる準備をしたのに。同盟の指導者たちは海で死ぬはずだったが、奴らはしぶとかった。そして魔導師は全旗の小島で奴らを仕留めることに失敗した。レディ・アラベルの勇者があの愚か者を殺していなかったら、私が始末していたところだ。
さらに奴らはガレンでの計画も阻止した。モーナード家は倒れ、私は統一されたドルイド帝国を味方につけているはずだった。そして揺るぎなき者の会を解散させ、超越騎士団に置き換えるはずだった。
魔導師は傲慢すぎたし、アークドルイド・オルレイスは臆病すぎた。他の者にまた裏切られるのはごめんだ。新たなドルイド王が立ち上がり、予言を実現して聖なる象徴を手にするべきだ。
私はこの瞬間を常に目指してきた。これは私の血の遺産なのだ。私はドルイド王カソレインの最後の生きた末裔。我が母の血筋により、ブレトンの遺産は私が手にするべきだ!私は自分が権力を集中させて計画を練っている間、しばらくはオルレイスに統治を任せてやるつもりだった。だがあの女は弱すぎた。今、私が足を踏み出さねばならないことがわかった。ルビーの玉座の腐敗に代えて、純粋なる蔦の玉座を置かなければならない。自然もそれを求めている。
王の象徴を手に入れ、ファイアソング山の真の力を目覚めさせたら、今の秩序など炎と灰の中に沈めてやる。そして灰の中から新たな秩序が立ち上がる。脆いルビーと石ではなく、絡みつき成長し、広がっていく茨と蔦、根の秩序だ。新たな緑の時代が幕を開け、古い時代の血を糧とするだろう!
ファウンズ・チケット調査メモFauns’ Thicket Research Notes
ドルイド・マデナ、ファウンズ・チケット
観察 45:
ファウンは目立たないながらも厳格な階級の下で生きている。群れはオスとメスのつがいによって率いられ、おそらく指導者のつがいに報告する副官たちを見分けられると思う。その下には食料を探すファウンや若者の世話をするファウン、危険を見張るファウンがいる。
観察 46:
すべてのファウンは明確にベリーと果物を好むが、最も若いファウンが常に、手に入る中で最も熟した食料を与えられる。これまで群れの中では見られなかった利他的行動である。
観察 47:
ある副官が群れを指導するメスと普段より長い時間を過ごしている。
観察 50:
ファウンには意識があるのか?これはガレンのドルイドたちの間で大いに議論されている。彼らは道具を使用する能力を示し、娯楽のためにゲームをする。しかしカラスも道具を使いゲームをするが、我々はカラスに意識があるとは考えない。ここでの観察を続けよう。この根本的な問いへの答えは、私の住居と海辺の間の距離くらいに、私の知性から遠く離れている。
観察 52:
ファウンたちは私の持ち物を漁り始めている。紙を踏みつけた者がいる。また別のファウンは、土に残った蹄の跡でわかるが、私の毛布めがけてわざとインクの瓶をひっくり返したようだ。この程度の被害で済んだことを喜ぶべきなのだろうが、そんな気にはなれない。毛布の染みはもう落とせないだろう。
観察 53:
指導者のオスが下剋上を狙う副官に気づいた。今夜は群れから多くの鳴き声が聞こえる。彼らの争いと議論で、私の休息が妨害されるのではないかと不安だ。
観察 60:
ファウンの戦闘における様々な戦法の図を書いた。機嫌の悪いファウンと戦う羽目になったら、彼らの蹄の威力についてより正確な予測ができるだろう。
観察 61:
狡猾な副官は群れから追放された。彼が肩を落として夜明けに去っていくのを見た。私も夜は眠れず辛かったが、あのファウンは間違いなく、それ以上に辛い思いをしたはずだ。
観察 63:
いくつかの石に警告と呪いの言葉を刻んでおいた。ファウンは私の怒りを恐れはしないだろうが、ドルイド魔術の匂いは知っている。私の住居は安全だ。今のところは。
観察 67:
指導者のつがいは宮廷での王や女王のように振る舞っている。彼らはチケットを大々的に巡回し、自分たちの優れた毛皮と、群れのファウンに対する支配力を見せびらかしている。若いファウンたちが女王に花や収穫したばかりのベリーを持ってくるのもこっそり見た。王は自分の領地を視察し、群れの安全を守るために歩哨を増やすべき場所を指図した。見事な光景だったし、彼らが複雑な階級を有しているという、私の信念を強めてくれた。
観察 70:
これは茶番だ。ファウンたちは私が観察しているのを見て、宮廷生活の真似事をしようと決めたのだ。王と女王だって?彼らは互いを好きでさえなかった。私が巡回を観察した後、「宮廷」のある若いメンバーが私のほうを向いて忍び笑いを漏らしたのに気づいた。彼らは領地を視察していたのではなく、チケット中を歩き回って、私によく見えるよう取り計らっていたのだ。
私はここに留まりすぎた。夜が明けたらすぐグリマーターンに出発しよう。ファウンたちが私をからかっていただけということにより、私の仕事はすべて台無しになってしまった。
ブレトンの遺産Legacy of the Bretons
ステファン・モーナードによる一連の考察
ブレトンとして学術を学んだ貴族であり、ガレンのドルイドと共に学んだ者として、私はしばしば自分の本当の素性について考える。要するに私はいつもブレトンであるとはどういうことか、我々の先人たちはどのような遺産を残したのかを理解しようと努めている。それ以上に重要なのは、後に来る者たちのために我々がどのような遺産を残すべきかということだ。
モーナード家の子でありブレトンである私の場合、どちらの遺産の方が大きく、今日の私を形作っているのだろう?それよりも、私はどちらの側を望むのだろう?人間でありエルフでもあるという私の二重の性質は、私の血管を流れる血に由来するのか?ブレトンは我々の歴史の初期、望まれぬ混血種と考えられていたが、我々はその暗黒時代を乗り越え、ハイロックと諸島の中核をなす民となった。だが、そのことは何を意味しているのか?私は人間か、それともエルフか?それとも合わさって新しい何かに、足したよりも優れた何かになったのだろうか?
現代のブレトンには二重の遺産がもう一対ある。騎士団の伝統と、我々が生まれ持つ魔術だ。それは我々の血の中に流れている。だがアルケインの呼び声は、我々の血筋を流れる唯一の魔術ではない。ドルイドの自然魔術は、ブレトンの出現からまだそれほど経っていない時代、ハイロックに最初のドルイド共同体が集まった後に生み出された、真の意味でブレトンが創った最初のものかもしれない。我々の魔導騎士や魔術師の魔術は独特な形式ながら、ドルイドの魔術と一定の類似を有している。呪文や儀式へ特に顕著に現れているが、アルケインが形式的な教えや魔術書に依拠するのに対し、ドルイドは自然の霊魂やイフレの神聖なる力に呼びかける。
これらすべてと関わるのは、古来よりの戦いである。すなわち、どちらの社会形態がブレトンをより代表しているのか?まずハイロックで発展し、それからシストレスに手を伸ばした騎士と城塞の家紋と栄光か、それとも自然の受容と純粋で飾り気のない生への呼びかけか、どちらがブレトン文化の真の証なのか?私はどちらの方式も、我々に共通の遺産を形成していると信じる。融合させて新しい、完全にブレトン的なものへ作り変える道を見つけたいと思う。それこそが正当なる遺産となるだろう。
ベライとモルモーBelaigh and the Molmor
上級歴史家、シリノ・ヘンター 著
全旗海軍がスラスに出航し、正義の稲妻のごとくスロードを滅ぼしたと一般に言われている。しかし、これが物語のすべてではない。スラスのスロードは無気力で臆病だったかもしれないが、彼らはハイ・アイルの造船所で形を取りつつあった破滅を予期していた。スロードは何度か巨大な海の怪物を解き放ち、シストレス諸島を攻撃させた。その中でも最強の怪物は、モルモーと呼ばれる獣である。
生存者の中には、滴り落ちる粘液に覆われた巨大なクジラと記している者がいる。また、タコのような触手でものを掴むと主張する者もいる。そしてモルモーを見た者の一部は、それぞれ騎士の槍よりも長い鋭い棘が、まさしく森となって生えていたと語っている。モルモーが泳げば、海は黒く泡立つ。そして海岸まで寄ってくると、その途上にあるすべてのものは粉砕される。
7年間、この獣はガレンの沿岸を荒らしまわった。全旗海軍の多くの船長がモルモーを倒そうとしたが、成功しなかった。ついに男爵提督ベンドゥ・オロは支援を呼びかけ、この獣を倒すことのできた者には誰であろうと、望みの褒美が与えられると約束した。
モルモーは狩ろうとしたほぼすべての者を溺れさせ、あるいは貪り食ってしまったため、最も勇敢な英雄でさえ躊躇した。しかしその時、無名の若いガレンのドルイドが前に進み出た。「私はエルダータイドのベライです」と彼女は男爵提督に言った。「その怪物を追い払いましょう。しかしあなたには約束を守り、私に褒美を与えてもらいます」
ベンドゥ・オロはすぐに同意したが、自分の約束について不安を抱いてはいなかった。ベライは20歳にもならないメイドであり、葦のごとく細身で、ボロを身にまとっていた。しかしこの若い女の態度の何かが、彼を困惑させた。そのためオロは自分の家から騎士を同行させ、彼女の行動を報告させることにした。
まずベライはガレンで最も高い丘に登り、その頂上から石の欠片を取った。そして彼女は島の森へ行き、最も元気なオークの木からドングリを拾った。次に、ベライは蒸気を噴き出す火口へ行き、灰を集めた。最後に、彼女は島の中心にある深い泉に行き、その清水を使って灰とドングリ、石を混ぜ固めた。「これで獣の相手をする用意ができました」と彼女は困惑する騎士に言った。
「濡れた土くれでどうやってモルモーを殺すつもりだ?」と騎士は嘲笑った。
「モルモーは自分で自分を殺すでしょう」とベライは答え、海辺に行って怪物を探した。モルモーを探すのは難しいことではなかった。モルモーは西の湾に浮かんで休んでいた。脇腹の部分から汚い泡が噴き出していた。乙女は湾を見下ろせる場所まで登り、怪物に呼び掛けた。「忌まわしき獣よ!私は小さな肉片だけど、あなたの腹を満たしましょう。来て私を食べるがいい!」
モルモーは彼女の叫びを聞き、急いでやって来た。そのあまりの素早さと恐ろしさに、ベンドゥ・オロの騎士は恐怖で転んでしまった。しかしモルモーが口を開けてベライを飲み込もうとした時、彼女は石と種、灰と水の塊を怪物の喉の奥に投げ込み、緑に呼びかけた。モルモーはあと少しのところでベライも飲み込んでしまうところだったが、彼女は横に飛びのいた。もう一度襲いかかる前に、大きな痛みが怪物の腹を襲った。
モルモーは咆哮を上げながらもがき、海に戻っていった。騎士が驚いたことに、以前は粘液が垂れていた穴から、生きた茨の蔦が噴出していた。怪物の触手や脇腹は石のようになり、急速に海底へと引きずりこまれた。そして突き出していた棘は木に変わっていた。ほんのわずかな間に、モルモーは海の中で大岩に変化し、海草で覆われ、小さな森を生やしていたのだ。
「終わりました」とベライは騎士に言った。「さあ、あなたの指導者のところへ連れていって」
騎士は求められた通り、ベンドゥ・オロに見たことをすべて伝えた。男爵提督はベライを見て頭を下げた。「約束は守ろう。望みの褒美を言うがいい」と彼は言った。
「ガレンの生きた木を切ること、石を壊すことをやめてください」と彼女は答えた。「あなたたちの木こりと鉱山労働者を呼び戻して。この島をあなたたちの艦隊を作るために利用してはなりません」
ベンドゥ・オロは無念そうにため息をついた。ガレンの力強い木々と豊富な鉱脈があれば、全旗海軍の建設に大きな助けとなっただろうに。しかし約束はすでになされた。そして彼は約束を守った。「よかろう」とオロは答えた。こうしてガレンは斧とつるはしによるこれ以上の被害を免れたのだった。
ベライについて、これ以上の物語は伝えられていない。だがモルモー島はガレン西岸沖の海に今でも残っている。
ヘレニー卿の冒険Dame Helenie’s Quest
モーナード家のヘレニー卿による、ヴァスティルの宝石を取り戻す危険な冒険を成功させた英雄物語。アルバトロス騎士団のランディル卿によって記録された
悪しき盗賊の一団が、モーナード城の衛兵たちを騙すことに成功した。無謀で傲慢ではあったが、盗賊たちは宝物庫への道を見つけだし、ヴァスティルの貴重な宝石を盗む程度には巧妙だった。盗みを働く間に血は一滴も流れなかったが、モーナード家に対する侮辱が無視されることはなかった。
ヘレニー卿は勇敢にも盗賊たちを追いかけることを志願した。彼女は二週間で盗賊どもを裁きにかけると約束した。モーナード家はこれを認め、旅のための物資を彼女に与えて送り出した。
ヘレニー卿は城を去ると、三日間盗賊たちの痕跡を追った。ヘレニー卿は馬に乗って進んだが、海からやって来た激しい嵐に巻き込まれ、ガレンの深い森へと逃げ込んだ。そこから彼女は道を見失わないため、機転と地形についてのわずかな知識を用いなければならなかった。彼女はスプリガンやファウンなど、自然に潜む凶暴な敵と戦い、眠る時はすぐに飛び起きて戦えるよう、剣を膝の上に乗せた。
盗賊たちにはモーナード城を出た後別々の道を行くほどの知恵がなかったので、ヘレニー卿は簡単に彼らの痕跡を追うことができた。盗賊たちは愚かにも、ガレンの自然深くにあるドルイド集落の近くにいれば、モーナード家も追手をよこすまいと思い込んでいた。だがヘレニー卿はそんなことで怯むような人間ではなかった。それどころか、彼女は道の途中で数人のドルイドに話しかけ、盗賊を見なかったかと尋ねた。大部分のドルイドは友好的で、貴重な情報を与えてくれた。彼女を追い払い、明確に敵意を見せた者はごくわずかだった。そのような障害に出会った場合でさえ、ヘレニー卿は礼儀正しく話し合いで解決した。彼女の任務はモーナード家のために犯罪者に裁きを下すことだけだ。それ以外は島の何も乱すつもりはなかった。
旅の10日目、ヘレニー卿の食料は残り少なくなり、馬は足を引きずるようになった。彼女は馬を休ませた。盗賊たちが野営した場所はすぐ近くにあることを知っていたからだ。彼女は盗賊たちの不意を突くため夜明けに起きた。影のように音もなく、ヘレニー卿は盗賊の野営地に忍び込み、一番近くにいた盗賊の首に短剣を突きつけた。彼女は口を開くなと言い、盗賊の手足を縄で縛った。そして彼女は他の盗賊たちに互いを縛り上げるよう命じた。その間もずっと、最初の盗賊の喉元に刃を突きつけながら。
盗賊たちを見事に捕えた後、ヘレニー卿は彼らの馬を集めて、盗賊たちを全員ヴァスティルまで送り届けた。彼女は大股で街を歩き城へ向かったが、見てもほとんどヘレニー卿だとはわからないほどだった。彼女の鎧は泥に覆われ、ブーツからは葉が突き出し、顔には引っかき傷や泥の汚れが付いていた。十四日の間、街の外にいた彼女は野生の獣のように見えた。だがヘレニー卿はモーナード家に盗賊たちを突き出して、にやりと笑った。その後、ヘレニー卿は自らの手でヴァスティルの宝石を宝物庫へ返却し、彼女を称える祝宴が開かれた。
ボルガによるガレンの獣ガイドBolga’s Guide to Galen Beasts
ミストラルの女狩人、ボルガ・グラブール 著
編者注:オークの狩人ボルガは友人を訪ねるため、美しいガレンに来ている。そのため彼女はペンを取って紙に記すことにした。ここではボルガが彼女なりの面白おかしい方法で、ガレン島の獣について教えてくれる。弱い獣から強い獣までの倒す方法と、食べて旨いかどうかを。
* * *
フェニックスモス
綺麗だけど燃えている。食べるには最悪。
ドルイドは自分たちがこの蛾を作る物語を話す。本当なら大したものだけど、ボルガは疑わしいと思う。
育つまでは熱い芋虫。お茶に入れるとすぐ暖まる。
藁のテントにでも住んでいるのでなければ、危険はあまりない。その場合、水を用意すること。
* * *
ハドリッド
大きな蟹の民。喋る?よくわからない。
とても危険。強力な魔術と鋭い武器を持つ。集団で狩るために移動する。できれば海辺は避けるべき。
小さなグアルのような生き物を飼っている。サメのようなグアル。サメル?グアサメ?
倒せるなら、食べるととても美味しい。喋る蟹の民を食うのは間違っている?そういう話は学者に任せる。もっとバターが欲しい。
* * *
マグマフロッグ
カエル。でも火がついている。どうして燃えないのだろう?
長い舌で打ちつけ、長い距離をジャンプする。オスには硬い角がある。ヘラジカに似ているけど、尖ってる。
最初のマグマフロッグはイフレの道の物語から飛び出してきたという話を聞いた。どういう意味かはよくわからない。
意外なほど美味。秘密のレシピ:肉の切り身を冷まし、塩とニンニク、パプリカを振る。果物のジュースに一晩浸けて柔らかくする。サラダに加えて食べる。
* * *
ファイアニクサド
これは一体何なの?虫?人間?気味が悪い。
刺すし、噛む。あなたがボルガの兄弟より馬鹿なら、服も燃える。
危険というより害虫。食べるのにはまるで向かない。熱すぎて舌が火傷するし、味は灰のようだ。
ヴァスティルの人がニクサドに、音に合わせてハミングする芸を教えていた。いい音だった。\
* * *
キメラ
首が三つあるライオンみたいなやつ。多分会うことはないだろう。見たら走って逃げたほうがいい。急いで。
友達が昔キメラの世話をしていたけど、死んでしまったと言っていた。その話をする時、彼女は悲しそうだった。
食べようとするのは労力に見合わない。ボルガを信じて欲しい。
* * *
ファウン
鹿の民。ボルガは友達になりたかったが、殺されそうになった。
鋭い武器と欺きの魔術。避けたほうがいい。
鹿は美味しい。でもファウンを食べるのはどう考えても間違っている気がする。ハドリッドと何が違うのか?
ボルガに聞かないで。ボルガは真実を書いているだけ。
* * *
アッシュホッパー
大きなバッタ。あまり危険はない。
味はとてもいい!体は食べ応えがあり、たんぱく質は豊富だ。火にかける前に濃いソースを塗る。溶岩に直接突っ込んでもいい。それでも焼ける。
* * *
フォレストレイス
ボルガには不気味すぎる。物語は聞くが、見たことはない。探そうともしなかった。
これはボルガの推測だけど、多分味もよくない。
* * *
パングリット
旅をしていたら、あのサメグアルの名前がわかった。パングリット!
アリットに似ている。口に脚が付いている。歯が多すぎる。
可愛くて調教しやすいだけでなく、かなり美味。この点ではグアルに似ている。
ハチミツを塗って焼くか、スパイスを効かせたベリーソースがいい。
マッドクラブのモリスMolith the Mudcrab
ガレンの潮だまりにモリスというマッドクラブが住んでいた。
誰も関わりたがらない、気難しい蟹だった。
彼は6まで数えることができた、脚1本につき1つ
そしてシャウラスの卵の色をした、自分の殻を誇りにしていた
大きな恐ろしい爪で、彼は小さい動物に命令した
シースラグや魚、水面を走るものに
爪を打ち鳴らして、彼はこうしろああしろと命じた
そして言い返す者がいたら、彼は叩き潰してしまった
「ウニやヒトデや、その他の雑魚どもよ
この仕事をやらなければ、すぐさま放り出すぞ!
そこの海草を片づけろ、その真珠を磨け
そこのフジツボを削り取って、投げ捨ててしまえ!」
動物たちは全員従い、仕事をすべてやった
海辺に投げ捨てられないようにするためにはそれしかなかった
海辺は乾いて不愉快な場所、拾い上げられて食べられるだけ
厳しく働くか、誰かのシーフードになるかだった
ほとんどのマッドクラブは宗教なんて言葉を知らないが
彼らが働いている間、モリスは内面に深く目を向けた
彼は塩水に浸った心の中に、愛と似ていなくもない温かみを感じた
そして大きな蟹が空の上から見守っていると考えた
彼は石でできた大きな爪を持つ蟹を思い描いた
自分の殻と似たような、明るく輝く殻を持ち
それから名前も!そう、名前だ!重要な蟹には名前がある
ゾリスとかゴリスとか、そういう名前が
大きな蟹が見たらどんなに素晴らしいことだろう
モリスが海のこの部分を手懐けたことを
この潮だまりは彼のもの、すべては美しく秩序だっている
どの表面も手入れされ、完璧に磨かれている
するとモリスのささやかな家の上に影が立ち上る
泡を突き抜けてブーツの底が現れる
そのわずかな一瞬だけ、彼はあの方が来たと思った
お空の大きな蟹が、一泳ぎするために降りてきた!
だがそれはゾリスでもゴリスでもなく、名のあるどんな神でもなかった
ジャンヌとかいう名前の、ただの若い船乗りだった
彼女は無頓着に潮だまりを駆け抜け
足を置く場所なんて気にもかけなかった
そして船乗りはやって来たと思ったらいなくなり
動物たちはがっかりしたかと思うだろう
彼らは泣き、肩をすくめてため息をついたかもしれない
マッドクラブのモリスが死んだ哀しみのせいで
でも潮だまりは静かになって、誰も命令しなくなった
海草が絡まっても、伸びすぎても誰も気にしない
フジツボが居座って、真珠がくすんだからどうだって?
誰も通りすがりのカモメに放り投げられるのを怖れなくてもよくなった
だから誰も汚れに文句を言わなくなった
潮だまりには活気が戻ってきた、シースラグとその粘液も戻ってきた
海草たちもすくすくと伸びた
今じゃフジツボの家族も、モリスという殻に住み着いた
ミナヘルのメモMinahel’s Note
エロリエンとラニウィスのように愚かな連中が、他にドルイドの小物を見つけていないか確認しなさい。とりあえずアンキュルは眠らせるしかなかった。彼はあの遺物の効果により早くやられてしまった。愚かにもあれを素手で触ったから。
妙な感覚がするようになったら、部屋を離れなさい。水辺を歩いたほうがいいかもしれない。新鮮な空気とそよ風は影響を緩和してくれる可能性がある。私たちはこの遺物が引き起こすらしい、最悪の衝動を抑えられるものがないか探している。
この遺物の力を抑制する方法を見つけてみせる。実際、遺物の作用を恒久的にどうにかする方法を発見できる日も遠くないかもしれない。でもそれには時間がかかる。できるだけドレッドセイルには近づかないように。奴らの規則的な生活は影響をそれなりに緩和しているけど、私たちが取り組んでいる解決法が完成するまで、バランスを崩したくない。
ミナヘル
ミラの日記:サルベージMirah’s Journal: The Salvage
(水で損傷しているため、この日記の記述の多くはほとんど解読できない)
滑らかな肌の者が地図と夢を持ってくるたびに金貨をもらえていたら、ミラはガラクタと交換で愚か者どもに自分の船を貸し出す必要なんてなかっただろう。今日、ガルスという財宝を嗅ぎまわる者がありったけの船乗りに頼み込んで、スラシア海域に連れていってもらおうとしていた。あの哀れな愚か者は、船乗りがどれだけ迷信深いか知らないらしい。
* * *
今日、あのガルスとかいう奴がまた来た。ミラは彼の地図に一瞬だけ目を通した。もしかすると、これは本物かもしれない。
* * *
ミラの目が恐ろしいとガルスが言う。ランターンが消えると、獣の目のように輝くと。この者はそれが悪いことだとは思わない。ミラは財宝を探す滑らかな肌の者の相手をする時、恐怖が強力な道具になることを学んだ。それに、夜中にランターンを消して航海するのはこの者の発案ではない。ガルスの奴が言い張ったのだ。今奴は地図に目を凝らしているが、それでも考えは変わらないらしい。爪の鈍った愚か者め、顔にほとんど毛もないくせに。ジョーンとジョーデよ、導きたまえ!
* * *
死んだサンゴ礁の端まで来た。ガルスは興奮しているようだが、この者にとっては危険な海域で1週間を無駄にしただけだ。しかし、ガルスには水泳の才能があるらしく、水中呼吸の魔術の知識も持っているようだ。奴は一日の大半を海に飛び込んで過ごし、石の破片や残骸を引き上げている。富を約束し、もうすぐだと言っているが、怪しいものだ。
* * *
今日、妙なことが起こった。釣りをしている時、この者はガルスが息継ぎのため針の近くに上がってくるのを見たように思った。ミラはよくも夕飯を追い払ったなと叱ろうとした。奴が持ってきた石を投げようと手に取ったほどだ。だがそれはガルスじゃなかった。この者が瞬きすると、財宝探しの顔が見えたと思った場所には、午後の陽を浴びて白く色褪せたサンゴの死骸があるだけだった。
* * *
3日間潜り続けた後、ガルスはついに金目のものを見つけた。アレッシア帝国のシンボルが印璽された、ゴールドの詰まった袋だ。この滑らかな肌の者は、全旗海軍の船の残骸を見つけたのだ。この下にはまだ何が眠っているかを思って、ミラは唾を飲み込んだ。
* * *
日没になったのに、ガルスはまだ息継ぎに上がってこない。いくら魔術が使えるといっても、奴がこれほど長い間水中にいられるはずがないことをミラは知っている。その意味を考えると、ミラの胃がぎゅっと締めつけられた。もう沖に出ていても仕方ない。太陽は低すぎるし、海風さえなくなった。ガルスが朝までに戻らなかったら、この者はヴァスティルに戻るため船を出す。
* * *
船体がノックされている?気のせいじゃない。何かが水面下から、船の外側を叩いているのだ。一刻も早く夜明けが来て欲しい。
* * *
奴の姿が見えた。ガルスだ。風を受けて、もうサンゴ礁から遠く離れているのに、この文を書いているミラの爪が震える。奴は歪められていた。異形の抜け殻へと変貌させられていたのだ。地図もあの海域もクソ喰らえだ。キナレスよ、ガルスをレレスウェアに導きたまえ。
* * *
ノックだ。まだノックの音が聞こえる。
王からの命令Orders from the Lord
ドルイド・エドレルド、
ギャリックズ・レストの地下にある庭園が満開だそうだな。完璧だ。積荷のワインを受け取ったら、以下のように事を進めてもらいたい。
お前が新たに開発した毒をワインボトルのうち1本に加えろ。私はボトルがレディ・アラベルへの贈答品に入るよう取り計らっておいた。彼女は疑いを強めており、我々が行動しなければ揺るぎなき邸宅にいる密偵を発見されてしまう可能性が高い。彼女はこの希少なビンテージの誘惑に耐えられまい。ワインには目がない女だからな。
エリア女公爵に送る贈り物にも同じようにせよ。その後残りのボトルを木箱に詰めろ。配達人が外でお前に会う。配達された品を受け取り、ワインの木箱を配達人に渡せ。配達人はそれをナヴィール城に送る命令を受けている。すべて計画通りに行けば、アラベルとエリアは両方とも死に、その責任は当然、デュフォート家の不平分子に課せられるだろう。
遺物については、私が離れている間お前に保管してもらう。揺るぎなき邸宅が私の留守中に破損した場合は、館の地下室の下にあるトンネルに入れ。そこにある文書はすべて破棄しろ。その時が来るまで、我々の真の素性を明かすわけにはいかない。
超越の王
火山の霊魂Spirit of the Volcano
(ドルイドの歌)
我らが山の歌は煙と炎をもたらす
熱を恐れるなかれ、手懐けようとするなかれ
大地は割れ、炎は飲み込む
不吉な予兆も、怒りも責めてはならぬ
山の震える言葉に耳を傾けよ
山が声を発するたび、木々は折れ
波も山に当たって砕け、その足元で煮え上がる
山はどんな王にも膝を曲げることはない
火山の霊魂は自らの織り機で命を紡ぐ
炎が弾けるところには、今や花が咲き
大地が割れるところには、島が育つ
快晴の空は、分厚い煙を貫いて現れる
夜が明けると、我らは山を称えて歌う
鳥たちはその燃え盛る視線から帰還し
新たな命が焼けただれたふもとから育つ
その霊魂は我々の生を越えて続く
我がシストレスを見るためにTo See My Systres
1.
亡霊の海の海岸を抱きしめ
囁き声を聞くたび飛び上がる
カイネの麗しき眷属に最期のキスを
だが私はシストレスを見たい
(コーラス)
進め、波に揺られながら
陽光のきらめきに包まれて
輝く青い海を越え、船を走らせる
我がシストレスのために
2.
作業員を乗せダンマーの国を進み
サクスリールの早口言葉を歌う
モロウウィンドで酒を飲み、罪を犯しに行けばよい
私はそれよりシストレスを見たい
3.
レヤウィンへ船を走らせ
上品な乙女や紳士と出会う
トパル湾から錨を上げ
シストレスを見るため船を出す
4.
カジートの地には暖かい砂
尻尾と髭には心地よい
だが猫の仲間たちは絶えず喉を鳴らす
我が甘美なるシストレスへの愛のために
5.
ボズマーの乙女が私に船代を払った
力添えを頼むために
金さえもらえば一晩中でも船を走らせる
我がシストレスを見るためならば
6.
ヴァルケルガードで吟遊詩人と寝た
逆らえない魅力を持っていた
サマーセットに太陽が沈むなら
昇るのは我がシストレスの上
7.
地上から離れず、足にまめを作って世界を歩く
そんな男の話ほど悲しいものはない
だがアリクルの声援と共に、彼も船に乗り
祝福されし我がシストレスに出会うだろう
(コーラス)
進め、波に揺られながら
陽光のきらめきに包まれて
輝く青い海を越え、船を走らせる
我がシストレスのために
8.
ストーントゥース要塞でオークのクランに出会った
牙とでこぼこの髭を持つ者たちに
海辺を遠く離れれば、もう戦わない
休戦は我が愛するシストレスのため
(コーラス)
進め、波に揺られながら
陽光のきらめきに包まれて
輝く青い海を越え、船を走らせる
我がシストレスのために
9.
人生は船乗りの歌のように長い
私は死のことなど考えない
運命の波に逆らうつもりもない
だから私をシストレスに帰してくれ
我々をシストレスに帰してくれ
歓迎しよう、新たなる者よ!Welcome, Initiates!
ようこそ、超越騎士団の入団者たち!
全旗の小島での事件以来、多くの者が我々は敗退したと信じている。だが理想の炎はそう簡単に消えるものではない。お前たちは噂をたどって我々にたどり着いた。他の者たちも遠からず、我らの地を支配している戦争狂の王族に抗う大波に加わるだろう。
シストレスに蜂起が迫っている。ガレンの事件は始まりにすぎない。ドルイドの同志に加わり、我らの正当な所有物を取り戻せ!カソレインの夢は現実となり、我らは力を合わせてブレトンの遺産を取り返す!
私はそれを誓う。
超越の王
救い出してくれRescue Me
(哀愁漂う旋律)
鎮まった海の岸から遠く離れて
私たちは遭難した
悲劇だ
やむを得ずグログを節約した
キナレスが我らを解放してくれるまで
孤独な漂流の旅、笑顔も消えた
故郷からは遠く
未知の領域へ向かう
この先に起こることを予期して
航海士の心は重く沈む
[リフレイン]
空は赤く光り、パンにはカビが生える
絶望が皆の心をふさぎ込ませる
我らは運命に絡めとられた、もはや手遅れだろうか
この呪われた戒めから逃れるのは
道を示してくれるものもほぼなく
我らは皆で祈った
遠く、道を見失って
希望はいまだ残っている、我らの湾を見つけて
宴会の日までに、故郷へ帰りたい
[リフレイン]
空は赤く光り、パンにはカビが生える
絶望が皆の心をふさぎ込ませる
我らは運命に迷い込んだ、もはや手遅れだ
この呪われた戒めから逃れるのは
[虚ろなこだま]
戒め
[長く響かせる]
戒め
キナレスよ許してくれ、我が願いを聞いてくれ
私を解放してくれ
この海から
この旅路で残されたのは私だけ
誰か、私を救い出してくれ
誰か、私を救い出してくれ
どうかキナレスよ、私を救い出してくれ
禁じられた島、イフェロンY’ffelon, the Forbidden Island
高名な学者にしてあらゆる文化の学徒、イグナティウス・ガレヌス 著
これはシストレス諸島のドルイドの島を旅した記録である。
この島に着いた時から、私が歓迎されないかもしれないことはわかっていた。この島から離れようとしない、秘密に包まれたドルイドの知識を記録し保存するために必要なリスクではある。 危険があったとしても構わないと思っていた。しかし、危険はあらゆる場所に潜んでいる。そして、ハイ・アイルやガレンのストーンロア・ドルイドから受けたような歓迎はイフェロンで受けられなかった。
島と建物を研究した結果、私はこの地のドルイドと接触を目指した。彼らは私の報告をより詳細にしてくれるし、その導きがなければ報告を完成できないだろう。どんな学術文書にも文脈は要る。ストーンロアは歓迎してくれたが、エルダータイドはそうでもなかった。
しかし羽根ペンを手にイフェロンのドルイド、ファイアソングの元へ向かうと、当初は混乱された。次に無表情となり、すぐに怒りが続いた。彼らに挨拶してから無害な質問を始めたが、質問が進むごとに表情が険しくなっていった。質問に対する彼らの反応はメモして、沈黙を唯一の非ドルイドとのコミュニケーションとして解釈を続けた。その時、ついにあるドルイドが前へ出て来てこちらを指さしてきた。無意識の反応として、敵意がないことを示すため手を上げようとした。しかし、羽根ペンのインクが乾き切っていなかった。それは指を指して来たドルイドの目に飛び込んだ。ただの事故だったのだが。
その場を離れるのが最善だと感じて、ドルイドから離れようとした。一歩離れるたびにドルイドは追ってきた。杖を握り、歯を剥き出して。理解できないが、私を傷つけようというのだ!必死に雇った船に戻って、船長に出港を願った。残念ながら、ファイアソング山のふもとに住むドルイドからこれ以上の情報は引き出せなかった。しかし、学術研究にはよくあることだ。
後は、学者仲間に任せよう。
現代のブレトン:人間かエルフか?Modern Day Bretons: Man or Mer?
ヴァスティルの歴史家、フィリバート・ビューシャム 著
ブレトンの歴史はかなり錯綜しており、長年の間多くの学者たちによって議論されてきた。この著作が出版されてずっと後になっても、議論が止むことはないだろう。それが謎というものだ。
積年の議論はある問題に集約される。ブレトンとは何者か、人間なのかエルフなのか?一般的な理解で我々ブレトンはそのどちらでもあるとされているが、どちらが優勢なのかについては様々な見解がある。
私の調査はもう何度も行ったり来たりを繰り返している。私はブレトンにおける人間性の優位についてと同じほどエルフの血の優位を論じてきたが、次の朝になると考えが変わってしまう!だが、ようやく一方の側に足を落ち着けることができたと思う。すなわち、エルフの側だ!
いかにしてこの結論に到達したのか、説明させて欲しい。ブレトンの起源として最も広く受け入れられている説は、神話紀におけるネードとアルドマーの交雑を基盤としている。ディレニ・クランがハイロックに来た時、彼らは我々のネードの祖先を見出したが、その中でも特筆すべきはガレンのドルイドと呼ばれる、ドルイド王の一族を通じてこの地域を統治していた集団であった。ディレニ・クランが影響力を行使し統治を行うにつれ、我らの祖先たちは封建的制度を構築し、それは多少の変化を加えながらも今日まで続いている。ディレニとネードの子供たちは人間よりエルフに近いと考えられたが、ディレニの親たちに受け入れられるには至らなかった。完全なエルフから排除される程度の違いはあったのである。
幸運にも、この違いは彼らを人間種から排除するほど大きくはなかった。むしろ、この違いは彼らの地位を高めたようだった。この子供たちはネード社会の中で有利な地位を占めた。そうして共同体が築かれ、その中で人々は繁栄した。
現在、我らブレトンがエルフよりも人間であると信じる者の多くは、我々の祖先が有利な立場にあったとはいえ、他の人間としか婚姻を許されなかったという事実に依拠している。文書や絵、その他の記述によっても、この事実は長年の間、我々の血統に一定の影響を及ぼしてきたことが見て取れる。尖った耳や角ばった顔、細身の体、特徴的な目などのエルフの身体的特徴は徐々に消えていった。その論理は確かに理解できる!我々の中のエルフの血が、時と共に薄められていったという考えは理に適っている。いわば池の中に落ちた絵具の雫のようなものである。
だが、ここからが私の仮説だ。我々がいくらかでもエルフ的血統の兆候を有しているということは、それが今でも我々の中で力を持っている証拠である。我々と、最初のブレトンの祖先たちは無数の世紀を隔てている。我々の特徴は時と共により人間的になっていったが、我々のエルフ的性質が完全に消滅していないことは重要である。ブレトン出身の人間としか子供を生むことを許されなかったのであれば、我々のうちにほとんどエルフは残っていないはずだ。これだけ長い間、これほど明確にエルフの性質が生き残ってきたことは、その強さを物語っている。
この文書で私は、問題が割合ではなく、強さであると申し上げたい!以下の23章で、私はこの仮説を詳細に解説し、これまでに集めた調査をより整理された形で展開していく。
古代ドルイドの血脈Ancient Druid Bloodlines
第二紀541年、レディ・ラリーナ・マーチャドによって依頼された詳細な系図調査
網羅的な調査を終え、ある程度の確実性を持って言えることは、あなたの一族が常に感じていたことがほぼ間違いなく真実だということです。マーチャドの血筋は確かに古代ブレトンの血筋であり、ハイロックにハーフエルフ種族が最初に出現した時にまで遡ります。さらに今日知られているこの一族が、ガレンのドルイドたちの最初の艦隊と共に、シストレス諸島に到着したドルイドにまで祖先を辿れる明確な証拠を発見いたしました。第一紀にハイロックを去ったドルイドです。
その上、マーチャドはブレトン原始ドルイドの祖先の一部だっただけでなく、明らかに王族の血筋であったことも自信を持って主張できます。ドルイド王カソレインが、現在のハイロックを統治する貴族に比較しうる存在と考えるならの話ですが。それにヴォロラスの血筋について我々が知っていることを付け加えれば、あなたのご子息は両王朝で最高の部分を受け継ぐことになるでしょう。
マーチャド家の紋章が種と葉を蒔く三つの器として描かれていることの説明は、ドルイドとの繋がり以外にありうるでしょうか?
〈この後にはこの文書が書かれた日からガレンの原始ドルイドの古い時代までたどり直す、複雑な系譜の記述が続いている。最後のドルイド王カソレインが明らかに家系図の中に示されている。この文書が記された日の最後の記述は、以下のようになっている〉
レディ・ラリーナ・マーチャド、第二紀521年――
ルーカン・ヴォロラス卿、第二紀516年――
(第二紀538年に結婚)
バカロ・ヴォロラス、第二紀540年――
使者の報告Messenger’s Report
倉庫長はあのフードを被った騎士たちが、造船所を警備するためデュフォート家に雇われたただの傭兵だと言っているが、信用できない。実際、デュフォート家の紋章を身につけた作業員がここには誰もいない。
はぐれ騎士団が造船所を奪取しているという、バカロ卿が受け取った報告は事実なのかもしれない。この情報をすぐにバカロ卿に届けたいが、倉庫長は出発前に造船所を巡っていくことを強く求めている。断れば疑いを招くかもしれない。揺るぎなき邸宅へ戻るには、少し待たなければなるまい。
使者への対処Deal with the Messenger
騎士隊長
揺るぎなき者の会はダンカン・ジェニスという使者をデュフォート造船所へ派遣した。我々が造船所を引き継ぐことを確認し、バカロ・ヴォロラス卿に我々の活動を報告する命令を受けている。到着したら、始末しておけ。我々の存在が確認されたことは、できる限り長い間秘密にしておかねばならん。
デュフォート造船所は我々の部隊を再建するために必須だ。必要と思うならばどんな方法でも使ってよい。支配を維持せよ。
超越の王
司祭とドルイドの議論12Argument Between Priest and Druid Number 12
八大神の司祭アーナレルウェとストーンロア・サークルのドルイド・マクセロットとの対話。
ドゥニウス・ソシアによってヴァスティルの路上で聞かれ、後世のために記録された。
(注記しておくべきと思われるが、著者はこの宗派間の議論がいつ起こるかを日常的に予想できるので、スイートロールを持って見物に来ていた。彼らのやりとりは友人同士の議論より、貴族が好む馬上槍試合に近いものである。著者はこれを大いに楽しんでおり、すべての議論を立ち聞きしている)
「ドルイドよ!質問を受ける覚悟はいいか!」
「おお、友よ。大聖堂では元気にやっているかね?」
「面倒な挨拶はいい。お前はなぜイフレだけに尽くす?八大神が与えたもう恵みには敬意を払わないのか?」
「その言い方はちょっと酷いだろう」
「それは謝るが、質問の意味は明確だろう、ドルイドよ。なぜイフレが唯一崇拝に値する神なのだ?」
「そうだな、他の者が何を信じているかは知らないが…まあ、周りを見てくれ。こんなに美しいものを見て、跪きたいと思わずにいられるだろうか?これはイフレの贈り物だ。私は自分に見える贈り物に感謝している」
「それでは心が狭すぎるのではないか?」
「そんなことはない。ああ!キナレスやマーラも称えるべきだと言いたいのか?それらの神々もいいだろう。君が彼らを称える歌を歌うならどうぞご自由に。しかし私は君の神々にあまり訴えるものを感じない。正直言って、八大神すべてを称える時間を君がどうやって見出しているのかわからないよ」
「時間だって?八大神のそれぞれには定められた饗宴や祝祭がある。我々は彼らの御業をすべての物事の中に認め、求められる通りに感謝を捧げるのだ」
「それじゃ同じことの繰り返しじゃないか」
「繰り返し?何を言う、反復はニルンの自然秩序だ。季節は回り続ける車輪のごとく巡る。鳥や獣の群れは規則的に移住する。雨は予測のつく道を通って降る。崇拝とはすべて繰り返しなのだ」
「だから君には自然の荒々しさが理解できないのさ。自然の自発性と神秘がね。確かに、私たちはイフレが教えるとおりの季節に従う。だが君は祭典や祝祭に従っている」
「八大神は称えられることを期待している」
「もちろんだとも」
「神々の知恵と命令に異を唱えたら、私は一体何になってしまうだろう?」
「単に自分の使命に忠実な司祭じゃないか?」
「この議論に勝ったと思っているのだろう?」
「まあ心配するな。きっと次はもっとちゃんと準備してくるんだろう」
「また明日、いつもの時間に市場でだな?」
「もちろん。たとえイフレが与えてくださるハチミツのためでも、議論の機会を逃したくはない!」
「今度は、大聖堂で崇拝することについて、お前の考えを聞かせてもらおう」
「大聖堂の中で?草と木から離れて?風を避けて?そんなところでは祈る相手がいないじゃないか」
「いや、いるのだよ!お前が崇拝する森の騒音から離れれば、我々の内に働く八大神を見出すことができる。我らの善行の一つひとつのうちに、神々の声を聴くことができる。そして――」
「アーナレルウェ!議論は明日のためにとっておけよ!」
「これは失礼。ではまた」
次の祝典に向けてFor Your Next Celebration
宛先:ナヴィール城、エリア・デュフォート女公爵
デュフォート家の昇格記念日に、貴家の大好物のワインならばお喜びいただけるのではないかと思いました。これの入手がいかに難しいかは承知しております。どうぞ貴家のため、お父上のため杯を掲げてください。デュフォート家による諸島の諸島統治よ、永遠なれ!
差出人:あなたの崇拝者より、情熱と感謝をこめて
自然の秩序を受け入れることEmbracing the Natural Order
ドルイドと生活した都会人の報告、パリッセ・エルガラ 著
私はヴァスティルで育った。この街はいつでも私の故郷だ。私は石に囲まれて、子供の頃は街路に導かれて育った。だがヴァスティルに住むすべての者と同じように、私は街の外にある自然の物語を聞き、想像力を満たしながら育った。ヴァスティルは島のほんの小さな一部分だが、それでも世界のすべてと感じられるような場所だ。少なくとも私にとってはそうだった。そしてヴァスティルの外にあるものはすべて魔法のような未知の何かで、大人たちの穏やかな声から聞こえてくるものだった。
私は同郷の大部分よりもガレンの他の場所に魅了された。ドルイドたちの物語に対する私の興味は尽きることがなかった。結局、都会は自分に向いていないと判断した。私は物語の中と蔓地区で見た数人のドルイドのように、緑の丘と自然への献身を求めた。両親は少女の空想癖と受け止め、いずれは過ぎ去るだろうと思っていたが、それは間違いだった。
17歳の時、私は食料とお気に入りの杖だけを持って出発した。街の北にあるストーンロア・サークルの居留地グリマーターンを目指して。ストーンロア・サークルがサークルの中で最も友好的であり、ドルイドの生き方を求める者を歓迎してくれることを知っていたからだ。私は新しい生活を始める覚悟を固めて、自信たっぷりに進んでいった。
ストーンロア・ドルイドは物語に言われていたとおり優しく歓迎してくれ、すぐに私のための休息所を用意してくれた。最初の夜、私は長旅で疲れていたにもかかわらず、自然の音で何度も目を覚ました。正体のわからない獣の吠え声や、葉のこすれる音、流れる水の踊る音を聞いた。その次の日、居留地の中や周辺を通っている無数の道を探検していた時、私は木の葉の堆積を踏みつけてしまい、それが足中に広がる発疹を引き起こした。この病気を治している時、私は何か食べて体力を回復するように言われた。残念ながら、ストーンロア・ドルイドの食事は私にとってあまり食欲をそそるものではなかった。食べ慣れていない味が多かったし、食感も不快に感じた。それにまだ虫のことを話していなかった。私は生きたまま喰われかけたと言ってもいい。自分の体のどこかを掻いていなかったことは一瞬たりともなかったくらいだった。
グリマーターンで5日間過ごした後、私はもう限界だと思った。ドルイド・パリッセになる夢は、自然という恐るべき現実によって速やかに打ち砕かれてしまった。ありがたいことに、私が最も親密にしていたストーンロア・ドルイドはとても優しかった。自然の中で生きるのに向いていないからといって、何も恥じることはないと彼らは言ってくれた。私はヴァスティルに戻った。腹は空き、体はかゆく、疲れ果て、完全に自分へ失望していた。そして私はここに留まったのだ。
この報告は、私自身の成長のためだけでなく、私のようにドルイドの風変りな生活を夢見て育った者たちにとっても重要な意義を持っている。私は自分の中の若者の欲望を尊重し、ヴァスティルの外の大地を探検したことをよかったと思っている。大人になった自分は最終的に、自然に囲まれているよりも街の中で安全にしていたほうが幸せだと判断したが、少なくとも試してみるだけの勇気はあったのだから。
自然の霊魂についてOn Nature Spirits
アークドルイド・デュアナ 著
私たちドルイドは周囲の霊魂と特別な、不可逆のつながりを結んでいる。森や山、川に結びついた霊魂は私たちの生活にとって、人間と同じほど欠かせない存在である。私たちは他の人々に感じ取れない方法で霊魂を知るが、自然の霊魂を称え、理解しようと努めて生を送ってきた私たちでさえ、霊魂を完全に知ることはできない。それが彼らの存在の美点である。自然とは予測不可能で、不可知なものなのだ。どれだけ解読しようとしても、完全に理解することはできない。
だからといって、私たちがイフレの意思に従う霊魂について何も知らないわけではない。
一部の自然の霊魂が恐ろしく強大なことはわかっている。感情を持つ霊魂もおり、深い優しさや激しい攻撃性を示すことがある。また霊魂の中には比較的この世界に来て新しく、葉に溜まる朝露のように新鮮なものもいるが、ガレンを歩んだ最初のドルイドと同じくらい古い霊魂もいる。私たちは霊魂も人間と同じように迷い、途方に暮れることがあるのを知っている。霊魂はまた私たちが目的、あるいは場所に迷っている時は、導きの力ともなりうる。
しかし自然の霊魂との協調は、私たちが彼らに敬意を払わなければうまくいかない。自然の霊魂をその居場所から追いだし、無理やり働かせ、霊魂を意思に従属させるような真似をすれば(そのようなことが可能だとしても)、彼らと交信する希望は失われる。いかなる時でも、私たちは協力を求める霊魂のそれぞれを理解しようと最善を尽くさなくてはならない。この霊魂は守護者か?門番か?動かない石の霊魂に作物の生育を助けるよう頼むことはできないし、心優しい花の霊魂に捕食者から私たちを守るよう頼むこともできない。自然の霊魂と交信するにはまず霊魂に自らを紹介し、友情とも呼べる関係を築かなければならない。
霊魂はドルイド魔術の影響を受けるが、私は多くの場合、その手段に反対している。霊魂が苦しんでいるのでない限り、自然な状態に介入する理由はない。攻撃的な霊魂でさえ、変化させようとするより手を出さずに放っておいたほうがいい。それが真の道である。私たちが自然を支配できたとしても、この世界のためにはならないだろう。イフレは決してそんなことを望みはしなかった。それに誤った魔術が霊魂の性質を歪めてしまったら、危険でもある。
まとめると、私たちドルイドは自然を尊重し、すでに存在するものの調和を乱さないよう努めている。この大地や海に住む多くの霊魂と交信できることは私たちにのみ許された栄誉であり、そのことを決して軽く考えてはならない。
出荷ラベルShipping Label
ショアバード運送代理店
差出人:ダガーフォール
宛先:揺るぎなき邸宅
内容
防具屋〈雄鹿と馬〉から木枠箱6個
担当者:揺るぎなき者の会、マルガリーテ隊長
助けになる揺るぎなき手A Helpful, Steadfast Hand
市井の歴史家、アダンドラ 著
揺るぎなき者の会はシロディールの戦場と、タムリエル中の自然災害の発生地でその名声を築いた。バカロ・ヴォロラス卿によって創設されたこの会は治癒師や看護師、および物資を抱えたチームを必要に応じて移動させるための、小規模な騎士団によって構成されている。
バカロ卿は繰り返しこう述べている。「我々はできることをやっている。これ以上のことができる人数や資源があればいいのだが」
ブラヴィルの街近くでは、エボンハート・パクトとアルドメリ・ドミニオンの軍が激戦を繰り広げた後で素早く現地に入り込み、戦争による負傷者や避難民に支援を提供した。著者は兵士と市民に話を聞いたが、どちらも戦いで受けた負傷を、この会の治癒のテントで治療している最中だった。
「ここの善良な治癒師たちの手早い治療のおかげで、私の足が救われたのは間違いない。あのハイエルフの槍で貫かれた時は、この足を失うことになると確信していた」と、北の僻地から来たノルドの兵士ヘイルブリットは説明した。
「私は何かの呪文の爆発に巻き込まれたんだ」とブラヴィルの住民ルリウスは言った。「私の家も破壊されたよ。この会がなかったら住むところもなく、家族は飢え死にしていただろう。バカロ卿の慈悲に感謝する!」
「この戦争は忌まわしい」と癒し手プロールは言った。「若者の内臓を、手で握らずにすむ日が来るのが待ち遠しいよ。でもそれまでは、力の限り支援を続ける。やらないわけにはいかない」
その後、私はハイ・アイルにある揺るぎなき者の会の本部を訪ねた。ここは携帯可能なテントでは処置できない、より集中的な長期の治療が必要になる負傷者を扱う診療所を擁している。バカロ卿は一族の地所のかなりの部分を、この会が使用するために割いている。
「私はその力がある者は誰でも、可能な限り他者の手助けをするべきだと信じている」とバカロ卿は言う。「良心があるなら、そうせずにはいられないだろう?」
三同盟すべてが揺るぎなき者の会の中立性と優れた活動を尊重し受け入れているが、だからといって自分たちの防備を顧みないわけではない。私はこの点について揺るぎなき者の会の副官であり、騎士団のリーダーであるマルガリーテ隊長に話を聞いた。
隊長は次のように説明してくれた。「私たちのテントやキャラバンは食料や医薬品などの物資を大量に運んでいるから、野盗や怪物の標的になりやすい。だから、基本的にその時発生している戦争に参加している戦闘員を恐れる必要はなくても、私たち自身を守る必要はある。騎士の数は多くないけど、私たちのところで働く騎士たちはよく訓練されていて、勇敢すぎるくらいよ。私は彼らの指揮官であることを誇りに思っているわ」
あなたが戦争や飢餓、病気のために支援を求めるようなことがあれば、揺るぎなき者の会の治癒のテントに掲げられた特徴的な旗を探そう。「私たちは助けを必要としている者なら、誰も追い返すことはない」とマルガリーテ隊長は言っていた。
新たな成功を祝して!Congratulations On Another Success!
宛先:ゴンファローネ湾マンドレイク邸、レディ・アラベル・ダヴォー
またしても、あなたは予想を上回る偉業を成し遂げました!あなたの行いにより、三同盟の指導者たちが苦痛に満ちた死から救われたのです。これで和平は単なる希望に留まらず、実現する可能性が残されました。私の称賛と共に、この希少なビンテージをお楽しみください。これからもご健闘のほどを!
差出人:あなたの崇拝者より、情熱と感謝をこめて
生命の儀式の始まりRitual of Life’s Commencement
あらゆる生命が存在するのは、それ以前の生命が存在したおかげである。我々はすべての生物の喜ばしい創造を祝い、その歓喜に浸ることを奨励する。
適切な時期に、儀式は指導役の二人組と共に開始される。彼らの模範は風に舞う種のごとく拡散するだろう。情熱を分かち合うことは、生命の報酬である。
次の月の周期に、我々はこの力を受け入れる。完了すれば、その力は満たされ旅立つだろう。
捜査官ヴェイルとダークマストInvestigator Vale and the Darkmasts
捜査官ヴェイルは港に立ち、地平線まで伸びる青い海をじっと眺めていた。ガレンを訪れるのは初めてだった。彼女はもう何度もシストレスを旅行していたが、これまではいつもハイ・アイル止まりだったのだ。
「どう思う、捜査官?」と騎士団長が尋ねた。「これは恐るべきダークマストの仕業だろうか?」
ヴェイルはため息をついて、再び木の板の上に横たわった死体を見た。明らかに港で働いていたこの地域の人間で、海風と船の油の匂いがするたくましい作業員だ。今は残念なことに、死臭がそれに加わっていた。
「海の近くで出た災害や死人をすべて海賊やシーエルフのせいにするのは簡単だけど」とヴェイルは言った。「この犯罪にはシーエルフの略奪らしい形跡がないわね」
騎士団長は顔をしかめた。「確かなのか?アダラードは明らかにこの埠頭で殺された。それに彼に加えられた暴力を見てくれ。ダークマストがもっと悲惨な目に遭わせるのを私は見てきた」
「そのとおり!シーエルフ海賊が沿岸までやって来て、たった一度の攻撃で済ませるなんて聞いたことある?略奪も破壊もせずに?それにこの傷はサーベルや戦棍のような、ダークマストが使う典型的な武器によるものじゃない。この男は作業員のフックで殺されたのよ。そして犯人は哀れなアダラードが殺される前に、これを何度か武器として使っている」
その時バラリン・ルモンズという作業員が進み出た。邪魔をしないよう離れていたが、ヴェイルと騎士団長の会話が聞こえる程度には近くにいたのだ。「違う、俺はダークマストの船をこの目で見たんだ!」と彼は怒鳴った。「アダラードを殺したのはシーエルフだ!シーエルフに間違いない!」
騎士団長はバラリンとヴェイルの間に入り、厳しく、だがなだめるような口調で言った。「落ち着け、バラリン。お前の証言は聞かせてもらった。捜査官に仕事をさせてやれ」
「ちょっといい、騎士団長」とヴェイルは口を挟んだ。「バラリンだった?あなたのベルトにフックが垂れ下がっていないのが、どうしても気になるんだけど。有能な港の作業員で、フックを持たずに歩く者なんて私は知らないわ」
バラリンは目を細め、表情は険しくなった。「一体何が言いたいんだ?」と彼は詰問した。
騎士団長はヴェイルからバラリンへと目をやり、彼の表情もまた険しくなった。「質問に答えろ、バラリン。お前のフックはどこだ?」
バラリンは答えず、騎士団長を捜査官ヴェイルに向けて突き飛ばし、向きを変えて逃げだした。それを予測していたヴェイルはあっさりと横に移動してかわした。ヴェイルは何気なく手を伸ばして木箱から魚をつかみ取った。もちろん、朝の漁獲分の残りである。そしてバラリンに向かって投げつけた。魚は彼の分厚い首の後ろに気持ちのいい音を立てて直撃し、気絶させた。男は地面にぐったりと伸びてしまった。
「バラリンのフックを見つければ、凶器が見つかる。これはシーエルフの襲撃の結果じゃない」とヴェイルは説明した。「仕事仲間同士の口論が行き過ぎただけよ」
騎士団長は意識を失った作業員を縛り上げてから、ヴェイルに向き直った。「問題が我々の間で起きていることを認めるよりも、外から来たものだと信じるほうが楽だったという話のようだな」
ヴェイルは木箱から別の魚を選び出して匂いを嗅ぎ、袋に入れた。「夕食用にもらうわ」とヴェイルは言った。「報酬から値段分を引いてくれてもいい。まあ、あなたの言うとおりよ騎士団長。私たちは身近にいる人々を仲間だと思いたがる。安全だとね。でも私の経験上、ほとんどの殺人事件の犯人は犠牲者が知っている人物で、偶然出会った未知の悪党じゃない」
立ち去ろうと向きを変える途中で、ヴェイルは付け加えた。「でもだからといって、ダークマストに警戒しなくていいわけじゃない。奴らはあなたの作業員を殺さなかったけど、危険には違いない。さて、この魚の調理法を知ってる人を探しに行かなきゃ。誰かいい人を知らない?」
太陽のごとく恐れを知らずFearless as the Sun
ガレンの詩人、ニネル・ドゥマリス 作
海に踊る太陽のごとく恐れを知らず
短く力強い一瞥で私の心を見抜く
私の恋人は夕刻の雨を駆け抜け
陸へ来て私を求める、彼の財宝を
だが別の乙女が彼の心を招き寄せる
私を選んだことを妬む、魅惑的な美女
千人の恋人を虜にしてきたこの敵手が
今や私の恋人に向かって声を張り上げる
女がただ呼びかければ、彼はそちらへ向かう
海鳥の笑い声、鐘の音、船長の呼び声
魅了された彼は、雄鶏が鳴くよりも早く去っていく
あの女の力は強く、私の力は弱い
だが泣いても仕方がないことは知っている
定命の女が海に勝てるはずはないのだから
注意!大樽に触るな!Warning! Do Not Touch Cask!
このエール樽の中身には極度の圧力がかけられている。いかなる事情があっても触れてはならない。
これは警告である。
嵐とひまわりThe Storm and the Sunflower
(シストレスの歌)
ひまわりよ、波の音が聞こえるだろうか
私たちを引き合わせてくれた海が、今は引き離そうとしている
私はもうすぐ最後の息を吐き
心に愛の傷を抱いて死ぬだろう
望まぬ戦争を終わらせる夢を見たことを、慰めと思いながら
さあ、頭を下げて
その柔らかな花びらのような唇で、最後の口づけを
抱き寄せて、私のひまわりよ
私たちが交わした愛は、罪ではない
ただマーラの慈悲を知ることを、時が許さなかっただけ
あなたが雨の雫を味わう時、私の唇を思い出して
あなたが顔に風を感じたら、それは優しく撫でる私の手
そして遠くに雷鳴が聞こえる時、それはあなたの名を呼ぶ私の声
雷がひまわりと出会う時は、辺りを炎に包むものだから
ひまわりよ、私を覚えていてくれるだろうか
結ばれて、誰にも縛られず自由になる夢を共に見たことを
それとも、あなたも私の後に続くだろうか
ただ一緒になりたいがために、私たちが犠牲にしたものを思いながら?
海を飲むつもりなら、雨を求めてあえがなくてもいい
嵐とひまわりThe Tempest and the Sunflower
ニヴィエンヌ・トネール 著
実話を基にした物語
レディ・マーラがナヴィール城の馬上槍試合の会場に微笑みかけた。二人の騎士、好敵手、よく似た心の持ち主の運命的な戦いに、これ以上ふさわしい日はなかった。
船大工を代表する、金髪のサンフラワー卿は、ガレンの長女、憂鬱なるレディ・テンペストと対峙した。どちらも、相手の家名に憎悪を抱くよう育てられてきたのだ。槍は互いに向けて勢いよく繰りだされた。乱戦の中、剣は交差し火花が散った。だが兜が外れた時、両者の間に沈黙が下りた。そこに生まれた穏やかな驚愕と好奇心は、見物人ならば煮えたぎる敵意と見誤っただろう。
二人は短く言葉を交わし、それから弱々しくそれぞれの地所に帰った。最大の負傷は、打ち砕かれた心だった。トーナメントの勝者となったのはレディ・テンペストだったが、儚き台風にふさわしく、先に威勢を弱めたのは彼女だった。
***
サンフラワー卿はレディ・テンペストの想いを震える両手で抱えた。彼女は多大な労力を費やし、手紙が彼の元へ届くよう取り計らった。エルダータイド・ドルイドへ秘密裡に諸島の反対側へ届けるよう依頼したのである。今、彼はレディ・テンペストの破滅になりえた。この女はトーナメントに勝利して、彼の家を侮辱したのだ。
だが、レディ・テンペストの言葉は夏の嵐のように届いた。手紙はまるでサンフラワー卿の心臓のうちに響くこだまを書き写したかのようだった。剣が交わされた時、彼女もずっとこのまま、二人が島を隔てることなく、すぐそばに居られるよう望んだのである。レディ・テンペストの想いに対して無感動を装うことは、彼にとって最大の苦痛だった。
家族の敵意は今や、この巨大な情熱に比べれば些細なものに感じられた。なんと勇敢な女性だろう!ドルイドに助けを頼むとは、なんと賢いのだろう。彼は返事の手紙にありのままに自分の愛を記し、「あなたの破滅」と署名した。彼女が微笑んでくれることを願って。
季節がいくつも巡り、潮が満ちては引く間も、二人は手紙を書き続けた。エルダータイドはシストレスを越えて彼らの秘密の手紙を運んだ。言葉を通して、二人は互いの魂を隅々まで探った。だが時を経るにつれ、言葉だけでは足りなくなった。
今度、先に折れたのはサンフラワーの方だった。
次にナヴィール城で会う時、テンペストはトーナメントの終わりに彼と結婚してくれるだろうか?
感動の波に包まれたレディ・テンペストは承諾した。だが、誰が結婚させてくれるのか、どこで結婚するのか?
ここで、サンフラワー卿はドルイドに助けを求めた。
だが今回、ドルイドたちは見返りを求めた。
***
彼らの結婚式とグランドメレーの夜、レディ・テンペストとサンフラワー卿は夕闇に紛れて会った。一緒にいられるのはごくわずかな間だけであることをどちらも知っていた。
サンフラワー卿は彼女を腕に抱いた。長い間待ち望んでいたのだ。サンフラワー卿は恋人に願いへ同意してくれるかどうか尋ねるような、愚かなことはしなかった。
ガレンの島を去れ、とドルイドたちは言った。お前たちが結婚し、両家が一つになったら、ドルイドでない者は二度とこの島に足を踏み入れるな。
愛のためなら大きすぎる代償などない、と強がることもできた。だが二人は、自分たちの家が決してそれを許さないことを知っていた。結び合わせるくらいなら、家族は二人の死を選ぶだろう。ましてやエルダータイドの求めるものを与えるなどもってのほかだった。
「ガレンが私だけのものであったなら、喜んで譲り渡しましょう」とレディ・テンペストは言った。まるで彼の考えを読むかのように。「ただ――」
「臣下たちを見捨てることはできない」とサンフラワー卿は彼女の心を読み、言った。
サンフラワー卿は彼女の目を見つめた。
「結婚する場所は気にしない。結婚などしなくてもいい。ただ一緒にさえいられれば」と彼は言った。「どんな名前でも、どんな旗の下でも、結婚しようがしまいが、私は君のものだ。トーナメントが終わったら、人目を盗んで抜け出し、私の父の船を奪おう。祝祭も、秘密の結婚式も忘れよう。シストレスが私たちを結び合わせてくれないのなら、そうしてくれる国を探そう」
そうして彼らは次の日に会う約束をして別れた。暗闇の中にエルダータイドの耳があることにも、復讐の罠が彼らの周りに仕掛けられつつあることにも気づかずに。
***
サンフラワー卿は彼の婚約者、正当なるチャンピオン、強敵テンペストと対峙した。これはすべて見世物だ、と彼は自分に言い聞かせた。今夜、彼は恋人と海辺から去り、死ぬその時まで共に暮らすのだ。
だがそれについて、実現したのは半分だけだった。
剣が最後に交わされた。誰が勝つかは問題ではなかった。ただ敵意が本物に見えればよかった。彼の剣が彼女の手首をかすめた時に滴った血は本物だった。彼女がバランスを崩し、膝をついて倒れたのも本当だった。彼は叫んで彼女を抱きとめ、彼女の顔が苦痛で歪む…待て、これは本当なのか?
「ドルイドが」レディ・テンペストは声を絞り出した。二人はようやく気づいた。剣に揺らめく毒に。エルダータイドはテンペストとサンフラワーがガレンを渡さないのなら、互いの破滅となることを確実にしたのだった。
レディ・テンペストが息絶えると、サンフラワー卿は首を垂れて泣いた。結び合うよりも死ぬことを世界が望むならば、彼は死ぬことを選ぶであろう。