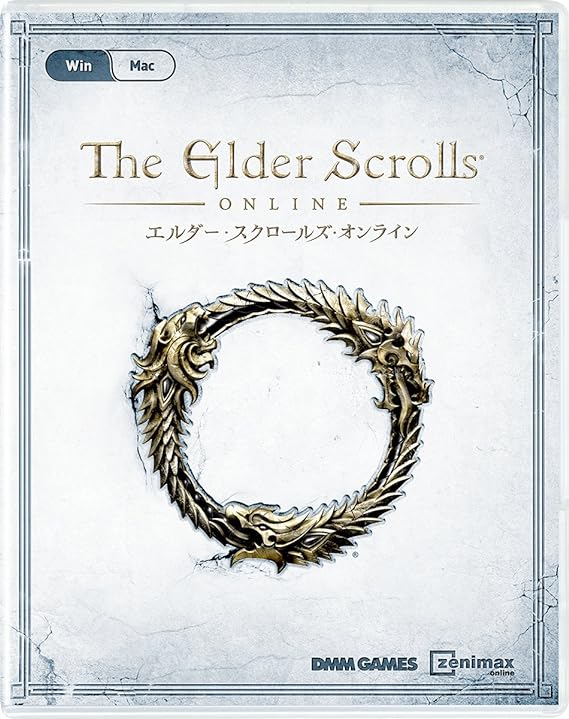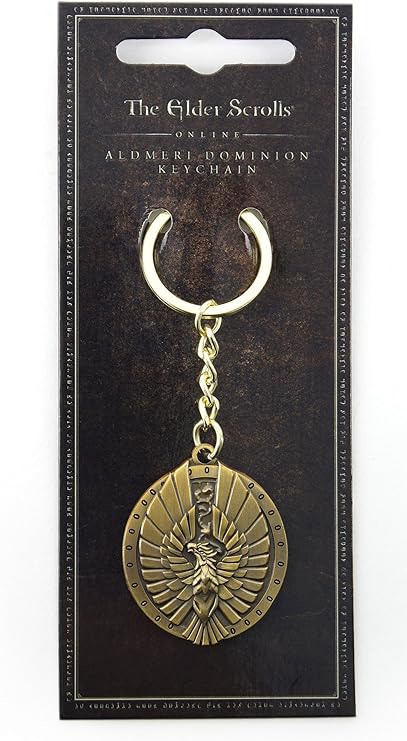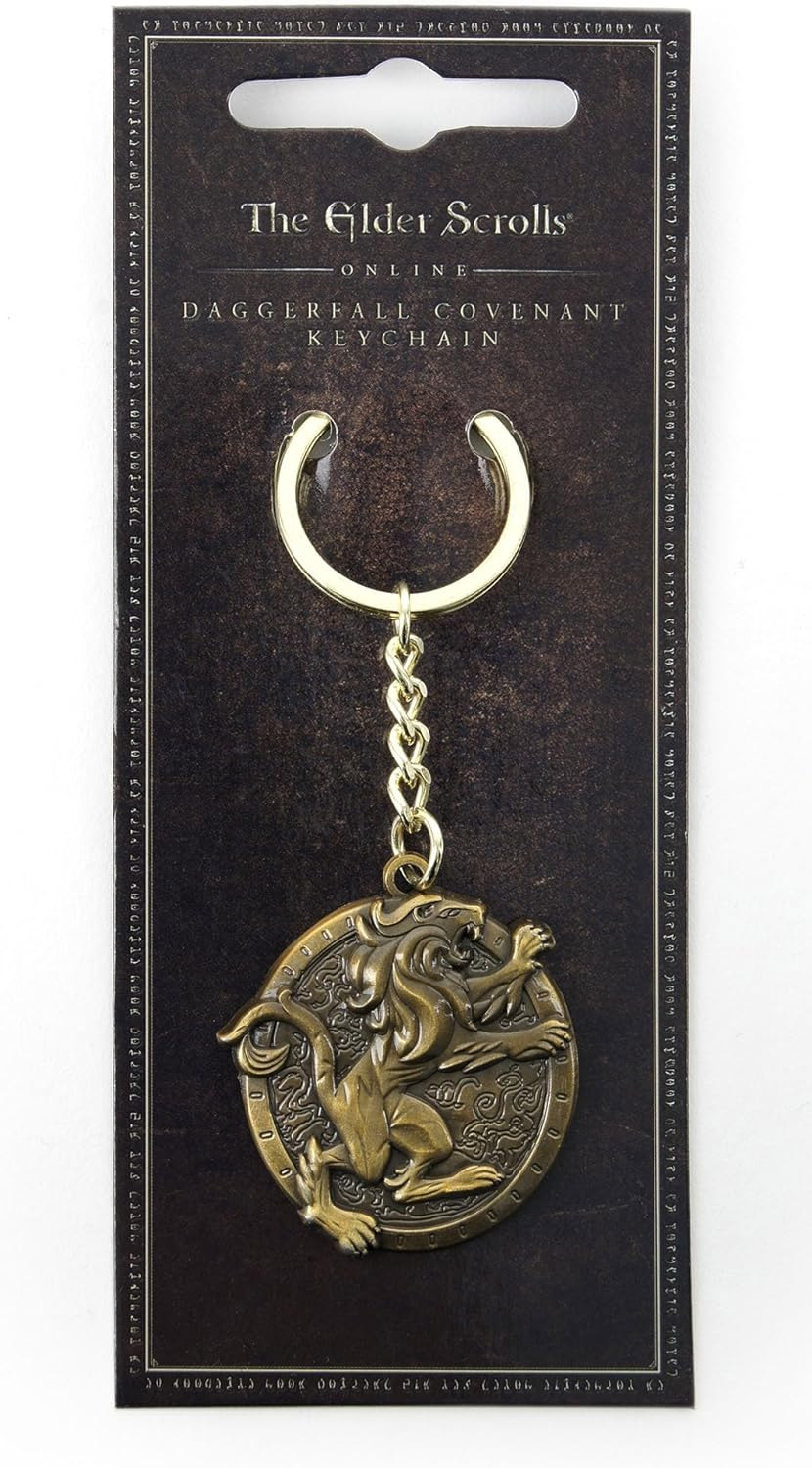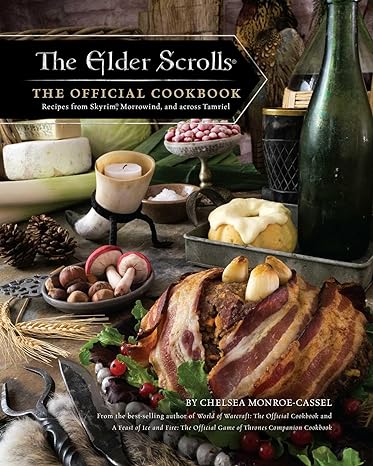スカイリムのオークOrcs of Skyrim
最果ての放浪者ソーラ 著
スカイリムのノルドにとって、これまでのところオークほど叩いても叩いても自分たちを悩ませる存在は他にない。あの牙の生えた連中が我々の麗しい郷土の占有を主張したのは、遠くイスグラモルが「亡霊の海」を渡る以前までさかのぼる。当時の記録はほとんど現存していないが、同胞団がスノーエルフを駆逐するかたわら、オーク要塞を一つ残らず滅ぼしたことについては、さまざまな歴史に言及がある。
オーク要塞は防備の堅い拠点であり、鉱物資源の鉱床の周囲に築かれることが少なくない。十数世帯が暮らせる施設を擁し、周囲には最強の軍勢以外どんな相手でも撃退できるよう設計された防壁が巡らせてある。領内のオーク要塞を滅ぼそうと企てた挙句、果たせずに命を落としたことで歌にうたわれ、記憶にとどめられている首長は数知れない。オーク要塞を単に滅ぼせないだけならまだしも、滅ぼしたはずの要塞が世代も代わらないうちに復活することもしばしばである。それを防ぐにはノルドの砦で対抗するしかないが、その場合は兵員と糧秣を絶えず補給しなければならない。
岩を積みあげただけの砦とも呼べないような代物を数年以上にわたって守る余裕のある首長などほとんどいない。だから、オーク要塞は依然として我々の土地の病巣であり続けている。オーク要塞の中にはこの調子で数千年とは言わないまでも、数百年存続しているものがある。イーストマーチのクレイドルクラッシュにある古いオーク要塞などは、地下の鉱脈が完全に枯れてしまったにもかかわらず、これまで攻め落とされたこともなければ打ち捨てられたこともないと言われている。
スカイリムにおけるオークの勢力が絶頂に達したのは、第二紀の初頭、ヤシュナグの族長国が樹立されたときである。ブレトンとレッドガードの連合軍によるオルシニウムの破壊を契機に民族大移動を強いられたオークたちは、北の大地全土に離散する。ハイロックを追われたヤシュナグとその民は東へと逃れ、いにしえの権利によって自分たちのものだと彼らが感じるスカイリムの土地を奪還しようとした。西スカイリム王のスヴァートルは、西王国を蝕むオークやリーチの民を撃退する能力に欠けていた。ヤシュナグの族長国は30年余りものあいだ西ファルクリースを悩ませ続けた末、第二紀の467年に「ヤシュナグ殺し」のハックヴィルドによって焼き払われた。
ハックヴィルドがファルクリースの首長になったのは、父親である先代首長が戦場でヤシュナグに殺されたからである。若き首長が継承したのは、西から攻めてきたオークの侵略者たちに大部分を占領された、崩れかけの砦以外にほとんどなかった。ハックヴィルドはヤシュナグとヤシュナグに従うオークの勇者たちに決闘の儀式で勝負をつけようと申し込み、1人ずつ倒していったと言われている。この知られざるオークの儀式をハックヴィルドがどうやって知ったのかは詳らかになっていないが、指導者が倒されたのを見て、ヤシュナグの追従者たちは族長国を捨て、去っていった。
ヤシュナグの族長国が崩壊すると、オークはスカイリムのさらに奥へと入り込んで散らばるか、または後退してロスガーの山々に分け入った。ヤシュナグの民を祖先に持つオークの諸部族は、スカイリムの歴代王に対して激しい憎悪を燃やしてきた。オークが数百年前に自分たちの故郷を焼き払ったタムリエル西部の民とさえ関係を修復していることを考えると、ノルドに対する彼らの敵意がこうまで大きくなったのは、皮肉としか言いようがない。
スカイリムの霊魂Spirits of Skyrim
学究の徒イシティルレ 著
スカイリムでも往来の少ない寂しい道には、さまざまな霊魂が出没する。そうした英魂の一部は凶暴で恐ろしい存在だ。彼らは定命の者を憎み、ねたんでいる。それ以外の霊魂は単にいたずら好きなだけだが、彼らが山ほど用意している無邪気ないたずらは、仕掛けられた側がきちんとそれに気づかないようだと危険なものに変わりうる。少数ながら、中には気立ての良い霊魂もいるとはいえ、そういう霊でさえ、こちらが礼節を欠いたり敬意に乏しかったりすれば敵意を露わにしてくる可能性がある。一口に霊魂と言っても、自由にさまようデイドラから、死んだ定命の者や自然の化身まで多種多様だ。もっとも、脅かされている当事者にとっては、そうした区別にさほどの意味はないかもしれない。あれこれ悪さをしてくる霊魂が、さまようデイドラだろうとこの世にぐずぐず居残っている村の小作人の亡霊だろうと誰が気にするだろう?どちらにせよ、実体を持たない存在であることに変わりはなく、危険な相手であることにも変わりはない。
ウィンドヘルムのずっと南に広がる「亡霊の森」は、遠い昔から謎と危険に満ちた場所だった。閃く光や抗しがたい囁き声が、どんなふうに旅人を森の奥へと誘い込むかを語る物語はそれこそ枚挙にいとまがない。本来ならば用心深いはずの地元の農夫や木こりたちでさえ、太陽が中天高く登る時、あるいは夜闇が大地を覆いつくす時、奇妙な物音や怪しい光景の犠牲になってきた。そういう話には事欠かない。
そうした霊魂の一種に、湖や丘や木立といった特定の土地に縛られた、ガーディアン・スピリットがある。彼らは緑のある一帯に出没し、そこを捨て去ったり、そこから遠く離れたりすることはできない。定命の者の前に現れるとき、ガーディアン・スピリットは定命の者の姿をとることが多い。だが、騙されてはならない。こうした霊魂は決して定命の存在ではないし、定命の世界からかけ離れていることはオブリビオンの住人と変わらない。彼らは定命の者の振る舞いを真似るかもしれないが、そうした振る舞いを理解することもなければ、そうした振る舞いにほんのわずかでも関係があるわけでもない。
ガーディアン・スピリットは決まりきった日常に飽きるかもしれない。また、縄張りに迷い込んできた新たな生き物に興味を抱くかもしれない。ことによると、自分の領分を訪れた定命の存在から侮辱を受けたと思い込んで、怒りに駆られることさえあるかもしれない。いずれにせよ、そういう場合はガーディアン・スピリットの注意を引いてしまう。あるいは、今挙げた3つとは全然違う理由から、ガーディアン・スピリットに目をつけられることも考えられなくはない。この世ならぬ存在が何に動かされているかなど、いったい誰に分かるだろう?
亡霊の森のガーディアン・スピリットは、物見高くいたずら好きではあるものの、定命の訪問者に対していきなり敵意を示すことはまれだ。あの森の中で何かをなくす、怪しい何かが現れる、無邪気ないたずらを仕掛けられるといった話には事欠かないが、森が底を訪れた定命の者に牙を剥いたという話はほとんどない。どうやら、少なくともこの霊魂に限っては、我々と何らかの関係を築こうとしているように見える。あるいは、そういう考えもまた、霊魂の意図を誤解しているだけなのかもしれない。ひょっとしたらこのガーディアン・スピリットは、単に森を訪れた者を油断させようとしているだけなのかもしれない。相手が気を緩めたところを見計らって、襲いかかるために。
ストームフィスト・クランThe Stormfist Clan
最果ての放浪者ソーラ 著
ノルドのクランはマンモスの群れのようにスカイリム全土に広がったが、その数と土地におよぼす影響力はマンモスの比ではない。もっとも、各クランが名を馳せる理由はそれぞれ違う。狩猟の腕前で知られるクランもあれば、森林に精通していることで知られるクランもあり、クラフトの技術で知られるクランもある。大柄なクランもあれば、小柄なクランもある。政府や共同体で華々しく活躍するクランもあれば、忌まわしく、暗いイメージがつきまとうクランもある。後者は誰もが関わり合いになるのを避け、その名を口にするのも憚られるクランだ。そうしたクランの1つとして、ホワイトラン・ツンドラを本拠地とする悪名高いストームフィストを挙げられる。
ストームフィストの系譜を遡れば、クランの始祖であり50年近くに渡って率いた力強い女族長、オグラ・ストームフィストに辿り着く。戦闘技能と鎧作りの腕前を高く評価されたストームフィスト・クランは、何世紀にも渡り、数々の戦いで中心的な役割を果たした。ホワイトラン要塞の戦い、ダイアルマーチの虐殺、ウィンドヘルム包囲…。ただ、ウィンドヘルム包囲を最後に、この一族は信頼を失い、忌むべき存在の烙印を押されてしまう。
第二次アカヴィリ襲来の前夜、東スカイリムを統べるマブジャールン女王の息子、強健王子フィルジョアは、異郷とそこに住む人々を自分の目で見るため西方に旅した。そこで王子はストームフィスト・クランの若い男女たちと出会い、後に大いに役立ってくれる友情と絆を育む。やがて、成人の試練に挑む覚悟ができたフィルジョアが旅を再開する際、ストームフィスト・クランの仲間が彼と旅を共にすることを決める。やがて彼らはストームフィスト旅団と呼ばれるようになり、フィルジョアは生まれながらの仲間ではないにもかかわらず、事実上の指導者となった。
もし、それ以前のストームフィスト・クランに何がしかの評判があったとしても、ストームフィスト旅団が築いた伝説の前で色あせてしまった。彼らは勇猛な戦士たちであり、冒険を求めては、王国で最も敵意に満ち、最も周囲から隔絶された地域へと足を向けた。フィルジョアに率いられた彼らは山賊の集団を潰走させ、埋もれた財宝を見つけ、怪物を倒した。アカヴィリの侵略軍が攻め寄せたとき、フィルジョアはストームフィスト旅団を率いて戦いの渦中に身を投じる。そうして彼らはついにウィンドヘルムまでたどりつき、マブジャールン女王及びその主力との合流を果たした。
ウィンドヘルムの陥落を防ぐことも女王を救うこともできなかったものの、ストームフィスト旅団は侵略軍を敗走させるために功があった。彼らはノルド連合軍の一翼を担い、土壇場で加わったダークエルフおよびアルゴニアンと共にアカヴィリを打倒したのである。しかし、それに続いて運命の決断がなされた。フィルジョアが姉ナルンヒルデの死によって空位となった玉座に就く意思を表明したとき、ストームフィスト・クランは王子を最も強く支持する輪に加わったのである。その結果どうなったかは承知の通りだ。ジョルンとフィルジョアは一対一の果し合いにおよび、結局ジョルンが玉座を勝ち取った。フィルジョアは追放の憂き目に遭い、いつか戻ってくることを誓ってスカイリムを離れた。
ストームフィスト・クランはフィルジョアに対する忠誠を最後まで貫き、ジョルンの前に頭を垂れることも、その王たる権威が自分たちに及ぶのを認めることも拒んだ。彼らは西の故郷に帰ってゆき、戦いに倦み疲れていたジョルン王もあえて止めようとはしなかった。以来今日に至るまで、ストームフィスト・クランは外界との交わりを絶ち、自分たちの縄張りから外に出ることも、クランより大きなノルドの共同体に加わることも稀だ。ただし、もし彼らが故郷のツンドラ地帯を離れ、他のクランの間で地位を回復しようと決意した場合、何が起きるかは誰にも分からない。特に、もしフィルジョアが自らの誓いを果たしたとしたら、そのときどうなるかは神のみぞ知る。
テルニオンのモンクThe Ternion Monks
書記エルガド 著
テルニオンのモンクについては、邪教の教団だと切って捨てる者もいれば、さらに悪しきものだという者もいる。しかし、彼らは三柱の古き神々とそのそれぞれに結び付いたトーテムを崇める伝統の担い手なのだ。古くから存在する信仰だが、今や帰依する者はほとんどいない。多くの点で、テルニオン信仰はゆっくりと死に向かっていると言える。というのも、現在のモンクによる布教の成果は微々たるものだからだ。三柱の古き神々の崇拝に改宗する者の数が減る一方であることを考えると、この信仰がただのぼんやりとした記憶と化してしまうのは時間の問題かもしれない。
治癒魔法で知られるテルニオンのモンクは、三柱の古き神々の姿を呼び出すことができる。それらの姿の助けを借りて、彼らは単なる定命の存在に許された範囲を超える務めを果たせるのである。それぞれの姿は三柱の古き神々を模している。すなわち、狐、熊、狼である。
狐はずるがしこく、機敏で、その姿は自分を呼び出したモンクの速度と敏捷性を増大させる。
熊は堂々たる体躯と膂力を有し、守護者となる。その姿は自分を呼び出した者の力を強くし、その者を危害から守る。
狼は抜け目がなく鋭敏で、獰猛かつ危険な存在だ。状況を見定め、待機し、行動を起こす絶好の機会を探す。その姿は自分を呼び出した者の視野や知覚を広げ、よりはっきりと物事が見えるようにする。その結果、隠れているものや曖昧なものに気付くようになる。
テルニオンのモンクは自分以外の誰かがほとんど近づけないような場所で瞑想にふけり、神々を崇めることを好む。モンクの魔法を使わないかぎり、そうした神聖な隠れ処にたどりつけないことも少なくない。ガーディアンは他のモンクか、よほど差し迫った必要に駆られた、道を開いて通すに値する相手に求められなければ道を開かない。
私はモンクたちと共に過ごすことで、彼らの流儀の幾分かを学び、彼らが実際に治癒魔法を使うところも目にした。彼らは価値ある伝統を守り、今に伝える善良な人々だと思う。けれども残念ながら、今の世代が死に絶えた時、テルニオンのモンクと三柱の古き神々の崇拝は、次第に消滅の道を辿るだろう。
そしてそれは、悲しむべき日になるに違いない。
フレイディスの王冠The Crown of Freydis
神話の作り手タレオン 著
我らが敬愛するマブジャールン女王が戴くフレイディスの王冠には、長い歴史がある。名高いその美しさについて知る者は多いが、この王冠の本当の使い道や、この王冠が作られた経緯を知る者は少ない。そして、フレイディス女王以前の君主たちもこの王冠を被っていたという事実も、ほとんど知られていない。
フレイディスの王冠は、実を言うとスカイリムでは2つめの王冠である。最初の王冠の栄誉は、「尖った王冠」に属する。これはノルドの初代王ハラルドがドラゴンの骨から作った王冠で、伝説によればハラルド王の血を引く最後の王ボルガスが、第一紀369年のワイルドハントで落命した際に行方知れずになったという。イスグラモルの系譜に連なる最後の1人であったボルガスには子がなく、彼の死は「継承戦争」と呼ばれる血で血を洗う内紛の引き金を引いた。
継承戦争は隻眼のオラフが新しいスカイリムの上級王になるまで、5年余り続いた。オラフが王に選ばれた主たる理由は、ヌーミネックスというドラゴンを退治したことで得た名声であり、仁徳や政治的手腕を見込まれてのことではまったくなかった。隻眼のオラフによる治世は、ノルドの間で大きな争いと分断が起きたことによって特徴づけられる。オラフがボルガス同様に明確な世継ぎを残さず死んだとき、上級王を選出するための新たな手続きを導入することが決まった。
かくして、スカイリムの各要塞から1人ずつ選出された魔術師たちが一堂に会する。目的は、上級王の有力候補の適格性をテストする魔法のアーティファクトを作製することだった。この時彼らが創り出したのが「認証の王冠」である。王冠の形をしたアーティファクトの作成は革新的なアイデアだった。というのも、「尖った王冠」が失われてから、オラフは一目でそれとわかる王権の象徴を身に着けなかったからだ。この新しい王冠が、比較的不安定だったオラフの治世後、新王の元で国がまとまる助けになるだろう。そう魔術師たちは感じた。この王冠が作製されたタイミングは、吉兆だったと言える。
さて、ムートは氷砕きのアサーンという族長を次期スカイリム上級王に選出する。アサーンはドラゴンを倒したことこそなかったものの、隻眼のオラフ同様、武勇無双の戦士だった。しかし、即位する前に、アサーンは完成間もない「認証の王冠」を被る必要があった。このアーティファクトが持つ、本当の力が明らかになったのはその時である。
王冠はアサーンを拒絶した。文字通り、彼の頭に載せられることを拒んだのである。激怒したアサーンは忠実な支持者たちを呼び集めて周りを固め、もし自分を正統な王として認めなければ皆殺しにしてやるとムートに迫った。アサーンとしては、王冠ごときに否定される気は毛頭なかったのである。すると、ムートのメンバーに名を連ねる語り口の穏やかな男が椅子から立ち上がった。彼は法に則り、アサーンに戦いを挑む。勝負は短時間で決着がついた。アサーンは打ち倒された。語り口の穏やかなその男が王冠を手に取り、難なく自分の頭の上に載せた瞬間、スカイリムの新しい上級王が誕生した。これが、「白のジョリック」が王位に登ったいきさつである。
以来今日まで、フレイディスの王冠は上級王から上級王へと受け継がれてきている。この王冠は上級王の候補について、それが誰であるかにかかわらず、ムートが適格性を確かめるために使われている。アサーンが倒されてからというものの、王冠の正当性やその力に疑義を唱える者は誰もいなかった。第二紀の431年、レマン帝国が四分五裂し、ログロルフ王が暗殺されるまでは。
ログロルフの娘フレイディスは庶子であり、したがって王位継承者はムートによって選ばれなければならない。ソリチュードのスヴァートル首長がそう主張したのである。「認証の王冠」を被ったフレイディスがウィンドヘルムで上級女王に指名されていたにもかかわらず、ソリチュードで開かれた不公正なムートはスヴァートルを上級王に選出する。それ以降、西王国はスヴァートルとその後継者たちによって統べられ、東王国は「認証の王冠」という呼称を自らの名を冠したものに改めた、フレイディスの跡継ぎたちによって治められた。
巨人のすべてAll About Giants
第二紀569年、スカイリムの巨人族の観察記録。放浪者ボノリオンの日記より
イーストマーチとリフトの雪深い辺境を探索したとき、私はスカイリムの原住民たちが「巨人」と呼ぶ風変わりで図体の大きな人々を観察する機会に恵まれた。スカイリムの原住民からして大柄だが、雪に覆われた原野を放浪する巨人の身長は、猪首で肩幅の広いノルドの平均身長の2倍(もしくはそれ以上!)もある。ここに、私が観察の結果知り得たことをいくらか書き記しておきたいと思う。将来この寒冷な地を旅する人々の役に立てば何よりだ。
巨人は背が高い
巨人たちは見たところ、いたっておとなしい。ただし、怖がらせれば話は別だ。そうなると彼らは巨大な棍棒を振りまわし、筋骨たくましいノルドさえ野や川の向こうまでぶっ飛ばしてしまう。これをやられたノルドは十中八九助からない。もっとも、巨人の全力攻撃を浴びて命を取り留めた者の話を聞けた試しがないから、あくまでも私の推測に過ぎないが。
巨人を怖がらせる行動としては、次のようなものがある。ただし、これらに限るわけではない。
側に近づく。
マンモスに手を出す。
矢を射かける。
私が話を聞いた人々の中に、巨人の女性や子供を見たという者はいなかった。巨人は子供でもボズマーより背が高いのだろうか?また、巨人の女性はひどく内気ではにかみ屋なのだろうか?この件については、さらなる観察が必要だ。
巨人は野営地近くの岩や木に絵を描く。この原始的な芸術は、希少な女性の巨人が近くを通りかかった際、誘い込むためのものかもしれない。あるいは、縄張りを示す印か。それとも、たんに絵を描くのが好きなだけかも。その辺りを見極めるには、さらなる調査が必要だ。
巨人はどうやっいぇマンモスの乳を搾るか?答えはおっかなびっくり搾る(注:ノルドはこのジョークがお気に入りだ。ハチミツ酒を何杯か飲んだ後は特に)。
話を聞いたノルドのなかに、マンモスチーズを口にしたことのある者はいなかった。別段食べてみたいとも思わないらしい。
何とかしてあの図体の大きな種族と親しくなる手立てを見つけなければ。あのすばらしく香り高いチーズをひとかけらでも手に入れるには、それしか思いつかない。
第二紀571年に記された博識家ジェゴードのメモ
ウッドエルフのボノリオンはクレイドルクラッシュと呼ばれる一帯にほど近い、大きな丘のふもとで見つかった。全身の骨が砕けていたという遺体の状態からして、どうやら彼は自分自身の戒めを無視したらしい。ノルドならどんなに血の巡りが悪い子供でも、巨人に近づかないだけの分別はあるというのに。ところで、ボノリオンの亡骸が見つかった場所にいちばん近い巨人族の野営地でも、1リーグ近く離れている。これに鑑みるに、ウッドエルフは巨人の棍棒で飛ばされれば、相当な距離を飛べるということが言えるかもしれない。
私は彼の日誌を回収し、保管しておいた。イーストマーチやリフトといった、巨人が住む地域を探索しようという者の役に立つかもしれないからだ。とにかく、巨人と親しくなろうなどとはゆめゆめ考えないこと。これは、たとえ筆者自身がなおざりにしたとしても、肝に銘じるべき教訓だ。
兄弟の戦争The Brothers’ War
アカヴィリの襲来が最高潮に達していた第二紀572年、ナルンヒルデ姫の双子の弟、スカルド王子ジョルンと強健王子フィルジョア(面と向かって口にされることこそなかったが、「癇癪王子」とも)はそれぞれ、まったく違う場所にいた。ジョルンは最も近しい仲間である「吟遊詩人団」とリフテンに、フィルジョアはスカイリムの北東沿岸で、姉と共にディル・カマルのアカヴィリを迎え撃っていた。アカヴィリがウィンドヘルムに迫るなか、ジョルンとその仲間たちも急ぎこの名高いノルドの都市を目指した。
一方フィルジョアは、沿岸部の支配を巡る攻防戦が激しくなるにつれ、武勇はもちろんのこと、天井知らずの怒りを何度も繰り返し示した。彼にも「ストームフィスト旅団」と呼ばれる側近集団があり、しばしばこれを率いて戦った。ストームフィスト・クランのメンバーで構成されるこの旅団は、フィルジョアの巡礼と成人の試練に付き従い、共に戦うことで強健王子に尽くしてきたのだった。
それぞれの側近集団を従えてウィンドヘルムに到着したジョルンとフィルジョアが目にしたのは、都市の城門が破られ、大きな突破口を開けられる光景だった。双子の兄弟はどちらも雄々しく戦ったが、都市の陥落もマブジャールンとナルンヒルデ(別名「短命女王」)の両女王の死も防ぐことはできなかった。二代の女王は宮殿と愛する民を守りながら命を落としたのである。双子の兄弟は、何年も疎遠だったにもかかわらず、血のつながった者同士で意気投合し、侵略者を撃退するために力を合わせて戦った。ジョルンがダークエルフと手を組んだこと、そして意外にもアルゴニアンが加勢してくれたことにより、アカヴィリの野望はついに潰えた。
ジョルンと配下の兵がウィンドヘルムに戻ると、フィルジョアが姉の後継者に名乗りをあげる。危機が去った今こそ潮時だと、そう強健王子は考えたのだ。彼はジョルンがおとなしく従うものとばかり思っていた。それまでも、フィルジョアの怒りと抑えきれない情熱の前に、ジョルンは大抵そうしてきたからだ。ところが、予想に反してジョルンは異を唱えた。スカルド王子は「スカルド王」になることを決意したのである。というのも、彼はフィルジョアの情熱がどういった性質のものか分かっていたからだ。確かに、戦を共に戦う味方としては頼もしい。しかし、民を導く指導者としてはどうだろう?本音を言えば、ジョルンは王位になど就きたくなかった。しかし、そうも言っていられない。フィルジョアが民にとって良い統治者になるとは到底思えなかったからだ。
ジョルンの反抗に怒ったフィルジョアは、ストームフィスト・クランをはじめとする自分の支持者を国中から集めた。結局のところ、彼は正真正銘のノルドの戦士であって、ジョルンのような歌い手でも学者でもないのだった。王国が内戦に突入することを危ぶんだジョルンは、フィルジョアに一騎打ちで決着をつけようと提案する。強健王子はほくそ笑んだ。吟遊詩人の兄弟など、簡単に倒せるという自負があったからだ。フィルジョアがこの提案を受け入れ、最近の歴史では最も長い3時間の幕が切って落とされた。文字通り、骨肉の果し合いが始まったのである。
双子の兄弟は、アカヴィリとの戦闘で被害を受けた宮殿の外の広場で戦った。この戦いは激しく、長く続いた。武器が切り結ばれ、受け流され、打ち合わされたと思うとまた離れ、相手に血を流させた。このままではどちらも優勢をとれないまま、疲労困憊して双方が倒れるだろうと思われたその時、ジョルンが予想外の底力を発揮した。彼は相手の武器を粉々に打ち砕くと、フィルジョアを地面に這わせ、降参するよう迫った。
他に選択肢がなかったため、フィルジョアはやむなく降参した。しかし、彼の憎しみの炎は燃え上がり、彼の怒りは吹き荒れる嵐のごとく彼の体を取り巻いた。ジョルンは心を鬼にしてフィルジョアを追放し、彼に肩入れした罪でストームフィスト・クランも罰した。フィルジョアはジョルンの名前を呪ってウィンドヘルムを離れた。スカルド王が務めに打ち込み、自らが有能で敬愛される君主であることを示している間、強健王子はダガーフォールカバナントが支配する国々に亡命したと噂された。ひょっとするといつの日か、この兄弟の骨肉の争いは再燃するかもしれない。
第二の侵略:報告Second Invasion: Reports
南中の月7日
アカヴィリの大船団が浜辺に押し寄せてくる。一部は撃退または撃沈したものの、こちらの防備をかいくぐった船のほうが多い。我が軍は前進し、浜辺を見おろす断崖の上で敵と相まみえることにした。地の利を活かす作戦だ。
見晴らしの利く崖の上から、女王は近づいてくる敵を眺め渡しておられる。ブラッドクローの獰猛さと強さを、女王は直にご覧になられるだろう!
南中の月8日
アカヴィリの船団は、沖合で錨を下ろした。恐らく我々の刃を恐れているのだろう。ならば、せいぜい船の上で飢えさせてやりましょう。私がそう申し上げると、ナルンヒルデ姫は首を振り、きっと彼らは臆病風に吹かれた訳ではなく、何か企んでいるのだとおっしゃる。私より賢くあらせられる姫のお言葉だ。私はさっそく斥候を差し向けた。敵が何か腰抜けの考えそうな策略を実行に移そうとしているのならば、その内容を突き止め、不埒な意図をくじいてくれよう。
南中の月19日
あれから1週間以上経つが、依然としてアカヴィリは攻めてこない。我が兵は落ち着きを失い、ナルンヒルデ姫も考え込んでおられる。斥候は空手で戻ってきていた。それでも、私は毎日のように斥候を出している。私に異論を唱える者などいないが、もう一度海岸沿いを哨戒してくるように命じられたときの彼らの表情を見れば、言いたいことは嫌でも分かる。
ブラッドクローは殺戮のために創設された部隊だ。待ち続けるためではない。
南中の月22日
野営地では口論やケンカが絶えなくなった。アカヴィリの船団は依然として我々の手の届かないところで待機している。海岸沿いの北と南では攻撃があったとの報告を受けた。特に南は、ダークエルフの領土までアカヴィリの攻撃が及んでいるという。よそで戦闘が起きているのに、なぜ自分たちはここでただ待っているのか。兵士たちは怪訝に思っている。そして、その怪訝な思いは怒りに変わりつつある。
目の前の船団こそが敵の主力であり、向こうは我々を誘い出そうとしているのです。女王がそう諭すと、兵士たちも頭を冷やし、短慮を慎むようになる。姫は彼らの怒りや反発をものともされない。もっと頻繁に兵士たちに語りかけてくださるとよいのだが。
南中の月26日
今日アカヴィリの船が1隻、浜に乗り上げた。夜明け前の、まだ暗い時刻だった。我が軍の兵士たちが船を取り囲み、矢が雨あられと射かけられるのを予想して身構えたか、意外にも敵の攻撃はない。今にして思えば、あれほどの大型船が浜に乗りあげること自体おかしかったのだが、兵士たちは退屈し、血に飢えていた。結局その船に仕掛けられた魔法の罠が作動し、我が方に7名の犠牲者を出した。
我が軍の兵士たちがあれほど怒りに駆られるのを、私は見たことがない。女王でさえ、なだめるのに苦労されたほどだ。アカヴィリが上陸してきたら、連中は八つ裂きにされるだろう。我々が自分の体を八つ裂きにしていなければの話だが。
南中の月29日
ダークエルフの地が蹂躙されているという報告が相次いで寄せられる。ノルドとダークエルフは本来不仲ではあるが、今度ばかりは彼らが感じているに違いない無念に共感せずにはいられない。報告で聞くかの地でのアカヴィリの狼藉ぶりに、我が軍の兵士たちは戦いへの飢えを募らせるばかりだ。
姫と話をした。今度の知らせで、ブラッドクローの鬱屈が未知の域にまで高まる恐れがあると申し上げる。王女は何もおっしゃらず、唇を一文字に結ばれただけだった。常に我々の数歩先を行っておられる姫のこと。もしや、私がまだ気づいていない何かに気づいておられるのでは?
収穫の月2日
今朝、アカヴィリが上陸してきた。ついに破壊の大波が波に打ち寄せたのだ。戦闘準備の号令が下るや、我が軍の兵士たちは冷静さを失ってしまった。彼らは闇雲に打って出、第一陣は戦列を整える間もなく敵の弓兵になぎ倒された。結局こうした無謀さの代償として我々は浜辺を失い、侵略者が我が領土に橋頭保を築くのを許す結果になった。
収穫の月3日
我々は後退を余儀なくされた。戦闘があまりに激烈なのを見かねたナルンヒルデ姫は、全軍にウィンドヘルムまで退くよう命じられたのだ。かくなる上は城壁で敵を迎え撃ち、地の利を生かして侵略者を完膚なきまでに叩きつぶしてくれよう!
収穫の月4日
この張りつめた空気。今夜にも、アカヴィリが総攻撃を仕掛けてきそうな気配だ。ナルンヒルデ姫も鎧に身を包んでおられる。ブラッドクローは姫に従うだろう。姫の命令がドラゴンの声のように聞こえるに違いない。だが、リスクは途方もなく高い。一方、双子の王子がすぐそこまで来ておられるとの知らせが届いた。戦いながらウィンドヘルムに向かっておられるという。お二人が間に合ってくださることを祈るばかりだ。
収穫の月7日
マブジャールン女王とナルンヒルデ姫は亡くなられた。ウィンドヘルムの城門が破られるのをご覧になった姫は、ブラッドクローを率いて戦いに身を投じられたのだ。彼らはかつて私が見たこともないような戦いぶりを示し、完璧な連携で暴れまわった。マブジャールン女王が討ち死にされると、皆が怒りに我を忘れそうになったが、ナルンヒルデが王冠を被られ、戦列に秩序を回復しようとされた。結局、アカヴィリは都から撤退した。向こうは我々を追い詰めたつもりかもしれないし、実際その通りだが、その結果覚醒した獣は、彼らの手におえる相手ではなかったのだ。
それでも、また彼らは戻ってきた。新女王ナルンヒルデ陛下はすでにない。本来であれば、私が配下の戦士たちを指揮し、制御できなければならなかった。死ぬべきは新女王でなく、私だったのだ。その死の責任は私にある。そのことを、双子の王子に直接説明申しあげなければ。
忍び足On Stepping Lightly
トレジャーハンターのナルシス・ドレン 著
スカイリムの土地に点在している古代ノルドの遺跡は、過去のノルド人の創造力を証明している。貴族階級の墓を建てる時、この「野蛮」と思われる人たちは、全く野蛮ではないことを証明した。我々の先祖は最も洗練されて賢い防衛策を開発していた。恐ろしいドラウグルの存在と合わせて、この墓はトレジャーハンター志望の者に相当な試練となった。
最も見落としがちなのが、墓中に展開する無数の罠だ。単純なワイヤー式落石から複雑な圧力版式ダーツトラップと幅広く、古代のノルド人はこれらの装置を多数活用した。ほとんどの罠は起動装置を探して避ければ回避できる。邪魔な物があるところによく設置されているから、床に注意したほうがいい。
ノルドの遺跡を生き残る鍵の1つが、罠を上手く使って遺跡の居住者に対して優位に立つことだ。多くの場合、起動装置の向こう側で彼らが罠にはまらないかと期待しておびき寄せるのは簡単だ。この優位はオイルトラップの時に発揮される。弓を使って犠牲者をオイルの上まで誘い出し、上にぶら下がったファイアポットに矢を放つ。ファイアポットは粉々に砕け散り、オイル溜まり全体に火がつき敵に熱い死を与える。自分がオイルのないところにいないように注意すること。さもなければ、この技で冒険が想定よりも早く終わるかもしれない。
恐らく遺跡で見つかるすべての技術で最も驚異的なのは、殺すために設計された罠がほとんどないことだ。鎖の引き方、レバー、スイッチ、圧力板をすべて活用し、苛立たしい障害がパズルとして現れて進行の邪魔をする恐れがある。これらの障壁の兆候に注意する。一ヶ所に複数のレバー、回転する柱に顔の彫刻がされていたり、大きな圧力板が部屋の床に並べてあったりする。ほとんどの場合パズルは実験でき、他の場合は遺跡のどこか別のところに答えがある。筆記用具と日誌を持っていき、見つけたあらゆるものを記録することを勧める。施設のどこかにあったものを、いつ参照しなければならなくなるか分からない。
ノルドの遺跡には通常スキーヴァーやクモなどの害虫が出没するが、ドラウグルと比べれば見劣りする。この動く恐ろしい死体はほとんどの墓にガーディアンとして発見され、無慈悲に墓を守る。ドラウグルは誰かが偶然出くわすまで休眠する傾向にあり、遭遇する狭い隙間や石棺を注意して見たほうがいい。このアンデッドは素早く静かに動くから、常に背後へ気をつける。通り過ぎた亡骸が突然動き出して、警告なしに襲いかかってくるかもしれない。
ノルドの遺跡の冒険には報酬がないわけではない。大きな建造物の埋葬室にはあらゆる財宝が入っており、金貨もあれば、魔法がかかった武器や鎧の場合もある。遺跡に点在する儀式用の骨つぼは決して無視してはならない。ほとんどが非常に価値のある古代の奉納物で満たされている。すべてではないかもしれないが、ほとんどの遺跡には大きな壁があり、魔法の碑文が書いてあるという噂があるが、まだ確認はされていない。
ノルドの遺跡について知っていることをできるだけ広範に記述したが、独自のまだ発見されていないものの中にも間違いなく危険が潜んでいる。墓に入る時は常にたくさんの装備と道具、そして頑丈な武器を持っていかなくてはならない。少しの辛抱と、鋭い眼で注意しながらそっと歩けば、ノルドの遺跡は大いなる富をもたらしてくれる。私の助言に従わなければ、多くの墓荒らしの先輩のよう、永久に閉じ込められてしまう。
夢歩きDreamwalkers
モーンホールドの学徒レイナルドによる考察
彼らは夢歩きと呼ばれている。簡単な呪文を1つ唱えるだけで、他人の夢の中に足を踏み入れることができる者たちだ。自分の最も暗い欲望、最も不埒な夢想、本当の自分自身、そういったものの一切合財が、夢歩きにかかれば開いた本のように丸裸にされる。かけがえのない思い出も、前夜の宴の残飯のように漁られ、丹念に改められてしまうのだ。
夢を歩く者たちは、デイドラ公ヴァルミーナに忠誠を誓っていると言われる。ヴァルミーナが支配する次元「夢中の歩み」に入る能力を得るため、魂を売り渡したのだ、と。この説の真偽を云々することは私の手に余る。ただ、夢歩きの技とヴァルミーナの司祭が行う秘蹟は、気味が悪いほど似通っている。
私が確認できたのは、夢の状態への入り方が違うということだけだ。ヴァルミーナの司祭は錬金術の調合薬を一滴だけ必要とする。最も優れた錬金術師の手で用意された水薬だ。これに対して夢歩きは、そういった薬を必要としない。その代わりに魔法を使うのだが、それは誰に教わったわけでも、何らかの相続手続きによって譲り渡されたわけでもない。純粋に天与のものに思える。彼らはデイドラ公の祝福を受けたのだろうか?それとも、彼らの両親が生まれてくる子供にこの力を授けようと、何らかの秘儀を執り行ったのだろうか?誰に聞いても本当のところはあやふやだし、人によっても言うことが違う。
しかし、夢歩き自身はどうなのだろうか。彼らは何のためにこの力を使うのだろう?想像してほしい。他人の夢に侵入することで、どんな大混乱が起こりうるか。考えただけで恐ろしくなる。
それでも、私が会った夢歩きたちは、みな親切で優しかった。彼らは他人を助けるために自分たちの力を使う。苦い記憶を消し、最も優秀な治癒師でさえ癒せない精神の病気を治す。単に相手の夢に触れるだけで、信じられないような奇跡を起こすのだ。なぜ私にそんなことが分かるのかというと、夢歩きがその力を使うところを、実際にこの目で見たからだ。
私の妻と子供たちはナハテン風邪を患った。さんざん苦しんだすえ死に至る、恐ろしい病だ。妻子をなくすと同時に、私は生きる意味も失った。ところが、そんな私をある夢歩きが憐れみ、チャンスをくれた。家族を失う苦しみを忘れ、家族を思い出すチャンスを。喪失の痛みから解放され、病気にかかる前の家族を思い出すチャンスを。幸せと愛を思い出すチャンスを。
その夢歩きは私の夢の中に入ってきた。目覚めると、私は穏やかな気持ちで満たされていた。何もかも大丈夫だという安堵。この先の人生を生きていけるという自信。私は礼をしたかったが、夢歩きはすでにいなかった。彼にはそれっきり会っていない。
夢歩きの正体がなんであれ、また彼らが結局のところ誰に仕えているのであれ、私は恩義を忘れないだろう。もっとも、だからといって、私の心の底にわだかまる恐れが消えるわけではない。はたして苦しみを取り除いてもらったことは正しかったのだろうか?記憶こそが、我々を唯一無二の存在たらしめているものではないのか?記憶が改変されてしまった私は、要するに別の誰かになってしまったのではないのか?これではまるで、苦悩の後釜に恐怖が居座ったかのようだ。はたしてどちらが良かったのか、私には分からない。