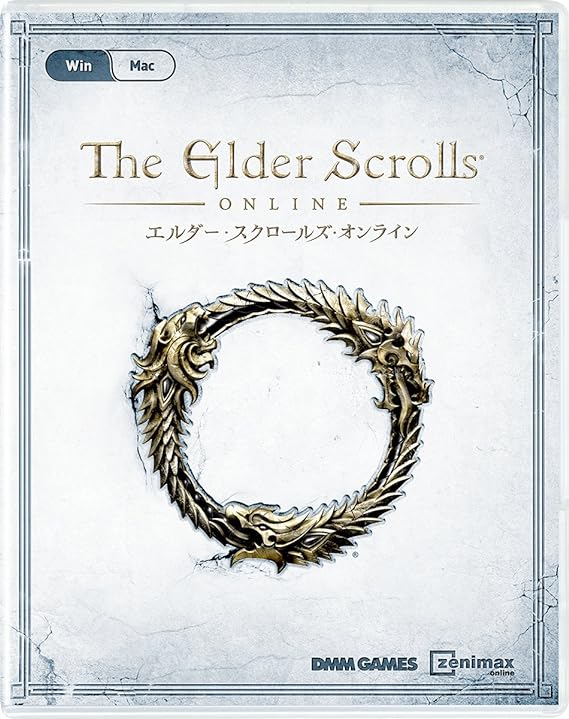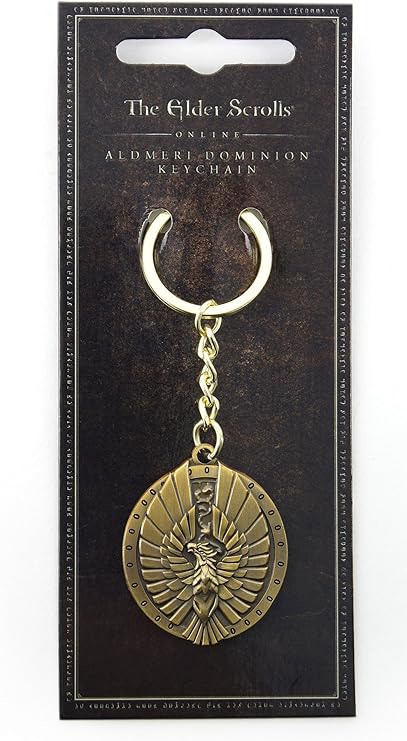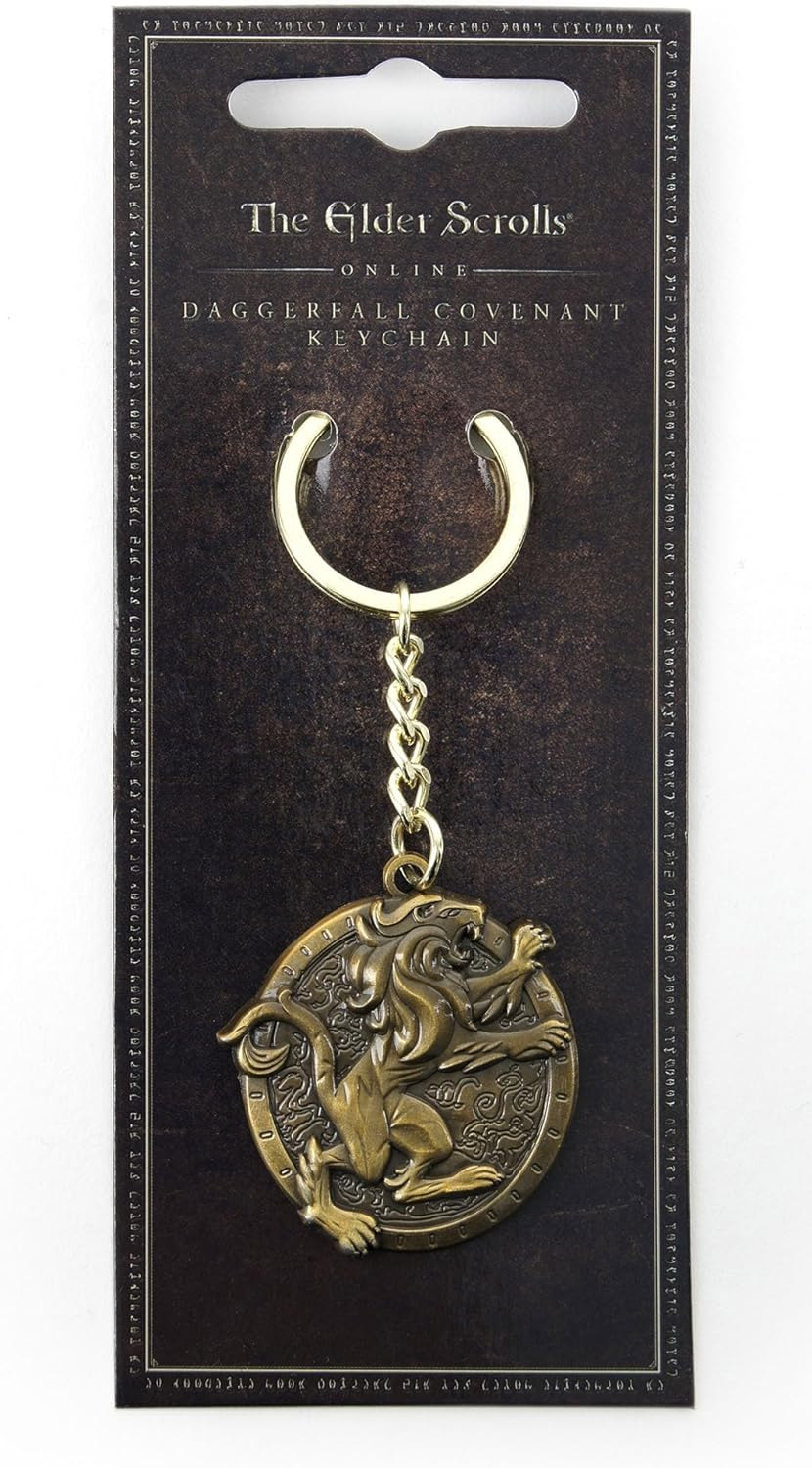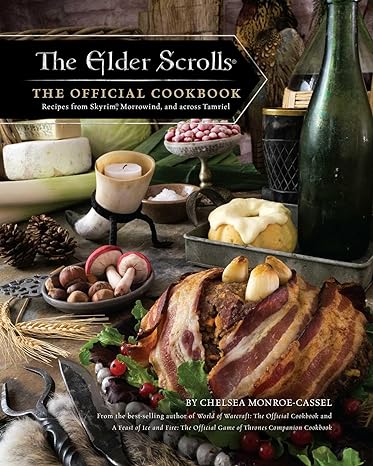2920年、第1巻The Year 2920, Vol. 1
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 暁星の月1日
モーンホールド(モロウウィンド)
アルマレクシアは毛皮のベッドに横たわり、夢を見ていた。太陽が窓に当たり、彼女の肌色の部屋に乳白色の光が注ぎ込まれて、ようやく彼女はその目を開けた。それは静寂と静けさであり、彼女が見ていた血と祝典で溢れていた夢とは驚くほどに違っていた。数分間、彼女は天井を見つめ幻視の整理を試みた。
彼女の王宮の宮廷には冬の朝の涼しさで湯煙を立てている、沸き立つプールがあった。手の一振りで湯煙は消え、彼女の恋人ヴィベクの顔と姿が北の書斎に見えた。すぐには話しかけたくなかった:赤のローブを着て、毎朝のように詩を書く彼はりりしく見えた。
「ヴィベク」彼女が言うと、彼は笑顔とともに顔を上げ、何千マイルもの彼方から彼女の顔を見ていた。「戦争の終わりの幻視を見たわ」
「80年も経った今、誰にも終わりは見えないと思うが…」と、ヴィベクは笑顔とともに言ったが、真剣になり、アルマレクシアの予言を信じた。「誰が勝つ?モロウウィンドか、それともシロディール帝国か?」
「ソーサ・シルがモロウウィンドにいなければ、私たちは負けるわ」と、彼女は返答した。
「私の情報によると、帝国は北部を春の早い段階で攻撃するであろう。遅くとも蒔種の月にはね。アルテウムへ行き、戻るよう彼を説得してくれるか?」
「今日発つわ」と、彼女は即座に言った。
2920年 暁星の月4日
ギデオン(ブラック・マーシュ)
女帝は牢獄のなかを歩き回っていた。冬の季節が彼女に必要のない体力を与えていたが、夏はただ窓の近くに座り、彼女を冷ましに来た、ムッとするような沼地の風に感謝するだけであった。部屋の反対側では、帝国宮廷での舞踏会を描写した、未完成のつづり織りが彼女を嘲るように見えた。彼女はそれを枠から破り取り、床に落としながら引き裂いた。
その後、自らの無駄な反抗の意思表示を笑った。修理するのに十分な時間があり、その上で更に100枚作る時間もあった。皇帝は7年前に彼女をギオヴェッセ城に監禁し、おそらく彼女が死ぬまでそこに拘留するつもりであろう。
ため息とともに、彼女の騎士ズークを呼ぶ綱を引いた。帝国衛兵にも相応しい制服を着た彼は、数分以内に扉の前に現れた。ブラック・マーシュ出身のコスリンギの民のほとんどは裸でいることを好んだが、ズークは衣服に前向きな楽しみを覚えていた。彼の銀色で反射する皮膚はほとんど見えず、顔、首、手のみを露出していた。
「殿下」と、お辞儀をしながら彼は言った。
「ズーク」と、女帝タヴィアは言った。「退屈である。今日は夫を暗殺する手段を話そうぞ」
2920年、第2巻The Year 2920, Vol. 2
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
暁星の月14日
帝都(シロディール)
南風の祈りを宣告する鐘の音が帝都の広い大通りや庭園に鳴り響き、皆を聖堂へと呼んでいる。皇帝レマン三世はいつも最高神の聖堂の礼拝に参列したが、彼の息子にして継承者である皇太子ジュイレックは、各宗教的祝日はそれぞれ違う聖堂にて礼拝に参列するほうが政治上より良いと思っていた。今年はマーラの慈善大聖堂であった。
慈善での礼拝は幸い短かったが、皇帝が王宮に戻れたのは正午を大きく回ってからであった。その頃には、闘技場の闘士たちは式典の始まりをしびれを切らして待っていた。最高顧問ヴェルシデュ・シャイエがカジートの軽業師の一座による実演を手配していたため、群衆はそれほど落ち着かない様子ではなかった。
「そちの宗教は我が宗教よりも都合がよいな」と、皇帝は最高顧問に謝罪するかのように言った。「最初のゲームは何であるか?」
「優れた戦士2人による、一対一の決闘であります」と、最高顧問が立ち上がりながら言った。うろこ状の皮膚が、日の光を受け止めていた。「彼らの文化に相応しい武装で」
「よいぞ」と、皇帝は言い、手を叩いた。「競技を開始せよ!」
二人の戦士が群衆の声援が沸き立つ闘技場に入るや否や、皇帝レマン三世はこのことについて数ヶ月前に約束したが、忘れてしまっていたことに気がついた。闘士の1人は最高顧問の息子サヴィリエン・チョラック。ギラギラした象牙色のうなぎは、アカヴィリ剣と小剣を一見細く、弱そうな腕で握っている。もう一方は、皇帝の息子、皇太子ジュイレック。黒檀の鎧とともに野蛮なオークの兜と盾、そしてロングソードを携えている。
「この見物は興味をそそります」と、最高顧問が息を漏らすように言い、細い顔でにこやかに笑った。「シロディールがアカヴィリとこのように戦うのを見た覚えがありません。通常は、軍対軍ですからな。やっとどちらの考え方が良いのか決着がつけられます…あなた方のように、剣と戦うために鎧を作るのか、それとも我々のように、鎧と戦うために剣を作るのか」
まばらにいるアカヴィリの参事と最高顧問以外はサヴィリエン・チョラックの勝ちを望んではいなかったが、彼の優雅な動きを目にしたとき、皆息を呑んだ。彼の剣は体の一部のようで、尻尾が腕から伸び、後ろの腕に合わせる。重量を平衝させる技で、若い蛇男を丸まらせ回転しながら、攻撃姿勢のままでの舞台の中央への移動を可能とさせた。皇太子はそれほど印象的ではない、普通の移動方法で、とぼとぼと前へ進んだ。
二人がお互いに飛び掛ると、群衆は歓喜の叫びを上げた。アカヴィリはまるで彼が皇太子の衛星軌道上の月であるかのように、後ろからの攻撃を試みるために楽々と彼の肩を飛び越えたが、皇太子は盾で防ぐためにすぐに旋回した。彼の反撃は、敵が地面に倒れこみ、スルスルと彼の足の間を抜けながら足を引っ掛けたので空を切った。皇太子は大きな衝突音とともに地面に倒れた。
皇太子はすべて盾で防いだが、サヴィリエン・チョラックが幾度となく皇太子に攻撃をしかけると、金属と空気が溶けて融合した。
「私たちの文化に盾はありません」と、ヴェルシデュ・シャイエが皇帝に呟いた。「息子には盾が奇妙に見えているのでしょう。私たちの国では、殴られたくなかったら、避けるのです」
サヴィリエン・チョラックが再度目もくらむような攻撃に備えて後ろ足で立ったとき、皇太子は彼の尻尾を蹴り彼を一瞬後ろに退かせた。彼はすぐに立ち直ったが、皇太子も地に立っていた。二人ともお互いの周りを回っていたが、そのうち蛇男が、アカヴィリ剣を突き出して前に回転しながら出てきた。皇太子は敵の策を見破っており、アカヴィリ剣をロングソードで、そして小剣を盾で防いだ。その短く突き抜く刃は金属にめり込んでしまい、サヴィリエン・チョラックは平衡を崩されてしまった。
皇太子のロングソードがアカヴィリの胸を切り、突然の激しい痛みが彼に両方の武器を落とさせてしまった。直後、戦いは終わった。サヴィリエン・チョラックは皇太子のロングソードを首に突きつけられた。解体される家畜同然であった。
「ゲームは終了である!」と、皇帝は叫んだが、闘技場内の拍手の音でかすかに聞こえただけである。
皇太子はにっこりと笑い、サヴィリエン・チョラックが立ち上がるのを手伝い、治癒師へ連れて行った。皇帝は安堵しながら最高顧問の背中を叩いた。戦いが始まったとき、息子が勝つ可能性の低さに気付いていなかった。
「彼はいい戦士になります」と、ヴェルシデュ・シャイエが言った。「そして、偉大な皇帝に」
「これだけは憶えておけ」皇帝は笑った。「アカヴィリには派手な技が多いが、我々の攻撃が1度でも通用すれば、それで終わりなのだ」
「よく憶えておきます」最高顧問は頷いた。
レマンは残りのゲームの最中、その言葉のことを考えていて心底楽しめなかった。最高顧問も、女帝がそうであったように敵なのだろうか?この件は監視することにした。
2920年、第3巻The Year 2920, Vol. 3
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 暁星の月21日
モーンホールド (モロウウィンド)
「なぜ私があげた緑のローブを着ない?」と、モーンホールドの公爵は若い娘が服を着るのを見ながら聞いた。
「合わないからよ」トゥララは笑った。「それに、赤が好きなのを知っているでしょう」
「合わないのは、太り始めているからだ」と、デュークは笑い、彼女をベッドに引き込み、胸や腹部に口づけをした。くすぐったくて彼女は笑ったが、起き上がり、赤いローブを羽織った。
「女性らしく出るところは出ているのよ」と、トゥララは言った。「明日会える?」
「いや」と、デュークは言った。「明日はヴィベクをもてなさなければならない、そして次の日はエボンハートの公爵がここを訪れる。アルマレクシアが居なくなるまで、私はアルマレクシアと彼女の政治手腕を大切に思っていなかった。信じられるか?」
「私と同じね」トゥララは微笑んだ。「私が居なくなって初めて大切に思うのよ」
「そんなことはない」公爵はせせら笑った。「今、大切に思っているさ」
トゥララは扉を出る前に、公爵に最後の口づけを許した。彼女は彼の言った言葉を考え続けた。彼女が太り始めているのは彼の子を宿しているからだと知ったら、彼はどれだけ彼女を大切に思ってくれるのだろうか?結婚するほど大切に思ってくれるだろうか?
2920年、第4巻The Year 2920, Vol. 4
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薄明の月3日
アルテウム島(サマーセット)
見習いたちが一人一人オアッソムの木へと浮かび上がり、高いほうの枝から果実もしくは花を摘み、地面へと舞い降りてくる様子を、その身のこなしの個人差を含めて、ソーサ・シルは眺めていた。彼は満足げにうなずきつつも、一瞬その日の天気を楽しんだ。大魔術師自身が遥か昔に手本となって作られたとされるシラベインの白い像が、湾を見下ろす崖の近くに立っていた。淡い紫色のプロスカートの花がそよ風に揺られて前後していた。その向こうには大海と、アルテウムとサマーセット本島を分けるもやがかった境界線が見えた。
「概ね良好だな」最後の見習いから果実を受け取りながら、彼は講評を述べた。手を一振りすると、果実も花も元あった位置へと戻っていた。もう一振りすると、見習いたちは半円状に妖術師を取り囲んだ。彼は白いローブの中から直径一フィートほどの小さな繊維質の玉を取り出した。
「これが何か分かるか?」
学生たちは質問の意図を理解していた。すなわち、謎の物体に鑑定の呪文を唱えよとのことだった。彼らは一人一人、目を閉じ、その塊が万物の真実の中にあるのを思い浮かべた。あらゆる物質および精神体がそうであるように、玉は独特の響きを発しており、それには負の要素、鏡面要素、相対経路、真の意味、宇宙における歌、時空の中での性質、そして常にあり続け、いつまでもあり続けるであろう存在の側面があった。
「玉です」ウェレグと名乗る若いノルドが口すると、歳の若い見習いたちの間で忍び笑いをする声も聞こえたが、ソーサ・シル本人を含め、多くの者は眉をひそめた。
「愚かな答えを返すなら、せめて愉快な答え方をするがいい」妖術師は叱るように言うと、困惑した様子の、若い黒髪のハイエルフの娘に目を向けた。「わかるか、リラーサ?」
「グロムです」と、リラーサは自信なさげに答えた。「ドゥルーがメフするものです。ク…ク…クレヴィナシムの後で」
「正確にはカルヴィナシムだが、良い答えだ」と、ソーサ・シルは言った。「どういう意味なのか、説明はできるか?」
「わかりません」リラーサは認めた。他の学生たちも首を振った。
「物事の理解にはいくつかの層が存在する」と、ソーサ・シルは言った。「そこらの者であれば、物を見る際に自らの考えの中に当てはめる。古き習わし、すなわちサイジックたちの法、神秘に長けた者たちは、物を見てその役割から素性を知ることができる。だが理解に達するには、もう一枚、剥がすべき層が存在する。物をその役割と真実から鑑定し、その意味を解釈する必要があるのだ。この場合、この玉は確かにグロムである。大陸の北部および西部に棲息する水棲種族、ドゥルーが分泌する物質の名称だ。ドゥルーはその生涯のうち一年、陸上を歩く時にカルヴィナシムを経験する。その後、水へ戻ってメフを体験する。すなわち陸上での生存に必要であった皮膚と器官を自ら貪る。そしてこのような小さな玉状のものを吐き出す。グロム、すなわちドゥルーの吐しゃ物のことだ」
学生たちは妙な表情で玉を見つめていた。ソーサ・シルはこの講義が何よりも好きだった。
2920年 薄明の月4日
帝都(シロディール)
「密偵だ」皇帝は風呂につかり、足にできたこぶを見つめながら漏らした。「余のまわりは裏切り者と密偵だらけだ」
妾のリッジャは皇帝の腰に両脚を絡めたまま、その背中を流した。長年の経験より、性と官能との使い分けは心得ていた。皇帝がこのような機嫌の時は、落ち着かせるように、なだめるように、誘惑するかのように官能的であるのが正解だった。かつ、直接何かを尋ねられない限りは一言も発しないことだった。
もっとも、すぐに質問がとんできた。「皇帝陛下の足を踏みつけた者がいたとして、「申し訳ありません、皇帝陛下」と言ってきたらどう思う?「お許しください、皇帝陛下」のほうが適切だと思わんかね。「申し訳ありません」では、まるであのアルゴニアンめが私が皇帝陛下であることを申し訳無く思っているかのようではないか。我々がモロウウィンドとの戦に負ければいいと願っているかのようにな。そう聞こえる」
「いかがなさいますか?」と、リッジャは問いかけた。「鞭打ちに処すべきでしょうか?所詮はソウルレストの武将に過ぎません。足元に気をつけるよう、思い知らせてやるのもいいでしょう」
「余の父であれば、鞭打ちにしていただろう。祖父であれば処刑していたな」と、皇帝は不満そうに言った。「だが私は足くらいならいくら踏まれてもかまわん。相応の敬意さえ表してくれればな。そして、謀叛を企てなければ」
「せめてどなたかは信用なさらないと」
「お前だけだよ」皇帝は微笑み、僅かに体をひねってリッジャに接吻をした。「息子のジュイレックもだろうな。あいつにはもう少し慎重さがほしいが」
「議会と、最高顧問は?」と、リッジャは尋ねた。
「密偵の群れと、蛇だ」皇帝は笑い、再び妾に接吻した。愛し合い始めつつ、彼はささやいた。「お前さえ忠実であれば、世は何とでもなる」
2920年 薄明の月13日
モーンホールド (モロウウィンド)
トゥララは黒い、装飾された街の門の前に立っていた。風が彼女の体に吹きつけていたが、何も感じなかった。
公爵はお気に入りの愛人が妊娠したと知って激怒し、彼女を追放したのだった。何度も何度も面会をと懇願したものの、衛兵に追い返されてしまったのだ。彼女はついに家族のもとに帰り、真実を伝えたのであった。真実を隠し、父親が分からないと言い張りさえしていれば。兵士でも、流れ者の冒険者でも、誰でもよかったのに。だが彼女は父親は公爵、すなわちインドリル家の一員であると話したのだった。誇り高きレドラン家の者である以上、彼らのとった対処は止むを得ないものであり、そのことは彼女も承知していた。
トゥララの手には、父が泣きながら押しつけた追放の烙印が焼きついていた。だが、彼女にとっては公爵に受けた仕打ちのほうが遥かに苦痛であった。トゥララは門を通して真冬の荒野を見渡した。歪んだ姿で眠り続ける木々と、鳥のいない空。もはや、モロウウィンドに彼女を受け入れてくれる者などいない。遠くへ行かなければ。
重い、悲痛な足取りで、彼女の旅は始まった。
2920年、第5巻The Year 2920, Vol. 5
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薄明の月16日
アネクイナ(今日のエルスウェア)、センシャル
「何かご心配事でも?」と、ハサーマ王妃は夫の機嫌の悪さに気づいて尋ねた。普段は恋人の日の夜となると、王は大抵上機嫌になり、他の招待客と共に舞踏場で踊っているのが常であったが、今夜は早めに引き上げてきたのであった。王妃が様子を見に行くと、彼は寝床で体を丸め、眉をひそめていた。
「あの忌々しい吟遊詩人が聞かせたポリドールとエロイサの物語、あれで気分を害してしまったよ」王は不満そうに唸った。「どうしてあのような気の滅入るような話をするのだ?」
「ですが、それこそがあの物語の真実ではないのですか?世の理の残酷さゆえに破滅を迎えたのでは」
「真実かどうかは、どうでもいいことだ。くだらん話に、下手な語り手だ。もう二度とやらせはすまい」ドローゼル王は寝床から跳ね起きた。その目は涙で曇っていた。「どこの出だと言っていたか?」
「ヴァレンウッド東端のギルヴァーデイルだったかと」と、王妃は動揺した様子で答えた。「あなた、何をなさるおつもりなのです?」
ドローゼルは一瞬で部屋を出、塔へと続く階段を駆け上がっていった。ハサーマ王妃は夫の意図を察していたとしても、彼を制しようとはしなかった。最近は妙な言動やかんしゃくが目立ち、ひきつけさえ起こしていたのだった。だが彼女は王の乱心の根深さも、吟遊詩人、および彼が語って聞かせた人間たちの残酷さと異常さに関する物語に対し、王がどれだけ憎しみを感じていたかも気づいていなかったのである。
2920年 薄明の月19日
ギルヴァーデイル(ヴァレンウッド)
「もう一度よく聞くんだぞ」と、年老いた大工は言った。「三つめの部屋に黄銅のくず鉄があるなら、二つめの部屋に金の鍵がある。一つめの部屋に金の鍵があるなら、三つめの部屋には黄銅のくず鉄がある。二つめの部屋に黄銅のくず鉄があるなら、一つめの部屋に金の鍵がある」
「わかったわ」と、婦人は言った。「言われた通りにね。だから一つめの部屋に金の鍵があるわけでしょう?」
「違う」と、大工は答えた。「もう一度最初からいくぞ」
「お母さん?」と、少年が母親の袖を引っ張って言った。
「ちょっと待っててね、お母さんお話し中なの」母親は答えると、謎かけに意識を集中させた。「あなた言ったわよね、「二つめの部屋に黄銅のくず鉄があるなら、三つめの部屋に金の鍵がある」って」
「いや、違う」大工は根気良く答えた。「三つめの部屋に黄銅のくず鉄があるのは、二つの…」
「お母さん!」少年が悲鳴を上げた。母親はようやくその意図に気づいた。
明るい赤色の霧が波となって町に押し寄せ、建物を次々と飲み込みつつあった。その前を赤い皮膚の巨人、デイドラのモラグ・バルが大股で歩いていた。その顔に笑みを浮かべて。
2920年 薄明の月29日
ギルヴァーデイル(ヴァレンウッド)
アルマレクシアは辺り一面の泥沼の中で馬を止め、川の水を飲ませようとしたが、飲みたがらないどころか水に嫌悪を覚えているようであった。モーンホールドからかなりとばして来たことを考えれば、喉も渇いているはずである。妙だ。彼女は馬を下りると、一行のいる方へと足を運んだ。
「現在位置は?」と、アルマレクシアは尋ねた。
婦人の一人が地図を取り出した。「ギルヴァーデイルという街に近づきつつあるはずですが…」
アルマレクシアは目を閉じ、すぐにまた開けた。その光景は耐え難いものであった。従者たちが見ている中、彼女は煉瓦と骨の欠片を拾い上げ、その胸に抱いた。
「アルテウムに急ぐわ」と、彼女は静かに言った。
2920年、第6巻The Year 2920, Vol. 6
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 蒔種の月15日
カエル・スヴィオ(シロディール)
皇帝レマン三世は、丘の上の見晴らしの良いところから、帝都にそびえる尖塔をじっと見ていた。彼には自分が温かい家、故郷から遠く離れた地にいることが分かっていた。この地の領主、グラヴィアス卿の邸宅は豪華なものだったが、帝国軍を敷地内にまるまる収容できるほどのものではなかった。山腹に沿ってテントが並び、兵士たちはみな卿自慢の温泉に行くのを楽しみにしていた。それもそのはず、そこにはまだ冬の空気が立ち込めていた。
「陛下、ジュイレック皇太子のご気分がすぐれないようです」
ヴェルシデュ・シャイエに声をかけられ、皇帝は飛び上がった。このアカヴィリが草地の中、一切の音を立てずにどうやって近づいてきたのか不思議だった。
「毒に違いない」と皇帝はつぶやいた。「早急に治癒師を手配しろ。いくら給仕が反対しても、息子にも私のように毒味役をつけるのだ。いいか、我々の周りには密偵が大勢いることを忘れるな」
「そのように取り計らいます、陛下」とヴェルシデュ・シャイエは答えた。「現在 政局は非常に不安定でございます。モロウウィンドでの戦いに勝利するためには、戦場に限らず、いかようなる手にも用心するにこしたことはございません。それ故、私が申し上げたいのは、陛下にこの戦いの先陣から退いていただきたいのです。陛下の輝ける先人、レマン一世、ブラゾラス・ドール、レマン二世がそうしたように、陛下も先陣を切りたいというお気持ちは重々承知でございます。しかし、あまりにも無謀ではないかと思われます。私のような者の言葉にどうかお気を悪くなされないでください」
「さようか」と皇帝はこの意見に賛同の意を表した。「しかし、それでは私の代わりに誰が先陣を切るというのだ?」
「お身体が回復されれば、ジュイレック皇太子が適任かと。もしだめなら、左翼にファーランのストリグとリバーホールドのナギー女王を、右翼にリルモスの族長ウラチスではいかがでしょう」とシャイエは言った。
「左翼にカジート、右翼にアルゴニアンをあてがうだと?」と皇帝は顔をしかめた。「私は獣人を信用しておらん」
皇帝の言葉をアカヴィリはまったく気に留めなかった。皇帝の指す「獣人」とはタムリエルに住む原住民を意味するものであり、彼のようなツァエシとは別であることを十分に承知していたからである。「陛下のお気持ちは分かります。しかし、彼ら獣人がダンマーを嫌っていることをお忘れなく。特にウラチスは領民がモーンホールドの公爵率いる軍隊に襲われて奴隷にされたことを恨んでいます」
それを聞いた皇帝は渋々納得し、ヴェルシデュ・シャイエは下がっていった。皇帝は驚いたが、この時初めてヴェルシデュ・シャイエが信頼に足る人物、味方として優秀な人材であると思えた。
2920年 蒔種の月18日
アルド・エルファウド (モロウウィンド)
「今、帝国軍はどのあたりに?」と、ヴィベクは尋ねた。
「2日の行軍でここへ辿り着きます」と、副官は答えた。「我々が今晩夜通し行軍を進めれば、明朝にはプライアイの小高い場所へと辿り着けるでしょう。情報によりますと皇帝は軍の殿を務めることになり、ファーランのストリグが先陣を、リバーホールドのナギーとリルモスのウラチスがそれぞれ左翼と右翼につくそうです」
「ウラチスか…」とヴィベクはつぶやいたが、ある考えが浮かんだ。「ちなみにその情報は信用してよいのだな?その情報はどうやって手に入れたのだ?」
「帝国軍に潜んでおりますブレトンのスパイです」と副官は答え、砂色の髪をした若い男に、前に進み出るよう促した。ヴィベクの前へ出たその男は頭を下げた。
ヴィベクは微笑んで、「名はなんと言う?なぜにブレトンがシロディールと戦う我が軍のために働くのだ?」と尋ねた。
「私はドワイネンのキャシール・オイットリーと言います。この軍のために働いているとしか申し上げられません。諜報活動を行う者はみな神のために働いているとは言いかねるからです。はからずも私はこの仕事のおかげで食べていけております」と男は答えた。
ヴィベクは笑って、「お前の情報が正しければそうであろうな」と言った。
2920年、第7巻The Year 2920, Vol. 7
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 蒔種の月19日
ボドラム (モロウウィンド)
ボドラムの閑静な村からは、曲がりくねった河、プライアイを見下ろすことができる。それは非常にのどかな風景で、ささやかに木が生い茂り、河の東には険しい崖に囲まれた渓谷、西には美しく彩られた花々が咲きほこる牧草地が広がる。モロウウィンドとシロディールの境界でそれぞれの珍しい植物が出会い、見事にまじりあっていた。
「仕事が終われば、あとはたっぷり眠れるぞ!」
兵士たちは毎朝この一声で目覚めた。夜な夜な続く行軍だけでなく、崖に切り立つ木々をなぎ倒したり、溢れかえる河の水をせき止めたりしなければならなかった。彼らの多くは、疲れたと文句を言うこともできなくなるほど疲労困憊であった。
「確認しておきたいのですが…」とヴィベクの副官は聞いた。「崖道を進めば敵の上から矢や呪文で攻撃することができる。そのために木々をなぎ倒すのですね?氾濫する河をせき止めるのは、敵の動きを封じ込め、泥沼の中で立ち往生させるためですよね?」
「半分は当たっておる」とヴィベクは満足げに答えた。ちょうどなぎ倒した木を運んでいた近くの兵をつかみ、「待て。その木の枝から真っ直ぐで丈夫な枝を選び抜き、それをナイフで削って槍を作るんだ。100人ぐらいの兵を集めてとりかかれば、我々が必要とする量は2―3時間で作れるだろう」
そう命じられた兵士はいやいやながら従った。他の者も作業に加わり、槍をこしらえた。
「このような質問は失礼かもしれませんが…」と副官は聞いた。「兵士たちにはこれ以上の武器は必要ないのではありませんか?疲れている上、もうこれ以上の武器を持てやしません」
「あの槍は戦いで使うために作らせているのではない」とヴィベクはささやいた。「兵士たちを疲れさせておけば、今夜はぐっすり眠れるからな」ヴィベクが兵士たちを指揮する仕事に取り掛かる前によく眠っておけということだ。
ところで、槍というものは先端が鋭いのは当然のことながら、全体の重量のバランスも大事である。最もバランスのとれた槍の先端部分には、よく見られる円錐形ではなくピラミッド型が望ましい。ヴィベクは槍の強度や鋭さ、安定さを測るため兵士に投げさせ、壊れれば新しいものを渡し、測定をくり返した。こうして兵士たちは疲労を抱えながらも槍の良し悪しを身をもってわかるようになり、最高の槍を作りだせるようになっていく。一度投げてみてから、ヴィベクは兵士たちにこの槍をどこにどのように配置するかを指示した。
その夜は戦の前日に行われる酒盛りもなければ、新米兵士たちが眠れず夜を明かすこともなかった。陽が落ちると同時に見張りを除いて皆が眠りに落ちた。
2920年 蒔種の月20日
ボドラム (モロウウィンド)
ミラモールは疲れていた。この6日間、彼は賭博へ売春宿へと夜通し遊び回り、昼は昼で行軍を続けていた。ミラモールは戦いの日を待ち望んでいた。しかし、何よりも待ち望んでいたものは戦いのそのあとの休息だった。彼は皇帝指揮下の後方部隊についており、そこが死から一番遠い場所であるのは良かったが、一方で前方の兵士がこしらえたぬかるみだらけの泥道を歩かなければならず、寝坊してしまえば隊から取り残されてしまう危険性もあった。
野生の花々が咲き乱れる中を進むも、ミラモールたち兵士の足元は足首まで冷たい泥に浸かっていた。進むのには骨が折れた。ストリグ卿に指揮された軍の先陣ははるか遠く、崖のふもとの草地に見えた。
その時だった。
崖の上に、昇り行くデイドラのごとくダンマーの軍隊が現れ、たちまちに砲火と矢の雨が先陣に降りそそいだ。その時、モーンホールドの公爵の旗を掲げた一団が馬に乗って岸辺へ飛び出してきたかと思えば、東の谷間の木立へと続く浅瀬の川べりに沿って消えていった。右翼を固めるウラチスはそれを見るや怒声を上げて追跡した。ナギー女王は崖の軍隊を捕捉するため、自分の軍を西の土手に進ませた。
皇帝はどうしたらよいか分からなかった。彼が率いる後方部隊は泥道にはまってしまい、前に素早く動けず、戦いに参加できないのだ。しかし彼はモーンホールドの軍に包囲されまいと、東の森林に向け突き進むよう命じた。モーンホールドの軍とは出くわさなかった。しかし、ほとんどの兵士は戦いを放棄し、西へ向かっていた。ミラモールは崖の上を見ていた。
そこで背の高いヴィベクと思しき一人のダンマーが合図を送った。その合図を受けた魔闘士たちは西の何かに向かって呪文を発した。何かが起こった。ミラモールはそれをダムのようだと思った。ものすごい激流が左翼のナギー女王を先陣へと押し流し、そのまま先陣と右翼の隊は東へと流されて行った。
打ち負かされた軍が戻って来るのではないかと皇帝はしばらく立ち止まっていたが、すぐさま退避を命じた。ミラモールは激流がおさまるまで急いで身を隠し、それから出来るだけ静かに急いで崖を渡った。
モロウウィンドの軍は野営地まで退いていた。ミラモールが河岸に沿って歩いていると、頭上から彼らが勝利を祝う歌声が聞こえてきた。東の方には帝国軍が見えた。兵たちは河にかけられた槍の網に引っかかり、下からウラチスの右翼軍、その上にストリグの先陣、さらにその上にナギーの左翼軍の兵たちが数珠つなぎに刺さっていた。
ミラモールはその死体のポケットや荷物を漁り、金目のものを探していたが、すぐにその場を離れ河を下りて行った。水が血で汚れていないところに行くまでは、何マイルも先へと進まなければならなかった。
2920年、第8巻The Year 2920, Vol. 8
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 蒔種の月29日
ヘガテ(ハンマーフェル)
「帝都からあなた宛にお手紙が届いてるわよ」尼僧長はそう言いながらコルダへ羊皮紙を渡した。若い尼僧たちは笑みを浮かべながらも驚いた表情をしいていた。コルダの姉、リッジャは頻繁に、少なくとも月に一度は手紙を書いてよこすのだった。
コルダは手紙を受け取り、お気に入りの場所、庭で手紙を読もうと出て行った。そこは砂色で単調な修道院の世界の中で唯一のオアシスであった。手紙自体には大した内容は書かれていなかった。宮廷内のゴシップや最新の流行ファッション(ちなみにワインダーク色のベルベット素材が流行るらしい)、ますますひどくなる皇帝の妄執などについてであった。
「あなたはこんな生活から離れて暮らせて本当に幸運よ」とリッジャは綴っていた。「皇帝はどうやら最近の戦での大失敗が、身内に密偵が潜んでたせいと確信してるみたい。私まで疑われる始末よ。ラプトガ様があなたに、あたしと同じようなおかしな生活を送らせませんように」
コルダは砂の音に耳をそばだて、ラプトガにまったく逆の祈りを捧げた。
2920年 恵雨の月3日
コールドハーバー(オブリビオン)
暗い王宮の濁った水に浸された廊下を、ソーサ・シルは全速力で進んでいた。彼のまわりでは、気味の悪いぶよぶよした生き物が葦の茎の間を這い回り、頭上のアーチでは白い炎が明るく燃え上がっては消え、死の腐敗臭と花の香水の香りが交互に襲ってきた。オブリビオンにデイドラ公たちを訪ねるのはこれが初めてではないが、ここへくるたびに違ったものに出迎えられるのだった。
だが、彼には目的があり、まわりの奇怪なものに気をとられている時間はなかった。
八人の最も位の高いデイドラ公たちが、溶けかけた丸屋根の広間で彼を待っていた。黄昏と暁のデイドラ公アズラ、企みのデイドラ公ボエシア、知恵のデイドラ、ハルマ・モラ、狩人ハーシーン、呪いの神マラキャス、災いのデイドラ公メエルーンズ・デイゴン、憤怒のデイドラ公モラグ・バル、そして狂ったシェオゴラスである。
頭上の空から歪んだ影が落ち、彼らの集いを覆い隠していた。
2920年 恵雨の月5日
アルテウム島(サマーセット)
ソーサ・シルの声が洞窟に響き渡った。「岩をどかせ!」
すぐに、見習いたちが巨石を転がして脇へやり、夢見る洞窟への入口を開いた。現れたソーサ・シルの顔は灰にまみれ、ひどくやつれていた。彼は何ヶ月、いや何年も旅してきたように感じていたが、実際は数日しかたっていなかった。ライラザが彼の腕をとり、支えようとしたが、彼は優しくほほえみ、首を振ってそれを断った。
「それで…うまくいったのですか?」と、彼女はたずねた。
「デイドラ公たちはこちらの提案を受け入れた」彼は感情のない声で言った。「ギルヴァーデイルに起こったような災いはこれ以上起こらない。彼らは今後、魔女や妖術師を通じてのみ、人間やエルフと関わることになる」
「それで、そのかわりに何を約束してきたんですか?」と、ウェレグというノルドの子供がたずねた。
「デイドラとの契約は–」イアケシス宮殿を、サイジック会の長の居所へ向かって進みながらソーサ・シルは言った。「入門まもない者には聞かせられない」
2920年、第9巻The Year 2920, Vol. 9
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 恵雨の月8日
帝都(シロディール)
嵐が皇太子の寝室の窓を叩き、湿った空気が香炉の吐き出す香やハーブの香りと混じりあっていた。
「お母様の皇后陛下からのお手紙をお持ちしました」と、使者が言った。「その後のお体の具合を心配しておられます」
「心配性な母親だ」ジュイレック皇太子はベッドの中で笑った。
「母親が息子を心配するのは当然のことです」と、最高顧問の息子サヴィリエン・チョラックが言った。
「アカヴィリ、我が家では何一つ当然のようにはいかないのだ。母は追放され、父が私を反逆者と疑い、毒を盛ったのではないかと案じている」皇太子はうんざりした様子で枕に頭を沈めた。「皇帝は皇帝で、自分のように食べるもの全てを毒見させるよう勧めてくる」
「多くの陰謀がありますから」アカヴィリはうなずいた。「あなたは3週間近くも床につき、国中の治癒師が舞踏会のダンスの相手のようにとっかえひっかえあなたの治癒にあたりました。とにかく、今は回復に向かわれているようですが」
「早くモロウウィンドへ兵を率いて行けるぐらいに回復したいものだ」と、ジュイレックが答えた。
2920年、第10巻The Year 2920, Vol. 10
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 恵雨の月11日
アルテウム島(サマーセット)
見習いたちは、庭園の開廊に整列していた。彼らの目前には大理石で覆われた長く深い溝があり、中ではまぶしいほどに火が焚かれていた。溝の上の空気は炎の熱気でゆらめいていた。サイジック会の一員として、生徒は恐れを顔に出さないようつとめていたが、彼らの恐怖は眼前の炎のように明らかだった。ソーサ・シルは目を閉じ、火炎耐性の呪文を唱えた。そして、ゆっくりと燃え盛る炎の中を歩き、無事に溝の反対側へついた。彼の白いローブには焦げ目一つついていなかった。
「他の呪文と同じように、この呪文も唱える者の思いの強さや能力によってその効力が高まる」と、彼は言った。「想像力と意思の力が鍵となる。空気に対する耐性や花に対する耐性が必要ないのと同じように、この呪文を唱えた後は火炎耐性の必要も忘れてしまうだろう。勘違いしてはいけない、耐性というのは、炎がそこにないと思い込むことではない。炎そのものを感じ、その質感や、攻撃性や、熱さえもを感じた上で、それらが何の害もなさないようにするのだ」
生徒たちはうなずき、一人また一人と呪文を唱え炎の中を歩いた。両手で炎をすくいあげ、空気にかざして燃え上った炎を指の間からこぼれ落とさせる者すらいた。ソーサ・シルはほほえんだ。彼らは見事に自身の恐怖を克服していたのだ。
教官長のサーガリスが回廊の向こうから走ってきて言った。「ソーサ・シル!アルマレクシアがアルテウムに到着した。イアケシス様が君を呼んでおられる」
ソーサ・シルが一瞬サーガリスのほうを向いたそのとき、叫び声が聞こえた。彼はそれが何を意味するか知っていた。ノルドの少年ウェレグが呪文を間違えて炎に焼かれていたのだ。髪や肉の焼ける臭いがあたりにたちこめ、慌てふためいた他の生徒たちが溝から脱出しようと引っ張り合っていた。しかし、溝に入ったばかりの場所は容易に後戻りができないように深く作られており、出ることができないのだった。ソーサ・シルは腕を振り、炎を消した。
ウェレグと他の数人が火傷を負ったが、それほど重傷ではなかった。妖術師ソーサ・シルは彼らに回復の呪文をかけ、それからサーガリスに向きなおった。
「今からアルマレクシアに会いに行くが、すぐ戻る。彼女と彼女の従者も長旅で疲れているだろうからな」ソーサ・シルは生徒に向かっていった。彼の声には感情がなかった。「恐怖は呪文を損なわないが、呪文を唱える者は疑いや自信のなさを捨てなくてはならない。ウェレグ君、荷物をまとめたまえ。明日の朝、船が君を本土へ送り返す」
アルマレクシアとイアケシスは書斎でお茶を飲みながら笑いあっていた。アルマレクシアは、ソーサ・シルの記憶よりも美しくなっていた。とはいえ、彼女は彼の覚えているようなきちんとした格好ではなく、毛布にくるまり、濡れた黒い髪を火にかざして乾かしていた。ソーサ・シルが歩みよると、彼女は飛び上がって彼を抱きしめた。
「モロウウィンドから泳いできたのか?」彼は笑った。
「スカイウォッチから海岸までの間が大雨だったの」と、彼女は笑顔で説明した。
「1.5マイルも離れていないが、ここでは雨など降っていない」と、イアケシスが自慢げに言った。「ここはいつもサマーセットや本土の騒動とは無縁だ。だが、外の世界へ行っていた者の話を聞くのは楽しいものだ。外の世界は騒動と混乱に満ちているからな。ああ、騒動といえば、このごろ聞こえてくる戦争の話は何なのだ?」
「この80年ほど、大陸を血で染めているあの戦争のことですか、会長?」と、ソーサ・シルは面白がって言った。
「多分そうだろうな」イアケシスは肩をすくめた。「今その戦争はどうなっているのだ?」
「私がソーサ・シルを説得してアルテウムから連れて行けなければ、我々が負けるでしょう」そう答えたアルマレクシアの顔からは笑顔が消えていた。そのことについては後でソーサ・シルと個人的に話すつもりだったが、アルトマーの老人は彼女に続けるように促した。「そういう未来が見えたのです。そうなると確信しています」
ソーサ・シルは少しの間黙り込み、イアケシスを見ながら言った。「モロウウィンドへ戻ります」
「君の性格はよく知っている。心を決めたなら止めても無駄だろうな」老いた会長はため息をついた。「サイジック会は何者にも倒されない。戦争は戦いで、国々は起こり滅びる。君が行くなら、我々も行かなくてはなるまい」
「どういうことですか、イアケシス?島を離れるおつもりですか?」
「そうではない。島が海を離れるのだ」と、イアケシスは夢見るような声で言った。「数年のうちに霧がアルテウムを覆い、我々は去るだろう。我々は生まれついての指導者だ。タムリエルには指導者が多すぎる。我々は去り、この地上が我々を必要としたときに、また戻ってくる。時をこえてな」
老アルトマーは危なっかしく立ち上がり、残っていたお茶を飲み干し、ソーサ・シルとアルマレクシアをその場に残して立ち去った。「最後の船に乗り遅れるではないぞ」
2920年、第11巻The Year 2920, Vol. 11
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 栽培の月10日
帝都(シロディール)
「陛下」と、最高顧問ヴェルシデュ・シャイエが自分の部屋の扉を開けながら笑顔で言った。「このところお目にかかりませんでしたね。ひょっとしたら陛下は…リッジャ様が愛らしすぎて具合が悪くなったのかと」
「彼女ならミル・コラップで風呂に入っている」と、皇帝レマン三世が惨めったらしい声で言った。
「さあ、入れ」
「とうとう3人の人間しか信じられないようなところまで来てしまった。お前と、我が皇太子と、リッジャだ」と、いらだたしそうに皇帝が言った。「元老院は単なる密偵の集団だ」
「どうかなさいましたか、陛下?」と、最高顧問ヴェルシデュ・シャイエが同情した様子で言いながら、部屋の厚いカーテンを閉めた。大理石の廊下を歩く人の足音や、春先の庭で鳴く鳥の声など、外からの物音はすべてすぐに遮断された。
「ボドラムでの戦いが始まる前に我々が野営をしていた際、わしの息子に毒が盛られたことがあった。その時、ブラック・マーシュ出身のオルマの部族民でカッチカと呼ばれる悪名高い毒殺者が、ケイル・スヴィオで軍隊と一緒にいたという情報をつかんだのだ。本当はわしを殺したかったことは間違いないが、その機会がなかったんだろう」と、忌々しげに皇帝が言った。「だが彼女を告訴するならまず証拠を出すべきだと元老院は言っている」
「もちろんそうでしょうね」と、思いやりを示すように最高顧問が言った。「特に、もしその中の一人二人が自ら筋書きに加担していたとすれば。私に考えがあります、陛下」
「何だ?」と、待ちきれない様子でレマンが言った。「早く言いたまえ!」
「この件は撤回すると元老院に申し出てください。私は衛兵を派遣してカッチカの所在を突き止めさせ、尾行させます。彼女と共謀しているのが誰なのかが判明するでしょうし、陛下の命を狙うこの陰謀が果たしてどの程度の大きさのものなのかもつかめるでしょう」
「そうだな」と、満足げに眉を寄せてレマンが言った。「それは名案だ。相手が誰であろうと、そのやり方で突き止めよう」
「もちろんです、陛下」最高顧問は微笑みながら、皇帝が部屋を出られるようにカーテンを開けた。部屋の外の廊下にはヴェルシデュ・シャイエの息子、サヴィリエン・チョラックがいた。少年は皇帝に会釈をしてから最高顧問の部屋に入った。
「何か面倒なことにでもなってるの、お父さん?」と、アカヴィリの少年はささやいた。「皇帝が、ナントカっていう毒殺者の情報をつかんだって聞いたけど」
「話術の最大のコツは–」と、ヴェルシデュ・シャイエが息子に語りかけた。「こちらが相手にさせたいと思っていることを相手がしたくなるように仕向けながら、相手が聞きたがっている言葉を言ってあげることだ。お前には、カッチカに手紙を届けてもらいたい。そして、そこに書かれている指示に完全に従わなければ、命が危なくなるのはこちらよりもむしろ彼女の方だということをちゃんと理解していることを、確認してきて欲しい」
2920年 栽培の月13日
ミル・コラップ(シロディール)
リッジャはぶくぶくと泡を立てている温泉にゆったりと浸かり、無数の小さな石で肌がくすぐられているような感覚を味わっていた。頭の上に突き出している岩のおかげで霧雨は当たらず、日の光だけが木々の枝の間から筋となってたっぷりと降り注いでいた。それは牧歌的な生活におけるのどかなひとときであり、入浴後には自分の美しさがすっかり蘇っているはずだということを彼女は知っていた。唯一足りないものは一杯の水だった。温泉のお湯は匂いこそ素晴らしいが、必ずチョークの味がした。
「水!」と、召使に向かって叫んだ。「水をちょうだい!」
目隠しするように顔に布を巻いた、一人のやせこけた女がリッジャのそばに駆けてきて、ヤギ皮の水袋を落とした。そのあまりの慎み深さにリッジャは思わず笑い出しそうになった–自分が素っ裸でいることを恥ずかしいとは思っていなかったのだ–が、布の透き間から見えた老婆の顔にはそもそも瞳がないことに気がついた。話には聞いたことがあるが一度も会ったことはないオルマの部族民のようだった。生まれつき目がない彼らは、それ以外の感覚がずば抜けて優れている。ミル・コラップの君主は召使の雇用に関してずいぶんと異国趣味のようだと、リッジャはひそかに思った。
すぐに女は立ち去り、その存在は忘れ去られた。そこにいると日の光と温泉のこと以外は何も集中して考える気になれないことをリッジャは感じていた。水袋のコルクを抜いてみたが、中の液体は妙に金属臭い匂いがした。気がつけば、そこにいるのは彼女一人ではなかった。
「リッジャ様」と、衛兵隊長が言った。「カッチカとお知り合いのご様子ですね?」
「知らないわ、そんな人」と、どもりながら言った。そして、憤然とした様子で言葉を続けた。「ここで何してるの?私の身体は下品な視線にさらすためのものじゃないのよ」
「お知り合いではないとおっしゃる。ついさっきご一緒におられたようですが」と言いながら隊長は水袋を拾い上げ、匂いを嗅いだ。「ネイヴー・イコーを持ってきたようですね?皇帝に毒を盛るためですか?」
「隊長」と、駆け寄ってきた衛兵の一人が言った。「アルゴニアンの姿が見当たりません。どうやら森に消えたようです」
「ああ、連中にはお手のものだからな」と、隊長は言った。「だが問題はない。宮中の連絡係を見つけたからな。殿下もお喜びになるだろう。この女を捕まえろ」
身もだえする裸の女を衛兵たちが湯船から引き上げると、彼女は叫んだ。「濡れ衣だわ!私は何も知らないし、何もしていない!皇帝がこれを知ったら絞首刑になるわよ!」
「ああ、もちろんそうなるだろうな」隊長が微笑んだ。「皇帝がお前を信用されればの話だが」
2920年、第12巻The Year 2920, Vol. 12
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 栽培の月21日
ギデオン(ブラック・マーシュ)
酒場「ブタとハゲワシ」は人目につくことなく行動できる場所で、今回のような相手に会う際にズークが好んで用いる店だった。彼とその連れ以外、薄暗い店の中にいるのは霧のような存在の数人の老人のみで、しかも酔いつぶれてほとんど意識がなくなっていた。汚れっぱなしの真っ黒な床は目ではなく足で確かめて歩くべきものだった。空中に浮かんだおびただしい埃はじっとして動かず、わずかに差し込んでくる夕陽の光に映し出されていた。
「激しい戦闘に加わった経験は?」と、ズークが訊ねた。「割のいい仕事だが、その分、危険も非常に大きい」
「戦闘経験なら言うまでもない」と、ミラモールが横柄に答えた。「2ヶ月前にボドラムの戦いに行ってきたばかりだ。そっちが責任を果たして、約束どおりの日時に、最小限の護衛を伴って皇帝が馬でドーザ峠を通るようにしてくれれば、俺は俺の責任を果たす。皇帝が変装しないで来るようにさせることだけは忘れないでくれ。皇帝レマンが隠れているかもしれないと疑って、峠を通る隊商を皆殺しにするのはごめんだからな」
ズークが微笑み、ミラモールはそのコスリンギー独特の思慮深そうな顔に自分の姿を見た。彼はその見た目が気に入っていた。完ぺきな自信に満ちたプロの顔だった。
「よろしい」と、ズークは言った。「残りの金は仕事が済んでからだ」
ズークは二人の間にあるテーブルの上に大きな収納箱を置き、立ち上がった。
「数分してから出てくれ」と、ズークは言った。「後はつけないように。依頼主は匿名のままでいたいと望んでいるから、万が一、君が捕まって拷問にかけられた場合のことも用心してる」
「心配するな」と、酒のおかわりを求めながらミラモールが言った。
ズークは馬に乗って迷路のように狭く入り組んだギデオンの道を駆け、ようやく門を抜けて国に入った時には、彼も馬もほっとため息をついたかのようだった。ジョヴェーゼ城に続く本街道は、春になると毎年そうであるように水浸しになっていたが、ズークは丘を越える近道を知っていた。枝にまで苔が生えて垂れ下がっている木の下を走り、つるつると滑りやすく危険な岩場も駆け抜けて、彼は2時間もかからずに城門に辿り着いた。そして直ちに、一番高い塔のてっぺんにあるタヴィアの独房へと駆け上がった。
「どんな男だった?」と、女帝が訊ねた。
「愚か者です」と、ズークは答えた。「しかし、この手の仕事にはむしろそのほうが好都合です」
2920年 栽培の月30日
サーゾ要塞(シロディール)
リッジャは、ただひたすら叫び続けた。独房の中でその声を聞き届けているのは、厚い苔に覆われてはいるがびくともしない大きな灰色の石壁のみだった。外にいる衛兵たちは、彼女だけでなくすべての囚人に対して聞く耳を持っていなかった。遠い彼方の帝都にいる皇帝にも、無実を訴える彼女の叫びはまったく届いていなかった。
おそらくもう誰も聞いてくれないことは十分に分かっていたが、それでも彼女は叫んだ。
2920年 栽培の月31日
カヴァス・リム峠(シロディール)
シロディールであろうとダンマーであろうと、トゥララが人の顔というものを最後に見てから何日、いや何週間も経っていた。道を歩きながら彼女は、これほどまでに住む人が少ないシロディールが皇帝の住まい、すなわち帝都となったのは本当におかしなことだと考えていた。ヴァレンウッドのボズマーにだって、このハートランドよりは住む人の多い森があるに違いない。
彼女は回想していた。モロウウィンドからシロディールに入る国境を越えたのは1ヶ月前、それとも2ヶ月前?今よりずっと寒かったのは確かだが、それ以外に時間的な手がかりは何もなかった。衛兵たちはぞんざいな態度ではあったが、彼女が何も武器を持っていなかったため、国境通過を許可するほうを選んだのだ。以来、彼女はいくつかの隊商に出会ったし、キャンプを張っていた冒険者たちと食事を共にしたことさえあったが、街まで乗せていってくれる者には一度も出会わなかった。
トゥララはショールを外し、後ろに引きずって歩いた。一瞬、背後にいる誰かの音が聞こえた気がして、振り返ってみた。誰もいなかった。小鳥が枝に留まって、笑い声に似た鳴き声を出しているだけだった。
彼女は歩き続け、立ち止まった。たいへんなことが起きようとしていた。お腹の赤ん坊はそれまでにも蹴ることがあったが、今回のけいれんは違う種類のものだった。うめき声を上げて彼女はよろよろと道の脇に向かい、草の上に倒れ込んだ。赤ん坊が生まれようとしていた。
彼女は仰向けになって力んでみたが、痛みと落胆で涙があふれてほとんど何も見えなくなるばかりだった。なぜこんなことになってしまったのだろう?荒れ地の中、一人きりでモーンホールド公爵の子を出産することになるなんて。激しい怒りと苦悩で発した叫び声に、木々の鳥が一斉に飛び立った。
先ほど彼女を笑っていた小鳥が道に降りてきて留まった。トゥララがまばたきすると小鳥は消え、そこに、ダンマーほど浅黒くはないがアルトマーほど青白くもない、一人のエルフの男が裸で立っていた。アイレイドのワイルド・エルフだということは、彼女にもすぐに分かった。トゥララは叫んだが、男が彼女を押さえつけた。数分間のもみ合いの後、すっと力が抜けていく感じがして、彼女は気を失った。
目を覚めさせたのは、赤ん坊の泣き声だった。その子はきれいに拭かれて彼女の隣に寝かせられていた。トゥララは女の赤ん坊を抱き上げ、その年に入ってから初めて喜びの涙が頬を伝うのを感じた。
頭上の木々に「ありがとう」とつぶやき、赤ん坊を両腕に抱えて彼女は道を西へと歩き始めた。
2920年、第13巻The Year 2920, Vol. 13
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 真央の月2日
バルモラ (モロウウィンド)
「帝国軍が南に集結しております」キャシールは言った。「二週間の進軍でアルド・イウバルとコロナチ湖に到達するでしょう。それと、きわめて重装備でありました」
ヴィベクはうなずいた。アルド・イウバルと湖の対岸の姉妹都市、アルド・マラクは戦略の要地とされる城砦だった。ここしばらく、敵が動くのではないかと懸念していた。ヴィベクに仕える将軍がモロウウィンド南西部の地図を壁から引きはがすと、開け放しの窓から舞い込んでくる心地よい夏の海風と格闘しながら、手で撫でつけてまっすぐに伸ばした。
「重装備だと言ったな?」と、将軍は訊いた。
「はい、将軍」キャシールは言った。「ハートランドはベサル・グレイにて野営しておりました。どの鎧も黒檀製やドワーフもの、デイドラものばかりで、上等な武具や攻城兵器も確認できました」
「魔術師や船は?」と、ヴィベクは訊いた。
「魔闘士の軍団がおりましたが…」キャシールは答えた。「船はないものかと」
「それほどの重装備なら、ベサル・グレイからコロナチ湖までは確かに二週間はかかる」ヴィベクは地図をじっくりとながめた。「さらに北からまわり込んでアルド・マラクへ向かおうとすれば、沼地にはまってもたつくことになろう。となれば、この海峡を越えてアルド・イウバルを攻め落とそうと考えるにちがいない。それから湖岸沿いに東進し、南からアルド・マラクを奪おうとする」
「海峡を越えてくるなら、やつらは袋のねずみですな」と、将軍は言った。「半分ほど渡りきってしまえばもうハートランドには引き返せない。そこで一気に襲いかかるのです」
「またもやそなたの機知に助けられたようだ」ヴィベクはそう言い、キャシールに笑いかけた。「今一度、帝国の侵略者どもを撃退してやろうぞ」
2920年 真央の月3日
ベサル・グレイ(シロディール)
「勝利しておきながら、かように帰還なさるおつもりですか?」ベサル卿は訊いた。
ジュイレック皇太子はまるでうわの空だった。野営地の後片づけをしている軍隊に意識を集中させていた。肌寒い森の朝だったが、雲ってはいなかった。午後の進軍は暑さとの戦いになりそうだった。これだけの重装備ならなおさらだ。
「早期撤退は敗北してこそするものでしょう」と、皇太子は言った。遠くの牧草地で、最高顧問ヴェルシデュ・シャイエが、村の食料や酒、それに女を用立ててくれた執事に謝金を渡しているのが見えた。軍隊とはじつに金がかかるものだ。
「しかしながら、皇太子…」と、ベサル卿は不安げに訊いた。「このまま東進なさるおつもりですか?それではコロナチ湖の湖畔にたどりつくだけでしょう。南東から海峡へ向かわれたほうがよいのでは」
「あなたは村の商人が約束の報酬をもらったかどうかを案じていればいい」と、皇太子は笑みを浮かべて言った。「軍隊の行き先は私が考えましょう」
2920年 真央の月16日
コロナチ湖 (モロウウィンド)
ヴィベクは広大な青い湖面の向こうをながめた。自らと軍の姿が青い水面に映り込んでいた。が、帝国軍の姿は映り込んではいなかった。森で待ち受ける災難を嫌って、とっくに海峡へ到着しているはずだった。羽根のように薄っぺらなひょろ長い湖岸の木々が邪魔になって海峡の様子はほとんどうかがえなかったが、かさばる重装備に身を包んだ一団が誰の目にもとまらずに音もなく移動することなど不可能だった。
「もう一度地図を見せてくれ」ヴィベクは将軍を呼ばわった。「他の進路があるとは考えられないか?」
「北の沼地には哨兵を配備しております。浅はかにも、やつらが沼地に入ってもがいている可能性もないとは言えませんからな」と、将軍は言った。「少なくとも報告があるでしょう。が、湖を越えるとしたら海峡を抜けるより他はありません」
ヴィベクはまた湖面に映った影を見つめた。彼をからかうようにゆらゆらと揺れていた。それから、ヴィベクは地図に視線を戻した。
「密偵か…」ヴィベクはそう言うと、キャシールを呼びつけた。「敵軍は魔闘士の一団を引き連れていたと言ったが、どうして魔闘士だとわかったのだ?」
「灰色の法衣に謎めいた紋章を身につけておりましたから…」と、キャシールは述べた。「魔闘士だと直感しました。あれだけの大人数でしたし。軍が治療師ばかりを同道させているとは思えませんので」
「浅はかなやつめ!」ヴィベクは怒鳴った。「やつらは変性の技巧を学んだ神秘士なのだぞ。水中呼吸の魔法を全軍にかけたにちがいない」
ヴィベクは手ごろな見通しのきく場所へ走って、北の方角を見渡した。水平線に浮かぶ小さな影でしかなかったが、対岸のアルド・マラクから襲撃の火の手があがっているのが見えた。ヴィベクは怒りの雄たけびをもらした。将軍はただちに、城砦を守るべく湖をまわり込むよう軍隊に指示を出しなおした。
「ドワイネンに帰れ」ヴィベクはキャシールに向かって言い放つと、戦いに加勢すべく出発した。「わが軍はもはやお前の力を必要としていない」
モロウウィンド軍がアルド・マラクに迫ったときにはもう手遅れだった。街は帝国軍の手に落ちていた。
2920年、第14巻The Year 2920, Vol. 14
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 真央の月19日
シロディール領帝都
最高顧問ヴェルシデュ・シャイエが帝都に凱旋すると、熱烈な歓迎が待っていた。男も女も通りにずらりと並んで、アルド・マラク陥落の象徴である最高顧問を褒め称えた。皇太子が帰還していたらこれ以上の群集が出迎えたであろうことは、シャイエにもわかっていた。それでも、彼は大いに気を良くしていた。タムリエルの民がアカヴィリの到着を歓迎するなど、それまでにないことだった。
皇帝レマン三世は心のこもった抱擁で彼を出迎えると、やおら皇太子から届いた手紙を突きつけてきた。
「どういうことかね」皇帝はようやく言った。喜んでいながらもとまどっていた。「湖にもぐったと?」
「アルド・マラクは、難攻不落の要塞です」最高顧問はそう言った。「それに加えて、われらの動きを警戒しているモロウウィンド軍が周囲を巡回しています。攻め落とすには不意を突いて、鎧の頑丈さにものを言わせて攻撃するしかありません。水中でも呼吸できる魔法をかけることで、われらはヴィベクに感づかれないうちに移動することができました。水中では鎧の重みもさほど気になりません。そして守備のもっとも手薄な砦の西側の水締めから攻め入ったのです」
「すばらしい!」皇帝は歓声をあげた。「驚くべき戦術家だな、ヴェルシデュ・シャイエよ!そなたの父親にもそれだけの才覚があったら、タムリエルはアカヴィリの領土になっていただろう!」
実のところ、その計画はジュイレック皇太子が考えたものだった。シャイエとしては、皇太子の功績を横取りする気はみじんもなかったが、大失敗に終わった260年前の祖先の侵略のことに皇帝が触れたとき、決心したのだった。シャイエは控えめな笑みを浮かべて、おもうぞんぶん賞賛を味わった。
2920年 真央の月21日
アルド・マラク (モロウウィンド)
サヴィリエン・チョラックは腹ばいになって壁まで進み、モロウウィンド軍が沼地と砦に挟まれた森の中へ撤退していくのを銃眼からじっと見つめた。絶好の攻撃機会のように思われた。敵軍もろとも森を焼き払ってしまえばいい。ヴィベクさえ捕らえてしまえば、敵軍はアルド・イウバルもおとなしく明け渡すかもしれない。チョラックはその案を皇太子に持ちかけてみた。
「ひとつ忘れているようだけど」ジュイレック皇太子は一笑にふした。「休戦交渉中は敵の兵士や指揮官に手を出さないと約束しているんだ。アカヴィルでの戦いに誇りは不要なのかい?」
「お言葉ながら、私はタムリエルで生まれ育ち、祖国を訪れたことはございません」蛇男は答えた。「が、それでも、あなたの流儀はどうも解せない。五ヵ月前に帝都の闘技場で戦ったときも、あなたは金銭を求めようとせず、私は一銭も払わなかった」
「あれは遊びだから」皇太子はそう言うと、執事にうなずいてみせ、ダンマーの戦士長を迎え入れた。
ジュイレックがヴィベクに会うのは初めてだった。この男が神の化身であるという話は聞いていたが、目の前に現れたのはひとりの男だった。屈強で端正な顔をした男で、知性にあふれる顔をしていたものの、やはりただの男だった。皇太子はほっとした。ただの男となら話せる。神であるなら話は別だが。
「はじめまして、わが称えるべき好敵手」と、ヴィベクは言った。「お互いに手詰まりのようだな」
「そうともかぎりません」皇太子は言った。「あなたはモロウウィンドを明け渡したくはないし、私としてもそれをとがめることはできません。が、外敵の侵略から帝都を守るため、モロウウィンドの沿岸地域はどうしても押さえておきたい。それと、この場所のような、戦略の要地である国境の砦もほしい。アルド・ウンベイル、テル・アルン、アルド・ランバシ、テル・モスリブラもすべて」
「して、見返りは?」と、ヴィベクは訊いた。
「見返りだと?」サヴィリエン・チョラックは笑い飛ばした。「いいか、勝者はわれらだ。お前じゃない」
「見返りとして」ジュイレック皇太子は慎重になって言った。「帝国はモロウウィンドを襲わないと約束しましょう。もちろん、そちらから攻めてきた場合は別として。侵略者があれば、帝国海軍が助けに駆けつけましょう。それから、領土も分け与えましょう。ブラック・マーシュから好きな土地を選んでください。帝都にとって無用な土地であればですが」
「悪くない条件ですが」間をおいて、ヴィベクは言った。「即答はできかねますな。シロディールが奪ったぶんだけ補償してくれるなど、これまでになかったことですから。数日の猶予をいただけますか?」
「では、一週間後に会いましょう」皇太子はそう言って微笑んだ。「それまでにそちらが攻撃をしかけてくることがなければ、秩序は保たれるでしょう」
ヴィベクは皇太子の私室をあとにした。アルマレクシアの読みの正しさを感じながら。戦争は終結した。ジュイレック皇太子は立派な皇帝になるだろう。
2920年、第15巻The Year 2920, Vol. 15
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 南中の月4日
帝都(シロディール)
皇帝レマン三世と最高顧問ヴェルシデュ・シャイエは、2人並んで宮殿の庭園をぶらついていた。彫像や噴水で飾られた、北の方の庭園が皇帝の今の気分に合っていた。何より夏の暑さを避けるのに好都合であった。よく手入れされた、青灰色と緑色に染まった花壇が、歩いて行く彼らの周りに階段状に広がっていた。
「ヴィベクは皇太子の和平の申し出を受け入れたようだな」と皇帝は言った。「息子は2週間もすれば帰って来るそうだ」
「素晴らしい知らせですね」とヴェルシデュ・シャイエは注意深く答えた。「ダンマーが約束を守ってくれればいいのですが。ブラックゲート要塞の件もありますし、それに関しては、私達も強く出るべきでしょう。しかし、皇太子は妥当な方法を採られたと思います。決して、平和のためだけに帝国を陥れるようなことはなさらないでしょう」
「このところ私が考えていることは、なぜリッジャが私を裏切ったかということだ」と言って皇帝は立ち止まると、奴隷女王アレッシアの像を崇め、言葉を続けた。「一つだけ考えられる理由は、彼女が皇太子の方になびいていたのかもしれない、ということだ。確かに私の権力や人柄には惚れ込んでいたのだろうが、しかし皇太子は若い、そして美しい。それに、ゆくゆくは皇位を継ぐことになる。もし私を暗殺してしまえば、彼女は若さと権力の両方をそなえた皇帝を手に入れられるのだから」
「皇太子が?彼がこの謀略に関係していると?」とヴェルシデュ・シャイエは尋ねた。皇帝の被害妄想の矛先はどこに向かうのか予想できなかった。
「いや、もちろん本気でそうだとは思っていない」と皇帝は笑って言った。「皇太子は私のことをとても愛してくれている」
「コルダのことはご存知ですか?リッジャ様の妹で、ヘガテにあるモルワ修道院の見習いなのですが」とシャイエは聞いた。
「モルワ?そこは何の神だったかな?」と皇帝が聞いた。
「官能と豊穣を司る、ヨクダの女神ですよ」とヴェルシデュ・シャイエは答えた。「もっとも、ディベラほどの好色ではありませんが。つまり、上品ですが官能的なんです」
「私は官能的な女性にはうんざりだ。女帝。リッジャ。欲望が過ぎる。強すぎる愛への切望は、強い権力への切望に通じているものだ」と皇帝は肩をすくめた。「しかし、ある程度の健康的な欲求を持った司祭見習いなら、理想的というものだ。ところで、ブラックゲート要塞の件についてはどう思う?」
2920年 南中の月6日
サーゾ要塞(シロディール)
皇帝がリッジャに話しかけたとき、彼女は冷たい石床にじっと目を落としていた。これほどまでに青白くやつれた姿を、彼は見たことがなかった。少なくとも、自由の身になって故郷に戻れることを彼女は喜んでいるのかも知れない。何故なら、彼女が帰る頃には、ハンマーフェルでは「商人の祝典」が開かれているからだ。だが、彼の見たところ、彼女は何の反応も示さなかった。このサーゾ要塞での1ヶ月半が、彼女の心をすっかり壊してしまったのだ。
「私はこう考えている」とうとう皇帝は切り出した。「お前の妹のコルダを、しばらく宮殿に置こうと思う。きっと、ヘガテの修道院よりは気に入ってくれると思うのだが。そう思わないか?」
彼女は反応した。キッと彼の方を見据えると、獣のような怒気を投げつけたのだ。そして、長年の監禁で伸び放題になっていた爪を、彼の顔面、目に向かって振り下ろした。彼が痛みに声をあげると、衛兵がすぐに駆けつけ、彼女を剣の峰でもって気絶するまで激しく殴った。
すぐに治癒師が呼ばれたが、皇帝レマン三世は右眼を失った。
2920年 南中の月23日
バルモラ (モロウウィンド)
水から出ると、ヴィベクは肌に照りつける太陽の熱を感じた。そして、召使からタオルを受け取った。ソーサ・シルがこの古い友人の様子をバルコニーから見ていた。
「傷跡がまた増えたようだね」とその妖術師は言った。
「アズラの話では、しばらくはこれ以上増えることはないはずだがね」とヴィベクは笑った。「いつこっちへ?」
「1時間くらい前だ」とソーサ・シルは言って、階段を降り、彼のそばに近寄った。「戦争は終わりに近付いているようだな。しかも、私の手を借りず、君の手によって」
「まあ、いくら終わらないとはいえ、80年は長すぎる」ヴィベクはそう返すと、ソーサ・シルと抱き合った。「こちらも譲歩したし、あちらも譲歩した。今の皇帝が死ねば、私達は黄金期に入るだろうね。ジュイレック皇太子は、年の割に聡明な青年だ。ところで、アルマレクシアはどこだ?」
「モーンホールドへ公爵を呼びに行っている。明日の昼には、2人ともここへ到着するだろう」
彼らは、ふと邸宅の角の方を見やった。2人に向かって、馬に乗った女が近付いて来ていた。長い道のりを走破して来たのは明白である。書斎に招じ入れられると、息を切らして話始めた。
「裏切られた」と女があえぐように言った。「ブラックゲートが帝国軍によって奪取されたわ」
2920年、第16巻The Year 2920, Vol. 16
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 南中の月24日
バルモラ (モロウウィンド)
ソーサ・シルがアルテウム島に行った後、モロウウィンドのトリビュナルのメンバー3人が一同に会するのは、実に17年振りであった。しかし、このような形での再会は、3人の誰も願ってはいなかった。
「我々の情報によれば、皇太子の指揮する帝国軍が南方のシロディールへと立ち去るのと入れ代わりに、別の帝国軍が北方から迫って来たようだ」と、石のように固まった表情の仲間に向かって、ヴィベクが言った。「もちろん、皇太子がこの攻撃を知らなかったという可能性もある」
「だが、その逆も考えられる」とソーサ・シルが答えた。「皇太子が気を引いている間に、皇帝がブラックゲートを討つ。いずれにせよ、これは講和協定の破棄と見るべきだな」
「モーンホールド公爵はどこに?」とヴィベクが尋ねた。「彼の意見も聞きたい」
「テル・アルンの夜母と会っているところよ」とアルマレクシアが静かに答えた。「あなたと話すまで待つよう言ったんだけど、でも、”この問題については、もう待てない”と」
「モラグ・トングを巻き込むつもりなのか?国の問題だぞ?」と言ってヴィベクは首を振ると、ソーサ・シルに言った。「全力を尽くして欲しい。暗殺は事態を逆戻りさせるだけだ。この問題には、外交もしくは戦闘しかない」
2920年 南中の月25日
テル・アルン (モロウウィンド)
大広間の夜母とソーサ・シルを、月の光だけが照らしている。彼女は、この上なく美しいドレスの上に簡素な絹の黒ローブを羽織って、長椅子にもたれかかっていた。夜母は赤マントの衛兵達を退室させると、彼にワインを勧めた。
「ちょうど公爵と入れ違いね」と彼女は囁いた。「彼、悲しんでいたわ。でも、私達がしっかり解決してみせます」
「公爵は、皇帝を殺すモラグ・トングの暗殺者を雇ったんだろう?」とソーサ・シルが尋ねた。
「はっきり言うわね。いいわ、そういう人、好きよ。時は金なりね。もちろん、私と公爵との話をあなたに教える訳にはいかないけど」と彼女はにっこり笑った。「商売上の守秘義務だから」
「もしも、皇帝の暗殺を止めさせるのに、同じだけの金を出すとしたらどうする?」
「私達モラグ・トングは、メファーラの栄光と利益のために動いているの」と夜母は言ってグラスを傾けた。「これは単なる殺しじゃない。そんなものは冒涜に過ぎない。三日以内に公爵から金が入れば、仕事にとりかかって、終わらせる。その逆の仕事をするなんてあり得ないこと。確かに、私達は利益を求めて動くけれど、需要と供給に従うわけではないのよ、ソーサ・シル」
2920年 南中の月27日
内海 (モロウウィンド)
ここ2日間ずっと内海を眺めていたソーサ・シルは、ついに目当ての船がやってくるのを見つけた。モーンホールドの旗を掲げた重装船である。妖術師ソーサ・シルは先手を取って、船が港へ着くのを妨害した。炎の帯が彼の体から噴き出し、声が変わり、炎はデイドラの形に変化した。
「その船を捨て去れ!」と彼は大声で唸った。「さもなくば、船もろとも沈めてやろう!」
実際に放った火の球は一つだけだったが、彼の思惑通り、乗組員達は暖かい海へと飛び込んで行った。全員が飛び込んだのを見計らって、彼は強烈なエネルギーを破壊的な波動に込めた。その波動は、空気と海水を震わせながら、公爵の船をことごとく粉砕し、船はモラグ・トングの報酬になるはずだった公爵の金と共に、内海の深くへと沈んでいった。
「夜母よ」と、湾岸警備員に救助が必要な船乗りがいることを知らせるために岸に向かって泳いでいる間、ソーサ・シルは考えていた。「需要と供給には誰もが従わねばならないのだ」
2920年、第17巻The Year 2920, Vol. 17
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 収穫の月1日
モーンホールド (モロウウィンド)
彼らは黄昏時に公爵の中庭に集まり、暖かい焚き火とビターグリーンの葉の香りを楽しんだ。小さな燃えかすが空へ舞い上がってはすぐに消えた。
「私は軽率だった」公爵は、冷静な口調でそう認めた。「そして、ロルカーンは彼らに味方し、全てが彼らの思うままになった。私がモラグ・トングに支払った報酬が内海に沈んだ今、皇帝の暗殺は失敗だ。君はデイドラ公たちと協定を結んだのではなかったのか」
「船乗りたちがデイドラと言っていたものが、本当にデイドラかどうか」と、ソーサ・シルが答えた。「船を壊したのは、狂暴な魔闘士や稲妻の類かもしれません」
「皇太子と皇帝は、我々との休戦協定に基づいてアルド・ランバシを占領するため、かの地へ向かっている。自分らの利権については交渉してくるくせに、我々には交渉の余地を与えないとは、シロディールの連中らしいな」ヴィベクは地図を取り出した。「アルド・ランバシの北西の、このファーヴィンシルという村で彼らを待つんだ」
「でも、そこで彼らを待って、話し合いをするのですか?」アルマレクシアがたずねた。「それとも戦うのですか?」
誰もそれには答えなかった。
2920年 収穫の月15日
ファーヴィンシル (モロウウィンド)
夏の終わりのスコールが小さな村を襲っていた。空は暗く、時折稲妻が曲芸のように雲から雲へと渡った。通りはかかとほどの深さのある川のようになり、皇太子はそう遠く離れた場所にいない指揮官たちと話すのに大声で叫ばなければならなかった。
「あそこに宿屋がある!あそこで嵐が過ぎるのを待ってからアルド・ランバシへ進むぞ!」
宿屋の中は暖かく、外の雨とは無縁のようで、にぎわっていた。バーの女たちがせわしなく、グリーフやワインを奥の部屋へ運んでいた。どうやら重要な人物が来ているようだった。タムリエル皇帝の後継者などよりもずっと重要な人物が。ジュイレックは面白がって彼女らの様子を見ていたが、そのとき、彼女らの一人が「ヴィベク」という名前を口にした。
「ヴィベク閣下…」と、ジュイレックは奥の部屋に駆け込んで言った。「信じていただきたい。ブラックゲートへの攻撃は、私のあずかり知らないところで行われたのです。もちろん、直ちに賠償をさせていただきたいと思います」彼は一瞬沈黙し、部屋の中に見慣れない人物がたくさんいるのに気付いた。「失礼しました、私はジュイレック・シロディールです」
「アルマレクシアです」皇太子が今までに見た中で一番美しい女性が名乗った。「こちらへお入りになりませんか?」
「ソーサ・シルです」白いマントをつけた厳格な面持ちのダークエルフが皇太子と握手し、椅子を勧めた。
「インドリル・ブリンディジ・ドローム、モーンホールド大公です」と、皇太子が席に着くと、隣に座っていた大柄な男が言った。
「先月に起こったことからもわかるとおり、帝国軍は私の指揮下にはないのです」皇太子はワインを注文し、話しはじめた。「帝国軍は父のものですから、まあ当然なのですが」
「皇帝陛下もアルド・ランバシへいらっしゃるのでしょう」と、アルマレクシアが言った。
「表向きはそういうことになっていますが…」と、皇太子は慎重に言葉を選びながら言った。「実際は、まだ帝都に残っているのです。不運な事故がありまして」
ヴィベクは公爵を見てから、皇太子のほうを向いた。「事故?」
「皇帝は無事なのです」と、皇太子は慌てて言った。「命に別状はないものの、片目を失明しそうなのです。この戦争とはまったく無関係の諍いの結果です。不幸中の幸いは、皇帝が回復するまで私が皇帝の代理になるということです。今、この場で結んだ条約は全て帝国を縛り、皇帝の代はもちろん、私が正式に皇帝になってからも効力を失うことはありません」
「それなら、さっそく始めましょう」アルマレクシアがほほえんだ。
2920年、第18巻The Year 2920, Vol. 18
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 収穫の月16日
ロス・ナーガ(シロディール)
ロス・ナーガの小村の眺めは、キャシールの目を楽しませた。色とりどりの家々がロスガリアン山脈の大地を見下ろす断崖に立ち並び、遠くハイロックまでを見渡すことができた。息をのむような素晴らしい眺めに、彼は最高の気分だった。しかし同時に、このような小さな村では、彼と彼の馬が満足な食事をとることはできなさそうだとも思っていた。
彼が馬で村の中心の広場まで来ると、そこに「イーグルズ・クライ」という宿屋があった。厩番の少年に馬をあずけ、餌をやるように言いつけてから、キャシールは宿屋に入った。宿屋の中の雰囲気は、キャシールを圧倒するようなものだった。ギルヴァーデイルで見たことのある吟遊詩人が、地元の山男たちに陽気な音楽を奏でていた。そういった陽気さは、今の彼にはうっとうしかった。音楽と喧噪から離れた場所にテーブルが一つあり、陰気なダークエルフの女性が座っていた。キャシールは自分の飲み物を持ってそちらへ行き、同じテーブルについた。その時初めて、彼はその女性が生まれたばかりの赤ん坊を抱いていることに気付いた。
「モロウウィンドから着いたばかりなんです」彼はどぎまぎして、声を落としながら話しかけた。「ヴィベクとモーンホールド公爵の側で、帝国軍と戦っていたんですよ。自分と同じ人種を裏切ってきたわけです」
「私も、同じ人種の人たちを裏切ってます」と、女性は言い、手に刻まれた印を見せた。「もう、故郷には帰れません」
「まさか、ここに滞在するつもりじゃないでしょうね?」キャシールは笑った。「ここは確かにいいところですが、冬までいてごらんなさい、目の高さまで雪が積もるんですよ。赤ん坊がいられるところじゃありません。その子、名前は何ていうんです?」
「ボズリエルです。「美しい森」という意味です。これからどちらへ行かれるのですか?」
「ハイロックの海沿いにある、ドワイネンというところです。よかったら一緒に行きませんか。連れがいたほうがいいんです」キャシールは手を差し出した。「キャシール・オイットリーです」
「トゥララです」と、一瞬考えてから、彼女は答えた。風習に従って苗字を先に言おうとしたのだが、その名がもはや彼女の名前ではないことに気付いたのだった。「ありがとう、ぜひ、ご一緒させてください」
2920年 収穫の月19日
アルド・ランバシ (モロウウィンド)
城の大広間に、5人の男と、2人の女が黙って立っていた。聞こえてくる音といえば、羽ペンが羊皮紙の上を滑る音と大きな窓を叩く雨の音だけだった。皇太子が文書にシロディールの印を押し、公式に戦争が終わりを告げた。モーンホールド公爵は喜びの声をあげ、80年間続いた戦争の終結を祝うため、ワインを持ってくるように言いつけた。
ソーサ・シルだけが、喜ぶ人々の輪から離れて立っていた。彼の顔からは、どんな種類の感情も読み取れなかった。彼は物事の終わりや始まりといったものを信じておらず、ただいつまでも続く繰り返しの一部分としか思っていなかったのだ。
「皇太子殿下」城の執事が、祝いの最中に申し訳なさそうに入ってきた。「お母様の皇后陛下からの使者が到着し、皇帝陛下に謁見したいとのことだったのですが、間に合わなかったために–」
ジュイレックは周囲に断り、使者と話すためにその場を離れた。
「女帝は帝都に住んでいないのか?」と、ヴィベクがたずねた。
「ええ」アルマレクシアは、悲しい顔で首を横に振った。「皇帝が、女帝が反逆を企てていると疑って、彼女をブラック・マーシュに幽閉したのです。女帝は莫大な資金を持ち、西コロヴィア地方の多くの領主と同盟関係にあったため、皇帝は彼女を処刑することも離婚することもできませんでした。皇帝と女帝は、ジュイレック皇太子がまだ子供のころから17年間、離れて暮らしています」
数分後、皇太子が戻ってきた。平静を装おうとしていたが、彼の顔からは不安の色がにじみ出ていた。
「母が私を呼んでいる」と、彼は簡潔に言った。「申し訳ないが、行かなくてはなりません。もしよければ、この条約文書を持っていって女帝に見せ、喜ばしい平和条約が結ばれたことを報告したいと思います。その後、文書は帝都に持ち帰り、公式に発効させます」
ジュイレック皇太子はモロウウィンドの三大神に丁寧な別れの挨拶を延べ、広間を出た。馬に乗った皇太子が夜の雨の中を南のブラック・マーシュへ向けて走ってゆくのを窓から見ながら、ヴィベクは言った。「彼が皇帝になれば、タムリエルはずっと良い国になるだろうな」
2920年、第19巻The Year 2920, Vol. 19
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 収穫の月31日
ドルザ・パス(ブラック・マーシュ)
荒涼とした石切り場の上に月がのぼり、熱い夏の間に溜まった沼気が立ち上っていた。皇太子と二人の護衛は馬で森を抜けたところだった。太古の昔、この地に住んでいた人々は北からの侵入者を防ぐために泥と肥やしを高く積み上げて土塁をつくり、それは彼らが滅び去った今も残っていた。しかし、侵入者たちはこの土塁を破っていたようだ。ドルザ・パスと呼ばれる道が、この何マイルも続く土塁を貫いていた。
土塁の上にはねじ曲がった黒い木々が生え、絡み合った網のような奇妙な影を落としていた。皇太子は、母の手紙のことを考えていた。その謎めいた手紙には、侵略の脅威がほのめかされていた。もちろん、そのことをあのダークエルフたちに伝えることはできなかった。少なくとも、もっと詳しいことを知り、皇帝に報告した後でなければ。何よりも、手紙は彼だけに宛てて書かれていたのだ。急を要しそうなその文面に、彼は直接ギデオンへ出向くことを決めたのだった。
女帝からの手紙には、最近、解放された奴隷たちがドルザ・パスで行商人を襲うことが多いので気をつけるようにとも書かれていた。そして、奴隷を使っていたダークエルフではないことを示すため、皇帝家の紋章が入った盾を目立つように掲げるようにとの助言が付け加えられていた。背の高い草が不愉快な川のように道を横切って生い茂っている場所があり、そこを通るときに、皇太子は盾を掲げるように命じた。
「奴隷たちが通行人を襲うならこのあたりでしょうな」と、護衛隊長が言った。「ここは待ち伏せにぴったりです」
ジュイレックはうなずいたが、心では別のことを考えていた。女帝のいう侵略の脅威とは何だろうか?アカヴィリがまた海から攻めてきたのか?もしそうだとしても、ジオヴェーゼ城に幽閉されている母がなぜそれを知り得たのか?そのとき後方の草の中で何かが動く音と、短い叫びが聞こえたので、彼の考えは中断された。
振り向くと、皇太子は一人になっていた。護衛が消えていたのだ。
皇太子は、月明かりに照らされた草原を見渡してみた。道を吹き抜ける風に草原はまるで大海原で潮が満ち引きするように揺れ、その様子は幻惑的ですらあった。この揺れ動く草の下で、兵士が格闘していても馬が死にかけてもがいていても、わかりそうになかった。ひゅうひゅうと吹く風がまわりの音を消し、伏兵にやられた兵士が声をあげても彼の耳には届かないだろう。
ジュイレックは剣を抜き、どうすべきか考えた。理性が、混乱する心に落ち着くよう告げていた。彼は、道の入口よりも出口に近い地点にいた。護衛を殺した者は、おそらく後ろにいるはずだった。馬をとばせば、逃げ切れるかもしれない。彼は馬に拍車をかけ、前方に見える黒い泥の丘へ向けて駆け出した。
彼の体が宙を舞ったとき、あまりにも突然すぎて、彼にはいったい何が起こったのかわからなかった。少し離れた先の地面に投げ出され、衝撃で肩と背中の骨が折れたようだ。全身がしびれ、馬のほうを見ると、かわいそうに腹に大きな傷を負って死にかけていた。草の高さのあたりから突き出ている数本の槍でやられたのだろう。
ジュイレック皇太子は、草むらから出て来た者の顔を見ることも、動いて身を守ることもできなかった。皇帝家の人間にふさわしい死の儀式もないまま、彼は喉を切り裂かれた。
ミラモールは、月明かりに照らされた死体の顔を見て悪態をついた。彼は以前、ボドラムの戦いで皇帝の指揮下で戦い、その際に皇帝の顔も見ていたので、この人物が皇帝でないことはすぐにわかった。死体の服を探り、彼は手紙と条約文書を見つけ出した。モロウウィンドを代表するヴィベク、アルマレクシア、ソーサ・シル、そしてモーンホールド公爵と、シロディール帝国を代表するジュイレック・シロディールの署名のある平和条約だった。
「ついてない」と、草のざわめく音の中、ミラモールはぶつぶつと独り言を言った。「皇太子しか殺せなかった。何の得にもならない」
ミラモールはズークに言われたとおり、手紙を始末し、条約文書はポケットにしまった。大抵、こうした珍しいものには金を出そうという者がいるのだ。彼は用のすんだ罠を取り外し、次はどこへ行こうかと考えた。ギデオンに戻り、依頼主に皇帝ではなくその後継者を暗殺したと報告し、いくらかでも報酬をもらえないかたずねてみようか?それとも他の土地へ行こうか?少なくとも、彼はボドラムの戦いで2つの有用な能力を身に付けていた。ダークエルフからは、槍を使った強力な罠の作り方を学んだ。そして、帝国軍を去ることで、草むらに忍んで動き回る能力を身に付けたのだった。
女帝タヴィアは彼女のベッドに横たわり、独房のなかを行ったり来たりする晩夏の熱風を感じられずにいた。喉は燃えるようにひりついていたが、それでも彼女は抑えきれずにすすり泣き、最後のつづれ織りを手で握りつぶした。彼女の嘆きの声はギオヴェッセ城の誰もいない廊下中をこだまし、洗い物をしていた召使の手や衛兵の会話を止めた。彼女の召使の1人が細い階段を登ってきたが、彼女の衛兵長ズークが入口に立ち、首を振った。
「彼女はたった今、息子の死を知った」と、彼は静かに言った。
2920年、第20巻The Year 2920, Vol. 20
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薪木の月5日
帝都(シロディール)
「陛下…」最高顧問ヴェルシデュ・シャイエは扉を挟んで言った。「扉を開けても大丈夫です。お約束します、完全に安全です。誰も陛下を殺そうとはしていません」
「ああ、マーラよ!」押さえ込むような乱心の混じった皇帝レマン三世の声がした。「誰かが皇太子を暗殺したのだ。そして彼は私の盾を持っていた。私であると思い込んだのかもしれないではないか!」
「確かにその通りです、陛下」最高顧問は軽蔑しながらも声から一切のあざけるような口調を消し去り言った。「そして、我々は陛下の息子の死に対して責任を負うべき悪人を探し、処罰しなければなりません。しかし、陛下なくしてそれはできません。帝都のために勇敢でおありください」
返答はなかった。
「最低でも出てきてリッジャ様の処刑指令書に署名願います」最高顧問は呼びかけた。「我々の知る、裏切り者であり暗殺者である1人を処分しましょう」
しばらく沈黙が続き、そして家具が床の上を引きずられる音がした。レマンは扉をほんの少しだけ開いたが、怒り、恐れている顔と、以前は彼の右目があった場所にある、引き裂かれた皮膚の盛り上がりが最高顧問には見えた。帝都の最高の治癒師の治療もむなしく、サーゾ要塞でのリッジャからの恐ろしい置き土産がそこにあった。
「指令書をよこせ」皇帝は怒鳴り声を出した。「喜んで署名してやる」
2920年 薪木の月6日
ギデオン(ブラックマーシュ)
沼地の気体と霊的なエネルギーの組み合わせであると教えられたウィル・オ・ウィスプの奇妙な青い光は、窓の外を見るたびにタヴィアを怖がらせてきた。今は妙に慰めているように見えた。沼地の向こうにはギデオンの街がある。17年間も毎日見てきたのに、あの街の街路に1度も足を踏み入れたことがないことを可笑しく思った。
「何か私が忘れているものを思いつくか?」彼女は忠実なコスリンギ、ズークに振り返りながら聞いた。
「何をすればよいのか、明白に分かっております」と、彼は簡単に言った。彼が笑ったように見えたが、彼女の笑顔が彼の銀色に光る肌に反射されたのだと女帝は気付いた。彼女は自分が笑っていることに気が付いていなかった。
「尾行されていないことを確認するのだぞ」と、彼女が警告した。「この長きに渡り、どこに我が金が隠されていたのかを夫には知られたくない。あと、自分の分け前はしっかりと取るのだぞ。そなたは良き友であった」
女帝タヴィアは前へと踏み出し、霧の中へと視界から消え落ちた。ズークは塔の窓に鉄格子を戻し、ベッドの上の枕に毛布を被せた。運がよければ明日の朝まで芝生に横たわる彼女を発見しないであろう。そしてそのころには、彼はモロウウィンドの近くまで辿りつけていることを期待していた。
2920年、第21巻The Year 2920, Vol. 21
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薪木の月9日
フィルギアス(ハイロック)
周囲にある奇妙な木々が、赤や黄色やオレンジがほとばしる毛糸の束のように見え、それはまるで虫の巣に火をかけ、様々な彩りの生き物が一斉に出てきたようであった。ロスガリアン山は霧のかかった午後にかすんでいった。トゥララは広い牧草地へと馬をゆっくりと進めながら、見慣れない、モロウウィンドとはまったく違った景色に驚いた。後ろでは、頭を縦に振りながら、キャシールがボズリエルを抱きかかえたまま眠った。一瞬、トゥララは野原をさえぎるペンキで塗られた低い柵を飛び越えようかと考えたが、それはやめておいた。キャシールに手綱を渡す前に、あと数時間寝かせてあげようと思った。
馬が野原に進み入ると、トゥララは森に半分隠れている小さな緑の家を隣の丘の上に見た。その姿は絵に描いたように美しく、彼女は半眠状態に引き込まれていくのを感じた。そのとき、角笛の音が身震いとともに彼女を現実へと引き戻した。キャシールは目を開けた。
「今、どこ?」と、彼が息をもらすように言った。
「分からないわ」トゥララは目を見開き、どもった。「あの音はなに?」
「オーク」と、彼はささやいた。「狩人たちだ。やぶの中へ、急いで」
トゥララは馬を小走りで木が数本集まっているところへと走らせた。キャシールは子供を彼女に渡し、馬から降りた。彼は、荷物を引き降ろし始め、やぶの中にそれらを投げ入れた。そのとき、音が鳴りはじめた。遠い足音の轟音、徐々に大きくなり、近づいてくる。トゥララは慎重に馬から降り、キャシールが馬から荷を降ろすのを手伝った。その間、ボズリエルは目を開いて見ていた。トゥララは時々、子供がまったく泣かないことを心配したが、今はそれに感謝している。すべての荷を降ろしたところで、キャシールは馬の尻を打った。そしてトゥララの手を取り、茂みのなかにしゃがみこんだ。
「運がよければ…」彼はひそひそと言った。「彼らはあの馬のことを野生か農場の馬だと思ってくれて、乗り手を探しには行かないだろう」
彼がそう言ったとき、オークの大群が角笛を轟かせながら野原に殺到した。トゥララは以前オークを見たことがあったが、これほど多数でもなければ、これほど野蛮な自信に溢れてはいなかった。馬とその混乱ぶりに狂喜しながら、彼らはキャシール、トゥララ、ボズリエルが隠れている茂みを急ぎ通り越していった。彼らの暴走で野花が舞い上がり、空気中にそのタネを撒き散らした。トゥララはくしゃみを押さえ込もうとし、上手くいったと思った。しかし、オークのうちの1匹が何かを聞きつけ、調査のためにもう1匹連れてきた。
キャシールは静かに剣を抜き、自分の中の自信をできる限りかき集めた。彼の能力、あまり良いとは言えないそれは、間諜であり戦闘ではなかった。しかし、彼はトゥララと赤子をできるだけ長く保護すると誓っていた。彼は思った。もしかしたらこの2匹は殺せるかもしれないが、叫んで大群の残りを呼び寄せる前には無理である。
突然、見えない何かが風のように茂みの中を通りすぎていった。2匹のオークは後ろに飛ばされ、背を地につけて死んでいた。トゥララは後ろを振り向き、近くの茂みから真っ赤な髪を持つ、しわくちゃの老婆が出てくるのを見た。
「私のところに連れてくるつもりかと思ったぞ」彼女はささやいた、微笑んでいる。「一緒にきたほうがよい」
三人は丘の上の家に向かって生えている、茨の付いた茂みの裂け目をとおりながら老婆の後についていった。逆側に出ると、老婆はオークたちが馬の残骸をむさぼり食っているのを見に振り返った。それは複数の角笛の拍子に乗った、血まみれの祝宴であった。
「あの馬はあんたのかい?」と、老婆が聞いた。キャシールがうなずくと、彼女は声をあげて笑った。「あれはいい肉すぎじゃの。あの怪物どもは、明日には腹痛をおこして、腹が膨れ上がっていることじゃろう。いい気味じゃ」
「歩き続けなくて平気なの?」老婆の大声に肝を抜かれて、トゥララは声を低くして言った。
「奴らはここへはこんよ」笑みを浮かべ、笑い返すボズリエルを見ながら老婆は言う。「奴らは我々を恐れておるのでな」
トゥララは首を振っているキャシールのほうを向いた。「魔女ね。ここは古きバービンの農場、スケフィンヌトン魔術結社と思って間違いではない?」
「おりこうさんじゃの」老婆は悪名高きことを嬉しく思い、若娘のようにクスクスと笑った。「私の名はミニスタ・スケフィンヌトンじゃ」
「さっきの茂みの中で…あのオークたちには何をしたの?」と、トゥララが聞いた。
「霊魂の拳を頭の右側に放ったのじゃ」とミニスタは言い、坂を上り続けた。その先には農場が開け、井戸や鶏舎や池があり、様々な年齢の女性たちが家事を行ない、はしゃぐ子供たちの笑い声がした。老婆は振り向き、トゥララが理解していないことに気が付いた。「あんたの故郷には魔女がおらんのかね?」
「知る限りでは、いないわ」と、彼女は言った。
「タムリエルには実に様々な魔法の使い手がおる」彼女は説明した。「サイジックたちは、彼らのつらい義務であるかのように学ぶ。真逆の対象として、軍の魔闘士たちは呪文を矢の如く浴びせかける。我々魔女たちは、呼び出し、集い、祝うのじゃ。あのオークたちを倒すには、私が親密な関係を持つ風の霊たち、アマロ、ピナ、タラサ、キナレスの指、そして世界の風にあの雑魚どもを殴り殺すようささやきかけただけじゃ。召喚とは、力や謎解きや古い巻物を苦しみながら読むことではないのじゃ。召喚とは良き関係を築くことである。仲良くすること、とも言えるの」
「特に、私たちと仲良くしてくれていることには感謝する」と、キャシールは言った。
「そうじゃが、さらに言うとな…」ミニスタは咳払いをした。「あんたらの種族が2千年前にオークの母国を破壊したのじゃ。それまでは、やつらがここまできて我々の邪魔をすることもなかったのじゃ。さて、旅のほこりを落として、食事にでもしようかの」
そう言うとミニスタは彼らを農家へと案内し、トゥララはスケフィンヌトン魔術結社の一家と知り合いになった。
2920年、第22巻The Year 2920, Vol. 22
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 薪木の月11日
帝都(シロディール)
リッジャは前の晩、寝ようともしていなく、今彼女の処刑時に演奏されている悲しい音楽には催眠効果があると思った。それはまるで、斧が振り下ろされる前に、自発的に無意識になろうとしているようであった。彼女の目は覆われていたので、彼女の前に座り片目でにらんでいる元愛人、皇帝の姿は見えなかった。彼女には、金色の顔に勝利の表情を浮かべ、彼の下で尻尾がきれいに巻かれた最高顧問ヴェルシデュ・シャイエの姿が見えなかった。彼女を抑えようと触れた執行者の手の感触は、しびれながら感じられた。夢から覚めたものが起きようとするように跳ね上がった。
最初の一撃は頭の裏にあたり、彼女は悲鳴をあげた。次の斬撃は首を叩き切り、彼女は死んだ。
皇帝は疲れたような素振りで最高顧問に向き、「これは終わったな。それで、彼女にはコルダという名のかわいい妹がハンマーフェルにいたと言ったな?」
2920年 薪木の月18日
ドワイネン(ハイロック)
魔女たちが売ってくれた馬は、前の馬ほどよくはなかったとキャシールは思った。霊の崇拝や生け贄や姉妹関係は霊魂の召喚には便利で役立つのかもしれないが、荷役用の動物にはあまり効果がないらしい。それでも、彼には文句を言う理由がなかった。ダンマーの女とその子供が彼の手を離れ、彼は予定よりも早く到着できた。先には彼の母国を囲う壁が見えた。ほぼ同時に、彼の周りには旧友や家族の人々が群がった。
「戦争はどうだったの?」従兄弟が叫びながら道に出てきた。「ヴィベクは皇太子との和平に応じたのに、それを皇帝が拒否したって本当なの?」
「そうじゃないだろう、違うのか?」と、友達の1人が輪に入りながら言った。「ダンマーが皇太子を殺させて、その後、条約の話をでっち上げたけど証拠がないって俺は聞いたぜ」
「ここでは何も面白いことは起きていないのか?」キャシールは笑った。「本当に、これっぽっちも戦争やヴィベクについて語る気がしない」
「お前はレディ・コルダの行列を見逃したぞ」と、友が言った。「大勢の取り巻きと一緒に湾を横切ってきて、帝都に向かって東に行ったんだ」
「でもそんなのは大したことないや。それで、ヴィベクって、どんななの?」従兄弟が熱心に聞いた。「彼は現人神のはずだよね?」
「もしシェオゴラスが退いて、他の乱心の神が必要になったなら、彼がうってつけだな」と、キャシールは偉そうに言った。
「それで、女は?」極稀な機会にしかダンマーの女性を見たことがない青年が聞いた。
キャシールはただ微笑んだ。トゥララ・スケフィンヌトンが一瞬頭をよぎり、すぐに消えた。魔術結社と一緒にいれば彼女は幸せであろうし、子供の面倒もしっかり見られるであろう。しかし彼女たちは、今では戦争や場所などの永遠に忘れたい過去の一部であった。彼は馬から降りて街に踏み入り、イリアック湾での毎日の小さな噂話に花を咲かせた。
2920年、第23巻The Year 2920, Vol. 23
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 降霜の月10日
フィルギアス(ハイロック)
彼女たちの前に立っている生き物はどんよりとした意識のないような目を瞬きさせ、口の働きを再確認するように開け閉めを繰り返していた。ひと筋のネバネバした唾の塊が牙の間からこぼれ落ち、垂れ下がっていた。トゥララは今までにこのような大きく、2本足で立つは虫類のようなものを見たことがなかった。ミニステラは夢中になって拍手をした。
「我が娘よ…」と、彼女は得意げに言った。「短期間でよくここまで成長したのう。このデイドロスを召喚したときに、何を考えておったのじゃ?」
トゥララは何かしらを考えていたか思い出すのに少々時間がかかった。彼女は単に、現実の壁を超えてオブリビオンの領域に手を伸ばし、精神の力だけでこの忌まわしい生き物をこの世に召喚できたことに驚いていた。
「赤色を考えていたわ」と、トゥララは集中しながら言った。「赤の簡素さとその透明度。そして…望み、呪文を詠唱したの。これが召喚されてきたものよ」
「望むということは、若い魔女にとっては強力な力じゃ」ミニステラが言った。「そして、この瞬間うまく調和しておる。このデイドロスは、単なる霊魂の力だからの。簡単に望めた時と同じように、その望みを捨てられるか?」
トゥララは目を閉じ、退散の祈りを口にした。怪物は混乱しているように瞬きをしながら、日にあせた絵画のように薄くなっていった。ミニステラは歓喜の笑いとともにダークエルフの愛弟子を抱きしめた。
「信じ難いが、魔術結社とともに暮らし始めて1ヶ月と1日、既にここで暮らす大多数の女性たちよりも遥かに進歩しておる。そなたの中には強力な血が流れておる、トゥララ、そなたは恋人に触れるように霊に触れられる。いつの日か、そなたはこの集会を導くであろう…私には見える!」
トゥララは微笑んだ。褒められるのは心地よかった。モーンホールドの公爵は彼女の可愛い顔を、そして、その名誉を汚す前の家族は彼女の礼儀作法を褒めてくれた。キャシールはただの旅仲間だったので、彼の賛辞は何の意味も持たなかった。しかし、ミニステラとともにいると、我が家にいるような気がした。
「まだまだ、この先何年間もあなたがこの魔術結社を導くわ、偉大な姉さん」と、トゥララは言った。
「もちろん、そのつもりじゃよ。だが、霊魂は素晴らしき友であり、真実の語り手ではあるが、「いつ、どのように」に関しては往々にして不明確じゃ。それに関して彼らを責めることはできんのう。「いつ、どのように」は、彼らにとってあまり意味のないことだから」ミニステラはデイドロスの苦い悪臭を消散させるために小屋の窓を開け、秋の風を吹き込ませた。「さて、これから使いでウェイレストへ行って欲しいのじゃ。行きに1週間、帰りに1週間だけじゃ。ドリャサとセレフィナを連れ帰ってきて欲しい。自給自足を実践してはおるが、ここでは育たない薬草があって、莫大な量の貴重品をまったく時をかけずに使ってしまうようじゃ。街の人々がそなたをスケフィンヌトン魔術結社の女性であると認識することも重要じゃ。悪名高きことの不便さよりも、利点のほうが遥かに多いことに気が付くであろう」
トゥララは指示されたとおりにした。彼女と他の姉妹が馬に乗る最中、ミニステラは彼女の子、生後5ヶ月のボズリエルを母親との別れの口づけをさせるために連れてきた。魔女たちは邪悪な公爵を父に持ち、帝国の森の奥深くでアイレイドのエルフたちによってこの世に引き出された、小さなダンマーの子をこよなく愛した。この子守り役たちは、命をかけて彼女の子を守るであろうことをトゥララは知っていた。たくさんの口づけと別れの挨拶の後、3人の若い魔女たちは赤色や黄色やオレンジ色が覆う、輝く森の中へと去って行った。
2920年、第24巻The Year 2920, Vol. 24
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 降霜の月12日
ドワイネン(ハイロック)
水曜日の夜にしては酒場、「愛されないヤマアラシ」はものすごく混んでいた。部屋の中央に掘ってある穴の中では、轟音をあげる炎が常連たちに邪悪そうな輝きを与え、それによって人々の集まりが、アラクトゥリアの異教によって触発された懲罰のつづれ織りのような装いを見せていた。キャシールは従兄弟たちと一緒にいつもの席に着き、エールの大瓶を注文した。
「もう男爵には会いに行った?」パリスは聞いた。
「うん、ウルヴァイアスの王宮で仕事をさせて貰えるかもしれない」誇らしげにキャシールは言った。「でも、これ以上は言えない。国の秘密とかの関係でね、分かるよな。何で今夜はこんなに人が多いんだ?」
「船でたくさんのダークエルフたちが港に到着したらしい。戦地からきたみたいだ。戦争体験者として紹介するために君が来るのを待っていたのさ」
キャシールは赤面したが、落ち着きを取り戻し、聞いてみた。「彼らはここで何をしているんだ?また停戦協定でも成立したのか?」
「よくは分からないんだが…」パリスは言った。「でも、皇帝とヴィベクはまた交渉しているらしい。この人たちはここでの投資を確認したがっていて、湾の周りの状況も十分落ち着いていると判断したんだろう。でも、実際のところは彼らと話してみないと分からないな」
それを言ったパリスは従兄弟の腕をつかみ、突然彼をすごい勢いで部屋の反対側へと引っ張っていった。ダンマーの旅人たちは4つのテーブルを占領して、街の人々と談笑していた。彼らは主に身なりを整えた商人らしい、感じのよい若い男たちであった。彼らは酒のおかげで身振り手振りが必要以上に大げさになっていた。
「失礼します」と、パリスは会話に入りこみながら言った。「私の照れ屋の従兄弟、キャシールも現人神、ヴィベクのために戦争で戦ってきました」
「俺が聞いたことのある唯一のキャシールは…」彼の空いている手を握り、大きく気さくな笑顔を携えたダンマーの1人が酔った口調で言った。「それはヴィベクに歴史上最悪の密偵だと言われたキャシール・ホワイトリーだけだ。俺たちはヤツの下手な諜報のおかげでアルド・マラクで負けたんだ。友よ、あんたのためにもあんたとヤツが間違われないことを祈るぜ」
キャシールは微笑んだままこの無骨者が彼の失敗談を面白おかしく話し、皆から大きな笑いを誘うのを聞いていた。何人かは彼のほうを見たが、地元の人間は皆、物語の愚かな主人公がここに立っていることを伝えなかった。一番突き刺さったのは、ドワイネンに英雄として戻ったと信じていた彼の従兄弟の視線であった。そのうち、男爵も当然この話を耳にするであろう。何度も語られるうちに、彼の愚かさが数倍にも増した形で。
魂の底から、キャシールは現人神ヴィベクを呪った。
2920年 降霜の月21日
帝都(シロディール)
ヘガテのモルワ修道院の司祭の制服である、目が眩むような白さのローブを身にまとったコルダは、今季初の冬の嵐が通りすぎる中、帝都に到着した。雲間から日が差し、麗しい10代のレッドガードの女性が大きな街路に護衛とともに現れ、王宮へと馬を進めた。彼女の姉は背が高く、細身で骨張り、高飛車であったが、コルダは小さく、丸い顔と大きな茶色の目を持った少女であった。地元の人々はその2人を比較するのが素早かった。
「リッジャ様の処刑から1ヶ月も経ってないのにね」お手伝いの女性が窓から外をのぞきながら、ブツブツと近所の人に言った。
「それとさ、修道院から出て1ヶ月さえも経ってないのにね」醜聞に喜びをあらわにしながら女性はうなずいた。「この娘は前途多難な道を進むことになるねえ。彼女の姉は無垢じゃあなかったけど、最後にどうなったかは知ってのとおりだしね」
2920年、第25巻The Year 2920, Vol. 25
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 降霜の月24日
ドワイネン(ハイロック)
キャシールは港に立ち、季節外れの凍雨が水面に落ちるのを見ていた。生まれつき船酔いする自分の性質を彼は残念がった。もうタムリエルの東も西も、彼が行ける場所はどこにもない。ヴィベクから生まれた、彼の密偵としての未熟さの物語は、酒場から酒場へと止めどなく広がっていた。ドワイネンの男爵も彼を仕事から放免した。ダガーフォールでも彼のことを笑っているに違いなく、ドーンスター、リルモス、リンメン、グリーンハートも同じであろう。それに恐らくアカヴィルも、そしてついでに言えばヨクダでも彼は笑いものであろう。もしかしたら、このまま水に飛び込んで沈んでしまったほうがいいのかもしれない。しかし、その考えは長く残らなかった。彼の心を悩ませたのは、失望感ではなく怒りだったからである。それは、果たすことのできない無力な怒りであった。
「失礼します」彼の後ろから声がして、彼を跳びあがらせた。「お邪魔してもうしわけありません。一夜をすごせる、安い酒場を教えていただけないかと思いまして」
それは肩に袋をぶら下げた、若いノルドの男性であった。明らかにたった今どこかの船から降りてきたのであった。ここ何週間かぶりに誰かが彼を、有名なとてつもない間抜け以外の何かとして見ていた。気持ちは晴れなかったが、友好的にならざるを得なかった。
「たった今、スカイリムからきたのかい?」と、キャシールは聞いた。
「いいえ、そこへ行くのです」と、若者は言った。「働きながら家へと向かっているのです。ここの前はセンチネル、その前はストロス・エムカイ、その前はヴァレンウッドのウッドハース、そしてその前はサマーセットのアルテウム。名前はウェレグです」
キャシールは自己紹介をして、ウェレグと握手を交わした。「アルテウムからきたって言ったかい?サイジックなのかい?」
「いいえ、もう違います」若者は肩をすくめた。「除名されました」
「デイドラの召喚に関して何か知っているかい?現人神と呼ぶ人もいるような、とある強力な人に対して呪いをかけたいのだけれど、なかなか上手くいかなくてね。男爵は私と目も合わせてくれないが、男爵夫人は私に同情してくれて、彼らの召喚の間を使うことを許してくれた」キャシールは唾を吐いた。「すべての儀式を行い、生け贄も捧げたが、何も得られなかった」
「それは私の昔の師匠、ソーサ・シルによる影響ですね」苦々しそうにウェレグは言った。「デイドラ公たちは、最低でも戦争が終わるまで素人には召喚されないと合意したのです。サイジックと、一握りの魔女や、妖術師のみがデイドラと交信できます」
「魔女と言ったか?」
2920年、第26巻The Year 2920, Vol. 26
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 降霜の月29日
フィルギアス(ハイロック)
トゥララ、ドリャサ、セレフィナが馬を進めていると、薄い日差しが森を洗う霧の向こうでキラキラと輝いている。地面は薄い霜の膜でぬれていて、荷で重くなっているため舗装されていない丘は滑りやすかった。トゥララは魔術結社へ戻れることに対する興奮を抑えようとしていた。ウェイレストは冒険であったし、街の人々が投じた恐怖と尊敬の眼差しは気に入っていた。しかし、ここ数日は姉妹たちと子供の下へ戻ること以外考えられなかった。
寒風が彼女の髪を前へとなびかせたので、正面の道しか見えなかった。騎手が彼女の真横に近寄ってくるのを、彼が手で触れるほど近寄るまで聞こえなかった。振り向いてキャシールを見たとき、旧友と会えたことに驚きと同等の喜びで叫んだ。彼の顔は青ざめやつれていたが、それは単に旅のせいだと思った。
「何の用事でフィルギアスへ戻ったの?」彼女は微笑んだ。「ドワイネンではあまり優遇されなかったの?」
「十分だったよ」と、キャシールは言った。「スケフィンヌトン魔術結社にお願いがあってね」
「一緒にいきましょう」と、トゥララは言った。「ミニステラのところへ案内するわ」
四人はそのまま乗り続け、魔女たちはキャシールをウェイレストの話で楽しませた。ドリャサやセレフィナにとっても、古きバービンの農場を離れるのはめったにない楽しみであったことは明白である。彼女たちはあそこで、スケフィンヌトンの魔女たちの娘や孫娘として生まれたのである。平凡なハイロックの都市生活は、彼女たちやトゥララにとっても魅惑的であった。キャシールはあまり話さなかったが、微笑みうなずいていたので、それだけでも十分な励ましになったはずである。幸いにも、彼女たちの話はどれも彼の愚かさにまつわる話ではなかった。少なくとも、彼には言わなかった。
見覚えのある丘を越えたとき、ドリャサは酒場で聞いた、質屋に一晩中閉じ込められた盗賊の話をしていた。突然彼女は話をやめた。納屋が見えるはずであるが、見えなかったのである。他の3人の視線も彼女の見つめる霧の先を追い、次の瞬間、全員出せる限りの速さでスケフィンヌトン魔術結社があった場所へと急いだ。
炎はだいぶ前に燃え尽きていた。灰と骨と壊れた武器が残されているだけであった。キャシールは即座にオーク襲撃の形跡を見分けた。
魔女たちは馬から滑り落ち、亡骸へと走り、泣き叫んだ。セレフィナがミニステラのマントの切れ端と分かる、破れた血まみれの布を見つけた。彼女は灰で汚れた顔にその布を押し当て、すすり泣いた。トゥララはボズリエルの名を叫んだが、戻ってくる答えは灰の上を行く風の笛吹音だけであった。
「誰がこんなことを?」涙が頬を伝いながら、彼女は叫んだ。「オブリビオンの炎を呼び起こしてやる!私の子に何をしたのよ?」
「誰の仕業かはわかってる」キャシールは馬から降り、彼女に向かって歩きながら静かに言った。「この武器は前に見たことがある。責任がある悪魔のようなやつらにドワイネンで会ったようだが、あなたを見つけるとは思っても見なかった。これは、モーンホールドの公爵によって雇われた暗殺者の仕業だ」
嘘は簡単に出てきた。臨機応変に。その上、彼女がそれを信じたことがすぐに分かった。公爵が見せた残酷さに対する彼女の憤りは、おさまってはいたが決して消えてはいなかった。彼女の燃え上がるような瞳を見た瞬間、それは彼女がデイドラを召喚し、彼と彼女の復讐をモロウウィンドに加えるであろうことを彼に告げていた。さらによいことに、デイドラたちは聞き入れると彼は確信していた。
そして、彼らは聞き入れた。望む力より強いのは怒りである。間違った方向に向けられた怒りであったとしても。
2920年、第27巻The Year 2920, Vol. 27
2920:第一紀 最後の年
カルロヴァック・タウンウェイ 著
2920年 黄昏の月2日
テル・アルン(モロウウィンド)
「男が一人謁見に来ております」と、衛兵が夜母に声をかけた。「帝国軍の要塞が置かれたギデオン地方ブラック・マーシュから来たコスリンギ族のズーク卿と名乗っています」
夜母は不快な表情を浮かべ、「私が会いたいと思える人物ですか?」
「亡きシロディール帝国の女帝の手紙を預かっているというのです」
「まったく忙しいというのに…」と、夜母は笑みをたたえながらも、すばやく手を打ち鳴らし、「お通しして」と告げた。
ズークは謁見室に通された。唯一露出している顔や手は、金属的に光る肌をのぞかせ、暖炉の炎や外の嵐の夜の稲妻を反射させた。夜母は、ズークの目に映っている自分の穏やかで美しい、恐怖をかきたてるような姿に気付いた。ズークは物言わず、ただ女帝から預かった手紙を手渡した。夜母はグラスにワインを注ぎ、手紙を読み始めた。
夜母は読み終えた手紙を折りたたみながらこう言った。「今年の頭に、モロウウィンドの公爵からも皇帝の暗殺計画を持ちかけられました。今となってはその報酬も海の底に沈んでしまいましたが。これ以上のやっかいごとは御免こうむりたいの。ただでさえ、宮廷に手下をまわすのが大変だったのですから。そもそもお金はちゃんとご用意できて?死者からお金をせびるわけにもいかないですからね」
「用意できております」と、ズークは率直に答えた。「外に待たせてある馬車の中にあります」
「では、それをここへお持ちくだされば、すべてが丸く収まります」と、夜母は笑って答えた。「皇帝は今年の暮れには命を落とすことになるでしょう。お金はアパラディスに渡してから帰っておくれ。それとも、ご一緒にワインでもいかが?」
ズークは夜母の申し出を丁重に断り、謁見室をあとにした。部屋を出た際、ミラモールが闇色のタペストリーから音もなくすっと出てきた。夜母はミラモールにワインを勧め、彼はグラスを受け取った。
「あの男のことはよく知っております」と、ミラモールは慎重に答えた。「だが、亡き女帝に仕えていたとは知らなかった」
「よければあなたの考えを聞かせて頂戴」と、夜母は言った。ミラモールが断らないことを知っていたのである。
「私の優秀ぶりをお見せいたしましょう。皇帝が独りになれば間違いなく、息子と同様に世から消してみせましょう。私は身を隠すこともできます。先ほど、タペストリーの後ろから物音立てずに現れたことをご覧いただけましたかと思います」
夜母は微笑んだ。
「あなたが短剣の使い方を知っているなら、ボドラムで見つけられるでしょう」と、夜母はミラモールにこれからの暗殺の手順を説明したのであった。
2020年 黄昏の月3日
モーンホールド(モロウウィンド)
公爵は窓の外をじっと眺めていた。四日目の早朝。街は赤い霧にすっぽり覆われて、稲妻の閃光が走っていた。通りには吹き荒れる風が巻きおこり、城の旗を強くなびかせ、家々の戸を固く閉じさせた。何か不吉な事が起こりそうな予感であった。彼自身、学識はそれほど高くはなかったが、彼の家臣も同様に、これから何か悪いことが起こりそうな気配を感じていた。
「伝令はいつ届くのだ?」と、公爵は城主に向かってうなるように言った。
「ヴィベク様は皇帝と協定交渉のため、遥か北の方へいらっしゃるのです」と、城主は恐怖におびえながら言った。「アルマレクシア様とソーサ・シル様はネクロムにいらっしゃいます。数日内には連絡をつけられると思われます」
公爵は頷いた。確かに伝令が到着するのも速いだろうが、それよりもオブリビオンの手の方が速いことを知っていたのだった。
3人の盗賊 パート1Three Thieves, Part 1
著者不明
「今の盗賊の問題は」と、レドスは始めた。「技術が足りないことだ。今も昔も盗賊に名誉なんてものがないのは分かっているが、昔は多少の誇りや技術、基本的な創造力はあった。我々のような歴史感覚のある者は絶望してしまうよ」
イマリンは鼻で笑い、荒削りのテーブルにグリーフの入ったフラゴンを乱暴に置いた。「どんな返事を期待している?”衛兵に会ったらどうするか”と聞かれたら、答えは”そいつの背中を刺す”だ。お前は別の選択肢を選ぶのか?子供の遊びで対決しろとでも?」
「野心は大きいが、教養がない」と、レドスは溜息をついた。「親愛なる友よ、我々は船で来たばかりのノルド人の観光客を襲うわけじゃない。靴職人のギルドなんて大したことないと思ってるかもしれないが、今夜、集めた会費があそこに集められてから銀行に送られる。警備はクワマーのケツの穴よりもきつくなるだろう。会った奴全員の背中を刺して金庫まで行くのは無理だ」
「はっきりとどうして欲しいか説明したらどう?」と、ガルシアが静かに尋ねた。大声でもめるのを避けるためだ。テル・アルンのプロット・アンド・プラスター・コーナークラブにいるほとんどの地元民は盗み聞きなどしないだろうが、どんな危険も避けるにこしたことはない。
「普通の盗賊は」と、レドスはグリーフを注ぎながら話に熱が入っていく。「短剣を敵の背中に刺す。これで倒せるだろうが、悲鳴を上げる時間を与え、襲撃者を血まみれにすることがある。これではダメだ。きちんと上手く喉を切れば、衛兵を倒すと同時に黙らせることができ、盗賊は血をほとんど浴びずに済む。それに強盗に入った後、通りを走る際に血塗れの姿を誰かに見られたくはないだろう。そんなことをすれば、テル・アルンでだって疑われる可能性が高い」
「相手が寝てるか休むかして横になっているところなら都合がいい。片手の親指を顎に当てて口を手で覆い、もう片方の手で喉を切って素早く頭を片側に向ければ血を浴びることもない。頭を動かすのが遅いと血が染みつく危険性がある。生きている内に刺すと血が1メートル近くは噴き出るため、不安ならそれを避けるために相手をまず絞め殺せばいい」
「私の良き友人で、名前は言えないがグニシスで盗賊をやっている者がいる。窒息させてから切る彼の技術には信頼を置いている。簡単に言うと、相手の喉を後ろから押さえて、絞めている間に顔を壁に叩きつける。そして相手の意識がなくなったところで、後ろから押さえたまま喉を切る。そうすれば服に血が飛び散る危険はほとんどない」
「もっと取っ組み合いが少なくて済む古くからの技は、相手の口を手で塞いで3回か4回、ヴァイオリンを弾くように喉を切る方法だ。これはほとんど労力を要さず、かなりの量の血が出るが、すべて前方に飛び散るため血を浴びることはない」
「喉を切ろうとする者なら、予備の道具を持っていくくらいの予防線は張るべきだろう。私の知る限りで最高の首切り技術を持つ奴は、丸めた布をナイフの鍔元につけて血が袖口に付かないようにしている。今回のような仕事には実用的ではないが、相手が1人か2人の予定なら、標的の頭にずた袋をかぶせてひもをしっかり締めてから、滅多打ちにするのが1番だ」
イマリンは大笑いした。「そのうち実演を見にいってもいいか?」
「近いうちにな」とレドスは言った。「ガルシアの仕事が終わったらだ」
ガルシアは最近盗んだばかりのギルドの地図を持ち出し、作戦を詳しく説明し始めた。
それまでの数時間はめまぐるしく事が進んでいた。3人が出会い、計画を練って、必要な物を買うか盗み、実行しようとするまで1日とかかっていない。3人の誰もが、自分以外の2人を駆り立てているのは自信なのか愚かな考えなのか分からなかったが、運命は一緒だった。これからギルドを襲おうとしていた。
3人の盗賊 パート2Three Thieves, Part Two
著者不明
ガルシアは最近盗んだばかりのギルドの地図を持ち出し、作戦を詳しく説明し始めた。
それまでの数時間はめまぐるしく事が進んでいた。3人が出会い、計画を練って、必要な物を買うか盗み、実行しようとするまで1日とかかっていない。3人の誰もが、自分以外の2人を駆り立てているのは自信なのか愚かな考えなのか分からなかったが、運命は一緒だった。これからギルドを襲おうとしていた。
日が落ちると、レドスとガルシア、そしてイマリンは街の東にある靴職人のギルドに接近した。ガルシアは石の花のカシューを使い、欄干を通る際に番狼から匂いを隠した。彼女はまた、偵察の先頭を切って歩き、レドスを感心させた。比較的経験が浅い割に、彼女は闇にまぎれて進む方法をわかっていた。
レドスは何度もその専門技術を披露することになった。多様な衛兵がいたため、何年もかけて磨いた音を立てずに暗殺する方法を残らず見せることができたほどだ。
イマリンは独特の順序立ったやり方で金庫を開けた。タンブラーが彼の指の下に落ちると、ボエシアの99人の愛人を語る古くて下品な酒場の歌を小声で歌った。集中力を高め、難しい組み合わせを整理するのに役立つのだと彼は言った。数秒で金庫が開き、金貨が手に入った。
侵入してから1時間後にギルドを出た。警報も鳴らず、金貨は消え、中にある石床の血だまりには遺体が横たわっていた。
「良くやったぞ、素晴らしい。立派なもんだ」とレドスは言いながら、金貨がジャラジャラ音を立てて不自然な膨らみができないよう特別に仕立てられたチュニックの袖に金貨を入れていった。「明日の朝、プロット・アンド・プラスターで落ち合って山分けするぞ」
そして、彼らは別れた。最も見つかりにくい街の下水道を通るルートを知るレドスは、ダクトに滑り込んで消えた。ガルシアはショールを身につけ、顔を汚して年老いた占い師を装い北へ向かった。イマリンは監視の目をかいくぐるために、自分の類まれな感覚を信じて東の公園へ向かった。
さて、これから彼らに最大の教訓を教えてやろう、とレダスはぬかるんだ迷宮のようなトンネル内をバチャバチャと進みながら心の中で呟いた。街の門のところでグアルが待っており、繋いでおいたチョークウィードの低木を簡単な昼食にしていた。
ヴィベクへの道すがら、彼はガルシアとイマリンのことを考えた。もしかしたら既に捕まり、質問を受けたかも知れない。尋問に耐える姿を見られないのが残念だった。どっちが最初に重圧に屈するだろうか?イマリンの方が間違いなく頑丈だが、ガルシアも恐らく何かまだ隠していた。それは単なる知的好奇心だった。2人は彼の名前がレドスで、プロット・アンド・プラスターで落ち合うものと思っている。だから衛兵が遠く離れたヴィベクで獲得した富を祝うセイシスという名前のダンマーを探しにくることはないはずだ。
日が昇り始める中、セイシスはグアルを急かしながら、ガルシアとイマリンが尋問を受けず、悪人として深い眠りにつき、どうやって分け前を使おうか夢見ている姿を想像した。2人とも起きたらプロット・アンド・プラスターへ急ぐだろう。イマリンが笑いながら騒ぎ、ガルシアが必要以上の注意を避けるためにイマリンを静かにさせる様子が目に見えるようだった。グリーフを2杯飲み、大盛りの食事を頼んで待っているかもしれない。だが、時間が過ぎるにつれて楽しい雰囲気も消えていく。裏切られた者なら誰もが見せる反応の連鎖だ。不安、疑念、狼狽、激怒。
セイシスがヴィベク郊外にある家の家畜小屋に着いた時、太陽は完全に昇っていた。彼はグアルを繋いで餌を与えた。他の小屋は空だった。使用人がグニシスの聖リルムズの祝祭から帰ってくるのは午後だろう。彼らは善人で、彼も良く扱っていたが、過去の経験から使用人は口が軽いと分かっていた。もし彼の不在を他の街で起こった盗みと関連付け始めたら、密告に行くか脅迫に来るかは時間の問題だ。結局彼らも人間だ。長い目で見れば、街から出て仕事をする時には、1週間の有給休暇を与えるのが1番だった。
彼は金貨を書斎の金庫に入れて、階段を上がった。予定は詰まっていたが、使用人が戻る前にセイシスは数時間の休憩を取った。テル・アルンの小都で使わざるを得なかった酷い寝床に比べて、彼のベッドは素晴らしいほどに柔らかく温かかった。
セイシスは悪夢でしばらくして起きた。数秒してから目を開けても、まだイマリンがボエシアの99人の愛人を歌う声が近くで聞こえる気がした。彼はベッドに横になったままジッとしていたが、いつもの古い家が軋む音しかしなかった。午後の日差しが寝室に差し込むと、ホコリがキラキラと光った。彼は目を閉じた。
歌がまた聞こえ、セイシスは書斎の金庫が大きく開くのを聞いた。石の花の匂いが鼻に充満して目を開いた。午後の日差しがわずかに麻袋の内側に差し込んだ。
強い女性の手に口を押さえられ親指が顎の下に突き刺さった。彼の喉が切り開かれ頭を横へ押された時、ガルシアのいつもの落ち着いた声が聞こえた。「教えてくれてありがとう、セイシス」
アージダルの転落Ahzidal’s Descent
ハルンド・グレイクローク 著
人が初めてスカイリムの大地を歩いた、今となっては誰も覚えていない時代、サールザルの街に偉大な付呪師が現れた。少年の頃から、彼が天性の魔法と技巧を持つことは家庭教師たちの目にも明らかだった。大人になった時には、彼の技能は教師の誰よりも優れていた。一族の中にいて学ぶべきことはもうないと気づいた彼は、妻と子を残し、達人エルフの下での修行へと旅だった。
1年、2年、3年の時が過ぎた。そしてようやくサールザルに戻った時、そこには廃墟しかなかった。エルフが街を荒らし、生きた者は皆殺されたか、去っていた。灰となり、まだくすぶっている故郷の廃墟に立って、彼は恐ろしい復讐の誓いを立てた。そしてそこから生まれた伝説が、憤激の破壊者アージダルという呼び名を彼に与えたのである。
一人きりでは何もできなかったため、他の誰よりも技能に打ちこみながら、彼は好機を待った。ドゥエマーからは、金属が持つ7つの性質と、それらを調和させる方法を学んだ。アイレイドからは、エルフさえ忘れ始めていた古代のルーンと原初の魔法を学んだ。ファルメル、チャイマー、アルトマーに混じって旅し、それぞれから学べることを学び、その間もずっと、それらの知識を復讐に活かす方法を考えていた。
ついに、イスグラモルと同胞団がアトモーラから新たにやって来たという噂が彼の耳に届いた。3昼夜かけて彼は北に向かい、氷で覆われた海岸に到着した彼らに会った。そこは彼らに立ち向かうエルフが要塞を築いたサールザルの廃墟に近い場所だった。彼はイスグラモルたちの力となり、それまでの労働で生み出したあらゆるものを差し出した。アトモーラの鋼鉄に彼の付呪が染み込んだおかげでエルフは目の前で倒れ、ようやく彼は復讐を遂げた。
しかし彼は満足しなかった。技術そのものが彼の人生となり、知識への渇望が彼を悩ませ続け、さらに深く追求せずにいられなかった。長い時間をかけてようやく彼はエルフの教えをすべて学んだが、まだ満足ではなかった。彼はドラゴンルーンの秘密を追求し、それによって大司祭の地位まで得たが、まだ満足ではなかった。ついにはオブリビオンの世界にまで目を向け、そこで力を得て、正気を失った。
そこで彼が危険を冒し、二度と戻らなかったという者たちもいる。あるいは、仲間のドラゴンプリーストに裏切られて殺されたか、愛するサールザルの地中の廃墟にある隠し場所に追いやられたという者もいる。ソルスセイムのスコールでは、彼がこの島へと逃げて、遺品と共にコルビョルン墓地の地中深くに埋葬されたと言われている。
しかしそれはウィンターホールドの吟遊詩人が語った物語に過ぎない。真実が何であれ、アージダルの伝説は戒めとして伝えられたものである。完ぺきを追求するうち、追求そのものに心を奪われてしまわないように、人は気をつけなければならないということだ。
アイスエルフ:事実か空想か?Ice Elves: Fact or Fiction?
アイスエルフは存在するのか?この奇妙な生物について聞いたことはあったが、つい最近までただの神話だと思いまともに取り合わなかった。しかし今、私はアイスエルフに会ったと確信している。
従兄弟のクヌデクと一緒にアモル砦の南で不毛な鹿狩りをしていたときだった。クヌデクがウサギよりも大きな獲物を仕留めると意気込んでいたのだ。ハチミツ酒を何本か飲み勢いづいたところで、彼は日が暮れるまでには上質のシカを手に戻って来ると言い、弓を振りながらどこかに走って行った。夜になったので、まもなく疲れて帰って来るだろうと思いキャンプを作ることにした。
ハチミツ酒をもう1本飲みきり小さなテントの中に潜り込んだとき、雪が降り始めた。それからほどなくして、奇妙な獣が近くの森の辺りでのたうち回っている音が聞こえた。私はクヌデクだと思い呼び掛けた。すると不気味なうめき声だけが聞こえたので、腕毛が逆立った。
弓を掴み取り、その生物との対決を決意した。テントから飛び出るときに、突風によって雪が舞い上がった。私はテントにもつれて前のめりに倒れ、小さなたき火に手が当たってしまった。驚いて叫び声を上げると、その生物も驚いてキャンプの近くで立ち止まった。
その生物は森に棲むトロールにしてはあまりにも小さかった。奇妙な音を立てたので怒鳴りつけて追い払おうとした。雪が降っていた上に火傷の傷みで涙が出ていたためその姿はよく見えなかった。その生物はさらに意味不明な音を立て続けていた。
人生最大の恐怖の中、死に物狂いで火傷を負っていないほうの手で熱い燃えさしを掴み取り、その生物の頭をめがけて投げつけた。私が熱さのせいでその生物よりもさらに大きな声で叫ぶと、その生物はのたうち回って雪の吹きだまりの中に倒れた。私はなんとか立ち上がり、その生物も必死で立ち上がろうとしていた。その生物は青白い肌で背が丸まっていた。襲ってはこなかった。私は手の痛みのせいで言葉を発することができなかった。
傷みは激しかったが、急いで逃げることにした。アモル砦に向かって走った。幸いにも砦に戻る途中の兵士の一団に遭遇した。彼らが治癒師のところに連れて行ってくれ、手の治療を受けることができた。クヌデクは数日後に姿を現した。迷子になり倒れて腕の骨を折った後、悪党の魔術師に襲われファイアボールを何度も投げつけられたらしい。アイスエルフを見れなかったことを残念がっていた。2人とも回復したら、また探しに行きたいと言っている。
アイスハンマー従士の伝説Legend of Thane Icehammer
遠い過去のその昔、クラグワロウのアイスハンマー従士が地を歩いていた。陽気で元気いっぱいのノルドである彼は人々から愛され、その賢明さと元気の良さのために信頼されていた。このように始まる言い伝えがほとんどそうであるように、良い時代は続かなかった。
ヨルグリム川流域での遠出の狩りから戻った時、アイスハンマー従士にとっての変化が始まった。もはや快活で騒々しくなるどころか、どういうわけか彼は気難しく、短気になった。そして数ヶ月が過ぎ、彼の機嫌はさらに悪く、気分は暗くなっていった。
「夫がこんなに変わってしまったのは、一体何が原因なのかしら?」アイスハンマー夫人は尋ね、カイネスグローブの番人たちに助言と援助を頼った。
番人たちは状況を調査するために若い侍者を派遣した。1日と1晩をアイスハンマー従士と一緒に過ごした彼女は、彼の行動を観察し、彼に質問をして、何が起きたせいで従士がそれほど腹を立てて怒っているのか突き止めようとした。
長時間一緒に過ごした後、ついに侍者は、アイスハンマー従士の脇腹から、上着に渡って黒いシミが広がっていることに気がついた。彼女は彼のシャツをはぎ取った。癒えぬであろう膿んだ傷が脇腹へと曲線を描いていて、そこから赤い槍の先が突き出ていた。「その名をハーシーンと奴は言った」と、従士は泣き叫んだ。「奴は私が獣人間を狩るべきではなかったと言ったが、それが何であるのか、私はどうやって知ればよかったと言うのだ?」
その時、怒りに我を失ったアイスハンマー従士は、カイネの侍者に殴り掛かって殺してしまった。夫の行動にショックを受けたアイスハンマー夫人は、クラグワロウの番兵に従士を取り抑えるよう命じた。しかし逃亡したため、彼らは山付近の下にある古代墓地まで彼を追った。彼を追って墓地に入る準備をした番兵は、夫人に呼び戻された。「だめだわ」と、悲しそうに彼女は言った。「怪物を救うためにこれ以上の命を危険にはさらせない。墓地を封印して」
こうして、デイドラ公に傷つけられたたもののまだ生きているアイスハンマー従士は、葬られた。
アイスハンマー従士は、終わりのない怒りとハーシーンの槍の魔法に煽られ、今でも墓地の部屋を歩き回っているらしい。
アヌラーメ姫の話The Tale of Princess Anurraame
アヌラーメ姫がバルコニーに出ると、冷たい風が彼女の足元、スカートに当たった。彼女は視線を上げて、塔を見つめた。何も見えないこと…召使の少女の言葉が嘘だったことを願いながら。最初は暗闇の他には何も見えず、何も動いている気配はなかった。彼女は安心して息をつき、風を防ごうと腕を組んだまま、立ち去ろうとしていた。
だがその時、雲が割れ、満月の灯りが塔を照らした。月に照らされて輪郭が浮かび上がった。彼女の愛する人と彼女の姉妹が、情熱的に抱き合っている姿がはっきりと見えた。
彼女は動けず、呼吸さえできなかった。彼女の心が曇り、一粒の涙が彼女の頬に落ちた。
アバマス占領The Taking of Abamath
ウッドオークは、自分達の腕力や霊魂の力、そして自分達の神の力に誇りを持っている。戦いに負けることはあっても、敗北することはないと信じているのだ。
しかしその誇りと信念はアバマスで打ち砕かれた。アイレイド軍がウッドオークの街に到着したとき、戦士達は「マラキャスの血」で戦化粧を施し、呪術師の魔法に頼って自分達を侵攻軍から守ろうとした。彼らは力強く立ち上がり、持ちこたえた。
そして彼らは敗れた。
そして死んだ。
逃げた者もいた。末裔の者を苦しめている恥だ。
アイレイドはアバマスを占領し、自分達の領土とした。ウッドオークはその敗北を記憶に刻み、スローガンとした。ウッドオークの多く、アバマス占領に関わっていた者の末裔達は特に、新たな残忍さを示すことで恥を洗い流そうと、未だに顔へ赤い化粧を施している。
アリクル(第二紀)The Alik’r (Second Era)
エンリク・ミルネス 著
センチネルの小さな酒場でウェルタンに会わなかったら、アリクル砂漠には決して行かなかったかもしれない。ウェルタンはレッドガードの詩人で、詩を読んだことがあるが、翻訳したものだけだ。ウェルタンはタムリエル語でなく、古いレッドガードの言語で書いている。一度、その理由を尋ねたことがある。
「タムリエル語では発酵し、絹のような、圧搾したサワーミルクの素晴らしく金持ちの子供は…チーズだ」とウェルタンはすすだらけの顔に困難を乗り越えた時のような大きな笑みを浮かべて言った。「対応する古レッドガード語はムルオ。教えてほしい。もし両方の言語に堪能な詩人だったら、どちらの言葉を使う?」
私は街の子供だ。騒音と腐敗、嵐の一夜と活気、文化と退廃の話をさせてもらった。ウェルタンは私の生まれた街の話を、畏敬の念を持って聞いてくれた。白い大理石で飾られた帝都では、皇帝のお膝元であり、きれいに清められた清潔な通りのために、すべての一般市民は自分たちが重要だと確信していた。帝都の大通りにいる乞食は宮廷に住んでいるようなものだと言われていた。スパイスの効いたエールを飲みながら、リバーホールドのにぎやかな市場、暗く陰気なモーンホールド、リルモスの土作りの村、ヘルストロームの素晴らしくて危険な小道路地、古きソリチュードの荘厳な大通りの話をウェルタンに楽しんでもらった。こうしたすべてに、彼は驚き、質問と意見をくれた。
「詩を読むと、あなたの故郷、アリクル砂漠を知っているかのように感じる。行ったことがないのに」と伝えた。
「そうか。でも詩から知ることはない。どんな詩でもアリクルを表現できない。最高の案内書よりもずっと、訪問したいという気持ちになるかもしれない。だが、タムリエルを知りたくて、真の市民になりたいなら、砂漠に行って感じないといけない」
アリクル砂漠のために婚約を解消し、貯金し(最大の挑戦だ)、都市生活から離れるのに1年かかった。ウェルタンの詩の本を何冊か、旅の案内書として購入した。
「火からたちのぼる聖なる炎、名もなき偉大な男女の亡霊、炎の中で盛衰する大昔に滅びた街、ディオスコリの啓示の歌、破裂する壁と不滅の岩、癒やして破壊する燃えさかる砂」
友の「不朽の塵の上に」のこの最初の6行は、アリクルの砂漠の第一印象となった。ほとんど公正に評価していないが。私の貧弱な文章力では、アリクルの過酷さ、偉大さ、はかなさ、そして永久不変さを書き表すのは難しい。
諸国がこの地に定めたどのような公国も国境もすべて、砂漠の砂の移動により消え去る。私はアンチフィロスやバーガマにいたかどうかを話すことはできず、話すことのできる住民はほとんどいない。我々はアリクルの一部なのだ。この考えは、砂漠の民の哲学に近い。
砂漠での最初の朝、ウェルタンが書いていた聖なる炎を見た。タムリエルの深い神秘からやって来たように見える、広大に広がる赤い霧だ。正午に日の光が差すよりずっと前に、霧は消えた。それから、ウェルタンの街を見た。アリクルの遺跡は、限りない風の一吹きで砂から現われ、次の一吹きで覆われる。この砂漠では何一つとして残り続けるものはないが、何一つとして永遠に死ぬものはない。
日中、テントに隠れ、この荒涼とした永遠の地を選んだ、レッドガードの最も重要な気質について考えた。彼らは生まれながらの戦士だ。集団としてはこれ以上ない。苦悩することがなければ、彼らにとって価値あるものにはならない。誰も彼らとは砂漠のために戦わないが、アリクルは偉大な強大な敵だ。戦いは続く。恨みのない憎悪のない戦いであり、言葉が常に示すとおりの意味での聖戦だ。
夜は、かなりの静寂の中、この地そのものについて考えることができた。しかし、この静寂はうわべだけのものだった。石自体は、太陽からのものでも、月のジョーンとジョーデのものでもない光と熱で焼けていた。石の力はタムリエル自体の心臓の鼓動によるものだ。
アリクルで2年過ごした。
これを書いている今、センチネルに戻っている。エボンハート・パクトとアルドメリ・ドミニオンの戦いのさなかだ。詩人、作家、そして芸術家たちは、ここの人々が戦いに持ち込んだ欲と高慢さに落胆している。最悪の状態、悲劇だ。古レッドガード語でいえば、アジシア、下落だ。
しかし、悲嘆に暮れている場合ではない。アリクルの栄光の中で過ごした年に、人が感覚を失っている間生き続ける永遠の石を見た。区切られることもなく、形もなく、変化もなく、変わりやすい土地に、内なる目を見つけた。ひらめきと希望は、人とは違うとはいえ、砂漠の石のように永遠のものである。
アリクルのアサシンThe Assassin of Alik’r
著者不明
シャドウスケールは命じられた場所に行き、必要なことをする。自ら裁きを下せない者たちに成り代わって裁きを下すのだ。モットーは速やかな死。なぜなら、いたずらに苦しみを与えることは、概して眉をひそめられるからだ。
私は新しい任務を希望した。この前アリクルで片づけたようなのとは違うやつだ。あの地方のさびれた海岸の塩の味が、いまだに舌に残っている。風に吹かれた砂が目に入る痛みを、いまだに感じることができる。
そしてあの悲鳴が、いまだに耳から離れない。
ところで、生まれながらのアサシンは、どうやってそれと知るのだろう?私の場合は予言だった。そして、それを知ったことで力がみなぎってくるのを感じた。これから学び経験することのすべてが、私の宿命を成就させるだろう、と。
一線を踏み越えた者は罰せられなければならない。この世には守るべき法というものがある。裏切りは許されない。金も稼がなければならない。
しかし、アリクルでの仕事は勝手が違った。私は数日かけて罪人たちを監視し、彼らが砂漠と呼ぶ、追跡不可能とされる荒地で彼らの後を追った。やがて、チャンスは海に臨む砂丘の頂で訪れた。
「ここまで来れば大丈夫よ」そう言う女の声は希望にあふれていた。
「大丈夫なんてことはもうないだろう」男は苦々しげに答えた。
刃物の鞘を払い、前に進み出ようとしたその刹那、頭上で風向きが変わる音が聞こえ、私は暗がりに戻った。
ハーピーの群れだ!悪臭を発する翼を大きく広げて旋回する怪鳥の群れに、2人の男女はまだ気づいていない。願いを叶えられる見込みなど端からない奴隷商人とその恋人の頭上で、ハーピーたちは明るい星空にシルエットを浮かび上がらせていた。
ハーピーの群れが鉤爪を剥いて襲いかかってくると、男女は悲鳴をあげた。ダンマーの柔らかな肉を、剃刀のように鋭い鉤爪が切り裂いてゆく。ハーピーは犠牲者をもてあそび、彼らの悲鳴をハーピーの言語らしき不明瞭な発声で真似た。
ダンマーたちが息絶えるのを確認してから、私はその場をあとにした。本来彼らが迎えるべき最期とは違ったが、それがどうしたというのだ?死は誰にでも訪れる。望まれもせず、待ちわびられるわけでもないそれは、時として頭上から訪れる。
アルゴニアンの侍女—口述による伝承The Argonian Maid—An Oral Tradition
発明家テレンジャー 著
つい最近、「好色なアルゴニアンの侍女」という舞台劇を見た。みだらで、愉快で、風刺に満ちていた。これまでこのような形で演じられていなかったことに驚いている。
調べたところ、「好色なアルゴニアンの侍女」は、旅の吟遊詩人が語った物語を元に作られたことが分かった。題名や内容はそれぞれの吟遊詩人で少しずつ違うが、最後はどれも同じだ。素朴な女性が野心的な既婚男性の魅力に屈するのだ。
南部では時々この物語は、「好色なボスメリ」や「シュガーのための2つの月」として語られていた。また北部と北西部の酒場では、「ショーンヘルムの好色な口」や「アリクルの砂の槍」、「処女の拘束」という題名も耳にした。
舞台劇では、観客の前で原作に登場する各人物に命が吹き込まれる。演技が優れていなければ、単調で陳腐なものになるだろう。それに舞台となると、伝説のカジート、テイル・シンガーのような、吟遊詩人の言葉による巧みな表現の効果は損なわれてしまう。この猫の吟遊詩人は、少女を服従させようとする男の様々な駆け引きを表現していた。少女はその駆け引きにより、次に何が待っているのか考えるようになり、脈拍が上がり、呼吸を乱すようになる。
「アルゴニアンの侍女」の大半がテイル・シンガーの歌から拝借したものであることは間違いない(作者として明記されているわけではないが、私にはすぐに分かった)。この物語の中では、少女が槍とパンとココナッツミルクを使って男を助ける。
幸運なことに、現在上演されている「好色なアルゴニアンの侍女」の出演者は実に素晴らしい。古いこの物語を新たな物語に発展させているのだ。狩人の槍への言及では、多くの不機嫌な人々も笑わずにはいられないはずだ。それとチーズの輪は…いや、この種のものは今までに見たことがなかったが、実に見事だった!
この舞台は炉端の楽しみとして慎ましく始まったが、今後数世紀にわたり、馬鹿げた楽しみのひとつとして演じ続けられていくことになるだろう。
アルマレクシアとマッドクラブAlmalexia and the Mudcrab
昔から伝わるダンマーの物語
昔あるところに、とても苦しんでいるマッドクラブがいました。足が不自由で、ゴホゴホと咳をしていました。殻がゆがんでいるせいで、体が痛みました。彼はいつも疲れていて、自分はきっとすぐに死ぬだろう、と皆に言っていました。ある日、彼は谷をぶらつきながら、話を聞いてくれる相手なら誰にでも、文句を言っていました。
ショークが殻の一部から留め具を作って、マッドクラブに渡しました。「マッドクラブ、これで君の足を支えてみるといいよ」と勧めました。
「いや、いや、だめだ」とマッドクラブは言いました。「前にも試したけどうまくいかなかった」
「マッドクラブ」今度はアリットが言いました。「君の殻をちょっとかじらせてくれよ。少しひびを入れたら、殻がゆるんで楽になるよ」
マッドクラブは答えました。「だまそうとしてもだめだ、アリット!ただおやつが欲しいだけなんだろう!」
この日、アルマレクシアは国を歩き回っていて、彼らの会話を耳にして谷に行きました。その時の彼女はどこにでもいるようなグアルに姿を変えていました。
「マッドクラブ」と彼女は言いました。「この水薬を飲んでみて。あなたの咳のために私が作ったの」
「グアル、君は治癒師じゃない。できの悪い治療薬を飲むくらいなら、痛みを我慢したほうがましさ」とマッドクラブは答えました。
そこでアルマレクシアはその生き物たちに、真実の姿を明かしました。彼らは驚いて息をのみました。「マッドクラブ」彼女は言いました。「この生き物たちは皆、あなたを助けようとしました。けれどあなたは断りました。あなたは文句を言うことが好きなのです。あなたが癒やされることはないでしょう」
アルマレクシアが教えてくれたのは、望まない者を助けることはできないということです。
イーテラーの年代記 第2巻Chronicles of Ehtelar, Vol. 2
イーテラーは暗闇の中で目を覚ました。少量の流れる砂が、彼女の額に落ちた。頭上にある遺跡での短い戦いの記憶が、彼女の意識に浮かんできた。
彼女と一緒に砂漠に入ったレッドガードの商人ラハドは、上の遺跡で気づかれないまま死んだ。彼の剣は、彼を殺した生き物の頭蓋骨の中で眠っている。
彼女は鉄と頭蓋骨がぶつかる不愉快な音を覚えていた。ぞっとするようなこすれる振動が、帰還する彼女の腕の中に残っていた。そして地面が割れ、世界を飲み込んだ。彼女はその下にある空間に飲み込まれた。
どれほど深く、どれだけ長く落ちたのだろうか?最深の闇が彼女を飲み込むまで、砂、そして星が彼女と一緒に落ちていったが、どう着地したのかは記憶になかった。
何も見えないまま、何かないかと周囲を手探りで探した。腕は自由に動いたが、足は砂の中で動かなかった。彼女は何とか掘り進もうとした。
その時、鉄のような血の香りが周囲に満ちた。暖かく不愉快な湿気が足に感じられた。それは固まった血の中の砂にしか思えなかった。
呪いの言葉を吐きながら、彼女はベルトを外し、ふくらはぎにある穴のすぐ上に冷たい皮を巻きつけた。暗闇の中、手探りでチュニックから布地を引きはがして、傷にあてがった。
これがもてば、間に合わせの品で血が止まるはずだが、感染を抑える薬は持っていなかった。急いでキャラバンへ戻る方法を見つけなくてはならなかった。
底知れない闇に包まれてまだ何も見えない彼女は、もう片方の足を砂から出した。荷物の中に、ラハドからもらったトークンがあるのが感じられた。
「ゴミの中での夜は、サタカルの胃よりも深い」彼ならそう言うだろう。「自分を見失ったら、長身のパパに祈れ。きっと導いてくれる」
彼女の指が小さなコインに近づいた。隠した場所から取り出して、彼女は目を閉じて「ラプトガ」と唱えた。突然の光にまぶたが赤く光り、彼女は目を開いて眼前に広がる洞窟の様子を観察した。
周囲には、落下して破壊された重い石が散らばっていた。さらに遠くには、たくさんの柱が木のように闇の中に伸びていて、黒く長い影を落としていた。
彼女は、上を見て息を呑んだ。ラミアの明るい目と口が、暗闇から彼女を見つめている。だが身動きがとれない。ラハドの剣は頭蓋骨の中にある。目をそらすまで、鼓動50回分の時間がかかった。
驚きから落ち着きを取り戻しながら、砂の上に散らばった長く、かぎの形をした投げ槍を探し続けた。一つ手に取った彼女は、荷物をつかんで孤独の砂から這い出した。
ブーツが石に当たり、彼女は大きな柱の一つに向けて槍を投げた。体を固定させることに成功し、彼女は立ち上がった。
負傷した足の具合を確認した。致命的ではないと確認すると、彼女は荷物を集め、埃を払って、闇の中へと向かった。
深い静寂の中、広大な無が彼女の周囲を包んでいた。鳴り続く石の音だけが彼女の道を示していた。
イル・アムハキムの航海 第3巻The Voyages of Il-Am-Hakim, Vol. 3
逆風の悪霊をものともしない勇敢なイル・アムハキムは、船を無人島へと向かわせた。船員たちは2週間以上も前に物資を使い果たし、日射病で疲れ切って横たわっていた。右隣で、誰かが住んでいる気配がないか切望して海岸を探す船長に、イル・アムハキムは目をやった。
「何も見えません」と、安堵と失望の様子で彼女は知らせた。
「では鐘を打て。まだ立てる者たちを起こすのだ」。身体が不自由になることや、乗組員が不在になることは、航海が終わることを意味した。彼は貨物を持って戻ってくるかもしれないし、戻ってすらこないかもしれなかった。
全員すぐに何もない甲板を離れ、開かれた島の海岸へと逃れた。木々には果実が実っていて、人を酔わせる糖分で酔った男たちは、死とよく似た昏睡状態に陥った。
イル・アムハキムは船の見張りをしていたため、濃厚なネクターに慰めを見いだしはしなかった。まさにその空気が、期待で震えた。
「お休みになったほうがいいでしょう」。彼の見張り望遠鏡の上に手がかかり、それを取り上げた。彼はうなずき、浜辺の簡易ベッドについた。しかし目を閉じた直後、彼は聞き覚えのある、波をかき分けるオールの音を聞いた。
「攻撃だ!」と、彼は鞘から剣を抜きながら叫んだ。皆の目が彼に向き、真昼の日差しが新しい1日を知らせていた。砂が大量の水のように、彼の顎髭から流れ出た。
「起こさないのが最善だと思ったのです」船長は顔を背け、ニヤニヤ笑う自分の顔を見せないようにした。それでも、船を漕いで食料を運んでいる労働者たちは、騒々しいどよめきをまた開始するのだった。イル・アムハキムには、彼らがそうしたことで恨むことはできなかった。
イル・アムハキムの航海 第7巻The Voyages of Il-Am-Hakim, Vol. 7
イル・アムハキムは、片手に新たな契約を、もう片方の手に望遠鏡を持ち、船の前方に立っていた。海の水しぶきがかかっても微笑んでいた。
「位置につきましょうか?」 彼はうなずき、その見晴らしのいい場所から降りた。今回、宝は逃げはしない。
一瞬弱気になったが、彼はその囚人と対峙するため船室に入り込んだ。彼女は見た目こそ優雅な花そのものだが、その口から出る言葉は毒々しいものだと彼はわかっていた。
彼は咳払いをした。「あの太鼓の音が聞こえますか?あなたの兄弟を見つけましたよ。彼には悪事の報いを受けさせる」
手で顔を覆っていたそのダークエルフは顔を上げた。「そんなことを私が気にするとでも?愚か者め」彼女は塩がついたその顔をイル・アムハキムから背けた。「私の兄弟は、裏切りの罪で死んだ私を見ることになる。彼の死は私の自由を意味する」
船長はその言葉に顔をしかめた。これが他の土地や自分自身の土地の王家のあり方なのだろうかと疑問に思わずにはいられなかった。次の港に着いた時、後援者に軽蔑されるだろうか?
彼は踵を返し、船室から出て扉を閉めた。しかしその直前、ダークエルフの手の中に光る尖った金属を見た。
エオリムの物語Eorim’s Tale
ストームフィスト旅団のすべての団員の中でも、私と兄は、いつでも強健王子フィルジョア、現フィルジョア・オークセインに最も近い存在だった。王子に初めて会ったのは、兄のギャドフだった。ギャドフはホワイトラン要塞に至る道で山賊に攻撃され、相手の人数は7倍もいた。どこまでもストームフィストである兄は健闘したが、ハンマーを一気に全員に向けて振りかざすわけにはいかなかった。山賊のうち2人を倒したが、いつのまにか負傷したために、血がふんだんに流れていた。
まさにその時、強健王子フィルジョアが現れた。残った山賊の真ん中に飛び込んだ彼は、力強い連続攻撃で相手を追い散らした。彼はギャドフの側で戦い、広い背中を兄の背中に合わせた。2人は山賊を倒し、フィルジョアは兄を運んで帰った。下の兄であるブラセックが、急いで助けにいった。フィルジョアの正体を知った2人は、強くカリスマ性のある王子のために、その命と敬意を誓ったのだった。
その当時私はまだ少女だったが、私は彼を見た瞬間に、その東からの見知らぬ人に恋をしたことを知った。フィルジョアは私たちの家に滞在し、ギャドフの傷が回復する間手伝ってくれた。彼らはよく話していたが、ストームフィスト旅団の案が初めて生まれたのは、まさにその時だった。フィルジョアがイメージしたのは、世界を旅して不正を正す、気の合った仲間のグループだった。彼は本当に理想家だったのだ!そして彼は、マブジャールン女王のことを、愛情と称賛をもって語った。
ストームフィスト・クランの中で最も強く勇敢な者から選ばれた12人のグループがようやく集まった時、彼らを立派に見送るための宴会が開かれた。宴は3日間にもおよび、4日目の朝に、ストームフィスト旅団は出発した。その特別なグループに参加することを決めた私は、ハンマーを取り上げて彼らの後を追った。ゴブリンの奇襲部隊に対抗する彼らを助けるべく、その初の戦闘真っ只中に私は飛び込んだ。兄が強健王子フィルジョアを必要としていた時に、彼がそうしたように。
それはすばらしい戦闘で、壮大な勝利となった!旅団にとって、後に収める多くの勝利の第一弾。しかし、兄たちは私に激怒した。彼らと一緒に旅に出るには若すぎると言ったのだ。でも、フィルジョアはただ笑ってくれた。「彼女はよく戦った」と彼は言った。「それに、彼女は私が大好きなんだ。我々の団員になるための資格が他にあるか?それに、13は12よりずっといい数字じゃないか」
アカヴィリの戦いで、私はフィルジョアのそばにずっといた。兄弟のスキーヴァー、ジョルンに王座を奪われた時も、そこにいて彼を慰めた。そして追放された彼について行って、彼が無から軍隊を築き、奥地にいたオークを集結させるのを見ていた。今私たちは戻ってきた。今回は、愛するフィルジョアが自分のものであるべき王座を、ついに勝ち取る瞬間を側で見ることになるだろう。それが例え、行動を起こすにふさわしい時が来るまで、洞窟の中で隠れることを意味しても。
カラスとレイヴン:3つの寓話Crow and Raven: Three Short Fables
カラスとレイヴンが、魚を追って水に飛び込むウを見ていました。「俺も水に飛び込めたらいいのにな」とカラスが言いました。「俺だって魚が食べたいよ」「ええ?」とレイヴンが言いました。「ウはあなたがやれないようなことをやれるって言うの?バカげてるわ。あなたはウよりずっと優秀な鳥じゃない」「それもそうだな!」と言うと、カラスは水に思いきり飛び込み、一瞬の後、激しくもがきながら水面に上がってきました。近くにはレイヴンが立っていました。「レイヴン!」カラスはあえぎながら言いました。「なんであんなこと言うんだよ?溺れるところだったぞ!」レイヴンは肩をすくめて言いました。「鳥が食べたくて」
カラスとレイヴンが、浅い水たまりで水浴びをするナゲキバトを見ていました。カラスは「俺も水浴びするか」と言って舞い降りると、水たまりの中で勢いよく水を跳ね上げ、レイヴンの隣に舞い戻ってきました。「前よりいいだろ!」とカラスが言いました。「何で?」とレイヴンが言いました。「羽もくちばしも目も、前と同じく真っ黒じゃない」「そのとおり」とカラスは言いました。「でも、俺が水たまりに降りたときに、ナゲキバトがびっくりして巣に戻っただろ。これで巣がどこにあるか分かったじゃないか」「お昼は卵ね!」とレイヴンは言いました。
カラスとレイヴンは、道端の宿屋の傍にある木にとまっていました。下で酒に酔った牛追いがいびきを立てて眠りこけていました。カラスはぴんと頭を起こして言いました。「あの眠ってる奴はシャツにキラキラ光るピンを付けてるな」「賞の印よ」とレイヴンが言いました。「エールを飲んであれをもらったの。あいつのマグに残ったエールを飲み干せば、あなたもキラキラするピンをもらえるわよ」「キラキラするピン!」カラスはそう言って、テーブルの上に舞い降り、残ったエールを飲み干すと、倒れて起き上がれなくなりました。レイヴンは舞い降りると牛追いのシャツからピンをむしり取りました。「キラキラするピン!」彼女はそう言って、飛んで行ってしまいました。
クンザ・リと悪魔Khunzar-ri and the Demons
月の歌い手による英雄クンザ・リの物語
時ができるよりも前、十六王国が十六の自惚れに過ぎなかった頃、偉大なる英雄クンザ・リはエルスウェアの国境で悪魔と出会った。
名をカールグロンティードといった悪魔は、力強い声でこう言った。「兄弟とともにこの地と財宝を奪ってやる。空の月さえもな!」
「それはどうかな、忌まわしき悪魔よ」とクンザ・リは言った。「エルスウェアとそこにある全てのものは、空の月さえも私が守る」
悪魔は笑った。「我らは止められないぞ、猫もどきめ!お前には軟らかい肉と毛しかないが、我々には鱗と歯と爪がある!」
クンザ・リは少し考えた。「そうかもしれないな、巨大な悪魔よ。確かに私の並外れた力でさえ、お前にはかなわない」。そして彼は心の中で言った。「だからこそ、私はクラ・ジュン、すなわち英雄たちの軍団を集める。力を集めれば、お前を止める方法が見つかるだろう、忌まわしき悪魔よ!」
そうして、悪魔たちがエルスウェアに襲いかかり、上空で月を追いかけ回している間、クンザ・リは彼のクラ・ジュンを形成するための冒険に向かった。彼は当時の最も偉大な勇者たちを集め、これまで一度もやったことがないことをするよう説得した。すなわち、協力することを。クンザ・リは繊細なる剣を持つアルトマー、完璧なるヌラリオンを味方につけた。悪魔狩人フリンシルドに、遥か北にある彼女の城を去るよう説得した。甘い言葉をネ・クイナル族の女王にして月の司祭である辛辣なアネクイナに投げ、仲間になることを承知するまで褒め称えた。最後に、クンザ・リは後に裏切り者となる男に力を貸してほしいと頼んだ。国中を探しても、彼以上の戦士はいなかったから。
クラ・ジュンは集結し、クンザ・リと仲間たちはカールグロンティードと悪魔の兄弟たちを倒しに向かった。四十一日と四十一夜の間、偉大にして凄惨な戦いがエルスウェア中で荒れ狂った。クラ・ジュンはそのうちいくつかの戦いに勝利し、いくつかには敗北したが、悪魔たちを殺す方法も、追い払う方法も見つけられなかった。ついに提案を出したのは、後に裏切り者となる男だった。「悪魔たちは月を飲み込もうとしている。そうさせてやったらどうだ?つまり、我々が降伏し、奴らの計画に従ったと思わせてやればいいのだ」
「素晴らしい考えだ!」とクンザ・リは同意した。「だが月を飲み込ませる代わりに、月に奴らの生命を奪い取らせてしまえばいい!」
月の司祭のアネクイナは賛同してうなずいた。「それならこの者がやるわ。この者はジョーンとジョーデと話して、悪魔たちを飲み込むよう頼める」
そうして、クンザ・リは自分の持てる限りの機転と魅力を使って、クラ・ジュンは今や悪魔たちに協力するつもりなのだと信じさせようとした。クンザ・リは有名な月の聖堂で会おうと悪魔たちに伝えて待ち、その間にアネクイナは月と交信した。「悪魔たちを完全に飲み込むのは、ジョーンとジョーデの本性にそぐわない」とアネクイナは言った。「でもジョーデは悪魔たちの生命力を吸い取って弱らせてくれる。そうすれば、私たちで奴らを封じ込められるわ」
「丁度いい場所がある」と完璧なるヌラリオンが高らかに声を上げた。「忘れ去られ、放棄されて久しい古き力の場所だ。あそこに悪魔たちを閉じ込めればいい」
クンザ・リはクラ・ジュンの知恵を誇りに思ったが、弱った悪魔たちを罠へと誘い込む方法が必要だった。悪魔たちは自らの意思でその場所に入らなければならない。たとえ弱っていても、悪魔たちはクラ・ジュンが相手をするにはあまりにも危険だった。そこでアネクイナとフリンシルドは考えた末、ある計画を思いついた。彼らがクンザ・リに伝えると、彼はにっこりとほほ笑んで尻尾を震わせた。「かぐわしいぞ!」と彼は言った。
そうして悪魔たちは月の聖堂に到着し、アネクイナは女王ではなく月の司祭として、ニルンとジョーデを一筋の月光の形にして繋げた。貪欲で、月の力に飢えた悪魔たちは我先にと月光の中へ足を踏み入れたが、すぐに騙されたと気が付いた。悪魔たちは生命力をジョーデに抜き取られ、苦悶の咆哮を上げた。カールグロンティードは残った力の最後の一片まで振り絞って抵抗し、兄弟たちを集合させた。悪魔たちは危険な月光の筋から脱出し、荒野へと逃げていった。
そこでアネクイナは悪魔の力が込められた月光の一部を壺の中に入れ、フリンシルドに渡した。フリンシルドとクラ・ジュンは壺を古き力の場所へと持っていき、その間にクンザ・リは最も得意なことをしに行った。悪魔たちを説得しておびき寄せ、自分の意志で罠にかかるように仕向けることを。彼はそうした。裏切り者がその名を得る前に。そのこともまた聞かせよう。
これが物語の言葉であり、真実の言葉になる。
クンザ・リと悪魔:パート1Khunzar-ri and the Demon: Part One
月の歌い手、長話のアザルゴによって記録された古いカジートの伝説
時ができるよりも前、十六王国が十六部族に過ぎなかった頃、偉大な英雄クンザ・リは数々の冒険に繰り出した。クンザ・リは401個のムーンシュガーパイを食べて巨人ドロルを倒した後、悪魔と出会った。
「悪魔は言った。兄弟とともにこの地と財宝を奪ってやる。空の月さえもな!」。クンザ・リは異議を唱えたが悪魔は笑った。「我らは止められないぞ、猫もどきめ!」
クンザ・リは言った。「私だけでは無理だ、忌まわしき悪魔よ。私はクラ・ジュン、すなわち英雄たちの軍団を集める。まずはアイレイドの虫たちの埋められた根と心を通わせる。アルトマーの完璧なるヌラリオンからだ」
これが物語の言葉であり、真実の言葉になる。
クンザ・リと悪魔:パート2Khunzar-ri and the Demon: Part Two
月の歌い手ミズビナによって記録された古いカジートの伝説
時ができるよりも前、十六王国が若く子猫のように遊んでいた頃、偉大な英雄クンザ・リは勇者の一団を結集させ、悪魔やその兄弟と戦った。彼らは空から月を盗むため、エルスウェアにやってきたのだ。
既にヌラリオンを味方にしていたクンザ・リは、次に仲間にする勇者に焦点を当てた。「月の力はもらったぞ、猫もどき」と悪魔は挑発した。「二人で大勢を止められるものか」
クンザ・リは言った。「うるさい悪魔よ、二人は三人になるのだ。この者が黒檀の植物が忍び寄るアイレイドの巣から、悪魔狩人フリンシルドを救出すればな」
これが物語の言葉であり、真実の言葉になる。
クンザ・リと悪魔:パート3Khunzar-ri and the Demon: Part Three
月の歌い手サタッリによって記録された古いカジートの伝説
時ができるよりも前、十六王国が荒野を駆け巡っていた頃、英雄クンザ・リは勇者たちを集め、恐るべき悪魔やその軍勢に立ち向かった。完璧なるヌラリオンと悪魔狩人フリンシルドを従え、クンザ・リは第三の仲間を探した。
悪魔は言った。「おお、小さな猫よ、楽しませてくれるな!3匹のイタチが、どうやって我々に対抗するのかな?」クンザ・リは笑った。「我々は小さいが、しつこいぞ!それに一筋縄ではいかない。すぐに分かる」
そしてクンザ・リはクラ・ジュンに向き直った。「我々にはもう1人必要だ。カジート女王にして、その名も高き辛辣なアネクイナ。大月の光を浴びながら、深く考えを巡らせる者だ」
これが物語の言葉であり、真実の言葉になる。
ケメル・ゼーの遺跡 パート1The Ruins of Kemel-Ze, Part 1
ロナルド・ノードセン 著
帝国協会で浴びた拍手喝采がまだ耳に残っているうちから、私はもうモロウウィンドへ戻る決心をしていた。帝都での贅沢な暮らしが名残惜しくないと言ったら嘘になるが、ラレド・マカイから持ち帰った驚きなど、モロウウィンドにあるドワーフの遺跡の上っ面をなぞっただけのものでしかない。あそこにはまだ目を見張るような宝が埋もれていて、掘り起こされるのを待っているのだ。出発しないわけにはいかなかった。それに、哀れなバナーマンの示唆に富む前例もあった。二十年前、ブラック・マーシュで一度きりの発掘を行い、今になってもそのおこぼれで食いつないでいるような男になるつもりなどない。私はそう誓ったのだ。
女帝の手紙を持っていたので、今回ばかりは帝国政府も全面的に協力してくれそうだった。もう、迷信深い地元民に襲われる心配もない。が、いったい次はどこを探せばいいのだろう?ケメル・ゼーの遺跡は妥当な選択だった。ラレド・マカイのように遺跡にたどりつくまでが苦しいということもない。「崖の街」としても知られるケメル・ゼーはヴァーデンフェル断層の本土側にあって、断崖絶壁の海岸線のたもとに広がっている。ヴァーデンフェルの東海岸からなら海路で訪れるのが一般的だが、近くの村から陸路をとっても、余計な苦労を背負い込むことなくたどりつける。
探検チームがセイダ・ニーンに集結すると、こうした文明の遅れた土地での作業につきものの面倒をうんざりするほど抱えたまま、私たちは遺跡にほど近いマログの村へと出発した。発掘の作業員はその村で雇えばいいだろう。私の通訳を担当するツエン・パナイはダークエルフらしからぬ陽気な男で、地元の軍司令官から推薦されてセイダ・ニーンで雇ったのだった。パナイいわく、ケメル・ゼーを熟知しているマログの村人たちは、祖先の代からあの遺跡を荒らしているらしい。ついでだが、テン・ペニー(その場でつけた彼のあだ名で、本人も気に入っていた)は雇っても後悔させない男で、モロウウィンドの原野への似たような探検を考えている同僚がいたら、ためらうことなく彼を推薦しようと思う。
マログ村で最初の困難にぶつかった。控えめで気品のある村の長は快く協力してくれそうだったが、村の司祭(この地で信仰されている、モロウウィンドの王宮に住んでいるというトリビュナルなる存在を崇拝するくだらない宗教の代表者)が遺跡の発掘に対して激しく抗議してきたのだ。この司祭は、この発掘が「宗教的禁忌」にあたると訴えかけることで村人を懐柔しにかかったが、私が女帝の手紙を彼の鼻先で振ってみせ、セイダ・ニーンに詰めている軍司令官の友人のことを口に出すと、たちまち静かになった。この猿芝居が、村人が画策した賃上げ交渉の基本戦術であることは疑いようがない。とにもかくにも、司祭は何やらつぶやきながら歩き去った。よそ者の悪魔に呪いをかけているのだろう。ほどなくして、なんとしても作業員の職につきたいという顔をした村人が列を成した。
契約条件や支給品などの委細を煮つめるのは助手に任せておいて、私とアルム師は遺跡まで馬を駆った。陸路から遺跡へ向かうには、断崖の壁面に沿って上からうねうねと伸びている小道を通らなければならず、一歩間違えば、眼下のいかつい岩場で渦巻いている海へと転がり落ちていくことになる。街への入口はもともと北東にあったに違いない。はるか昔、レッドマウンテンの噴火によってこの度肝を抜かれる火口が生まれたときに、それは海面下に沈んでしまっていたのだが。足場のぐらつく小道を首尾よく突破すると、大部屋のような場所へやってきた。片側は吹き抜けになっていて大空が広がり、もう片側は闇の中へ消えていた。歩を進めていくと、鉄くずの山をブーツで踏みつけた。古代遺跡で見かける陶片のように、ドワーフの遺跡ではお馴染みのものだ。略奪者たちはきっとこの場所で、遺跡の奥から見つけてきたドワーフ製の機械から金になる外殻だけをはぎ取り、無駄な部品を置き去りにしたのだろう。そのほうが、機械を分解しないまま崖のてっぺんまで運ぶよりはずっと楽だろう。何人もの戦士が知らず知らずのうちにドワーフ製の機械の一部を背負いながらタムリエルを歩きまわっている姿が浮かんできて、私はほくそ笑んだ。もちろん、それがたいていの「ドワーフの鎧」の正体、つまり、古代の機械人間の強化外骨格にすぎないのだ。完全な姿の機械であったらどのくらいの値がつくのだろうと思い、ふと我に返った。大広間の床を埋めつくす鉄くずの量から判断するに、この遺跡がドワーフ製の機械装置の宝庫であることは確実だろう、いや、確実だったろう。何世紀もかけて、略奪者はここを荒らしまくってきた。外殻だけでも、鎧として売れば、まとまった金になるのだ。たいていのドワーフの鎧は雑多な部品の寄せ集めのため、かさばって扱いにくいというのが通説だ。が、完全な一体の機械から作られる鎧一式なら、金に換えられる以上の価値があるだろう。すべての部品が滑らかに重なり合い、そのいかつさがほとんど気にならなくなるのだから。もちろん、どんなに価値があろうとも、見つけた鎧を壊すつもりなど毛頭ない。科学的研究のために協会に持ち帰るつもりだった。今度の講義で鎧をお披露目したときの同僚たちの驚嘆ぶりを思い描いて、私はまた微笑んだ。
ケメル・ゼーの遺跡 パート2The Ruins of Kemel-Ze, Part 2
ロナルド・ノードセン 著
私は足元の鉄くずの山から、捨てられた歯車を拾った。まだ新品のように輝いていた。ドワーフ製の合金は時が経っても腐食しない。目の前に横たわる空洞の迷宮にはいったいどんな秘密が眠ったままになっているのだろうか。略奪者の企みを寄せつけないまま、気の遠くなるような時間を経て再び光のもとにさらされ、輝く時を待っている。私のことを待っている。私が見つけるためだけにとどまっている。急き立てるようにアルム師を手で呼んでから、私は暗がりに歩を進めた。
アルム師、テン・ペニー、そして私は数日間かけて遺跡を探検した。助手が崖のてっぺんに野営地を設営し、村から物資や装備品を運んできてくれた。私は実りの多そうな場所が見つかればいつでも発掘に取りかかるつもりでいた。遺跡内の前人未踏の場所へと続く、略奪者の触れていない封鎖された通路や廊下が見つかれば。
そういった場所はすでにふたつほど見つけていたが、すぐに、何本かの曲がりくねった通路が封鎖地点を迂回して背後にある部屋へと通じていることがわかった。こうした外縁地域にも略奪者の手は伸びており、何世紀にもわたる発掘でほとんどのアーティファクトは奪われてはいたものの、目に映るものすべてに考古学者の興味はそそられた。はるか昔の地殻変動で蝶番がふっ飛んでしまった巨大な青銅の扉の背後に、壮麗な彫刻が壁に施された大部屋を発見した。疲れ果てていたテン・ペニーでさえも目を見張っていた。彼はモロウウィンドのドワーフの遺跡なら完全踏破したと豪語していたのだが。壁の彫刻は何らかの古代の儀式を描いたものらしかった。古典的なあごひげを生やしたドワーフの長老が長い列を成して横の壁を行進していた。どのドワーフも、正面の壁に彫刻された巨大な神らしきシルエットにお辞儀をしているように見えた。そのシルエットは山の火口から一歩踏み出し、煙か水蒸気の雲に飛び込もうとしていた。アルム師の話では、これまでにドワーフの宗教儀式が描かれたことはなく、とても刺激的な発見だと述べた。私は作業班に命じて、彫刻された石板を壁からはぎ取らせようとしたが、表面を傷つけることさえできなかった。詳しく調べてみると、この大部屋は手触りも見た目も石に模した金属性物質で表面加工されているため、手持ちのツールではまったく歯が立たなかったのだ。アルム師の魔法で壁を爆破してもらおうかと考えたが、彫刻そのものを破壊してしまうリスクを負うことはできず、諦めた。これらの彫刻を帝都に持ち帰りたいのはやまやまだったが、石ずりをとるだけで我慢した。協会の同僚が興味を示せば、石板を安全に取り外せるだけの知識が備わった、名人級の錬金術師のような専門家を紹介してもらえるだろう。
私は変わった部屋をもう一つ、蛇行する長い階段のてっぺんに見つけた。天井から落っこちた瓦礫をかき分けてなんとか進んだ。階段を上がりきると丸天井の部屋になっていて、大がかりな壊れた装置が中央に据えてあった。丸天井の表面のところどころに星座が描かれているのが今もまだ見てとれた。この部屋は天文台のようなもので、中央の装置はドワーフ式天体望遠鏡の残骸だろうということで、アルム師と私の意見は一致した。装置を取り外して狭い階段で運び下ろすには、完全に分解する必要があった(だからこそこの装置は略奪者の目に留まらずに済んだのだろう)ため、ひとまずは持ち帰るのを諦めることにした。が、この天文台の存在が、この部屋がかつて地上に出ていたことを示唆していた。構造を細かく調べてみると、この部屋は掘り穿たれたわけではなく、実際の建物であることがわかった。もう一つの出口は完全に塞がれていた。崖のてっぺんから最初の部屋まで、さらにこの天文台までの深さを慎重に測定してみたところ、私たちは現在の地表から250フィート以上も地下にいることがわかった。もはや忘れられているが、レッドマウンテンの噴火はそこまで凄まじいものであったのだ。
この発見によって、私たちの意識はさらなる地下へと向けられた。古代の地表のおおよその位置がわかった今、それよりも上にあるふさがれた通路は無視してもよくなった。私の興味をとらえたのは、模様の彫られた円柱が両端に並んだ幅広の通路だった。はなはだしい落石のせいで行き止まりになっていたが、略奪者の掘ったトンネルが瓦礫の山の途中まで続いていた。発掘チームとアルム師の魔法が揃えば、先駆者が諦めた地点から作業を引き継ぐことができそうだった。ダークエルフのチームを呼んで通路を片づけさせ、ようやくケメル・ゼーの本格的な発掘にとりかかれる。私は安堵した。じきにこのブーツで、世界が始まってから一度も踏みつけられたことのない埃を巻き上げることになるのだろう。
こうした期待感に興奮しすぎたのか、私は採掘人をいささか追い立てすぎてしまったようだ。テン・ペニーの報告によると、彼らは労働時間の長さに文句をつけはじめ、こんな仕事はやってられないと口にする者までいるらしい。ダークエルフに気合を入れ直させるには鞭で脅すのが一番だというこを経験上学んでいたので、私は彼らのリーダーを鞭打って、通路が確保されるまで残りの採掘人たちを働かせた。セイダ・ニーンから数名の帝国兵を同道させたのは正解だった。採掘人たちは最初こそ渋い顔をしていたが、トンネルが貫通したさいには一日分のボーナスを与えると約束すると、意気揚々と作業に取りかかった。文明生活に慣れてしまっている読者には野蛮なやり方に聞こえるかもしれないが、こういう人種を作業に従事させるにはこうするより他はないのだ。
ケメル・ゼーの遺跡 パート3The Ruins of Kemel-Ze, Part 3
ロナルド・ノードセン 著
落石の規模は思ったよりもひどかった。結局、通路を確保するまでにほぼ二週間を要した。採掘人のつるはしが最後の穴を開けて反対側の空洞へと抜けたときには、私も彼らに混じって大喜びし、終わりよければすべてよしという意味で地元の酒をまわし飲みした(ひどい味だったが)。採掘人が向こうの部屋に進めるよう穴を広げるのを見ながら、私ははやる気持ちを抑えられなかった。この通路は古代都市の新たな階層へ続いていて、そこには消息を絶ったドワーフの残したアーティファクトが埋まっているのだろうか。それともただの袋小路で、どこにも続いていない横道にすぎないのだろうか。私は興奮に打ち震えながら穴をくぐり抜け、その先の暗闇でしばらくしゃがんでいた。足元で砂利が擦れる音がして、あたりに鳴り響いた。大きな部屋にいるらしかった。それもかなり大きな部屋だ。私はゆっくりと立ち上がり、ランタンの覆いを取り払った。灯りが部屋を満たし、呆気に取られながら部屋を見渡した。それは想像を遥かに超える驚愕すべき光景だった。
ランタンの洩らす光が落石地点の向こうの部屋を満たしていき、私はまたもや驚きの眼差しをぐるりと投げかけた。ドワーフ製の合金の放つほのかな輝きで満ちていた。古代都市の未知の領域に足を踏み入れたのだ!興奮のあまり心臓が早鐘を打っていた。私はあたりを見渡した。部屋はあきれるほど巨大で、天井はランタンの光が届かない闇まで突き抜けていた。部屋の奥は暗くてよく見えないが、思わせぶりな光のまたたきが、まだ見ぬ宝物の存在をほのめかしていた。両側の壁に沿って機械人間が立ち並んでいて、荒らされた様子はなかったが、奇妙な点がひとつだけあった。儀式的な意味でもあるように、その頭部が取り外されて足元に置かれていたのだ。考えられることはただひとつ。私は偉大なドワーフの貴族の墓を発見したのだ。ひょっとすると、ドワーフの王のだ!この種の墓所は何度か発見されていて、もっとも有名なのはランサム率いるハンマーフェルの発掘で出土したものだろう。が、完ぺきな状態の墓は未発見だった。そう、今までは。
が、これが本当に王族の墓所だとしたら、その主はどこにいるのだろう?私はそろそろと前進した。時代を超えてそうしてきたように、頭のない人形の列が静かに立ちすくんでいる。取り外された頭部の瞳で見つめられているような気になった。ドワーフの呪いに関する突拍子もない話ならさんざん聞かされていたが、私はそのたびに迷信だとして笑い飛ばしていた。が、今こうして、この都市を作った謎の建築家が吸ったのと同じ空気を吸っていると、そして彼らに災いをもたらした天変地異が起きてからひっそりと眠りつづけていた都市に立っていると、恐怖心がわいてきた。何らかの力が漂っている。私の存在に立腹している邪悪な力が。私はしばらく立ち止まって耳をすませた。ひっそりと静まり返っていた。
いや…かすれるような音が聞こえてきた。呼吸するように一定の間隔で。私はパニックに襲われそうになるのを懸命にこらえた。武器もない。塞がれた通路の向こうを探検したいと気が急くあまり、危険が待っているなどはつゆほども思わなかった。脂汗をたらしながら、気配を感じようと暗がりに視線を這わせた。部屋は暖かい。ふと気づいた。これまでのどの部屋よりもかなり暖かく感じる。興奮が舞い戻ってきた。いまだに機能している蒸気パイプ網につながっている区画を見つけたのだろうか?遺跡のいたるところで見かけた配管が壁沿いに走っていた。私は配管に近づいて触れてみた。ほとんどさわれないほど熱かった。古代の配管のあちこちが腐食して、か細い蒸気が噴き出しているのがわかった。私が聞いた音はこれだったのだ。自らの早計さを笑った。
さて、私はさっそうと奥まで進んだ。ついさっきまでは気圧されそうな迫力があった機械戦士たちに笑顔で敬礼をしながら。光が数世紀ぶんの闇を追い払っていき、台座にそびえるドワーフ王の巨大な彫像が露わになっていくにつれて、私は勝利の笑みを浮かべた。ドワーフ王はその鉄の手に錫杖をにぎっていた。これまでの苦労が報われたぞ!私は台座をゆっくりとひと回りし、古代ドワーフの職人芸にため息をもらした。黄金の王は高さが20フィートほどで、ドーム型のクーポラの下に立っていた。先端が反り返った長いあごひげを威厳たっぷりにたくわえていた。ぎらつく鉄の視線にずっと追われているような気がしたが、私の迷信深さはもう消えていた。私は慈しむように古代ドワーフ王を眺めた。わが王、既にそんなふうに思いはじめていた。台座に乗っかって彫刻された鎧を間近で観察しようとした。と、彫像の眼が開き、篭手をつけた拳を振りあげて殴りかかってきた!
黄金の腕が振り下ろされ、私は身を翻してかわした。直前まで立っていた場所から火花が飛び散った。蒸気を吹き、歯車をきしませながら、彫像はぎこちない動きでクーポラの天蓋から歩み出ると、ものすごい勢いで私のほうへ迫ってきた。慌てて後ずさりをする私の姿をその眼が追っていた。またもや拳が振り下ろされると、私は円柱の陰にさっと隠れた。うろたえるあまりランタンを落としてしまい、光の池から闇の中へとすべり込んだ。あわよくば、顔のない像の間をすり抜けて安全な通路まで逃げられるようにと。怪物はどこにいったんだ?20フィートもある黄金の彫像を見失うなんてありえないと思うだろうが、王の姿はどこにもなかった。弱々しいランタンの火がわずかに部屋を照らしていた。暗がりのどこに王がいてもおかしくなかった。私は這うように進んだ。何の前触れもなく、目の前に並んだつやのないドワーフ戦士が飛び上がるや、怪物のような守護神が目の前にそびえ立っていた。逃げ道をふさがれた!執念深い機械が矢継ぎ早にパンチを繰り出しながら追ってきて、私は後方へかわしながら逃げた。やがて、部屋の片隅に追いつめられた。逃げ場所も絶たれてしまった。壁を背にして立っていた。私は敵をにらみつけて覚悟を決めた。巨大な腕から最後の一撃が振り下ろされた。
ケメル・ゼーの遺跡 パート4The Ruins of Kemel-Ze, Part 4
いや…かすれるような音が聞こえてきた。呼吸するように一定の間隔で。私はパニックに襲われそうになるのを懸命にこらえた。武器もない。塞がれた通路の向こうを探検したいと気が急くあまり、危険が待っているなどはつゆほども思わなかった。脂汗をたらしながら、気配を感じようと暗がりに視線を這わせた。部屋は暖かい。ふと気づいた。これまでのどの部屋よりもかなり暖かく感じる。興奮が舞い戻ってきた。いまだに機能している蒸気パイプ網につながっている区画を見つけたのだろうか?遺跡のいたるところで見かけた配管が壁沿いに走っていた。私は配管に近づいて触れてみた。ほとんどさわれないほど熱かった。古代の配管のあちこちが腐食して、か細い蒸気が噴き出しているのがわかった。私が聞いた音はこれだったのだ。自らの早計さを笑った。
さて、私はさっそうと奥まで進んだ。ついさっきまでは気圧されそうな迫力があった機械戦士たちに笑顔で敬礼をしながら。光が数世紀ぶんの闇を追い払っていき、台座にそびえるドワーフ王の巨大な彫像が露わになっていくにつれて、私は勝利の笑みを浮かべた。ドワーフ王はその鉄の手に錫杖をにぎっていた。これまでの苦労が報われたぞ!私は台座をゆっくりとひと回りし、古代ドワーフの職人芸にため息をもらした。黄金の王は高さが20フィートほどで、ドーム型のクーポラの下に立っていた。先端が反り返った長いあごひげを威厳たっぷりにたくわえていた。ぎらつく鉄の視線にずっと追われているような気がしたが、私の迷信深さはもう消えていた。私は慈しむように古代ドワーフ王を眺めた。わが王、既にそんなふうに思いはじめていた。台座に乗っかって彫刻された鎧を間近で観察しようとした。と、彫像の眼が開き、篭手をつけた拳を振りあげて殴りかかってきた!
黄金の腕が振り下ろされ、私は身を翻してかわした。直前まで立っていた場所から火花が飛び散った。蒸気を吹き、歯車をきしませながら、彫像はぎこちない動きでクーポラの天蓋から歩み出ると、ものすごい勢いで私のほうへ迫ってきた。慌てて後ずさりをする私の姿をその眼が追っていた。またもや拳が振り下ろされると、私は円柱の陰にさっと隠れた。うろたえるあまりランタンを落としてしまい、光の池から闇の中へとすべり込んだ。あわよくば、顔のない像の間をすり抜けて安全な通路まで逃げられるようにと。怪物はどこにいったんだ?20フィートもある黄金の彫像を見失うなんてありえないと思うだろうが、王の姿はどこにもなかった。弱々しいランタンの火がわずかに部屋を照らしていた。暗がりのどこに王がいてもおかしくなかった。私は這うように進んだ。何の前触れもなく、目の前に並んだつやのないドワーフ戦士が飛び上がるや、怪物のような守護神が目の前にそびえ立っていた。逃げ道をふさがれた!執念深い機械が矢継ぎ早にパンチを繰り出しながら追ってきて、私は後方へかわしながら逃げた。やがて、部屋の片隅に追いつめられた。逃げ場所も絶たれてしまった。壁を背にして立っていた。私は敵をにらみつけて覚悟を決めた。巨大な腕から最後の一撃が振り下ろされた。
そのとき、広間に閃光が殺到してきた。紫のエネルギー弾がドワーフの怪物の鋼鉄の殻を引き裂いた。怪物の動きが止まった。新たな敵の姿を認めようとして半分振り向いたところだった。アルム師が駆けつけてくれた!私が歓喜の声をあげかけた時、巨像がこちらへ振り向いた。アルム師の放った稲妻の魔法にもびくともせず、最初の侵入者を叩きつぶそうと決心していた。私は叫んだ。「蒸気だ、蒸気を使え!」巨像は拳を振り上げて私を地面にめり込ませようとした。しゅっという音とともに冷気が吹き抜け、私は顔を上げた。怪物が氷の殻に覆われていた。今まさに私に仕留めようとする姿で。アルム師はわかってくれたのだ。私はほっとして壁にもたれた。
氷がひび割れた。巨大な黄金の王が目前にそびえていた。氷の殻がはがれ落ちると、勝ち誇ったような顔で私のほうを向いた。このドワーフの怪物を止める手立てはないのだろうか?と、彫像の眼から光が消え、腕をだらりと下げた。氷の魔法が奏功し、蒸気機関が冷やされたのだ。
アルム師と採掘人がやってきて私を取り囲み、奇跡の生還を祝福した。私はぼんやりとしていた。帝都に帰還したらどうなるだろうか。きっと最大級の賛辞を浴びることだろう。越えることのできない発見をしてしまったのだ。次の道を模索する時なのかもしれない。伝説の「アルゴニアの瞳」を探し当てたら…またもや大騒ぎになるぞ!私はほくそ笑んだ。この瞬間の栄光を満喫しながらも、次の冒険に思いを馳せていた。
サマーセットからの脱出Exodus from Summerset
勇敢に偉大なことを成し遂げた者
預言者としてのヴェロスは、社会の中心の腐敗と霊的な破綻に対して盲目だった者達によって軽蔑された。ヴェロスは、真実に無関心で全体の利益などはさらに気にもしない者達によって追放され、見捨てられた。他者に貧困や無知、奴隷状態を強いて、自尊心と地位の保全だけを追い求める者達によって追放されたのだ。ヴェロスは高貴な生まれだったが、勇敢にもアルドメリ社会の堕落した鎖を断ち切った。
秘術師としてのヴェロスは、野心や強欲、堕落の上に成り立っていた社会の改善に希望を持てず魂が疲れ果てていた者、息も絶え絶えになっていた者達に呼び掛けた。伝統を守り、公正さを称え、正当な報いを受ける社会を願っていた者達にとって、ヴェロスの声は騒音の中に鳴り響く黄金の音色だった。
巡礼者としてのヴェロスは、新天地と明るい未来を求め、信者と共に海を越えて、慣れ親しんだ土地を離れた。
サミリルの本、第1節Sumiril’s Book, Passage 1
これはある少年の物語。土地の物語。少年と土地がどのようになったかの物語である。
少年の名前はオスティオン。土地を形作る力があった。どうしたいか指示をささやくと、土地は進んでその通りになった。しかし少年は孤独だった。
サミリルの本、第2節Sumiril’s Book, Passage 2
間もなく、力ある者たち数人が少年のことと、どのように土地を形作るかを知るようになった。力ある者たちは、少年の力が天賦の才だと理解しなかった。その中の力だけに目を向けていた。少年に勝ちたいと思った。
そこで、少年を試すことにした。
サミリルの本、第3節Sumiril’s Book, Passage 3
力ある者たちはオスティオンをヴァレンウッドに行かせた。ヴァレンウッドを形作り、そこに大きな街を建てろと。手伝わせるために建築家たちを送った。しかし、ヴァレンウッドはオスティオンが育った地とは違っていた。ヴァレンウッドは荒々しく怒っており、少年が動いてほしいと頼んでも、「いやだ」と言った。
サミリルの本、第4節Sumiril’s Book, Passage 4
オスティオンとヴァレンウッドは戦った。オスティオンは土地に何度も動くよう命じたが、ヴァレンウッドは何度も拒否した。この争いの中、彼らは他のことをすべて忘れてしまった。オスティオンは一緒に送られた建築家たちのことを忘れ、ヴァレンウッドは中に住む人々のことを忘れた。
サミリルの本、第5節Sumiril’s Book, Passage 5
少年と土地はこの争いを気に入るようになった。どちらも孤独だったのが、そうではなくなったからである。しかしそんな中、建築家たちは怪我をして殺された。かつては少年に優しかったサミリルさえも。
突然、オスティオンは自分が何者か、何のためにここに送られたのか思い出した。サミリルの遺体を見つけ、サミリルを死から蘇らせるのを手伝ってほしいと土地に頼んだ。
サミリルの本、第6節Sumiril’s Book, Passage 6
一度だけ、ヴァレンウッドは願いを聞いた。そして、オスティオンとヴァレンウッドは一つになった。共に、オスティオンと私はさまよえる王になった。サミリルは我々の最初の創造物であり、死から蘇らせたホロウの者だ。
これは、我々の存在について真実を語るものである。
ジール城の恐怖 パート1The Horror of Castle Xyr, Part 1
バロス=クル 著
一幕
登場人物
クラヴィデス:帝国軍の衛兵隊長 シロディール人
アナーラ:ダンマーの侍女
ユリス:帝国軍の衛兵副隊長 アルゴニアン
ゾラッサ:若きアルゴニアン魔術師
第一幕
深夜。洗練された家具やつづれ織りで十分に飾られている、スキャス・アヌド城の玄関大広間で芝居は幕を開ける。松明だけが唯一の明かりをもたらしている。広間の中心には、城への正面入口である大きな鉄の扉が立っている。上の踊り場へと続く階段は扉の横にある。舞台左手には、今は閉じられている蔵書庫への扉がある。舞台右手には、もうすこしで部屋の天井に届く、20フィートもの巨大な鎧の1式が立っている。誰も見えないが、女性の歌声が蔵書庫の扉から伝わってくる。
正面扉を叩く大きな音。歌をやめる女性。蔵書庫への扉が開き、何の変哲もない侍女、アナーラが部屋から出てきて正面扉へと急ぐ。帝国軍の制服をまとった見栄えの良いクラヴィデスが目の前に立つ。
アナーラ:こんばんは。
クラヴィデス:こんばんは。ご主人はいるかね?
アナーラ:いいえ、不在です。いるのは私だけです。私のご主人様であるセデゥーラ・ケナ・テルヴァンニ・ホルダルフ・ジール様は避寒地にいます。私で何かのお役にたてますか?
クラヴィデス:かもしれない。入ってもいいかね?
アナーラ:どうぞ、お入りください。フリンでもお持ちしましょうか?
クラヴィデスは広間に入り、あたりを見回す。
クラヴィデス:いや、結構。名前は?
アナーラ:アナーラです。
クラヴィデス:アナーラ、ご主人はいつスキャス・アヌドを発った?
アナーラ:2週間以上前です。なので、私しか城にはいないのです。閣下にお仕えする他の召使や奴隷たちはみんなご主人様に同行しています。何かあったのですか?
クラヴィデス:うむ、あったのだ。サル・カリファという名のアッシュランダーを知っているかね?
アナーラ:いいえ。知りません。
クラヴィデス:では、これからも知ることはないな。彼は死んだのだよ。数時間前、アッシュランドで凍傷によって死にかけているところを発見されたのだ。彼は狂乱していて何を言っているのかほとんど理解できなかったが、最後の言葉は「城」と「ジール」だった。
アナーラ:アッシュランドの夏に、凍傷によって死んだのですか?妙な事が起こるものですね。ご主人様がその人を知っていた可能性はありますが、彼はアッシュランダーでご主人様はテルヴァンニ家です。失礼な言いかたですが、お友達ではなかったと思います。
クラヴィデス:あれがご主人の蔵書庫?中を見てもいいかね?
アナーラ:どうぞ、どこへでもご自由に。何も隠すものはありません。私たちは帝都の忠臣です。
クラヴィデス:テルヴァンニは皆、そうであると聞いている。
(劇作家からの覚え書き:この台詞は皮肉抜きで読まれるべきである。観客の笑いを信じて―地元の政治情勢に関係なく、失敗はない)
クラヴィデスは蔵書庫に入り、本を見越す。
クラヴィデス:蔵書庫はほこりを払う必要があるな。
アナーラ:はい。ちょうどあなた様がいらっしゃった時に行なっていたのです。
クラヴィデス:それには感謝する。もし終わっていたら、つい最近持ち去られたかなり大きな本があった場所の、ほこりの付いていないところに気が付かなかったであろう。あなたのご主人は、どうやらウィザードらしいな。
アナーラ:いいえ。というか、彼は研究熱心ですが、もし呪文を唱えることがウィザードを意味するなら、彼はまったく唱えません。彼はケナで、大学なども出ています。あの、今になって考えると、昨日、大学から他のケナがやってきて、何冊か本を借りていきました。ご主人様の友人なので、問題ないかと思っておりました。
クラヴィデス:そのケナだが、名前はワーヴィムか?
アナーラ:だったかも知れません。覚えていません。
クラヴィデス:大学に、我々が昨夜拘束したケナ・ワーヴィムという名の疑わしい死霊術師がいる。彼が大学で何をしていたかは分からないが、違法行為であったことは間違いない。本を借りたのはそのケナか?足が萎れて不自由な、小さい男?
アナーラ:いいえ、その人は昨日のケナとは違います。彼は大きくて、しっかりと歩いていたのを見ました。
クラヴィデス:家の他の場所も見させてもらうぞ。
クラヴィデスは階段を登り、次の台詞を踊り場、および上の部屋から言う。アナーラは下の階の整頓を続け、床を磨くために背もたれの高い長椅子を鎧の前へと移動する。
アナーラ:何を探しているのか聞いてもいいですか?お手伝いできるかもしれません。
クラヴィデス:これが城のすべての部屋かね?秘密の通路はないのかね?
アナーラ(笑いながら):なぜ、セデゥーラ・ケナ・テルヴァンニ・ホルダルフ・ジール様が秘密の通路を必要とするのでしょう?
クラヴィデス(鎧を見ながら):あなたのご主人は大柄なのだな。
アナーラ(笑いながら):からかうのはやめてくださいな。あの巨大な鎧はただの飾りです。ご主人様が10年前にあの巨人を倒し、その記念品として取っておかれているのです。
クラヴィデス:そうだ、それは初めてここに赴任してきたときに聞いた覚えがある。巨人を殺したのがジールという名字のものであったのは知っていたが、名がホルダルフだったとは思わなかった。記憶とは薄れていくのだな。巨人の名は何であったかな?
アナーラ:残念ながら覚えておりません。
クラヴィデス:私は覚えている。トルファングだ。「トルファングの盾から出た」
アナーラ:何のことでしょう。トルファングの盾?
クラヴィデスは階段を駆け下り、鎧を調べる。
クラヴィデス:トルファングの盾から出られたようなことをサル・カリファが言っていた。気が狂い、取りとめのない話をしていたと思っていたのだが。
アナーラ:ですがその通り、それは盾など持っていません。
ジール城の恐怖 パート2The Horror of Castle Xyr, Part 2
クラヴィデスが背もたれの高い長椅子を動かすと、鎧の基部から据え付けられた大きな盾が見えた。
クラヴィデス:持っているね。あなたがあの長椅子で覆ったのだ。
アナーラ:わざとやったのではありません!掃除をしていただけです!毎日あの鎧を見ていますが、ああ、神よ、誓ってその盾に気付いたことはありません!
クラヴィデス:もうよいアナーラ、信じるよ。
クラヴィデスが盾を押すと、それは後退して下への地下道をあらわにした。
クラヴィデス:セデゥーラ・ケナ・テルヴァンニ・ホルダルフ・ジールには秘密の通路が必要なようだな。松明を持ってきてくれるか?
アナーラ:ああ、恐ろしい、そんなのは見たことがありません!
アナーラは壁から松明を外し、クラヴィデスに手渡す。クラヴィデスは地下道へと入って行く。
クラヴィデス:ここで待つように。
アナーラはクラヴィデスが地下道へと消えて行くのを見守る。彼女は動揺しているように見え、ついには正面扉へと走っていく。扉を開けると、入口には帝国軍の衛兵副隊長であるアルゴニアンのユリスが立っていた。彼女は叫ぶ。
ユリス:驚かせて申し訳ありません。
アナーラ:今は駄目!どこかへ行って!
ユリス:お嬢さん、隊長はそれをあまり快くは思わないと思います。
アナーラ:あなたは…隊長殿と一緒ですか?ああ、よかった。
クラヴィデスは顔面蒼白で地下通路から出てくる。話すまでしばらく時間がかかる。
ユリス:隊長?下には何が?
クラヴィデス(アナーラへ向かって):あなたのご主人が死霊術師であることを知っていたか?地下室が死体で溢れていることも?
アナーラは気を失う。ユリスが彼女を長椅子まで運び、横たえる。
ユリス:隊長、見せてください。
クラヴィデス:慌てなくてもすぐに見られるさ。死体を運び出すには駐屯地にいる全兵士が必要だ。ユリス、私はたくさんの戦闘を見てきたが、こんなのは見たことがない。2体として同じものがない。カジート、スロード、ダンマー、シロディール、ブレトン、ノルドたちが、生きたまま焼かれ、毒を飲まされ、感電させられ、溶かされ、バラバラにされ、内蔵を出され、切り刻まれた上で縫い合わされているんだよ。
ユリス:それが、脱出したアッシュランダーの身に起きたというのですか?
クラヴィデス:分からない。なぜこのようなことをするのだ、ユリス?
扉を叩く音。クラヴィデスが出る。若いアルゴニアン女性のゾラッサが小包と手紙を携えて立っている。
ゾラッサ:おはようございます、あなたはジール卿ではありませんね?
クラヴィデス:違う。それは何だ。
ゾラッサ:閣下に配達するはずの小包と手紙です。閣下はすぐ戻りますか?
クラヴィデス:いや、戻らないだろう。差出人は誰だ?
ゾラッサ:大学にいる私の講師、ケマ・ワーヴィムです。彼は足が不自由なので、これらを閣下に届けるよう言われました。正直に言いますと、本当は昨夜届けるはずだったのですが、忙しくて。
ユリス:おはよう、姉妹よ。我々が小包を閣下に渡しましょう。
ゾラッサ:ごきげんよう、兄弟よ。りりしきアルゴニアンがスキャス・アヌドにいるとは聞いていました。残念ながら、小包は閣下の手に直接届けると、ケマ・ワーヴィムに約束してしまいましたので。もう遅れていますし、置いて行くわけ…
クラヴィデス:お嬢さん、我々は帝国軍の衛兵だ。私たちがその小包と手紙を預かる。
ゾラッサは渋々とクラヴィデスに手紙と小包を渡す。帰るために逆を向く。
ユリス:もしからしたらお話を伺うかもしれませんが、大学にいますか?
ゾラッサ:はい。お元気で、兄弟よ。
ユリス:良い夜を、姉妹よ。
ゾラッサが退場するなか、クラヴィデスが小包を開ける。何枚ものバラ紙が挟まった本である。
クラヴィデス:どうやら紛失していた本を見つけたようだ。我々のこの手に届けられるとはな。
クラヴィデスがその本を黙読し始める。
ユリス(満足そうに、自分に話しかける):スキャス・アヌドにアルゴニアンがもう1人。しかも可愛い。彼女に対してあまり無礼でなかったならいいのだけれど。もうツルツルとした乾き肌の女性はうんざりだ。非番の時に会えたら最高なのだが。
ユリスは自分に話しかけながら、手紙の封を切り読む。
ユリス(続く):彼女は私と同様、南からのようだ。北ブラック・マーシュからのアルゴニアンは…その…アレだ…
ユリスは読み続け、その手紙に立ちすくむ。クラヴィデスは本の最後へと飛ばし、最終章を読む。
ジール城の恐怖 パート3The Horror of Castle Xyr, Part 3
クラヴィデスは本の最後へと飛ばし、最終章を読む。
クラヴィデス(読み上げる):黒のインクで、「カジート男性は簡単な雷の呪文に対しても驚くほどに低い耐性を見せたが、中位の酸の呪文をゆっくりと数日間にわたってかけることで、興味深い生理的な結果を得た」余白部分に赤のインクで、「ああ、なるほど。酸の呪文は被験者の全体に均一にかけられたのですか?」黒のインクで、「ノルド女性は16時間の冷気の呪文にさらされ、最終的には結晶化して仮死状態になり、それが原因となって息絶えた。ノルド男性もアッシュランダー女性も違った。彼らはさらに早い段階で昏睡状態に陥ったが、後に回復した。その後アッシュランダーは脱出を試みたが、拘束した。ノルドはその後、簡単な炎の呪文に対して興味深い過剰な化学反応を起こして息絶えた。付随の図解を参照ください」赤のインクで、「ああ、なるほど。腫れと損傷の傾向が何らかの内面燃焼を示唆していますね、もしかしたら、長い期間の冷気の後の短い炎の発射によって引き起こされたのかもしれませんね。実際に実験を見にいけなくて残念ですが、素晴らしい記録に賛辞を述べます」黒のインクで、「侍女アナーラにゆっくりと被毒させることを提案してくれてありがとうございます。提案してもらった用量は、ゆっくりと彼女の記憶を巧妙に侵食する、非常に興味深い結果を得ました。用量を急激に増やし、彼女が気付くまでどれくらいの期間がかかるかを見るつもりです。そういえば、アルゴニアンの被験者がいなくて残念ですが、奴隷商人が秋には健康な試験体を約束してくれました。彼らの代謝作用をエルフや人間と比べてみたいものです。私の理論では、中位の連続した雷の呪文の波は、シロディール女性やあの巨人のように、アルゴニアンにとって少なくとも数時間が致命的なラインであると感じています」赤のインクで、「秋まで待たなければならないのは残念です」
ユリス(手紙を読み上げる):赤のインクで、「このアルゴニアンをどうぞ。結果を教えてください」これは署名されています。「ケマ・ワーヴィム」
クラヴィデス:ああ、神キナレスよ、これは死霊術ではない。これは破壊だ。ケマ・ワーヴィムとケナ・テルヴァンニ・ホルダルフ・ジールは死の実験を行なっていたのではなく、魔法による拷問の限界を調べていたのだ。
ユリス:この手紙はケナ・テルヴァンニ・ホルダルフ・ジールに宛てられていません。宛先は、セデゥーラ・アイアチラ・ジールです。彼の妻でしょうか?
クラヴィデス:アイアチラ。その名前こそが巨人殺しに関連して聞いたジール家のテルヴァンニだ。侍女をここから連れ出さなければ。彼女は治癒師に行かなければならん。
クラヴィデスがアナーラを起こす。混乱している様子である。
アナーラ:何が起きたのですか?どちらさまですか?
クラヴィデス:心配はいらない、すべて大丈夫だ。あなたを治癒師へ連れて行く。
ユリス:上着は必要ですか、アイアチラ?
アナーラ:いいえ、ありがとう。寒くはないです…
アナーラ/アイアチラは止まり、捕まったことに気付く。クラヴィデスとユリスは剣の鞘を払う。
クラヴィデス:閣下、指に黒のインクが着いています。
ユリス:扉で私を見たときに、あなたの友人であるワーヴィムが送ってきたアルゴニアンだと思った。だからあなたは、「今は駄目!どこかへ行って!」と言ったのですね。
アナーラ/アイアチラ:あなたはアナーラよりも観察力がありますね。彼女は、私が毒の呪文を3倍にして、私が観測した感じでは非常に苦しみながら息絶えるときでさえ、何が起きているのかが完全に分かっていませんでした。
ユリス:私には最初に何をかけるつもりでしたか、雷、それとも炎?
アナーラ/アイアチラ:雷。炎は予測しづらい。
彼女が話している最中、松明の炎が消される。舞台は完全な暗闇。
争う音がして、剣が音をたてる。突然、稲妻の閃光が走り、沈黙に包まれる。暗闇の中からアナーラ/アイアチラが話す。
アナーラ/アイアチラ:非常に興味深い。
幕が下りるなか、さらにいくつかの雷の閃光が走る。
完
ストームクラグ家の墓地The Stormcrag Family Crypt
ブンヒルデ・ストームクラグ 著
第一紀後期に富を築いたラグノール・ストームクラグは、イーストマーチとそれを越えた領域において、ストームクラグ家を影響力を持つ一族として確立した。彼は探鉱者として最初の財を成し、ヴェロシ山脈のいたるところに利益を生む一連の鉱山を開いた。ストームクラグの富と保有地が増えたため、ラグノールは運送業、鎧および武器の手工業、銀行業、宝石製造業を始めとする、関連事業に投資した。
長かった成功の人生も終わりが近づき、ラグノールは所有する鉱山の1つを、自分の一族のための墓地にするというプロジェクトを開始した。彼が生きているうちに壮大な埋葬室の完成を見ることはなかったが、彼の息子であるアゲモールが墓地を完成させた時、ラグノールは地下墓地の最も深くに埋葬された。
ストームクラグ家は実業界の大物や、将軍、魔術師、従士、その他の著名人を各世代で輩出してきた。彼らの最期が来た時には、ほとんどの者が一族の墓地にて名誉と敬意の場所を与えられた。長生きの末に自然死する者もあれば、病気や事故、あるいは戦いによって早死にする者もいた。それから、ソルガ・ストームクラグという者がいた。
魔術師だったソルガは魔術師ギルドのメンバーで、アルケインの力を集めることで頭がいっぱいになっていた。研究と訓練では自分の求める力を得られなかったソルガは、苦肉の策に頼り始めた。噂によると、その中にはデイドラが関係しているものもあった。
一族の家長が女性だった時代に、自分の姪が闇の道を歩き出したことを聞き、コラーラは激怒した。「ノルドはデイドラと取引しない」と、彼女は公言した。しかし、ソルガの計画を変更させるコラーラの努力は伝わらなかった。さらに悪いことに、一族は闇魔法と、ソルガ・ストームクラグに関連する殺人の噂を聞くようになった。それだけ聞けば、コラーラには十分だった。
コラーラはソルガを勘当して一族から追放し、彼女が一族の財産を告げず、相続を行えないようにした。さらに彼女は、一族の墓地ではデイドラを愛するノルドの遺体を一切保持しないと宣言した。
「私が一族の墓地に立ち入り禁止になるなら、ストームクラグの誰1人として、そこで眠ることは2度とないでしょう!」とソルガは宣言した。彼女は墓に呪いをかけて死者を蘇らせ、沈黙の底で死の騎士を解放した。
今日に至るまで呪いは依然としてかかったままだ。ソルガが勘当されてから、墓地に埋葬されたストームクラグは誰もいない。
ソーサ・シルと書記Sotha Sil and the Scribe
韻文の予言者アンドルナル 著
書記はこめかみをこすった。神話と記憶の意味を理解しようとしてまた長い一夜を過ごしたため、頭が痛くなっていた。考え事から彼を揺さぶり起こしたのは、ソーサ・シルの声だった。
「もっと休息を取ったほうがいい。疲れた心は単純な物事も謎かけにしてしまう」。書記は目を上げた。シルはそこにいると同時にいなかった。いつものように。
「また会うとは思いませんでした」と書記は言った。意図したよりきつい言い方に響いたかもしれない。本当は、自分が目にしているものに心が躍っていた。
「今回、文が書けなかったのは」とソーサ・シルは言った。「私のためだったからか?」
書記は肩をすくめた。「書けるはずがありませんでした」。解答はそれだけで十分だった。お互いにとって何を意味しているか、二人とも分かっていた。
セトは微笑んだ。友人といる時でさえ、珍しい光景だ。「君があの庭にしたことは気に入った。ローランドの涙。見事だ」
「小手先の技です」と、書記は不愉快そうに言った。
ソーサ・シルは両腕を広げた。今度はどちらの腕も肉体にすることを選んだ。「それが書記の役目ではないか?」
「私は自分が理解するように、彼らにあなたを知ってほしかった。しかし、言葉が出てこなかった。他の者に仕事を委ねるしかなかった」
「つまり君にとってあまりに大切で筆を取ることもできなかった仕事を、他の者に任せたわけだ」。セトの言い方には珍しく、いたずらっぽい調子が含まれていた。「我々のような者にとって、それは悪いことではない」
書記は頭を振った。「間違うことを恐れていたのです」
「違う、君は完璧でないことを恐れたのだ」。ソーサ・シルは古い本を呼び出し、ページを繰った。「君はいつもそうだ。彼らのことがそんなに好きか?」
書記はゆっくりと立ち上がり、部屋の壁に貼られたニルンの地図に視線を向けた。「いいえ」と彼は静かに本音を口にした。「だが私は彼女を愛している。そして彼女は彼らのところにいる」
「役立つかどうかは分からないが、私が言ったことは真実だった」
「分かっています」と書記は言った。「あれは何回も読みました」
「気に入ったんだな」とセトは言った。
「ええ」
ソーサ・シルは自分のために椅子を作って座った。書記は友人であり、師であり、多くの父親と共有する子供でもある存在に向き直った。「お別れを言いに来たのですか、セト?」
「ある意味では」とセトは答えた。彼の声に悲しそうな響きはなかった。「おそらく私に似た別の形が現れて、また別の物語で必要とされる役割を演じるだろう。そうしたら私はいなくなる」
書記はうなずいて再び椅子に座った。書き物机越しにソーサ・シルの顔とセトの目を見た。
「私たちがやろうとしたことは十分だったのでしょうか?」書記はそう言いながらも理解していた。知識の光は囚人に勇気をもたらすが、書記にもたらすことはない。
「この世界が平和を知ることはない」と神なるソーサ・シルは言った。「それを管理する者も知らない。決して十分にはならないが、我々は夜明けの美しさのため、長い夜に耐えて世界を保存する」
そして、セトが前に身を乗り出した。「どんな親も、自分のしたことが十分だったとは思わないものだ」
それで書記は多くの後悔について考えを巡らせたが、口に出したのは1つだけだった。「私はあなたを助けようとした」と彼は言った。「神話にいくらかの重みを与えて。だが物事のあり方を止めることは、私にはできない」
「君がそうしなかったのは、私を愛しているからだ」。またしても、神の言葉は真理だった。
「あなたは謎の父だ」と書記は言った。
「では、私は行かなければならない。たとえ望まなくとも」とセトは言った。「ソーサ・シルが残れるように」
書記は再びうなずいた。「我々のために何か伝えておくことは?」
クロックワークの神は唇をすぼめ、言った。「確かさへの跳躍には気をつけるように。名のあるデイドラには多くの姿がある。多くの顔がある。1つの姿に他の姿を圧倒させてはならない。混沌の使者であるから。本性を硬化させれば、自己満足と破滅を導くだろう。この闘争の時代は、彼らが単純だとする嘘を駆逐するまで終わることはない」
書記は沈黙のうちに同意して頭を下げ、再び目を開いた。「それであなたはどうするのですか、セト?」
「私は自分が試みた全てのことに不完全を見た」とセトは言い、ニルンの地図を眺めた。「不完全をなくそうとする試みのうちにさえもだ。それでも、手を加えるのを止められない。創造を止めることはできない。あまりにも愛しているからだ。すでに愛を知っている者に、私は何も教えるつもりはない」
ソーサ・シルの体は非物質化し、千の小さな光になった。光は部屋を跳ね回って本や巻物、地図を聖なる黄金の輝きで照らし出した。最後に話したのはセトだった。
「それは君に任せよう」
落ち着かない沈黙が書記の部屋に残った。薄暗い部屋は、新たな荘厳な目的で満たされた。ついに書記の口は微笑みへと変わり、彼は再び筆を取った。
タズゴルの幻視の追及Tazgol’s Vision Quest
タズゴル・グロベトニクはまだ3度も戦っていないうちに、ベトニクの断崖絶壁を登った。海の向こうに広がる世界の果てまで見通せるほどの高みまで登ってやろうと思い立ったのである。
食べものも飲みものも持たずに登攀を始めた彼は、岩壁の裂け目に溜まる雨水を飲んで渇きを癒やし、鳥の高巣からくすねた卵を食べて飢えをしのいだ。
タズゴルは3日かけて頂に到達し、そこで3日間、体を休めた。
その間、モーロッチが彼に次のような幻視を見せた:
タズゴルは1匹の大蛇が3つに切り刻まれ、ひとまわり小さな3匹の蛇になるのを見た。
3匹の蛇は世界を3つに分けあった。
1匹は地を這い、それからこう言った。「私は大地と、そこで育まれるものすべてをもらう」。
別の1匹は深淵を泳ぎ、それからこう言った。「私は水と、それを飲むすべてをもらう」。
3匹目は翼を生やし、それからこう言った。「私は空気と、それを呼吸するすべてをもらう」。
それぞれが宣言通りにするやいなや、3匹の蛇は諍いを始めた。考えてみれば、大地から生まれない生きものなど存在するだろうか?また、水を飲まない生きものなど存在するだろうか?あるいは、空気を吸わない生きものなど存在するだろうか?だから、3匹の蛇はそれぞれ、自分がほかの2匹を支配すべきだと考えたのである。
やがて諍いは三つ巴の争いとなり、結局は3匹とも息絶えた。
タズゴルは自分の目で見たその光景に困惑し、断崖絶壁から降りて賢者スルガに打ち明けた——モーロッチにこんなものを見せられたと。
それまでも数々の幻視を解釈してきた賢者スルガは答えた。「その幻視には2つの教訓が込められているね。1つは、統合なき分裂は致命的だということ」
「でも、どうしたら分裂と統合が両立するのですか?」タズゴルが訊ねた。
「未熟者が訊きそうなことさ」賢女は吠えるように答えた。「たとえば族長の3人の妻たちは互いに憎み合っていながら、族長のことは愛している。だとすれば、彼女たちは同じ願望を共有していると言えないかい?また、若いオークが族長に挑戦するとき、そこには分裂があり、新しい族長が勝ち名乗りを受けるとき、そこには統合があるのではないかい?だからこそ、自分たちが3匹の別々な蛇ではなく3つに分かれた1匹の蛇だということを忘れた結果、彼らは滅んだのさ」
「でも、どうしたら分裂と統合を維持できるのですか?」若い戦士はいぶかしんだ。
賢女は笑いをかみ殺した。「それこそがお前の見た幻視に込められた2つ目の教訓だよ。つまり、過去を忘れるなということさ」
チャルマン砦に立つ者Those Who Stood at Chalman Keep
ここに集え、誇り高き戦士たちよ。
口を閉ざし、力強く立て。
眠るものに頭を垂れよ、
彼らはチャルマン砦の大地の下に。
戦いの炎が大地を焦がし、
無慈悲な手がすべてを破壊した。
玉座を狙うドミニオンの兵士たちの中で、
チャルマンは臆することなく、ただそこにあった。
蹄の音が草原にとどろき、
死がすべての者に近づいた。素早く、揺るぎなく。
守護者たちはチャルマンの防壁に立った。
勇敢なる戦士たち、それはカバナントの英雄たち。
前方からドミニオンの軍団が押し寄せた。
アルケインの魔法と輝く剣を携えて。
攻城兵器のうなりが、壁を揺るがし、
破城槌が砦の門に打ち付けられた。
侵略者の集中砲火に外門が破られた。
エルフとカジートが中庭に突撃した。
その攻撃で内門もまた奪われた。
襲撃者は、死体とがれきを跳び越えた。
守護者たちは己の力を知らしめた。
魔法の閃光が広がり、死が与えられた。
怒りが侵略者たちの頭上に降り注いだ。
カジートとエルフ、すべての命を奪うまで。
休息の時はない、回復の時はない。
門と城壁の裂け目をふさがなければ。
すべてが修復され、元に戻った。
その時新たに、激しい攻撃が始まった。
またも、すさまじい戦闘が繰り広げられた。
戦う者たちに死が与えられた。
砦の中に混乱が広がり、
砦を埋め尽くし、死体が山となった。
ドミニオンの軍団はまたも敗北し、
ふたたび流血の波は引いた。
オーク、レッドガード、ブレトンたちは生き残った。
チャルマン砦の誇り高き生存者たち。
ドミニオンの戦士はもう一度攻撃を開始した。
これまでよりはるかに多い軍勢で。
疲弊した守護者たちをなぎ払い、
最奥の広間にたどり着いた。
英雄たちは壁際に追い詰められた。
ドミニオンの勝利の声が高らかに響いた。
そのとき混乱とともに、突然パクトがなだれ込み、
戦いに疲れた敵軍を見渡した。
カバナントとパクトに挟まれて、
エルフとカジートは勇敢に戦って死んだ。
残ったのはパクトとカバナント、
そして、守護者がふたたびその場を一掃した。
一息の間、短い休息。
今やカバナントが優勢となった。
ドミニオンが最後の攻撃を開始した。
数えきれない兵士の波が押し寄せた。
勝利を固く決意する者。引くことを断固拒否する者。
ドミニオン軍は引くことができなかった。
守護者は最後の1人まで戦う覚悟だった。
剣の一振りごと、呪文の一唱ごとに敵を倒した。
一人ずつ、勇ましい戦士が倒れていった。
ブレトン、レッドガード、オークが立派に戦い死んでいった。
チャルマン砦に捧げられた彼らの命、
彼らは永遠の名誉の中、眠りについている。
ドミニオンの旗が広間に掲げられた。
それからドミニオンの皇帝がすべてを支配した。
チャルマンに平和が訪れ、砦は修復された。
戦士たちは各地へ散り散りに。
皇帝は去り、その治世は、はるか昔。
今では何が残っている?何が続いている?
チャルマン砦に立ち、死んでいった者が、
最後に示した勇気だけ。
チャンスの愚行 パート1Chance’s Folly, Part 1
ジルモック・ゴルジ 著
ミネヴァ・イオロスは16歳になるまでに、バルモラのあらゆる店や邸宅から歓迎されざる客となっていた。ときに価値のある物を洗いざらい盗み、ときに鍵や罠を出し抜く方法を見つけるという行為は、彼女にとって純粋な楽しみだった。どちらの状況であれ、彼女は名刺代わりに一対のサイコロを目立つ場所に残し、誰が泥棒に入ったのかを家主に教えた。そんな妖しい幽霊のような存在として、地元の人間から「チャンス」として知られるようになったのである。
当時バルモラでは、こんな会話がよく交わされていた。
「あの素晴らしいネックレスはどうしたんだ?」
「ええ、それがチャンスに盗まれてしまったの」
チャンスにとって自分の趣味が嫌になるのは、計画どおりに行かなかった時や、家主や衛兵に見つかった時だけだ。今までのところ、彼女は捕まったことも見られたこともないが、何十回も危ない橋を渡った。ある日、彼女は自分の活動範囲を広げようかと考えていた。そしてヴィベクかグニシスに行こうかと考えていたところに、ある夜エイトプレートでヘランの先祖の墓の話を聞いたのである。それは罠がたっぷり仕掛けられた古代の墓で、ヘラン家の財宝が数百年分も貯め込まれているという。
ヘランの墓の魔法を解き、中の財宝を手に入れるという考えはチャンスを魅了したが、ガーディアンに立ち向かうのは未知の経験だった。どうしようか思案していると、ウルスティア・モレスビーがいつものように1人で近くのテーブルに座っているのが目に入った。彼は巨漢のブレトンで、穏やかで少し変わった人物である。彼は偉大な戦士でありながら心を病んでしまい、外の世界よりも自分の頭の中で響く声に耳を傾けるという噂だった。
この計画に相棒が必要だとしたら、この男がうってつけだとチャンスは思った。彼は戦利品を平等に分けるという発想を要求することも、理解することもないだろう。もしヘランの墓の住人に太刀打ちできなかったとしても、彼がいなくなったところで悲しむ人もいない。たとえチャンスが彼の相手に疲れて置き去りにしたとしても。
「ウルスティア、初めてお目にかかるわ。私はミネヴァ」そう言いながらテーブルに近づいた。「ヘランの先祖の墓へ行こうかと思ってるの。モンスターの相手をしてくれたら、扉や罠の解除は私がやるわ。どうかしら?」
ブレトン人は返事に少しかかった。まるで頭の声の助言を熟慮しているようだった。彼はついに頷いてぶつぶつと言った。「ああ、はいはい、岩を支える、熱い鋼鉄。キチンだ。壁の奥の扉。53。2ヶ月して戻る」
「素晴らしいわ」と彼の話を気味悪がることもなく、チャンスは言った。「明日の朝出発しましょう」
チャンスの愚行 パート2Chance’s Folly, Part 2
ジルモック・ゴルジ 著
翌朝チャンスがウルスティアに会った時、彼はキチンの鎧を纏い、魔法でかすかに輝く珍しい剣を装備していた。旅が始まると彼女は会話を試みたが、彼の返事は意味不明なものであったため、早々に諦めた。突然の暴風雨が平原でうねり、ずぶぬれになったが、彼女は鎧を着ておらずウルスティアは滑らかなキチンの鎧を着ていたため、歩みが遅れることはなかった。
そして2人は、ヘランの墓の奥深くへと入っていった。彼女の直感は正しかった–彼らは良いパートナーになった。
彼女は太古のワイヤーの罠、落とし穴、トゲなどを作動させる前に発見し、あらゆる種類の鍵を破った。単純なタンブラー、組み合わせ錠、ねじれ留め金式、そして名前すらない大昔の錠前や、本物の鍵があったとしても開きそうにないサビの塊まで、さまざまな鍵を開けた。
一方ウルスティアも役目を果たし、チャンスのような都会の少女が見た事もない、奇妙な獣たちを倒した。火の魔法がかけられた剣は、特に氷の精霊に効果的だった。彼女が足場を失った時や床の割れ目に落ちそうになった時に助けたりもした。
「汝自身を傷つけるな」そう言った彼の顔は本当に心配していた。「壁の奥に扉があり、53だ。吸い取る指輪。2ヶ月で戻る。岩を支える。来い、マザー・チャンス」
チャンスはウルスティアの小言をあまり聞いていなかったが、彼が「チャンス」と言った時はギョッとした。彼女はミネヴァと名乗っていたのだ。もしかしたらあの農民たちの言葉は正しかったのだろうか。発狂した人間はデイドラ公シェオゴラスと話していて、自分の知識を超える助言や情報をもらっているのだろうか?あるいはもっと常識的に考えて、鍵開けのことを「チャンス」と呼ぶようになったバルモラの人々の話を聞き、単に繰り返しているだけなのかもしれない。
奥へと進む間、チャンスはウルスティアの呟きのことを考えた。顔を合わせた時、彼はその場で思い浮かんだように「キチン」と言い、実際に彼が着てきたキチンの鎧は役に立っている。「熱い鋼」も同じだ。では「壁の奥の扉」はどういう意味なのか?または「2ヶ月で戻る」は?「53」とは何の数字なのか?
ウルスティアが自分と墓について秘密の知識を持っているという考えに取りつかれ、チャンスは落ち着きをなくした。彼女は財宝が見つかったら、この相棒を置き去りにすることに決めた。彼はダンジョンのどんなガーディアンも切り捨ててきたのだ。入った道をこっそり帰るだけなら、守る者がいなくても大丈夫だろう。
彼の言葉の1つには、思い当たるものがあった。「吸い取る指輪」だ。彼女は以前バルモラにある邸宅の1つで、ただ可愛いと思って指輪を1つ盗んだ。それが人々の生命力を奪うものだと分かったのは後になってからだ。ウルスティアはこの指輪のことを知っているのだろうか?彼に使ったら驚くだろうか?
彼女は広間を降り続けながら、ブレトン人を見捨てる最適な計画を考えていた。そんな時、通路の奥に金の鍵がかかった大きな金属の扉が現れた。チャンスは素早く2つのタンブラーとボルトを外し、扉を開けた。ヘランの墓の財宝は中にあった。
チャンスは静かに手袋をはずし、指輪を出しながら部屋に入った。そこには金が入った53の袋があった。彼女が振り返ると、2人の間で扉が閉まった。内側からは扉ではなく、壁になっていた。それが壁の奥の扉だった。
何日もの間チャンスは叫び続け、部屋から出る方法を探した。数日後、彼女はぼんやりとした意識のなかで、シェオゴラスの笑い声を聞いた。2ヶ月後にウルスティアが戻った時、彼女は死んでいた。彼は岩を使って開いた扉を支え、財宝を持ち去った。
ドゥエマーの夢Dwemer Dreams
トレジャーハンターのナルシス・ドレン 著
この遺跡を発見したのは、周辺の地方を慎重に調査した後のことだった。訓練された経験豊富な私の目からすれば、この施設が見つけた場所に存在することは明らかだった。私はそこを、付近にあるブサヌアル遺跡に近いことと高度の関係から「ブサヌアル下層」と名付けた。ドゥエマーの他全ての遺跡と同様に、その場所の真の目的を知ることはできない。しかしだからといって、夢を見て推量を試みられないわけではない。
それにいつもそうだが、私の推量はモーンホールドの塔や魔術師ギルドホールに座っているような、いわゆる学者が提案する理論よりも真実に近いだろう。
私が描いた施設の地図を調べていると、頭の片隅に考えが思いついた。それについては一晩考えることにし、クモやスフィアが活動的に近寄ってこない安全な場所を見つけた。私はギアのブーンという音と蒸気のシューッという音を聞きながら眠りに落ちたが、寝ている時に夢を見た。
夢の中で私はさらに南の小さな部屋に立っていて、息をしている生きたドゥエマーに囲まれていた。彼らは仕事に取り組むあまり、その中を通る私に気がつかなかった。私は、彼らが簡単には識別できない物質である金属やその他の奇妙な部品を動く機械に飲み込ませるのを見ていた。話しもせず、休むために中断もしない彼らは、自分たちが作っている装置と同じくらい機械的であるように見えた。
夢の中で私は、理解しがたいドゥエマーの仕事は本人たちに任せ、東の廊下を使って出た。転がりながら通りすぎるスフィアを無視しながら、私は北へと曲がった道を進んだ。大きめの部屋の中で、奇妙な光景に出くわした。数十人のドゥエマーが中央壇に集まり、その掲げられた舞台で行われている何らかの催しを注視していた。センチュリオンがその壇にいるのが見えたが、それは周辺にいるドゥエマーの群衆よりもずっと背が高かったからだ。しかし、ドゥエマーをそれほどに魅了する、一体何が起こっていたのかを把握することはできなかった。もっとよく見るために群衆を押し分け始めた時、何かに腕を掴まれた。
私はそれを、その瞬間まで私を完全に無視していたドゥエマーの誰かにちがいないと思ったが、私を掴むその手は冷たく機械的だった。それに握られた時、私は痛みに叫んで目を開けた。夢は霧が晴れるように消え去り、私は自分がドゥエマーの蜘蛛に捕まっていることに気がついたのだ!
まあ、この記述を読んでいるということは、私がいつものように死の危険から逃れたことはもうすでにお気づきだろう。気品、知性、そして堂々たる態度。見ていればさぞ驚かれたことだろう!
だが、部屋の離れた隅の一番暗い影の中で私が偶然見つけた宝箱の中で見つけたものが何かは言わせてほしい。その宝箱は、様式も機能もドゥエマーのそれではなく、もっと最近になって遺跡に加えられたもののようだった。だから、この遺跡を発見した最初の探検者は結局私ではないのかもしれないと思った。しかし、不自然な宝箱の中身はこの私、トレジャーハンターのナルシス・ドレンとほぼ同じほど優れていた。それは信じてほしい!
ドロジラの物語The Tale of Dro-Zira
複写・解説:ソニア・ヴェット
(以下の物語は、カジートの父親が隊商の野営準備中に若者へ話しているのを小耳にはさんだものだ。カジートはあまり自分たちの歴史を語らないため、話を記録しようと試みた。本当は彼が話すことはないと思っていたが、その夜消費した大量のムーンシュガーが手伝った)
こっちで火に当たって毛を温めろ、マラシーア、ドロジラがどうやって最も偉大なカジートになったか話してやる!(編者:ドロジラとはこの場合名誉ある先祖と解釈)
古代のカジートは時の偉大な猫王アルコシュ(編者:帝国ではアカトシュ、スカイリムではアルドゥインとして知られている)の大きな鳴き声を聞き、声の下に駆けつけた。3日間でタムリエルを横断し、ムーンシュガーのためであろうと休まない。当時のカジートはそれだけ速かった。
彼らはアルコシュの群れに加わり、最強の戦士になった。しかしローカジュは、(編者:ノルドのショール)カジートの戦士を困らせるため、ラウルファースに力を貸した。アルコシュに捧げられる愛を妬んだんだ。
カジートの戦士たちの凶暴さを見て、ラウルファースは彼らを倒せる気がしなかった。ローカジュから受け取った咆哮を使い、彼はマッサーとセクンダと話して、空に満ちた彼らを動かしてもらった。カジートの戦士はセンチになったが、ローカジュが彼らを奪った。
ラウルファースが戻ってきてレッドマウンテンにかみつくと、彼の民に援助を呼びかけた。ドロジラは「ロジート」の中で唯一覚えていた1人で、召喚に応えた唯一の者だった。
しかしノルドの吟遊詩人は(編者:悪態は削除)で、偉大な灰の王がどうやってレッドマウンテンの上でドロジラに乗って、ダンマーの中心地を攻撃したか歌わない。彼の剣が灰の王の喉元にあったからしゃべれなかった時、どうやってドワーフオークのドゥマラキャスの頂上を襲撃したか決して語らない。
彼らはどうやってローカジュが、勇敢に灰の王を救うためにシェッゴロスの土地からドロジラに戻ったのかも歌わない!だからもしカジートを悪く言う吟遊詩人がいたら、背中に鉄の爪痕を残して誰がスカイリムを救ったか思い出させてやれ。
残った「ロジート」は小さくなり、狡猾さを失った。だからこそ、奴らが荷馬車に近づいたらためらわずに攻撃しなければならない。私の父にそう言われ、今お前に話した。
さて、いい子だから甘いケーキのためにムーンシュガーを取ってきてくれ。
(私にとって話のほとんどは自慢話と大差ないが、我々が信じる伝説の裏側の真実とも一致するようだ。これは何故我々はカジートの歴史をあまり知らないのか、我々の歴史に記録されていないかもしれないが、どんな役割を果たしたのかという疑問を起こさせた)
バーン・ダルの最初の巻物(抜粋)First Scroll of Baan Dar (Excerpt)
ダガーフォール、第二紀225年、恵まれし者アルカンの見習い、ジャーヴス 翻訳
エルスウェア東部にあるヴリード湖近くで、アラバスターの壷に入っていた上質羊皮紙、バーン・ダルの巻物を完全翻訳しようと、学者達は何年も苦労してきた。私自身はこの翻訳の信頼性について何も断言できない。読者は注意のこと!
— 「ほら吹き」の忠実な信徒、ヤナバー・ジャ
– – – – – – – – – – – – – – – –
伝説のバーン・ダル。盗賊、妖術師、闇の主人、自慢屋。極悪計画の黒幕。これらを含む様々な表現が使われる伝説的なバーン・ダルは、山賊の神と呼ばれた。亡命者。のけ者。しかし真実は?
バーン・ダルはもっと単純であり複雑な存在だ。私はこの話を高齢と屈辱的な矢による負傷のためにゆっくりと死にながら記す。真実がバーン・ダルという伝説に何かを足すことになるのか、何かを奪うことになるのかは分からないし、バーン・ダル自身が真実を知られたがったかも分からない。そのため、私が消え去る時にはこの話を隠しておき、運命(それはバーン・ダルにとって真の師であり動機であった)に決めてもらうことにする。
初めてバーン・ダルに会った時、私は12季の子供だった。数多く起きた地区内の境界争いの最中に、奴隷職人の襲撃によって孤児になった。機転と手先の器用さ、そして幸運を生かして、生まれ故郷の裏通りと脇道で生活していた。街外れの崩れた外壁近くの市場で、地元の露天商人からちょうどパン1個と小さなリンゴを少数「拝借」したところだった。ごちそうを楽しむために暗い路地に引き揚げた時、自分と同類の年上の集団に取り囲まれた。年上かつ怠け者な類いで、盗っ人から盗むという楽で危険の少ない手法を常としていた連中だった。
いじめっ子は5人で、自分達の方がごちそうを手に入れる権利があると考えて、終始笑いながら杖で痛めつけ、私は半分死にそうになっていた。地面に横になり、頭と股間を守ろうとして力の限りきつく丸まりなっていると、静かな声がその連中に「埠頭に行って同類のネズミから食べ物を取る方が似合ってるんじゃないのか、でなければ、その遊びは同じ大きさと数の相手に試したらどうだ?」と言うのが聞こえた。
私の「連れ」が新参者に気を取られ、とりあえず殴ったり蹴ったり平手打ちしてこなくなったので、見上げてみると、ブーツとマントと鎖のフード姿をした暗い影が、路地の突き当たりで壁に寄りかかっているのが見えた。
他の連中は、連中らしく、これを自分達の男らしさに対する挑戦だと受け取り、そして数で優勢な上にさらには金という報酬も期待できる楽な獲物だと考えた(そうでなければ、1つ目の点については黙認していただろう)。私の遊び仲間集団のリーダーはその見知らぬ者に、彼らが夕食を終えてから私と一緒に前述の埠頭で命を終えたくなければ、その埠頭から飛び降りろと言った。
下っ端からほくそ笑いと勇気をもらい、リーダーは杖を胸の前に持ちながら前に踏み出した。その後は具体的に何が起きたのか分からないが、短時間の間にいじめっ子のリーダーは胸に短剣を受けて地面に横たわり、2番目のいじめっ子はブーツでやられて歯を3本失い(今でもそれを思い出の品として皮袋に入れて持ち運んでいる)、3人目は自分の杖をつま先(の親指!)の間から押し込まれ動けないようにされた。4人目と5人目はもう面白くないと考え直して、慌ててどこかへ去っていった。
バーン・ダルは私を起こすと、汚れを払って、近くの酒場へと引きずっていき、そこで私達は食事と飲み物を分け合った。私は命を救ってくれたお礼を言った。どうやったらこの恩返しをできるかと聞いた。彼の返事は短く、的を射ていて、それ以降の人生における行いに影響を与えるものだった。
彼はこう言った。「親切は返すな。他の誰かにあげてやれ」
バスタードの墳墓The Bastard’s Tomb
神話の作り手タレオン 著
生前、草喰いヨレッグは札付きの悪党だった。最初は盗賊と襲撃者として、その後は地主と実業家として一財産を築いた。そのすべての仕事において、彼はその後呼ばれるようになったある名前にふさわしいということを証明した。バスタードのヨレッグだ。皆が口を揃えて言うことには、彼はその名前を好み、その長く卑劣な人生がついに終わりを迎えたときには自分の墓にその名前を使いさえしたという。これはその経緯についての物語である。
バスタードのヨレッグはウィンドヘルムでも最年長者の1人であったが、自分の半分の年の者と同じくらい強靭ではつらつとしていた。街中には店や露店、酒場や馬小屋を数多く所有しており、西の壁の先の牧場の大部分も所有してした。しかし「所有」という言い方は少し控え目すぎるかもしれない。ヨレッグはそれらの不動産を従士や首長と同等の権力によって支配していた。ヨレッグのために働こうものなら召使か奴隷のようにこき使われ、土地を借りようものならそのうぬぼれ屋の前では謙虚な臣下のように振る舞うことを強要された。
つまり、彼はまったく真のバスタード、ろくでなしだったのだ。
財産を増やし、彼に恩がある者を恐怖に陥れ続けながら、彼は墓の作業にも取りかかった。若かりし頃に盗賊と襲撃者として初めて財を築いた場所である南東の離れた場所を選んだ。かつて略奪を繰り返していた頃に本部として使っていたその古い隠れ家は、南部イーストマーチとリフトを隔てる山々の洞窟の中にあった。才能ある石工師であるシュレグ・ロックフィンガーズを雇い、その簡素な洞窟を彼にふさわしい墓に作り替えさせた。彼女は期待通りの仕事をした。
シュレグの仕事ぶりを見ようとヨレッグが墓に向かったとき、彼は人生で数回しか犯さなかったような明らかな過ちを犯してしまった。そしてその過ちによって彼は大きな代償を払うことになろうとしていた。実はシュレグはヨレッグに恨みを持っていたのだ。もちろん会った者はほとんど全員が、その不愉快な男に対して恨みや不満や反感を持っていた。しかしシュレグの恨みはもっと個人的で根深いものだった。
シュレグ一家がヨレッグから借りた農場で骨を折って働いていたときに、ヨレグはシュレグの両親から何十年にも渡って金を搾取した。シュレグは両親の苦しみを覚えていたが、めったに文句は言わなかった。家族が稼いだ金はほとんどすべて借金返済として払っていたにも関わらずだ。しかもそれだけではなかった。母親が病気になって支払いが滞ると、ヨレッグとその手下達はあっさりとシュレグ一家を追い出し、シュレグはそれをただ見ていることしかできなかった。その日、シュレグはどうにかして復讐すると誓った。
ヨレッグは墓を見て、シュレグの仕事ぶりに満足した。豪華で広々としたその墓は、彼の肥大した自尊心と名誉欲を満たした。主埋葬室の中心を担う高座と祭壇を気に入り、その荘厳な雰囲気を醸し出す高い天井はエゴをかき立てた。「よし」彼は言った。「申し分ない」
シュレグはその老人を壁に沿って立っている彫刻が施された開いた石棺へと導いた。「中に入っていただけますか」シュレグはできるかぎり悪意を顔に出さずにそう言った。「正確な寸法を測りたいので」ヨレッグは微笑んだ。彼はもうその豪華な石棺に足を踏み入れるのが待ちきれなかった。しかしヨレッグは高齢になってもなお大柄な男だった。そしてその棺は体にぴったりの大きさだった。
「体をねじ込んでください」シュラグはヨレッグのがっちりとした肩を押し込みながらそう言った。ヨレッグは体をねじりながら何度も挑戦し、シュレグはようやくその石棺の巨大な蓋を閉じることができた。
「どうですか?」 シュレグは優しく尋ねた。
「ちょっと窮屈だな」ヨレッグはそう認めた。「しかもすごく暗い」
「あなたの魂と同じですね」シュレグは石棺ごしでも聞こえるように大声でそう言った。
「何だって?何と言った?」 ヨレッグはそう問い正したが、その声には混乱と怒りと、芽生え始めたわずかな恐怖が込もっていた。
「両親の仇だ」シュレグは石棺の蓋を封印しながらそう言った。「永遠の眠りを楽しんでください」
シュレグは、叫び声が部屋中に鳴り響いているのを聞きながら墓を去った。長い長い時間をかけて死ぬようにと、彼女は願った。
ハマン・フォージファイアの伝説Legend of Haman Forgefire
物語の紡ぎ手、ロガー・クリフサイドによる改作
ハマン・フォージファイアの話は聞いたことがあるだろう?王たちの生産者であり、金属を操る者であるフォージファイアは、この地で最も偉大な鍛冶師として知られている。首長、従士、そして桁外れの額を動かせる者たちは、フォージファイアが素晴らしい切れ味の短剣、頑丈な盾、強力な戦鎚、精巧な造りの鎧を作れることを知った。間もなく、フォージファイアは一定の期間に受ける依頼の数を制限しなければならなくなった。支障をきたすほど多くの仕事を受けたがらなかったからである。
他の鍛冶師たちは、フォージファイアが鉱石と話し、ウィンクと囁きで不純物を取り除けると主張した。ほとんどの者は男を崇敬し、その技術に畏怖していた。しかし、フォージファイアの業績に嫉妬する者も何人かいた。彼らはフォージファイアを中傷し、彼の技はまさに魔法、それも卑劣な魔法、デイドラの魔法によるものに他ならないと主張した。こうした鍛冶師の代表は、防具屋のガーヒルド・コールドハートだった
コールドハートは、フォージファイアと彼の技についての疑惑を大声で声高らかに主張した。偶然飲みに入った混雑して騒がしい酒場で、誇り高く得意げなハマン・フォージファイアは金属に奇跡を起こすため、邪悪なデイドラ公に何を誓ったのかと、大声で問いを投げかけた。もちろん、事実からはほど遠い。フォージファイアには素晴らしい才能があるだけだ。しかし、コールドハートが事あるごとに噂を広めるのを止めることにはならなかった。まもなく、フォージファイアへの憎しみで他のものは目に入らなくなり、嫉妬が大きくなって苦しむようになるまでは見事なものだった、作品自体にも影響するようになってきた。
フォージファイアは広まっていく作り話を無視するよう最善を尽くしたが、コールドハートの噂が広がるにつれて、依頼は少なくなってきた。ハマンはなぜコールドハートが偽りのひどい話を断固として語るのか、理解できなかった。彼はまだ入っている仕事のために最善を尽くし、下り坂となった運命が逆転するよう祈っていた。その時、ハマンの経歴における最大の依頼が戸口に現われた。
偉大な英雄、「舌の」ヴェネルが、新しい武器を求めて市場に来ていた。ただの武器ではない。品質が良く、お気に入りの剣エドゥジに合った武器でなければならない。次の冒険のために、ヴェネルは手斧を欲しがっていた。そして、伝説の鍛冶師、ハマン・フォージファイアがそれを作ることを望んでいた。好機を喜び、やりがいのある仕事に興奮し、ハマンは最高傑作に取り掛かった。手斧オーキンに。
一方、ガーヒルド・コールドハートは怒り狂った。「舌の」ヴェネルに、新しい武器を鍛える仕事を任せるよう求めていたのである。最善を尽くしたにもかかわらず、彼女ではなくハマンが選ばれた。腹を立て、思いつくただ一つのことをした。コールドハートは、フォージファイアについて流した噂話通りのことを考え、デイドラ公に助けを求めた。モラグ・バルに祈りを捧げたのである。
5日と5晩の間、コールドハートは自分の鍛冶場で祈り、モラグ・バルに祈りに応えるよう乞うた。6日目の朝、残虐の王が呼びかけに応えた。デイドラ公に頼みを聞いてもらうのは、決して簡単ではない。特に、モラグ・バルには必ず代償を払わなければならない。代償は血で払わなければならなかった。「自分の手で鍛えた刃で、その鍛冶師を殺せ。そうすれば、フォージファイアが望んだよりもずっと有名にしてやる」とモラグ・バルは約束した。
ハマン・フォージファイアはオーキンを完成させた。見事なものだった。次の旅に間に合うよう、斧をヴェネルに引き渡し、鍛冶場に戻った時、炉の前にコールドハートが立っていた。火から発する光に影を落としていた。コールドハートはこう尋ねた。「偉大なノルドの英雄の賞賛は堪能した?ハマン?そうだといいけど。人生の最後に受ける栄誉なのだから」
コールドハートは剣を取り出し、フォージファイアの心臓を貫いた。熟練の鍛冶師はよろめき、自分の炉で激しく燃える炎の上に倒れた。身体は炎に飲み込まれ、3日間焼かれたが、燃え尽きることはなかった。この間、コールドハートは悲鳴をあげた。どんなに遠くに逃げても、フォージファイアの苦悶の叫びが聞こえてきたからである。ヴェネルはガーヒルド・コールドハートをこの時代の最悪の悪人と宣言し、罪により処刑するため、ウィンドヘルムの従士の元へ連れて行った。この時、コールドハートは本当にハマン・フォージファイアよりも有名になったのである。
コールドハートの首が身体から離れた時、フォージファイアは鍛冶場とすべてのものがタムリエルから消えた。今の今まで、フォージファイアはコールドハートの影を追い、嫉妬深く不実なガーヒルド・コールドハートに復讐する機会を探していると言われている。また、邪魔しようとする者は誰であっても復讐を受けると言われている。
ペリンでのピクニック(恐怖の物語)Picnic at Pelin (A Horror Story)
デヴィッテ・ボルボワ 作
「ファリーヌ、おいでよ」と僕は言った。「きっと楽しいよ」
「どうかしらね、ジャック」とファリーヌが答えた。彼女にしては珍しく、いたずらっぽい顔に隠しきれない困惑がにじみ出ている。「とにかく…名案だとは思えないわ」
「何が?ピクニックに行くことが?ハイロックが第一帝国から独立したことを祝う独立記念日だよ。誰だって独立記念日にはピクニックに行くだろ!」
「ええ。でもペリン墓地には行かないわ。それにピクニック向きのお天気でもなさそうよ…すごくどんよりしてる」と彼女は身震いした。
「心配いらないよ」先頭に立って錬鉄の柵を抜け、広い墓地の中に入りながら、僕は言った。「屋根があるもの。この古い霊廟の中で食事をするんだ」
「えっ、ええ?」とファリーヌは言った。「でもここはお墓じゃ…」
「君の名前の由来となったファリーヌ・ギマール女男爵のね。独立記念日にバンコライの兵士達を率いてたんだろ?ちょうど同じだ」僕は微笑んでお辞儀をし、手を振って彼女を暗い霊廟の中に入るよう促した。
ファリーヌは中をのぞき込むと息を飲み、それから言った。「分かったわ、ジャック。私を脅かそうとしても無駄よ」そして頭を軽くすくめると、女男爵の最後の憩いの場にもぐり込んだ。
僕は大げさな身振りでピクニック用のブランケットを広げながらその後に続いた。「さあどうぞ!暗く陰気な地下墓地で、じめじめする変なしみの付いた敷石に直接座る必要はない。快適さと優雅さが僕のモットーだからね!」
「笑えるわ」彼女は勇敢に微笑むと膝をついて座り、僕はブランケットの真ん中にピクニック用のバスケットを置いた。「で、何を持ってきたの?」
「アンカーズ・ポイント宿屋のシェフ・アントワーヌによる、豪華なピクニック用の軽食だよ!骨を取り除いたカワラバトのつがいのグリルのコームウォートのチャツネ添えに、バロム・プディングに、シラバブが入った水差しが1つ。さあ召し上がれ。絶対に…」
「…しあ…たい…」地下墓地の奥の方でささやく声がした。
「あ…反響だよね。間違いない!い——今の聞こえた、ファリーヌ?」
「…ファリーヌ…っしあ…ぐんたい…!」ささやき声が帰ってきた。こんどはもっと大きな声だ。
「間違いなく聞こえたわ!」ファリーヌはそう言って飛び上がった。「ジャック、これは何の悪戯?」
「アレッシアの軍隊だと!どこだ?」その声ははっきりとそう言った。そして僕らの大きく見開かれた目の前に、急で狭い階段状の吹き抜けから漂うように青い幽霊が昇ってきた。
ファリーヌは悲鳴を上げて後ずさると、遠く離れた壁にぴったりと張りつき、マヒしたように動かなくなった。僕は背中に冷たい石が当たるのを感じ、自分も同じようにしたのだと悟った。
古めかしいデザインの鎧を身に着けた半透明の青い幽霊は、僕達の間に漂ってきて、入口で止まると振り向いた。「今日がその日であったな。違ったか?」彼女はうつろな調子で尋ねた。「攻撃の日だ!」
「そ——そうです、女伯爵」と僕は言って、自分がしゃべれることに驚いた。「正にそ——その日ですが、世紀が違います」
「何だと?」彼女はぼんやりした手をかぎづめのように持ち上げて僕に飛びかかってきた。僕はどうにかしてさらに深く壁の中に引っ込んだ。「何だと?また…ではないのか」
「そのとおりよ!」とファリーヌが割り込んだ。「世紀も違うし、年も違う!もう一度眠って、おばあちゃん」
「年が…違う」幽霊はゆっくりとそう言った。「もう一度…眠る」
そして果てしなくほっとしたことに、女伯爵の幽霊は階段の下へ向かって漂ってゆきながら消えていった。
「キナレスの風にかけて!」ファリーヌはそう言って床にへたり込んだ。「1杯飲みたいわ。あなたは?」
「ああもちろん。最低でも1杯は欲しい」僕は彼女がシラバブを注いでいる間にそう答えた。「何をもたもたしてるんだい?」
「手が震えちゃって。さあどうぞ」
僕はミルクとサイダーを混ぜたものを1滴残らず飲み干すと、追加を求めてマグを返した。そして大きく1つ息をついてから切り出した。「ファリーヌ、本当に本当にごめん。思ってもみないことになって…」
「そのことは気にしないで」と彼女は言った。「さあ、もっと飲んで。アンカーズ・ポイントに戻ったら、最高の話の種になるわ」
「怒ってない?本当に?」
「いいえジャック、怒ってなんかいないわ」
「それじゃあ肉を切り分けさせて…ん、おかしいな」ハトの皿に手を伸ばした僕は、体中を冷たいものが通り抜けるのを感じた。そして僕の手はそこまで届かなかった。「一体どうなって…?」僕は立ち上がろうとしたが、膝をついたところでブランケットの上に倒れてしまった。「ファリーヌ、何か…何か変だ」
「何でもないわ」彼女は甘い微笑みを浮かべながら言った。「あなたのシラバブにしびれ薬を入れただけよ」
「く——薬を入れた?」と僕はつぶやいた。「何で?」
「参加条件がとても厳しいクラブがあって、そこに入りたいの。ナミラの忘れ去られた者たちよ。でも参加を認めてもらうためには人の肉を食べなくてはならないの。本当にぞくぞくするわ、ジャック!」彼女はベストからほっそりとした鋭い刀剣を引っ張り出した。「さてと…どこから始めようかしら?」
マブリガシュの試練The Mabrigash Trial
愛しきファリ
君は旅の途中で出会った変わった人々や場所の話を聞くのが好きだったね。モーンホールドを去った後、おかしなダークエルフに出会ったよ。彼の振る舞いは他のダークエルフよりはいくらかは打ち解けたものだったけど、それでもどこか人を信用できない雰囲気をまとっていた。野営地でワインとパンを申し出ると、少しの時間を共にするくらいにはありがたく思っているようだった。
自分のことを「マブリガシュ」だと言ったので、アッシュランダー・クランの分派か何かだと思ったが、ヴァーデンフェルからこんなに南まではるばるやって来るクランがいるとは知らなかった。彼の旅について尋ねると、目的地は決めていないということだった。ただ谷には戻れないと言っていた。
理由を尋ねると、谷が故郷だと教えてくれた。その奇妙な場所で彼のクランが蛇と亡霊を守っていると言っていた。そのお返しとして「ゴーストスネーク」がクランを見守ってくれていると。2人でワインを数本空けていたので、ここまで話したところで彼は少し酔い始めていたが、ゴーストスネークは実在すると断言していた。谷を去った理由を尋ねた。彼はしばらく黙っていた。その後ようやく、試練に失敗したからだとつぶやいた。どういうことか尋ねると、怖気づいて道を歩くことができなかったから逃げたのだと言った。「もう2度と戻れない」彼はそう言った。「家族の面目をつぶしクランの名誉を汚してしまった」
はらはらと泣き始めたので私は荷作りに忙しいふりをしたが、1分後にもう彼はいびきをかいていた。かわいそうなやつだ。太古の儀式や部族の儀式というものには明らかにおかしいものもある。朝にテントを畳む時、故郷に帰るよう励ましてやるつもりだった。しかし明け方に目を覚ました時には、彼はもういなくなっていた。
相変わらず君がいなくて寂しい。また数日中に手紙を書くよ。
——ソーゴ
マル・ソッラの呪いMal Sorra’s Curse
ダンマーの名家の高位の一員であるマル・ソッラというダークエルフは、残酷で血に飢えていた。戦いを好み、より強い敵に対して己の技量を試していた。また、闇の魔法を実践し、高位の死霊術師でもあった。不幸にも、所属する名家は闇の魔法を全く好まず、死霊術にさえあまり寛容ではなかった。しかし、マル・ソッラは気にしなかった。実のところ、習慣などを公然と軽視することで彼女は興奮し、血は熱くなった。
マル・ソッラは大きな興奮と絶え間ない危険を求め、残酷さと悪行はさらにひどいものとなったため、この死霊術師はさらに大きなことを試すようになった。名家の者やトリビュナルの高官の前でも力を誇示し、彼らに説教や罰を与えようとさせるか、原始的な衝動を抑えようとさせた。最初の無言の挑戦は自分の父親に対するもので、父親は名家の長であり、彼自身が強力な魔術師でもあった。マル・ソッラは競争を楽しみ、自分を育てた男に対抗できるのか知りたいと熱望していた。最終的に、マル・ソッラは挑戦に生き残っただけでなく、父親をマジカの決闘で殺した。
単に父親を殺すだけでは満足せず、呪文の集中砲火で殺し、ゾンビとして蘇らせた。このアンデッドを操り、服従し、あらゆる命令に従わせた。名家の他の者はこのひどい冒涜に恐れおののき、目に余る闇魔法を使ったことにより、マル・ソッラは罰せられるべきだと要求した。このことを聞いたマル・ソッラは笑った。力の誇示と現在の長を尊重していないことを示すのが大好きだったからである。
マル・ソッラはさらに厄介で危険な存在になったため、母親はもう十分過ぎると決意した。子供のことを悲しんだが、悪行を野放しにしておくことはできなかった。母親と魔術師の幹部が私室に入って来た時、マル・ソッラは驚いた。大胆なことをするものだと面白がり、恐れも不安も感じなかった。しかし、母親が儀式を始めた時、初めて危険だと感じた。そして、いつも通り面白がった。しかし、他の魔術師が加わった時、覚えている限り初めて恐怖を感じた。
母親は娘を罰するために、闇の魔法の力を利用した。娘の存在がなくなるのは耐えられなかったが、一家への脅威を終わらせなければならなかった。闇の魔法はマル・ソッラを圧倒し、拘束した。自分の闇の魔法に捕らえられ、マル・ソッラは生きたまま一番長い時間を過ごした場所、一族の墓に閉じ込められた。魔術師たちは魔法を組み合わせてポータルを開いた。墓はポータルに飲み込まれた。
「呪われなさい、娘よ」母親は目に涙をためて宣言した。「お前とお前の悪をオブリビオンに追放します。トリビュナルの慈悲があらんことを。お前がお前の犠牲者に見せることがなかった慈悲が」こうして、マル・ソッラはニルンに再び現れることはなくなった。
マンモス飼いの戦いの声War Call of the Mammoth Herders
…そしてその瞬間、生と死のどちらに転ぶか分からない中で、セウナーはその時が来たと悟った。マンモスの牙が凍った地面に叩きつけられた。セウナーはその力強い筋肉を使い、獣の巨大な鼻を大剣で切りつけた。獣は、怒りで再び甲高いうなり声を上げた。
セウナーは周囲から発された巨体の声を聞いた。巨大な獣達が鳴き声を発し、未熟な言葉で互いにうめき合った。そして自前の武器を地面に叩きつけ、セウナーの血を欲した。
分厚い木製の鎧が獣の脇腹を飾っていた。セウナーの巨大な剣は、その傷ついた表面から跳ね返った。セウナーも戦いの雄叫びを上げ、獣の前脚の下でかがんだ。戦士セウナーは上手で切りつけ、その剣は汚れと糞まみれの皮に刺さった…
ラジーンと石の乙女 パート1Rajhin and the Stone Maiden, Pt. 1
何年も前にラジーンが川を通りかかった時、遠く離れた対岸からすすり泣く声が聞こえた。向こう岸では女性がポケットに石を詰め込んでいた。石を入れ終わると女は川に入っていった。
彼女を溺れ死にさせられなかったから、ラジーンは川面を泳いで渡り、墓場になるであろう川から彼女を引き揚げた。
「神様、なぜ助けたのですか?」と彼女は聞いた。「トリックスターの神であるお方が、私の意図を分からないとでも?」
「お嬢さん、意図は分かるが理由が分からない」
女はしかめつらをして背を向けた。「私の苦境が理解できるはずもない。お願いだから石を集めて歩みを続ける私の邪魔をしないでください」
ラジーンはしかし、理由を聞くまで彼女が石を集め続けることを許さなかった。
その女、ムニリにはマザラムという婚約者がいて、二人は心から愛し合っていた。だがムニリの義父、アゼリト・ラは欲深い男だった。結婚の許しを与える前に、彼はマザラムの莫大な財産以上の、そして理不尽なほどの持参金を強く要求した。
アゼリト・ラは二人が住む村の長で、彼の不正に声を上げようとする者は皆無だった。しかしマザラムはアゼリト・ラに屈せず、義父の憎しみは増す一方だった。それでもマザラムは駆け落ちでムニリに不名誉を与えることはなかった。婚約者が義父の要求によって破滅するのを見るのではなく、ムニリは川を選んだ。
「義父が村を支配しているのか?」
「鉄の爪を用いてです、神様」ムニリは悲しげに答える。「賄賂を贈らない者は借金があるのです。マザラムのような少数だけが支配を逃れていて…義父はあらゆる手を尽くして、彼らを破滅させようとする」
「ちっぽけな村を支配して義父は満足だと思うか?」ラジーンは聞いた。
「満足?」涙を拭きながらムニリはあざ笑った。「彼はその言葉の意味を知らないわ」
「それなら力になれるかも知れない。さあ、マザラムを探そう」
村へ行きラジーンは若い娘に計画を説明した。
午後になりマザラムとムニリはアゼリト・ラのムーンシュガー大農園邸の玄関で彼に話をもちかけた。正式に婚約していたにもかかわらず、手をつなぐ二人を見てアゼリト・ラは腹を立てた。「それで、小さな貧しい人」義父はマザラムを迎えて言う。「持参金を了承したのかな、それともやっとお別れかな?」
マザラムは怒らずにさっと頭を下げた。「村長、持参金を用意できないのは確かですが、もっとよいものをお渡しできます」
アゼリト・ラの耳がぴくりと動いたが、懐疑心からせせら笑った。「もっとよい?一人娘のために要求する金額よりよいのか?いいだろう。取引の内容を話せ。十分であればそれでよい。だが違った場合、お前の尻尾には永久に去って貰う!」
ラジーンと石の乙女 パート2Rajhin and the Stone Maiden, Pt. 2
「結構です」マザラムは息をついた。マザラムは海運業で財産を成していたが、使者の一人から支配者のいない土地が近くにあると聞いた旨、彼は説明した。「その土地はこの村よりずっと広大なのに、暗闇の中で真珠のように輝いています。村長が所有権を主張できる土地ですが、使者の助けなしには絶対に辿り着けません」
アゼリト・ラは蔑んだ笑いを浮かべた。「そのような土地は存在しない!娘と結婚する間は私に邪魔をさせないというつまらない策略か?はっ!お前の企みには騙されないぞ!」
「企みじゃないわ、おじさん」ムニリが断言した。「母の名誉に誓って、私はその土地を見たことがある。おじさんもそうよ!その土地の美は物語や歌で有名よ!」
これにアゼリト・ラは面食らった。ムニリがマザラムとの結婚を望んでいることと同じくらい、彼女が正直であることも知っていた…そして彼女は亡き母の名誉を自分の命と同様に重んじていた。それでも彼はまだ疑っていた。信用できない男というのは簡単に信じないものだ
「いいだろう。私が見たことがあって知らないとお前が語る、広大な土地とは何だ?」
マザラムは指を振った。「いえ、だめなんです…無償で教えたとして、村長が私を置いて征服しないとどうして分かるでしょうか?使者の助けが必要だと言っておきます。しかし、一人で行ったら愚かなことをするかも知れない」
「分かった」アゼリト・ラは咳払いをした。「教えてくれないならお前が本当のことを言っているとどうして分かる?」
「私の使者が」マザラムは応じ、「今夜そこへ村長を連れていくでしょう。その場合、持参金を用意したと認めてくれますか?」
「策略だ」欲深い義父は考えた。「奴らの土地へ向かう「旅」の準備をしている間に逃げる魂胆だな。ふん、足止めしてやる!」
「乗った!」アゼリト・ラは大声で言ったが、周りの召使達にとっては非常に意外だった。「だが旅をするのなら、その前に婚約の宴を開かなくてはだめだ!お前、マザラムは私の右に、ムニリは左に座ることとする!」
「はっ」彼は一考し、「目と鼻の先で逃げてみるんだな!」
しかし二人は同意した。アゼリト・ラは食料庫とワインセラーを村中に開放せざるをえなかった。宴は午後一杯続いた。習慣どおり、大農場の経営者は貪欲に食べて、他の誰も彼より食べないように目を光らせた。二人は控えめに食事をして彼の横からは決して離れなかった。そのうちアゼリト・ラは眠くなり、そして不機嫌になった。
「双子の月が昇り始めているぞ、マザラム!お前の使者はどこにいる?」と村長は聞く。
「すぐ後ろにいます、村長」ささやく声がアゼリト・ラの耳を鳴らした。
老人は飛び上がったがすぐに立ち直った。振り向くと、つば広帽を被ったさすらい人のような者がいた。旅人は尻尾を振っているが、緊張なのか楽しみのせいなのかはアゼリト・ラには分からなかった。
「さて、それではお前の土地はどこだ!」アゼリト・ラ は男に向かって大声を出した。「出発の準備…いや、お前とマザラム両方の背を見送る準備はできているんだぞ!」
「準備はいいか?」さすらい人が問いかける。「では行くとしよう!」。さすらい人は瞬く間につば広帽を捨てた。そこに立つのは荘厳に映るトリックスターの神、ラジーンであった。二言目を発することなくラジーンは肥満男が着る染みのついたチュニックを掴み、二人は流れ星のように空へ飛躍した。間もなく二人の瞬きは最大の月、ジョーデの真珠大の輝きへと消えていった。
「本当よね」ムニリは思いを口にして言う、「村から見える土地」
「そして真珠のように美しく輝く」
村人達が衝撃から立ち直ると婚約宴は披露宴になった。双子の月が沈むまでに、ザラムとムニリは夫婦となっていた。
しかし、寝室で横になると二人に寒気が襲ってきた。ロウソクは今にも消えそうになった。暗闇が押し寄せる。ムニリは大声を上げ、マザラムは暗闇を手探りで剣を探した。
突然閃光が走った。目の前にはラジーンが立ち、衣服から月の埃を払っている。「さてさて、どこにいるのかな?」二人の恋人がぽかんとする中で彼は思いを巡らす。「ああ、ここにいた!」
目に留まらぬ速さで動いたラジーンは、手を伸ばして空を掴んだ。そして、身に着けているたくさんの小物入れの一つに手を突っ込んだ。部屋はまた明るくなった。
「今のは何ですか、神様?何を掴んだのですか?」ムニリは問いかけた。
「肥満男の影さ!新しい土地に連れて行ったのが速すぎたせいで、影をすっ飛ばしたのだ!」
彼らの笑いはこだまとなって川岸に響いた。
ラジーンのセブンシャドウ パート1The Seven Shadows of Rajhin, Pt. 1
グレイメーンは言う。太陽の光も月の光もニルンの民全てに平等に降り注ぐが、その後で何が起きるかは分からない。
ラジーンのセブンシャドウの伝説を例に挙げよう。未熟な若者でも知っているように、満悦の虚言者ラジーン、神のようなトリックスター、歩く猫は堅苦しい金言など大して気にしない。限界に挑戦し、真実以上のものにたどり着こうと生きている。彼にとって、シャドウ一つでは目的にまったく達しない…
ある日、ラジーンは熱い日差しの中を歩いていた。ケナーシを呼んでたてがみに風を吹かせるつもりだったが、風の神は手が離せなかった。そしてラジーンはアルコシュに頼んで、昼間を短くして涼しい夜にしようとした。だがアルコシュは、泥棒の神の言葉に従って昼間を盗んだりはしなかった。ラジーンの他の願い事も叶わず、トリックスターは自分で何とかするしかなくなった。
やがてラジーンは巨大な石の影で裕福な商人に出会った。「友よ」ラジーンは言った。「この不幸な私と、休憩の場所を分かち合ってくれないか」
だが商人は文句で返した。「場所はないぞ、放浪者よ。石の影は1人分の大きさで、2人は無理だ!」
ラジーンはこの言葉の真意を知った。ひどい言葉だが、反論はしなかった。その代わりに、こう機嫌良く言った。「道の途中で金の入ったカバンを落とさなかったか?すぐ近くで、そういう宝物の近くを通り過ぎたぞ」
商人は驚いて、眉をひそめた。すぐに太った男は、何とか立ち上がった。「何だと、手に入れなくては!頼む、どこで見たかを教えてくれ。石の影はお前に譲る!」
ラジーンは、欲深い商人に、自分が来た道を指し示した。すると商人は駆けていった。だが彼が去ると、トリックスターは太った商人の日陰が石よりも大きなことに気づいた。
「目の前に雌鳥がいるのに、卵で我慢する必要があるか?」ラジーンは考えた。隠し持っていたナイフを取り出して、泥棒の神は太った商人の影をきれいに切り取った。商人は気づきもしなかった。
すぐに彼は影の足を自分の影に結びつけると、自分の影と反対側に彼の前に広がった。トリックスターの神は涼しくなり、燃える太陽から身を隠した。
ラジーンは笑いながら道を歩き続けた。2つの影が、彼の前と後ろで踊っていた。
レイクウォッチの塔Lakewatch Tower
昔々、ガラッチは銀色に輝く青白く光った月光の夢を見た。それは女性の形となり、男のそばに来て横たわった
夜明けの光が部屋に差し込むと女は狼に姿を変え、いなくなってしまった
数ヶ月後、男は女が自分の元に戻ってくる夢を見た。まず彼女は——狼は、子を産んだ。子たちを大切に彼のそばに置き、そして女に変身した
「この子たちはあなたの子です」彼女は優しく言った。「大切に愛してね」
恐怖から、男はその子たちを殺した。その後、女は、男が二度と愛と優しさを理解せず、恐れと憎しみのみを感じるように呪いを掛けた
目が覚めると、男は自分の狼——子供の弱々しい体に囲まれており、過去にやってしまったかも知れないことに泣いた
永遠に語り継がれる物語A Tale Forever Told
シルヴェナールは目を見開き、ヴァレンウッドを歩いた。最も重要な姿から切り離されたその心臓は、空の穴になっていた。
荒野から、他の者とは違うボズマーがやって来た。彼女は火の目と雨風の髪を持ち、彼女をじっと見つめる者は恐れにおののいた。ただし、シルヴェナールだけは違った。
彼女が牙をむき出しにしても、彼は尻込みしなかった。薮の中で彼をまこうとしても、蔓は彼が追えるように道を空けた。彼女は唸り、残りたいという気持ちと立ち去りたい気持ちという、混乱した欲求を共に抱えた。
明るい空き地で彼女はシルヴェナールと戦い、爪と歯で彼を引き裂こうとした。彼はその打撃をかわしたが、それでも血が草の上に染み込み、花は血のしずくを垂らした。怒りは尽き、グリーンレディはついに後ろに下がってシルヴェナールに話しかけた。
「なぜ私についてくる?お前は仲間ではない!」地面に唾を吐きかけた彼女の拳はまだ握りしめられたまま、彼の血で汚れていた。
「でも、私はあなたの仲間だ」シルヴェナールは静かに言った。「おいで。緑の歌声に君を目覚めさせよう」
興味を抱いたグリーンレディは、シルヴェナールに近づいた。長い間話さずに見つめ合った後、彼らは繋がって暖められた。心と体が一つになった時、森が震えた。
彼に触れられて葉の舞踏を見た彼女は、ヴァレンウッドのやり方と策略を知った。彼の空虚は彼女の情熱でいっぱいになり、何とも言いようのない渇望は徐々に弱まった。
彼らの結合は荒野を飼い馴らし、緑の草木を活気づけた。
仮説上の裏切り パート2A Hypothetical Treachery, Part 2
アンシル・モルヴァー 著
一幕 パート2
登場人物
マルヴァシアン:ハイエルフ魔闘士
インゾリア:ダークエルフ魔闘士
山賊数名
場面:エルデンウッド
恐ろしい泣き声が空気を切り裂き、マルヴァシアンとインゾリアは一旦止まる。それが消えてなくなると、重い足取りで再び歩き始める。
インゾリア:ただの知的訓練として、もしこれ以上の戦闘もなくここから出られたとしたら、あなたは私にどのような呪文をかけるのかしら。
マルヴァシアン:まさか、暗に宝を独り占めするために、私があなたを殺そうと思っていると言いたいわけじゃないよね?
インゾリア:もちろん違うし、私もあなたにそんなことをしようと思っていないわ。ただの知的訓練よ。
マルヴァシアン:なるほど、それでは単純に知的訓練として、私はおそらくあなたの生命力を奪い、自分を治癒するために体力奪取の呪文をかけるね。結局、ここからシルヴェナールまでの道中には山賊がたくさんいて、貴重なアーティファクトを持った手負いの魔闘士は魅力的な獲物だろうしね。ただ単に野原で死ぬために、エルデングローブを生き抜くのはごめんだよ。
インゾリア:理にかなった返答ね。私としては、何度も言うようにこのようなことをしようとは思ってもいないけれど、突然の雷撃で十分役目を果たせると思うわ。山賊に関しての意見は同じだけれど、回復の薬があるのを忘れないで。ごく簡単にあなたを殺して、自分を完治できるわ。
マルヴァシアン:言うとおりだね。そうすると、最終的な疑問は、その瞬間にどっちの呪文の効果のほうが高かったかっていうことになる。もしお互いの呪文が反作用して、結局私があなたの生命力を奪い、あなたの雷撃で活動不能になったら、2人とも死んでしまうかもしれない。または、あまりの瀕死状態で、単なる回復の薬では2人ともはおろか、どちらか1人の助けにもならなくなる。もし2人の画策する魔闘士が、画策していると言っているのではなく、この知的訓練のためにね、死に直面し、マジカも枯渇し、1本だけしか回復の薬がなかったとしたら、どれだけ皮肉なことか。その場合、誰が手に入れる?
インゾリア:必然的に先に飲んだほうでしょうね。この場合、持っているのだからあなたになるわね。じゃあ、もし私たちのうち1人だけが傷ついたけれど、死ななかった場合は?
マルヴァシアン:論理に従うと、画策する魔闘士が薬を取り、傷ついたほうを精霊の慈悲に任せて立ち去るんじゃないかな。
インゾリア:それが最も賢明に見えるわね。でも、画策するような類ではあるものの、その魔闘士たちがお互いにある程度の敬意を持っていたらと仮定してみて。その場合、例えば、ひどく怪我をした相手の近くにある木の上に、勝者が薬を置くとか。そして、怪我をしたほうが十分なマジカを補充できたとき、彼または彼女は木の枝まで浮揚して薬を回収できる。その頃には勝った魔闘士がすでに報酬を受け取っているでしょうね。
近くの茂みから聞こえてくる音に一瞬、足を止める。慎重に木の枝に登り、その場を凌ぐ。
マルヴァシアン:何を言いたいかは分かるけど、被害者を生かすなんて、私たちが仮説をたてるような画策する魔闘士には柄にもないことに見えるけど。
インゾリア:そうかもしれないわね。でも私の観察では、多くの画策する魔闘士は誰かに勝ち、屈辱に耐えさせるためにその人を生かしておく感覚を楽しむわ。
マルヴァシアン:この仮説上の画策する魔闘士って…(興奮して)太陽の光だ!見える?
二人は枝の上を素早く渡り、茂みの裏に落ち、舞台から姿を消す。一方で、キラキラと光る日光の光輪が見える。
マルヴァシアン(背の高い茂みの後ろ):出られた。
インゾリア(同じく、背の高い茂みの後ろ):確かに。
突然、電気の爆発と凄まじい赤い光のオーラが発生する。辺りは沈黙に包まれる。しばらくして、何者かが木に登る音が聞こえてくる。それは、高いところにある枝の上に薬を置くマルヴァシアンである。含み笑いをもらしながら木から下り、幕が下りる。
エピローグ
シルヴェナールへの道中で幕が上がる。山賊の一味が杖に寄りかかり、辛うじて立っているマルヴァシアンを囲み、簡単に宝箱を彼から引き離す。
山賊1:なんだこりゃ?そんな病気で道をぶらつくのは危ねえって知らねえのか?ほら、荷物を運ぶのを手伝ってやるよ。
マルヴァシアン(弱って):お願いだ…放っておいてくれ…
山賊2:どうした、術者さんよ、奪い返してみろよ!
マルヴァシアン:無理だ…弱りすぎている…
突然インゾリアが飛び入り、雷撃を指先から山賊へと放ち、その山賊たちは急いで逃げていく。彼女は着地して、宝箱を拾い上げる。マルヴァシアンは死にそうに倒れこむ。
マルヴァシアン:仮定で、もしも…魔闘士がその場では彼を傷つけず…生命力とマジカを徐々に流失させ、その場では気がつかないが…回復の薬を置いていくほど十分な自信を感じる呪文を相手にかけたとしたら?
インゾリア:彼女は最も不実な魔闘士でしょうね。
マルヴァシアン:そして…仮定で…彼女は、彼が生きて屈辱に耐えているのを楽しむために、倒れた相手を…助けそうか?
インゾリア:私の経験上、仮定で、いいえ。彼女は間抜けではなさそうだし。
インゾリアが宝箱をシルヴェナールへと持ち去る。マルヴァシアンは舞台上で息を引き取る中、幕が下りる。
感謝の印A Token of My Affection
グワエリングが最初にそれを見た。ヒョウだ。その目は頭上で輝く月のように光っていた。その日のうちに囮を設置して、ヒョウが近づいたときに、矢を放ってそれを解放した。
どういうわけか、その獣は私達の企みに気付いていたのだ!あの老いぼれた怪物はきびすを返すと、物陰を睨み付けた。私達は藪の中にしっかり身を隠していたつもりだった。それはうなり声を上げると、黒い風のように全速力で私達に迫ってきた。
グワエリングが矢を放った。矢は雷のように獣の目を射貫いた、だがその獣は立ち止まらなかった!そして獣は私の槍の間合いに入ってくると、私を突き飛ばした。気が付くと手には槍がなく、私は頭上にあった木の中で大の字になっていた。その断末魔はすさまじかった。
グワエリングは剣を使ってその瞳の炎を消した。私は頭蓋骨を持ち帰った。感謝の意を示すために、それで形見を作るつもりだ。
空の狼The Wolf in the Sky
俺が初めて空に狼を見たのは、まだ子供のころだった。
「ただの雲でしょ」少し苛立った様子で母はそう言った。空想にふけるなど、戦士の息子にふさわしくないと思ったのだろう。
「でもしっぽがあったもん!それに牙から血が滴ってたよ!」
「ただの雲でしょ」母は繰り返した。彼女は俺を家の中に追い立てると、自分も中に入って重い木の扉を閉ざし、しっかり閂をかけてしまった。
当時俺はほんの4、5歳だったが、それでも母親の怒りが自分に向けられたものでないことは分かった。彼女はその狼を恐れていたのだ。
それ以来、俺は狼のことを口にしなくなった。もっとも、狼の姿は頻繁に見ていた。空や森の中に。時には目の端に映ることもあった。どこに行こうと、その狼がついてきているのだと分かっていた。母親は怖がったが、俺は相変わらず平気だった。
エボンハート・パクトが結ばれたその日まで、俺は狼のことはひた隠しにした。けれども、我々ノルドがそれぞれの首長から、ダークエルフとそのペットであるトカゲと手を結ぶと告げられたことで事情が変わった。俺は反乱に加わったのだ。
そして、とうとう指導者に刃を向ける謀反人になったことを自覚した俺は、狼の力を借りることに決めた。
新月の夜、俺はかがり火を焚いて狼を呼び出すべく、丘の上に木の枝を積みあげた。それまでに仕留めてきたさまざまな獲物の記念品、パラフィン、脂肪、干したサルビアの葉の束といった品々を焚き木の山に加える。そしていざ焚き木の山に火をつけようとする俺の口から、一度も耳にしたことがない言葉が次々にあふれ出てきて、詠唱となった。
すると、「それ」が現れた。いや、ずっとそこにいたのだ。煙の向こうに、狼は立っていた。いつも以上に本物らしく、その両眼は熾火のように赤かった。
「狼よ!俺はお前の正体を知らない!」俺は叫んで両腕を大きく広げた。「だが、生まれてからずっと、お前は俺のそばにいてくれた。どうか、忌まわしいパクトに対する反乱に加わってほしい!」
狼は尻を落として座り、小首をかしげた。そして空を見あげ、吠えた…いや、笑い声をあげた!
「お前たち定命の者とは愉快なものよ!」と狼は言った。「狼1匹がどうして何かの役に立つなどと思うのだ?さてと、こいつはもう脱ぎ捨てなければ。蚤が湧いてかなわん」
そう言うと、狼はかがり火に飛び込み、炎に包まれた。俺はというと…あんぐりと口をあけ、呆然とその場に立ち尽くしていた。ずっと自分につきまとっていたものが果たして何だったのか、俺にはいまだに分からない。
その晩、俺はかがり火の脇で捕えられた。俺も仲間も(ついでに言うと、仲間の誰一人として狼の姿を見た者もいなければ、声を聞いた者もいなかった)、俺のしたことのせいで明日処刑される運命だ。
この手記が俺の最後の願いを聞き入れてモンクが代筆してくれたものであることを示すため、俺の印を添える:X
古い塔の亡霊Ghosts of the Old Tower
サタカラームの歌姫、ベールをとったアザディエ 著
——尊敬すべき方、どうかお聞き下さい。亡霊が住む塔の物語でございます。
——亡霊が住む塔?本当にあった話か?亡霊が住む塔の話はあまりに多過ぎて、もはや彼らが住まぬ塔はないかのように思えるほどだ。歌姫の物語の泉もついに枯れ果てたか?
——そのようなことはございません。英知をもって治める者よ、どうかご辛抱を。フォールンウェイストの古い塔の物語は、これまでお聞きになったどの物語にも似ておりません。
——では続けよ、雄弁なる者よ。話を聞き終えるまで判断は控えよう。
——英知と同時に辛抱強さまで兼ね備えておられるとは!本当に、その足元にありとあらゆる敬意の印を捧げましょう、尊敬すべき方。
——語の先を聞かせよ、歌姫。ご機嫌取りの言葉は宮廷のおべっか使いの犬どもから散々聞かされている。
——ご命令とあらば。フォールンウェイストの人里離れた場所にある、ある高い山の尾根に、遠い昔から背の高い不格好な塔が立っておりました。レッドガードが牙の生えた人々と戦っていた頃、1人のバーガマの勇士の斥候が、この塔を手に入れた上で、観察者兼哨戒兵としてそこに留まることを命じられたのです。彼の名は三つ傷のアバダマンといいました。
——そして夜になるとそのアバダマンの元に、嘆き悲しむ年頃の女が姿を現したか?それとも遠い昔に亡くなった父親の亡霊が、時宜を得た忠告を携えて現れたか?いや待てよ、分かったぞ。殺された男の霊魂が、復讐を果たすまでは永遠の眠りにつけぬと黄昏時にうめき声を出すのだな。
——いいえ、そのどれも起こりませんでした。しかし亡霊は現れました。しかも奇妙なことに、それは真昼の金色の光の中で起こったのです。こんな風に。三つ傷のアバダマンは、午前の務めを終えていました。その中身は古い塔の上までたくさんの階段を上り、コンパスのあらゆる方角に目を凝らして、見たものを記録すること。ですが大したものは見えませんでした。そこで彼は砂漠へと散歩に出かけました。このアバダマンは考えごとが好きで、考えごとをする時は歩きたがったのです。とりわけこの日はあてもなく歩いているうちに、塔のある尾根の下の乾燥した平地まで降りてきてしまいました。そこで彼の考えごとは目の前の驚くべき光景にさえぎられました。明るい真昼の日差しの下に亡霊の集団が立っていて、差し迫ったできごとが起こるのを待つかのように辺りを見回しているではありませんか。
——面白い。今まで聞いた亡霊話にこんなものはなかったぞ。
——気前の良いお言葉ですが、事実の通りなのです。亡霊は8人で、陽炎が立つような日差しの中でははっきりと感じ取ることが難しくはありましたが、彼らがそこにいることは否定しようがありませんでした。皆若いレッドガードで兵士の鎧を身に付けていましたが、その鎧はアバダマンのものと似ているようでもあり、似ていないようでもありました。彼はその中でも存在感があって、将校のようなたたずまいを持つ1人の亡霊を捕まえました。そのレイスの将校が首をひねってアバダマンと目を合わせたとき、豪胆な斥候は驚いて悲鳴を上げました。
——何を隠そう、私でもそうしたかも知れぬ。
——そうかも知れませぬが、それを疑うことをお許し下さいませ。斥候の叫び声を聞くと、その亡霊はこだまのように繰り返しこう言いました。「ようこそ、斥候よ。胸に見慣れぬ仕掛けをつけておられるが、仲間の兵士とお見受けする。あなたが我々を裏切った者に正義の裁きを下してくださるのか?」
——なるほど!復讐の物語か。言わなかったか?こういう亡霊どもはどれも変わらぬ。
——そのとおりです、有能なお方よ。でも、そうではないとも言えるのです。続けてよろしいですか?
——望むところよ。
——仰せのままに。亡霊の言葉に好奇心を刺激され、返事をしてみようという気になった勇ましいアバダマンはこう言いました。「彼岸より来る霊魂よ、そちらの話は何ひとつ分かりませぬが、もっと詳しく聞かせてもらいたい」「私はフェイダ隊長と申します」と亡霊は言いました。「そしてこれらは裏切りによって殺された部下の兵士達です。裏切り者に正義の裁きを下したいと思っていますが、困ったことに我々は死者でありながらまだ生まれていない。我々を殺した者は人を殺したが、まだ我々に危害を加えていないのです」
——謎かけとは驚いた!それでその斥候は何と答えたのだ?
——彼は言いました。「隊長よ、謎めいた言い方をなさる。私にはよく分かりませぬ。どんな裏切りを受けたか話してくだされば、もっと分かるやも知れませぬ」影のような隊長はうなずいてこう言いました。「そうしましょう。我々はあの古い塔の占拠を命じられました。とは言えその命はまだ下っておりませぬが。我々の知らぬ間に、仲間の1人が我々の敵である侵略者の帝国に恩義を受けておりました。とは言え誰もまだ侵略などしておりませぬが。その者は密かに敵をこちらの防衛線に引き入れ、我々を破滅させたのです。とは言え、まだその出来事は起こっておりませぬが。その裏切り者の名は赤き手のアミルと申します」
——ああ、ようやく分かったぞ。その亡霊は正気を失って、筋の通った話ができぬのだな。
——いいえ。なぜならアバダマンは不意に言葉の意味を理解し、打たれたかのように後ろによろめいたのです。「ああ!」と彼は叫びました。「今すべてが分かったぞ!お前達は死人だが、まだ生まれてはいない。なぜならお前達の生も死も、これから起こるできごとだからだ!まだ起こらぬ裏切りの話をしているが、それは今から何年も先に起こるのだ。嘆かわしき亡霊よ、私の前に現れたのは、私が唯一その裏切り者に正義の裁きを下せるからだな。だが私がその役目を果たすことはない」
——なぜそうなる?早く説明してくれ!
——ああ、我が高官よ、物語というのは川と同じ、流れる方にしか流れませぬ。でもこの物語はもうすぐ終わり。「名誉ある兵士だというのに、その役目は果たさぬと?」と将校の亡霊はうめきました。「一体なぜです?」「なぜなら私のまだ幼い息子の名はアミルといって、生まれつき手に赤いしみがあるのだ。だから去れ、しつこい亡霊どもよ。私はお前達を助けぬ。そしてお前達はその運命から逃れられぬ」そして三つ傷のアバダマンは踵を返し、古い塔への道を昇ってゆきました。
子供の物語Cub Tales
我が兄弟エナク・ドウの10回目の誕生日のために。
兄弟のエザグより。
* * *
どこか遠い昔、人々は森の中に住み、平原で狩りをする生活に満足していました。彼らは子供たちを育て、食事をし、結婚しました。何もかもがうまくいっていました。でも、それはとても簡素な生活でした。人々は時々、2本足の姿を見て、もし空にまで手を伸ばせたら、もっといろいろなことができるはずなのにと思いました。
そうしてある日、年老いた賢いモンクが人々のところにやってきました。自分の名前はアズラーだと彼女は言いました。彼女は人々をずっと観察してきて、贈り物をあげようと決めたのだと言いました。特別な飴だよ、と彼女は言いました。
子供の遊びA Child’s Play
グリーンレディ、グワエリングの未公認伝記より引用
彼女が足を踏み出した場所は花が輪になって育ち、彼女の足跡の輪郭を埋めた。時に彼女は後ろ向きに歩いて、緑のまきひげが開き、その先が水色や黄色や赤の花となって咲くさまを眺めた
「やめなさい」ナウッテは不機嫌に言った。「そんなつまらないことに力を無駄遣いしないの」
グワエリングは一歩踏み出す途中で停止し、首を傾げた
「花のことを考えるのは何でもないもの」そう答えると、また慎重に一歩踏み出し、反抗的にもうひとつ輪を作った
「伯母さんは素晴らしい未来を予言したのに」母は厳しく言った。「私に予感できるのは鞭の一発だけよ」
グワエリングは笑い声を上げ、踊りながら母のもとに行き、改悛の情を示すキスをした。その時ウルソーンが窓から覗いている姿が目に入り、彼女は他のことをすべて忘れた
「ウルソーンと遊んでもいい?」
「行ってらっしゃい」
母の唇から言葉が離れるとほぼ同時にグワエリングは行ってしまった。溜息をついてナウッテは静かにつけくわえた。「許される間は遊ぶといいわ」
施錠された部屋 パート1The Locked Room, Part 1
ポルベルト・リタムリー 著
アースカミュは指導者として、ヤナのような生徒が一番嫌いだった。ヤナは素人でいることの玄人だった。アースカミュは彼の砦で、あらゆる種類の犯罪者を指導していた。一般的な泥棒から知能的な脅迫犯まで、彼の生徒たちはみな野心あふれる若者や子供たちで、錠前破りの技と原理を学び、それを仕事に生かそうという意欲があった。そのため、彼らはより単純明快で簡単な方法を知りたがった。しかし、ヤナのような生徒はいつも例外や発展的な方法、奇抜なやり方を見つけたがり、実践的な技術を重視するアースカミュをいらつかせるのだった。
このヤナというレッドガードの少女はいつも、錠前の前に何時間も座りこみ、針金やピックで突っついてみたり、幾種類ものピンやドライバーをとっかえひっかえしてみたり、普通の犯罪者が見向きもしないような部分を観察することに夢中だった。他の生徒がとっくに実習用の錠前を開けて次の段階に進んでいても、彼女だけはまだ自分の錠前をいじり続けていた。しかし、最終的にはどんな難しい錠前であっても開けてしまうので、そのことが逆にまたアースカミュをうんざりさせた。
「お前は簡単なことを難しくやりすぎなんだ」アースカミュはよく彼女に平手打ちをくらわせ、声を荒げた。「仕事の速さが大事なんだ、技術だけ覚えたって仕方ないだろ。もし、この錠前に合う鍵をお前の目の前に置いてやっても、お前はそれを使おうともしないんだろうな」
ヤナはアースカミュの罵倒にも理性的に耐えていた。何といっても、授業料は先に払ってあったのだ。確かに、巡回の衛兵に追われながらどこかに忍び込むために錠前を破るときなどは速さがものをいうだろう。だが、それは彼女には当てはまらなかった。彼女は純粋に、知識だけを求めていたのだ。
アースカミュはあらゆる方法でヤナに早く作業を進めることを教えようとした。体罰や叱責は驚くほど何の効果もなかった。彼女が錠前を開けるのにかかる時間は新しい錠前に向かうたびにどんどん長くなり、それぞれの錠前の特徴や性格をじっくりと調べなければ気がすまないのだった。そしてとうとう、アースカミュは我慢できなくなった。ある日の午後遅く、ヤナが完ぺきにありふれた種類の錠前の前でぐずぐずしていると、アースカミュは彼女の耳をつかんで砦の中のある部屋へ引っ張っていった。その部屋は他の生徒たちの立ち入りが禁じられている区域にあった。
真ん中に大きな木箱が置かれている以外、部屋には何も無く、扉は入口の一つだけで、窓もなかった。アースカミュは彼女を木箱のほうへ乱暴に押しやり、外から扉を閉めた。鍵のかかる音がはっきりと聞こえた。
「優等生にテストを受けてもらうよ」彼は扉の向こうで笑った。「そこから出られるかな」
ヤナはにっこり笑って、いつものようにゆっくりと錠前をいじり回し、調べはじめた。数分がたったころ、また扉の外でアースカミュの声がした。
「教えといてやるよ、これは速さのテストだ。後ろに木箱があるだろ?その中に、吸血鬼の爺さんが入ってるんだ。何ヶ月もここに閉じ込めてあるから、もう完全に腹ぺこだろうな。あと何分かで日が暮れる。もしそれまでにこの扉を開けられなけりゃ、皮だけになるまで血を吸われるぞ」
ヤナは一瞬、アースカミュが冗談を言っているのかと考えた。彼は極悪人だが、いくらなんでも指導のために生徒を殺そうとするだろうか?しかし、次の瞬間木箱の中から衣ずれの音が聞こえたので、彼女はこれが冗談ではないと理解した。彼女はいつもの試行錯誤をとばして、針金を錠前につっこみ、釘を圧力板に突き立て、扉を押し開けた。
アースカミュが廊下の向こうで意地悪く笑った。「さっさと仕事を終わらせることの大事さがわかっただろ」
ヤナは涙をこらえながら、アースカミュの砦を飛び出した。アースカミュは、彼女が二度と彼の砦へ戻らないだろうと思っていた。そして、最後に非常に重要なことを教えてやったのだとも。次の朝、予想に反してヤナが砦に戻って来たとき、彼は驚きを顔には表さなかったが、内心は腹立たしさでいっぱいだった。
「そんなに長居はしません」と、彼女は静かに語った。「でも、新しい種類の錠前を発明したんです。それで、先生の意見を聞けたらと思って」
アースカミュは肩をすくめ、その錠前を見せるように促した。
「これを、あの吸血鬼の部屋に取り付けてみてもいいでしょうか。実際の錠前として使えるかどうか見てもらいたいので」
アースカミュは訝しく思ったが、このやっかいな少女とこれ以上関わらなくてすむと思うと気分がよく、最後なのだから好きなようにやらせてやろうという気持ちになっていた。彼はヤナにあの部屋へ入る許可を与えた。ヤナは朝から午後遅くまでかかって、吸血鬼が眠っている部屋で古い錠前をはずし、彼女の新しい錠前を取り付けた。そして、彼女の元・指導者に錠前を見るように頼んだ。
施錠された部屋 パート2The Locked Room, Part 2
ポルベルト・リタムリー 著
アースカミュは訝しく思ったが、このやっかいな少女とこれ以上関わらなくてすむと思うと気分がよく、最後なのだから好きなようにやらせてやろうという気持ちになっていた。彼はヤナにあの部屋へ入る許可を与えた。ヤナは朝から午後遅くまでかかって、吸血鬼が眠っている部屋で古い錠前をはずし、彼女の新しい錠前を取り付けた。そして、彼女の元・指導者に錠前を見るように頼んだ。
彼は専門家としてその錠前を調べたが、目新しい特徴はほとんどなさそうだった。
「これは、世界で最初の、そして唯一の破れない錠前なんです」と、ヤナが説明した。「正しい鍵が無ければ絶対に開きません」
アースカミュは嘲笑し、ヤナに自分を部屋に閉じ込めるように言った。扉が閉まり、鍵のかけられる音がして、彼は仕事にとりかかった。錠前は思ったよりも開けにくい構造になっており、彼はうろたえた。知っている全ての方法を試したが開けられず、どうやら、あの憎らしい生徒のようにゆっくり時間をかけて錠前全体を徹底的に調べなければいけないらしかった。
「そろそろ行かなくちゃ」と、ヤナが扉の向こうから言った。「行って、街の衛兵をこの砦につれて来ます。ここの決まりに反することになるけど、腹ぺこの吸血鬼が逃げ出したら村の人たちにも危険が及びますから。もうすぐ暗くなるし、もし先生が錠前を破れなくても、吸血鬼のほうは体面なんか気にせず鍵を使ってそこから出るでしょうし。覚えてますか?「もし目の前に鍵を置いても、それを使おうともしないだろうな」と、言われましたよね」
「待て!」と、アースカミュは叫んだ。「俺は鍵を使うぞ!どこにあるんだ?鍵を渡すのを忘れてるぞ!」
しかし、返事はなかった。扉の向こうで、廊下を去ってゆく足音だけが聞こえた。アースカミュは必死に錠前に取り組んだが、恐怖のために手が震えた。部屋に窓がないので、時間がわからなかった。何分ぐらいたったのだろうか、それとも何時間?わかっているのは、吸血鬼が日暮れと同時に起きてくるだろうということだけだった。
アースカミュが狂乱状態でいたるところを捻ったり叩いたりしているうちに、道具が役に立たなくなった。針金が鍵穴に入ったまま折れてしまった。まるで、彼の生徒がやるような失敗だった。アースカミュは叫びながら扉を叩いたが、誰にも聞こえるはずはなかった。もう一度叫ぼうと息を吸い込んだ瞬間、後ろで木箱がきしみながら開く音がはっきりと聞こえた。
吸血鬼の老人は飢えて正気を失った目で熟練の錠前師を見すえ、狂ったように彼に飛びかかった。アースカミュが死ぬ直前、彼は鍵のありかを知った。それは鎖につけられ、吸血鬼が眠っている間にその首にかけられていたのだった。
湿地を照らす光A Light on the Moor
ある夜、雨で水浸しになったグレナンブラの沼地に続く街路を歩く巡礼者が霧中にランプを見た。
見つめようとして足を止めた彼は「おや」と口にし、風変りな白い帽子を押し上げ視界を確保して「哀れな旅人が道に迷った!」と言った。
「おーい、そこの人!」と大声を上げた彼は「道はここだ!」と叫んだ。
返事がないとはいえ仲間のエルフを沼地の慈悲に置き去りにはできず、巡礼者は己の道から外れて、彼と光の間にある悪臭を放つ沼へと歩んでいった。黒い汚泥をバシャバシャと音を立ててブーツが進み、前方の霧の中で、微かな光はまず見分けられなかった。
己の危険はほとんど考えず、挫けず前へ進み続けた。「ここなら間違いなく聞こえるだろう」と考えてもう一度大声を上げた。
「おーい、良き友人よ!道はこっちだ!」
やはり返事はないので周りを見渡してみた。見えるのは暗がりの霧のみ。馬も荷車も残してきた場所に確認できなかった。己の灯光の中で身が震え、絶望的に道に迷ってしまった彼は、街道へ戻れるのだろうかと思いを巡らした。
一人でさまようよりも二人の方がうまくいくと決めて、腰まで及ぶ泥炭や悪臭を放つ水に浸かりながらも、彼は光を目指して進み続けた。
ブーツが一つずつ沼地にさらわれた。吸い込む穴に深く埋り、通った道には跡がついた。無益に感じたが、行けるところまで進み続けた。
雑木林から現れた木の枝にぶら下がる小さなガラス製のランプを見たのはそのときだった。持ち主の気配を探ると、地面に捨て置かれているつば広帽を見た。その場で考え込んでいると、小さなランプで明るい黄色の炎がゆらぎ、そして消えた。
肩まで達する水の中で幸せそうに動く己のランプに目を向け、彼は一歩踏み出したが、動けなかった。確かに腰がほとんど動かせず、はまったぬかるみはあまりにもどろっとしていた。
空を見て上にある木の枝を掴もうと手を伸ばしたが、届かなかった。
そして彼は暗闇で濁水が喉、口、そして風変りな帽子を飲み込むまでそこに立っていた。最後の呼吸が気泡となって泥から湧き上がり、それが巡礼者の最期となった。
ある夜、雨で水浸しになったグレナンブラの沼地に続く街路を歩く商人が霧中にランプを見た。
見つめようとして足を止めた彼は「おや」と口にし、風変りな白い帽子を押し上げ視界を確保して「哀れな旅人が道に迷った!」と言った。
狩人の真実、パート1The Truth of the Hunter, Pt. 1
セリエルは高く生い茂った草に頭を低くしてゆっくりと広大な林を移動した。林を見てマラバル・トールの絶壁を登ったときのことを思い出した。密林の一帯からは、広々した空を見ることができなかった。双子の月と星に思いをはせた者達が最高峰の絶壁で見たのは、避難所の上のみだった。
彼女は林の外れで雄ジカに気づいた。イチジクとベリーを食べていた。彼女が見た中では一番長い枝角を生やしていた。
セリエルは矢を準備した。弓を引いて矢をつがえた。息を殺し、3つ数えて矢を放つ。そして彼女は弓を射た。
雄ジカは肝を冷やした。弓は音を立てて大気を進み、最も高い草の葉を切り裂いた。雄ジカは駆け出した。雄ジカが草を食べていた背後の木に矢が突き刺さった。
セリエルは林へ駆け出した。獲物の姿を見失ってしまったが、小鼻は真っ赤になっていた。つんとする臭いが近くの断崖から漂ってきた。
セリエルは崖へ向かい、登り始めた。
狩人の真実、パート2The Truth of the Hunter, Pt. 2
セリエルは慎重に岩から岩へと手を動かした。素早く雄ジカを見つけなければならないと分かっていた。頂上までやってくると、獲物を見つけて逃げ道を遮った。
彼女は草の根を掴んで、次の露出部に向けて身体を引き上げようとするが、自重に負けて落ちてしまった。落下する中でセリエルは狩猟用ナイフを掴み、土壁に突き刺した。
ナイフは落下速度を緩めたが、十分ではなかった。突き出た岩に身体を強く打ち、多少跳ね返って絶壁に通じる小さな裂け目に滑り落そうになった。茫然とするセリエルは血に染まった手を尻で拭った。時間が経ちすぎてしまった。雄ジカには完全に逃げられてしまった。
セリエルは怒りでうなり、岩につばを吐いた。慎重に立ち直るともう一度登り始めたのだった。一掴み、一掴みと彼女は進み、常に空を見ていた。彼女が通った絶壁は間もなく血の手形の跡が残った。
ついに絶壁の頂上へ辿り着き、崩れ落ちて苦しさに息をのんだ。横向きになると小さな苦笑いが漏れた。そしての茂みの中に対の黄色い目を見つけた。20歩足らずのところだ。
セリエルは狼から決して目をそらさずに起き上がった。脇へ跳躍してナイフを引き抜き、挑戦的なうなりを発する。容易い獲物にはならない。
狼は疾走し歯をむき出しにしたが、躊躇した。彼女はためらわなかった。ナイフを投げつけたのだ。刀身が狼の眉間に叩きつけられた。狼は力なく地面に倒れた。
セリエルは息をついた。狼からナイフを引いて山林を見つめ、獲物の気配を探る。東に動きが。枝角だった。まだ捕まえられる。
彼女は森林へ駆け出した。
狩人の真実、パート3The Truth of the Hunter, Pt. 3
セリエルは身をかがめて山林を移動した。獲物として狙う雄ジカの足跡を探した。数分、いや数時間?彼女には分からなかった。もう追跡しか残されていなかった。
セリエルが小川を見つけたとき、自分がどんなに疲れているか初めて気が付いた。先ほどの一匹狼との戦いは、思った以上に彼女を消耗させた。冷たい水に手をつけて飲み始めた。しばらくの間目をつむった。
何度かしばらくすすった後、彼女はもう一度目を見開いた。何時間も追跡した雄ジカが5歩離れたところで、まったく同じ小川で水飲みをしている。セリエルは凍りついた。
雄ジカは一瞬セリエルを見つめたようだった。そして空へ向かって立ち上がり大地へひづめをたたきつけた。
セリエルは後方へ跳び下がった。弓を引いて矢をつがえた。雄ジカはもう一度立ち上がった。セリエルは息をひそめた。雄ジカは彼女に目を向けたまま跳躍してきた。セリエルは数えた。1、2、3——
雄ジカはひづめを下げ、踵を返した。セリエルはその後ろに3匹の小さな雄ジカを見た。動くことはできなかった。今度は雄ジカが彼女に向かって静かに歩き、弓をつついて押しのけた。
躊躇しつつもセリエルは手を差し出した。雄ジカは彼女の手を優しく舐めた。そして鼻を鳴らし、山林へと歩いて引き返した。小さな雄ジカ達は後を追って行った。セリエルはそうしなかった。
*****
彼女は絶壁の頂へと戻った。狼は同じところにいて、ハイエナには食べられていなかった。彼女は皮を剥いで肉を収穫し、荷物に詰め込んだ。そうして長い家路についたのだった。
祝福の短剣The Blessed Dagger
昔、一人の乙女がレキに導きを求めて祈った
「霊剣の祝福された聖者よ」乙女は言った「どうか示してください!母の命に従って結婚するべきでしょうか?それとも拒否するべきでしょうか?」
未来の夫はかなり年上の男で、前妻を殺してうまく隠蔽したと言われるが、証拠はない。それでも、近隣の街での名声は非常に高く、花嫁の価格の交渉をあえて拒む者は誰もいなかった
このザリネーという名の乙女は、一昼夜聖堂でひざまずいて祈ってから、村に戻った。返答は得られず、結婚式の日が近づくと、乙女は絶望した
結婚式の前夜、ザリネーは漁をして、海に網を投げ入れ引いている夢を見た。網を船に引き込むたびに、魚の鱗ではない銀の光を見た。3回目に網を引いた時、銀の光を調べてみると、硬い木でできた曲がった持ち手のついた、小さな短剣だと分かった
ザリネーが目を覚ますと、枕の下によく似た刃物があることが分かった。眠りについた時にはなかったものだった
それから、ザリネーの夫は新しい花嫁を前妻のように簡単に捨てられないと知った。ザリネーが剣を見せてレキへの祈りのことを話した時、彼女が聖人に守られていると分かった
二人は長く一緒に暮らし、夫はザリネーを大事にした。いつもザリネーが持っている祝福の短剣のことを心に留めながら
純潔泥棒Thief of Virtue
これから「純潔泥棒」の話をしよう。ハンマーフェルのサッチという街にたいそう裕福な男爵が暮らしていた。男爵は珍しいコインの収集家として有名だった。男爵夫人のベロニクは夫の趣味などまったくもってくだらないと断じていたが、男爵の富がもたらす生活は気に入っていた。
ラビウス・テリヌスは名うての泥棒だった。伝説の盗賊ギルドの大盗賊であると豪語していたものの、それは大見得を切っていたにすぎなかった。世に知られる唯一の盗賊ギルドは450年前に滅びていたのだから。
ラビウスは思い立った。男爵は富を分け与えるべきなんだ、とりわけこの俺と。ある晩、この狡猾な盗っ人は男爵の居城に忍び込み、「ひと仕事」を働くことにした。
その城の外壁はあまりに高く、とうていよじ登れないことで知られていた。ラビウスは機転をきかして「貫通の弓矢」を使い、銃眼のついた胸壁のてっぺんにロープを張った。まんまと胸壁をよじ登ったあとは、男爵の衛兵をやり過ごさなくてはならなかった。銃眼の陰に入って身を隠しながら、誰にも気づかれずにずんずん進んでいった。
ラビウスほど腕のいい泥棒にとっては、砦に入ることなど朝飯前だった。が、男爵の私室の扉は13本ものピンのついた意地の悪い鍵で守られていた。ラビウスはたった9本の開錠用ツールでこの扉を破ってみせ、フォークとわずかな糸と革製の酒袋だけでもって、男爵のコインコレクションを防護する7つの罠を外してみせた。彼はまさしく一流の泥棒であったのだ。
首尾よくコインをせしめると、ラビウスはその場をずらかろうとした。が、退路はふさがれていた。扉が開いていることに男爵が気づき、衛兵をたたき起こして城内をしらみつぶしに探させていたのだ。ラビウスは、追っ手の衛兵の一歩先を行きながら、城の奥へ奥へと逃げていった。
ラビウスが脱出するには、ベロニク男爵夫人の寝室を通り抜ける以外に道はなかった。寝室に入ると、男爵夫人がベッドを作っていた。ここでひとつ言っておきたいのだが、ラビウスは男ぶりの良さで、男爵夫人は器量の悪さで知られていた。両者のどちらも、たちまちこの事実に気づかされた。
「私の純潔を奪いにきたのですか?」と、男爵夫人は震えながら訊いた。
「いいえ、マダム」と、ラビウスは機転を利かせて言った。「あなたの純潔のような繊細な花を「奪おう」だなんて、あまりにがさつというもの」
「主人の大切なコインを盗み出してきたのね」
ラビウスは穴が開くほど男爵夫人の瞳を見つめ、この夜を生きて脱するための唯一の道を見てとった。ふたつの犠牲が求められそうだった。
「このコインもことのほか高価なのでしょうが、お金に換えがたい秘宝を見つけてしまったようです」と、ラビウスはすらすらと言った。「教えてください、美しき人よ。どうしてご主人は、かように安っぽいコインのために容赦ないワナをいくつも備えておきながら、美しい妻の部屋の扉には簡単な鍵をひとつしかつけないのでしょうか?」
「主人は大切なものしか守らないから」と、ベロニクは怒りもあらわに答えた。
「私なら全財産をはたいてでも、あなたの輝きに浴せる一瞬を求めるでしょう」
そう言って、ラビウスは苦労して盗んだコインを床に置いた。男爵夫人が彼の腕にしなだれかかってきた。彼女の私室を調べさせてほしいと衛兵隊長が告げると、彼女はラビウスを巧みにかくまった。床のコインをひっくり返し、泥棒が窓から逃げるときに落としたんだわ、と訴えた。
こうして最初の犠牲がなされ、ラビウスはふたつめの犠牲を果たすべく勇を鼓した。その晩、彼は男爵夫人の純潔を盗んだのだ。何度も何度もそれを盗み、夜が明けそうになるまで勢いは衰えなかった。心地よい疲労感を感じながら、ラビウスは朝ぼらけの中へと逃げ出したのである。
焦げたページSinged Page
小さいブロッゴは寒さが大嫌いだった。暑さが大嫌いだった。暖かく晴れた日すらも好まなかった。彼は奇妙な小さいノルドだった、だがそれこそが小さいブロッゴを英雄にした
冬の終わりのある日、雪が強く勢いよく降っていた時
象牙の王:英雄の誕生、1巻The Ivory Lord: A Hero Born, V. 1
その兵士は息を殺して待ち受けていた。拳が白くなるほど、剣の柄をきつく握りしめている。しんがりに立ち、攻撃の機をうかがっている彼の利き腕は落ち着きなく震えていた。もういつアレッシアの偵察隊が通りかかってもおかしくない。しかし、彼は心のなかでこう問わずにいられなかった。いったい自分は何に首を突っ込んでしまったんだ?
彼は名をエリック・ディレインといった。そして、どこでどう間違ってこんな役回りを演じる羽目になったのか、分かってさえいなかった。エリックは宿屋の息子で、成人したばかり。彼の家系図には馬飼い、農場の働き手、そして彼の父親のような料理人といった人々が文字通り鈴なりになっていた。彼の体内を流れる戦士の血の量は、彼の両腕と背中の筋肉の量と同じだった。つまり、ほとんど無いに等しい。にもかかわらず、彼は貧弱な体にぶかぶかの防具を身に着け、使いかたさえろくに知らない剣を握り、こうしてここに立っているのだった。
エリックは、できることならこう言いたかった。復讐を果たすため、または名誉を手に入れるために民兵に加わったのだと。アレッシアの襲撃で両親を亡くしたとか、生涯の恋人を連れ去られ、邪悪なアレッシアの強制労働収容所に送られたとか、その手の動機が欲しかった。八大神にかけて、とにかく身内がアレッシアに危害を加えられたという内容であれば、なんでもよかった。
しかし、エリックの家族は息災だ。福々しく太った両親はハイロックに点在する小さな街の1つで宿屋を営み、満ち足りた暮らしを送っている。では「生涯の恋人」は?そんなものいやしない。エリックは乙女の抱擁を受けたこともなければ、メイドのキスを味わったこともなかった。それなら、なぜアレッシアと戦いたいと思ったのか。たしかに、アレッシアの狼藉ぶりは耳にしていた。しかし、エリックにとって、それは噂とほのめかしの域を出なかった。彼は安全な場所で安穏と暮らしてきたのだ。
いや、エリックが勇猛なカジートの乙女キシュナやハンサムなアイレイドの騎士カリンデンと並んで立っている理由は、さほど高尚なものではなかった。彼を今この場所に導いたのは、単なるはずみと偶然だったのだ。エリックは以前から夜な夜な森にこっそり出かけては、武術の練習に励んでいた。といっても、街の衛兵隊の訓練を、見よう見まねで再現しているだけだが。戦いかたを見につけたいとは思ったものの、練習しているところを人に見られたくなかったからだ。彼は所詮料理人の息子に過ぎない。武術の練習なんぞに励んでいるところを誰かに見られたら、からかわれるのが落ちだ。それで、エリックは夜な夜な錆びの浮いた剣とサイズの合わない防具をひっつかんでは、練習のために森に入っていったのだった。
だが、今夜は違う。もう練習はない。
いつものように、よく知っている壁の穴を目指して裏通りを走っていたエリックは、角を曲がったところで、彼らに出くわしたのだ。エリックは息を飲んだ。さまざまな文化圏の男女から成る一団が、ひとかたまりになって、ひそひそと囁きを交わしている。彼らはおそろいの立派な装束に身を包み、それらに輪をかけて立派な武器を携えていた。
エリックは用心深く彼らに近づいていった。しかし、忍び足の技能も優美な身のこなしもろくすっぽ持ち合わせていない彼のことだ。足がもつれてバランスを崩し、バシャッという派手な音を立てて水たまりに突っ伏してしまった。戦士の一団はいっせいに振り返り、険しい目をして武器の鞘を払った。ところが、エリックのいでたちと武器を見て、有志と勘違いしてくれた。怖くて否定することもできず、エリックは彼らの仲間として迎え入れられたのだった。
要するに、単なる誤解だった。後のエリックなら、それを運命と呼んだかもしれない。
しかし、今夜は?今夜はエリック・ディレインが死すべき夜だった。そしてそのことによって、彼を取り巻く世界は永遠に変わってしまうのである。
象牙の王:英雄の誕生、2巻The Ivory Lord: A Hero Born, V. 2
鎧のガチャガチャいう音と、次第に近づいてくる足音が、暗い街路にこだましている。行軍している兵たちが、誰に聞かれようが構わないと思っていることは明らかだ。それどころか、必要以上に大きな音を立てようとしているようにさえ聞こえる。
エリック・ディレインは目を閉じて耳を澄ました。近づいてくる軍靴の数を読もうとしてみる。もっとも、数の問題じゃない。やってくるアレッシアが10人だろうが2人だろうが、エリックには結末が予想できた。「俺は頭を剣で貫かれて一巻の終わりだ」と彼は思った。
肩に誰かの手が触れるのを感じてエリックは目をあけた。黄金色の長髪をなびかせたアイレイドの騎士カリンデンが、安心させるようにエリックの肩をぎゅっとつかんで言った。「俺から離れないようにしろ」。
うなずきながら、エリックは気持ちが落ち着いてくるのを感じた。アイレイドの騎士にはエリックの心中がお見通しのようだった。アレッシア兵の足音がだんだん近づき、大きくなってきていなければ、エリックはその考えにもっと安心感を覚えていただろう。
エリックを挟んでカリンデンと反対側に立つカジートの戦士キシュナは、2つの剣を鞘から抜きはらって一方を掲げた。それが彼女のトレードマークなのだ。路地にいるその他の傭兵たちは体を左右に揺すり、攻撃命令が下るのを待っている。彼らの目は、興奮と恐れでぎらぎらと輝いていた。
足音はどんどん大きくなってくる。そして…静寂が訪れた。
エリックは驚いて周囲を見まわした。いまだ姿の見えない行軍はなぜ止まったのだろう?傭兵たちもエリック同様、困惑しているようだった。ただ、キシュナとカリンデンだけは違った。キシュナが掲げた剣は、微動だにしていない。
エリックには後になって分かったことだが、次に起きたことは、他人を剣や短剣で突き刺すことにためらいを覚えない連中を雇った時、通常起こることだった。傭兵たちはしびれを切らし、早く誰かの血をぶちまけて稼ぎたいという気持ちを抑えられなくなっていった。たいていの場合、こうした規律の乱れは、彼らのような雇われ兵たちを一段と速やかに破滅へと導く。そしてあいにく、最初に抑えがきかなくなったのはエリックのいるグループだった。
「奴らをぶっ殺せ!」
エリックの左後ろで、誰かが雄叫びをあげた。傭兵たちはだしぬけに駆けだした。それは戦闘隊形というよりも、押し合いへし合いする群衆のようだった。武器を振りかざして突進してゆく傭兵たちに、エリックは押しのけられた。
「あの馬鹿どもは何をしてるんだ?」身を潜めていた路地から傭兵たちが飛び出していくのを見て、キシュナは誰にともなく問いただした。やがて彼女はやれやれというようにかぶりを振ると、二刀流の剣を構えて彼らのあとを追った。
カリンデンがエリックのほうを向いた。「俺の言ったことを忘れるな」。そう言うと、エルフは背中に担いだ大剣の鞘を払い、戦いに加わるべく走っていった。
エリックはパニックに襲われるのを感じ、凍りついたようにその場から動けなくなった。武器や盾が打ち合わされる音。戦う者たちの雄叫び。苦悶の叫び。すべての音が、エリックの耳にはくぐもって聞こえた。両脚は丸石を敷き詰めた街路に根を生やしたように動かない。とうとう戦火が目の前までやってきたというのに、エリックはそれをただ眺めることしかできなかった。
永遠とも思えるような数秒が経ってから、エリックはようやく身動きできるようになった。片脚を上げ、それをもう片方の脚の前方に下ろす。ゆっくりと、慎重に、エリックはこの動きを繰り返して路地の出口までたどりついた。そこで深呼吸してから、恐る恐る壁から顔を覗かせる。
象牙の王:英雄の誕生、3巻The Ivory Lord: A Hero Born, V. 3
見渡すかぎり、どこを見ても白い鎧とアレッシアの旗しかない。傭兵たちが攻撃を仕掛けたのは偵察隊などではなく、アレッシアの本隊だったのだ。
傭兵たちは懸命に戦ったが、いかんせん彼らは訓練された兵ではない。鎧に身を固めた兵士たちの壁に、酒場でケンカをする酔っ払いのようにぶつかっていっては、1人また1人と簡単に斬り伏せられた。アレッシア兵は攻撃を淡々と受けとめ、かわし、愚かな敵を嘲ってから斬り伏せた。
まともに渡り合っているように見えるのは、傭兵部隊のなかでカリンデンとキシュナの2人だけだった。アイレイド騎士カリンデンの振るう巨大な両手持ちの剣は、鎧も肉も骨も難なく切り裂いてゆく。一方、カジートの戦士キシュナが振るう2つの刃は、エキゾチックな死の舞踏を踊る彼女の周りで旋回していた。
エリックは目の前で繰り広げられる戦いを畏怖の念に駆られながら見つめた。自分などが加勢したところで、錆びた剣でアレッシア兵の盾にかすり傷をつけることすらできないうちに斬り伏せられてしまうのが落ちだ。しかし、だからといってもし身をひるがえして逃げ出せば、万一傭兵の誰かが生き延びた場合、臆病者のニセ傭兵として記憶され、最悪追っ手をかけられる可能性さえある。こうした考えがぐるぐると頭のなかで渦巻き、ぶつかり合う間、エリックは迷いと恐怖から凍りついたようにその場に立ち尽くしていた。
しかし、鋭い剣の切っ先が目の前の空気を切り裂き、顔面に迫ってくることほど頭をはっきりさせてくれるものはない。エリックはすんでのところで身をかわしたが、アレッシア兵はすぐさま追い打ちをかけ、エリックを地面に打ち転がした。エリックが握りしめていた錆ついた剣は、仰向けに倒れた拍子に手から飛んでいった。兜はそれまでエリックがそばに立っていた壁にぶつかり、彼の視界はしばらくのあいだ真っ暗になった。
次にエリックが気づいたのは、カリンデンが傍らに立ち、自分を起きあがらせてくれたことだった。通りのあちこちにアレッシア兵の骸が転がっている。アイレイドの騎士は何も言わず、くるりと背を向けて戦いの渦中へと戻っていった。
エリックにはもう充分だった。これ以上は耐えられない。彼は必死で逃げ道を探した。生き残っている傭兵は片手で数えることができたが、アレッシアの軍勢はそれこそ怒涛のようで、横の連なりと奥行きはダガーフォールの海岸に打ち寄せる波ほどもあった。その刹那、エリックは悟った——自分は死にたくないのだと。彼は方角を定め、走り出した。一番激しい戦闘が行われているそのすぐ横を通り過ぎるルートだ。
半ば脚が勝手に動き、戦っている兵士たちの脇をすり抜けざま、エリックは地面に転がるおびただしい数の死体の1つの近くにあった剣に手を伸ばし、それをつかみとった。自分でも意外な底力を発揮して、彼は足を速めた。とにかく、一番近くの開いている戸口までたどりつくか、または次の角を曲がることだけに意識を集中させる。戦闘の現場から離れさえすれば、裏通りに姿をくらませる自信があった。もうすぐだ。やれるとも。
エリックが角を曲がり、脱出に成功したと思ったその刹那、体の前で構えていた剣が何か柔らかく湿ったものを刺し貫いた。見れば、アレッシアの将校の、エリックに負けず劣らず驚いた顔がそこにあった。その将校はいくつも勲章をつけていたが、どれ一つとして当人の命を救ってはくれなかったことになる。エリックの剣は将校の鎧の脇の隙間から侵入し、肋骨の間を通って肺に穴を開けていた。将校はあえぐと白目をむき、膝からくずおれた。
地面に突っ伏した将校の手から象牙色の角笛がこぼれ、そのまま転がってエリックの右足の傍らでとまった。エリックはそれをしばらく見つめてから、拾ってベルトに挿した。何に使おうという目的があったわけでもないのだが、そのときはそうするのが良い考えのように思えたのだ。
エリックの背中に矢が突き刺さったのはそのときだった。命中した箇所から痛みが放射状に広がり、彼は前方によろめいた。早くも視界が霞みはじめる。カジートとエルフが走り寄ってくるのが見えた。その後ろから、アレッシアの兵たちが追いすがってくる。エリックはなんとか息をしようと試みたが、痛みがいっそう酷くなるだけだった。
やがて一切合財がおぼろになり、ついには何一つ見えなくなった。
情熱的なアルゴニアンの吟遊詩人 第1巻The Sultry Argonian Bard, Vol. 1
エルヤ・エルデイン 著
第6幕 第2場 続き
クルーンテイル:奥様、ご要望にはお応えいたしかねます!
エルヤ・エルデイン:あら、あなたには速すぎて?
クルーンテイル:楽器を傷めてしまうのではないかと。
エルヤ・エルデイン:でもあなたは楽器の扱いがとても上手そうに見えてよ。
クルーンテイル:おだてないでくださいまし。
エルヤ・エルデイン:本当よ。ずいぶん大きくて立派な楽器ね。触っても良いかしら?
クルーンテイル:お願いですからおやめください!人目につく場所でそのようなことを、宿屋の主人は許すはずがありません。
エルヤ・エルデイン:では人目につかない場所で披露してはもらえない?できれば宿屋の騒音が届かない、お互いにあなたの非凡な才能を堪能できるような場所で。
クルーンテイル:まさか奥様のお部屋にご一緒するようにと仰るのですか?
エルヤ・エルデイン:そのとおりよ。可愛い人。正にそう言っているの。
第6幕 第2場 了
森の伝説Legends of the Forest
グラム修道女 著
アイスウインド・ピークスの呪われた深い森には、奇妙な物語や、さらに奇妙な生物が長い間存在してきた。我々はこれらの物語をこの本にまとめ、これまで真夜中にノルドのキャンプファイアを囲み、口承で伝えられてきたことを記録した。
森の中の声
小さいブロッゴは大きなノルドではなかった。速いノルドでもないし、強いノルドでさえなかった。しかしブロッゴは多くのノルドにない性質を持っていることで、自分の短所を補っていた。ブロッゴは頭が良かったのだ。何をするにも時間をかけてよく考え、一族の大抵の者が激しい感情に左右される中で、それに屈することを拒んだ。そしてそれは、結果的に彼の命を救うことになった。
小さいブロッゴはある日、一緒にいた仲間とはぐれてしまった。彼は知らない内に、呪われた森で一人、道に迷ったのだ。だんだん怖く、空腹になりながらふらふらとさまようブロッゴは、森の中の空地によろめき入った。少し休むことにした彼は、午後の太陽を浴びた比較的平面で滑らかな石の上で大の字になった。ブロッゴが深い眠りにつくのに、長くはかからなかった。
その後目覚めて目を開けると、森に夜が訪れているのに気がついた。何かが彼を眠りから呼び戻したのだ。それは、音だった。その音は若い女のささやき声と、くすくすという笑い声のようだった。誰か、あるいは何かが笑ったのは確かだったが、真上にある上弦の月の青白い輝きに照らし出された彼は、空地に一人きりのようだった。ブロッゴが空地の向こうの暗闇を見ようと一生懸命になっている時、ささやき声がまた聞こえ始めた。
「ああ、彼のかわいい根を見て!」森の中の声は言った。
「それにあの黄金色の葉!」もう1人が言った。
「あら、彼は私のものよ。私が先に彼を見たんだから」
「あなたは前回手に入れたじゃない!今回は私よ!」
大きなゴラップルの木の近くにある空地の外れに幽霊のような物影が2体現れた時、ブロッゴは気絶しそうになった。森の霊魂2人が彼のことで口論していたのだ。定命の者と霊魂が交わるべきでないことは知っていたが、彼にはこの状況を恐がるべきか光栄に思うべきかわからなかった。暗闇の中で森を走り抜けても、そこまで遠くへ行けるとは思わなかった。霊魂と戦うこともできないと確信したブロッゴに残された選択肢は1つだった。
「やあ」と、ブロッゴーは霊魂に声をかけた。「ゲームをしないか?」
霊魂は最初、恥ずかしがっているように見え、ブロッゴを少し怖がってさえいるようだった。2人は定命の者が直接話しかけてくることに慣れてはいなかったが、時に姿を見せた状態で、そして時に暗闇で姿を消した声として、徐々にそのノルドとふれ合い始めた。ブロッゴはカードとサイコロ、そして粘土のチップを使ったすばらしいゲームの説明をした。さらに言えば、それは2人の霊魂も、そしてどんなノルドも聞いたことがないようなゲームだった。ブロッゴはでまかせを話していたのだ。
すぐにブロッゴに身を寄せて近づいてきた森の霊魂は、この小さなノルドの言う一語一句を熱心に聞いた。最後には声を揃えて、「ゲームをしたいわ!」と叫んだ。
「残念なことに」ブロッゴはとてもがっかりした様子で、「カードもサイコロも、泥のチップも持っていないんだ。旅仲間のいる荷馬車に置いてきてしまってね。それに、荷馬車がどこにあるかわからないんだ」と言った。
「問題ないわ!」1人目の霊魂が言った。
「荷馬車がどこへ行ったか案内してあげる!」
そして、霊魂たちはそのとおりに案内した。もちろん、彼女たちはブロッゴが仲間たちと再会し、自分たちを追い払ったときは不満そうだった。荷馬車が亡霊の森から転がり出て行くと同時に、ブロッゴは日記を出して書き始めた。
「何をしているんだ?」旅仲間の1人が彼に聞いた。
「今夜、最高のゲームのアイデアが思いついたんだ。記憶が鮮明なうちに書き留めておきたくてね」
真のバランスThe True Balance
「アワスに知らせないと。コスリンギがすぐそこまで!」
2人のアルゴニアンが視線を交わす。その黒い目が動くと、陰の中でほんの少し光って見えた。
「もう行く」と興奮気味に言うと、サナックスは濁った水の中へ消えていった。
ゆっくりと彼女の後を追いかけるジューネイ。沼地の畔は燃えており、アルゴニアンの目しか見通せないほどの濃い煙が上がっていた。
気のせいではなかった。振られた斧がキラリと光ったのだ。息の詰まるような声を耳にしたが、その後は何も聞こえない。不格好な乾燥肌がこんなに静かに動けるなんて誰が思っただろうか?
ジューネイは誓いを立て、ザンミーアへと続く泥道を見つめた。先は長く危険に満ちていたが、彼はアワスに知らせる必要があった。
ジューネイをその道に追いやった奴らは、武器を振り回しながらもほとんど音を立てない。ザンミーアの石の建造物が視界に入ってきた時、彼は尻尾を掴まれ、地面に引き倒された。
彼を殺そうと汚れた斧を持ち上げていたのはコスリンギの悪漢であった。彼は叫んだ。その時だった。コスリンギのナイフが飛んできて悪漢の喉元に突き刺さったのだ。
泥の中から現れたのはアワスだった。彼女はナイフを回収するとジューネイに手を差し伸べた。
「どうしてここに?」ジューネイは息を飲んで、コスリンギのナイフに注意を向けた。
「ヒストの夢で得た教えよ」と小声で言うとアワスはさらに続けた。「敵を真に理解するには、敵の武器を使えって」
アワスをじっと見つめたジューネイは、死んだコスリンギの斧を手にする。そして彼らは足早にザンミーアへ向かうのであった。
聖なる目撃者 パート1Sacred Witness, Part 1
エンリック・ミルネス 著
私は今まで、公爵夫人や高級娼婦、魔女、戦火の中を生き抜く淑女や平和を謳歌する遊女、そのような女たちをたくさん見てきた。しかし、夜母のような女性には会ったことがなかったし、これからもないだろう。
私は作家であり、無名な詩人である。おそらく、私の名前を聞いたことがあるという読者はほんの一握りだろう。最近までの数十年間、私はハンマーフェルの海沿いにあるセンチネルという街に住み、その地の芸術家や画家、織物職人、作家などと交流を持っていた。彼らのうち誰もが、あの暗殺者の顔を知らなかっただろう。彼らの最後の女王、血の花、死の淑女、夜母のことを。
しかし、私自身は彼女のことを知っていた。
数年前、私は高名な学者のペラーヌ・アッシと知り合う機会を得た。彼はちょうど、ダイアグナ騎士団に関する著作の取材のためにハンマーフェルを訪れていたのである。彼の小論「闇の兄弟たち」、およびイニル・ゴーミングによる「炎と闇:死の同志たち」は、タムリエルの暗殺集団を論じる上で欠かせない資料であるといわれている。幸運にも、ゴーミングもまた同時期にセンチネルを訪れており、私は彼ら二人とともにスラム街のスクゥーマ窟に座り、闇の一党やモラグ・トング、夜母などについて語り合うという素晴らしい経験をしたのだった。
アッシは、夜母が一人の不死もしくは長命の人物を指す呼び名である可能性も否定はできないとした上で、夜母というものが何人もの女性たち–時には男性もいたかもしれない–に代々受け継がれる称号のようなものであると考えていた。夜母が一人の人物であると考えることは、一人のセンチネル国王がずっと国を治め続けていると考えるのと同じくらい非論理的であるというのが彼の主張だった。
ゴーミングは、夜母の存在自体を疑っており、少なくとも夜母という人間は実在しないと主張していた。夜母とは闇の一党がシシスの次に崇拝しているメファーラの別名であるというのが彼の考えだった。
「実際のところは、確かめる方法はないのでしょうね」と、私は議論を仲裁しようとして言った。
「いや、方法はあります」と、ゴーミングがにやりと笑い、小声で言った。「あの隅にいる、マントの男に聞けばいいんですよ」
私はそんな男がそこにいることを気付いていなかった。その男はフードを目のあたりまでかぶり、汚く粗雑な石の床に一人で座っていた。私はイニールのほうに向き直り、なぜあの男が夜母について知っているのかとたずねた。
「彼は闇の一党の一員ですよ」と、ペラーヌ・アッシが囁いた。「それは火を見るよりも明らかです。彼に夜母のことを聞こうだなんて夢にも思ってはいけませんよ」
話題はモラグ・トングについての議論に移っていったが、私の頭の中には一人で座っているあの男の姿が焼きついていた。汚い床の隅に座り、スクゥーマの煙を亡霊のように体にまとって、その目はどこも見ていないようでもあり、すべてが見えているようでもあった。それから数週間後、私はセンチネルの街角で彼を見かけ、後をつけた。
そう、彼の後をつけたのである。読者は当然、「なぜ」や「どうやって」という疑問を抱かれることだろう。
「どうやって」という疑問にお答えするには、私がどれほどよくこの街を知っているかを説明せねばならない。私は泥棒ではないし、音を立てずに歩くこともできないが、その代わり何十年もの間センチネルの大通りや路地を歩きまわり、知り尽くしていたのである。どの橋がきしんで音を立てるのか、どの建物が不規則に長い影を地面に落とすのか、鳥たちがいつ日暮れの歌を歌いだし、やめてはまた歌いだすのか、全てが頭に入っていたのである。私はそれほど苦労することなく、闇の一党の男に気付かれずに彼を尾行することができた。
「なぜ」という疑問への答えはもっと簡単である。私は生まれついての作家であり、好奇心にあふれていた。奇妙な生き物を見かけたら、観察せずにはいられない、それが作家の性というものである。
私はマントの男の後を追い、街の裏側へと入っていった。通る道はどんどん狭くなり、住宅と住宅の間の隙間や破れた柵を抜けた。そして、突然、私は思いがけなく見覚えのある場所に出た。それは建物に囲まれた小さな墓場で、十数本の腐りかけた木の墓標が立っていた。まわりの建物にはこちら向きの窓がなく、住人ですら誰もこんなところに小さな死者の村があるとは知らないだろう。
誰も知らないはずのその場所に、6人の男と1人の女が立っていた。それに私も。
そのとき、女が私の方を見、手振りで自分たちのほうへ来るように誘った。私は逃げようとしたが– いや、実のところ、逃げようとはしなかった。私のよく知るセンチネルの街に謎の部分があると知りながら、そのままそこを離れることなどできなかったのである。
彼女は私を知っており、優しく笑いかけながら私の名前を呼んだ。夜母は、小さな老婆であった。柔らかい白髪で、しわはあるがまだ若さの残るりんごのような頬を持ち、イリアック湾のように青い瞳は人懐っこく輝いていた。彼女は優しく私の腕を取り、墓場の中心で殺人について話し合っている人々の輪の中に座らせた。
彼女はいつもハンマーフェルにいるわけではなく、全ての暗殺を彼女自身で行うわけでもないらしかったが、彼女の顧客と直接話すことが好きなのだと言った。
「私は、闇の一党に暗殺を依頼しに来たのではないのです」と、私は丁重に申し出た。
「じゃあ、どうしてここへ?」と、夜母は、私の目を見据えたままでたずねた。
私は、彼女について知りたいのだと言った。答えは期待していなかったが、彼女は話してくれたのである。
聖なる目撃者 パート2Sacred Witness, Part 2
エンリック・ミルネス 著
「私は、闇の一党に暗殺を依頼しに来たのではないのです」と、私は丁重に申し出た。
「じゃあ、どうしてここへ?」と、夜母は、私の目を見据えたままでたずねた。
私は、彼女について知りたいのだと言った。答えは期待していなかったが、彼女は話してくれたのである。
「あなたたち作家は、私について想像をたくましくしていろいろ書くけれど…」彼女はくすくす笑った。「そういう話を読むのは嫌いじゃないわ。面白かったり、宣伝になったりしますからね。カルロヴァック・タウンウェイの小説の中じゃ、私は長いすに横たわる妖艶な美女なのよ。でも本当のところは、私の経歴なんて面白い物語にはならないわ。ずっと、ずっと昔、私は盗賊だったの。盗賊ギルドができたばかりの頃の話よ。私たち泥棒にとって、家に忍び込んで、見つからないようこっそりと動き回るのはとても大変で、住人を絞め殺すのが一番いい方法だったの。一番手っ取り早かったから。私は盗賊ギルドの中に、殺人の方法と技術を専門とする部門を作ろうと提案したの」
「その提案があんなに議論を呼ぶとは思わなかったわ」夜母は肩をすくめた。「ギルドの中にはこそ泥の専門家もいたし、スリや錠前破りから、見つかったときの言い逃れまで、盗賊の仕事に必要な全ての分野の専門家がいたのよ。でも、盗賊ギルドは、殺人を推奨することだけは盗賊業のためにならないと思っていたの。やりすぎだ、って言うのよ」
「彼らのほうが正しかったのかもしれないわ」と、老婆は続けた。「でも、殺人にはもっとたくさんの利点があったのよ。つまり、見つかることを心配せずに物を盗めるだけじゃなく、もしその殺した相手に敵がいたら、その敵から報酬までもらえるっていう利点がね。お金持ちには大抵、敵がいるものでしょう。それに気付いて、私は殺しのやり方を変えたわ。相手を絞め殺した後、死体の目の中に石を入れることにしたの、片目に黒い石、もう片方に白い石」
「なんのために?」と、私はたずねた。
「名刺がわりですよ。あなたは作家でしょう…自分の本の表紙には、名前を載せるでしょう?私は名前を知らせるわけにはいかなかったけど、私と私の仕事のことを、殺人を依頼したいと思ってる人たちに知ってほしかったの。今はそんな必要もなくなったからもうやってないけれど、その頃はそれが私のサインみたいなものだったの。すぐに噂が広まって、私の商売は大繁盛したわ」
「それがモラグ・トングの始まりですか?」と、私はたずねた。
「あらまあ、いいえ、違いますよ」夜母はほほえんだ。「モラグ・トングは、私が生まれるずっと前からあったんです。私はおばあちゃんだけど、そんなに長く生きてはないのよ。私はただ、先の最高顧問の暗殺のあと解散しかけていた彼らのうち、何人かを雇っただけ。彼らはもうトングを抜けたいと思っていたし、そのころ他の暗殺組織といったら私のところしかなかったので、彼らは私の仲間になったの」
私は、慎重に次の質問を口にした。「全てを話してくださったということは、私を殺すつもりなんですね?」
彼女は悲しげにうなずき、おばあちゃんのようなため息をもらした。「あなたみたいな人の良い、礼儀正しい若い人と知り合ったばかりで、もうさよならしなくちゃいけないのはつらいわ。もし、ひとつかふたつの条件を守れば殺さないでおいてあげると言ったら、どうしますか?」
私は、あの時出された条件をのんだことを生涯恥じ続けるだろう。私はそこで彼女と会ったことを誰にも言わないと約束した。しかし、数年たった今、これを書くことでその約束を破っている。このことで、私は自分の命を危険にさらすことになるだろう。何のために?
私が隠してきた秘密を書き残すためである。
私は夜母と闇の一党の、ここには書けないほど恐ろしく忌まわしい仕事を手伝ったのだ。あの夜から、私が彼らに売り渡してきた人々のことを思い出すたび、私の手は震える。私は詩人としての創作を続けようとしたが、まるでインクが血に変わってしまったような心持ちがして無理だった。私は逃げ出し、名前を変えて、誰も私のことを知らない土地へ移り住んだ。
そして今、私はこれを書いている。直接夜母と会って本人から聞いた、彼女の真の経歴である。これが私の最後の作品になることは間違いない。ここに書いたことは、全てが真実である。
私の無事を祈ってほしい
——編集者注:この文章は当初、匿名で発表されたにもかかわらず、多くの読者は作者の正体を見抜いている。エンリック・ミルネスの詩を読んだことがある者ならば、専門家でなくとも「聖なる目撃者」の文体や言葉のリズムが「アリクル」など彼の作品のそれと酷似していることに気付くだろう。この文章を発表した直後、ミルネスは何者かによって殺害され、犯人は未だに見つかっていない。ミルネスは絞め殺され、眼窩に白と黒の石を押し込まれた無惨な姿で発見されたという。
聖域の英雄たちHeroes of the Sanctuary
エルダマールの模倣者 著
聖域の英雄たちについては聞いたことがあるだろう。サマーセットの船が安全に寄港できるヴァレンウッドの海岸を見つけるため、嵐の海に、深海の怪物に、未開で野蛮な種族に勇敢に立ち向かった3人のアルトマーだ。
これは永遠の物語だ。エルダマールは誠実な指導者で、海を越えての冒険は果てしないと心に描き、他の者が愚かな計画だといっても聞かなかった。ヒルメはごつごつした海岸を守る蛇を殺すために深い海に潜り、その心臓を取り出した。日が出て落ちるまでの間彼女が息を止めていたので、大蛇の死と共に現れるまで、仲間でさえ彼女は死んだと思った。
そしてメルーランを忘れてはならない。新しく素晴らしい船を特別な目的のためだけに造った。船は海上を疾走し、風が途切れても遅くならなかった。風を味方につけ、外国の岸に問題なく船を送れるように、名工が神々、もしくは長く忘れられていた神と取引したと言われている。
そしてついに、3人の英雄が敵の海岸にたどり着き、その地の人が好戦的で敵の肉を食すことを発見したという話がある。船員は野蛮人と戦い、彼らを追い払おうと騒いだ。だが聖域の英雄たちは、早まった馬鹿なエルフの言うことを聞かなかった。
ウッドエルフの指導者と会う代わりに、彼らの習慣を研究した。彼らはグリーンパクトを学んで森に危害を加えることを禁じていることを知り、ミート・マンデイトを学んで彼らがエルフに戦いで負けた者を食べるよう命じることを知った。そして最も重要な、窃盗の権利について学んだ。
ウッドエルフはお互いから盗み、その後返す時は同じ価値を持つ代わりのものを要求するのが慣例だった。
聖域の英雄たちは、たいそうな価値のある杖を持ってきていた。そこで彼らはウッドエルフと取引をした。ウッドエルフが杖を奪えたら、彼らは去り、二度と戻らない。だが、もし彼らがウッドエルフの樹の従士それぞれから何か奪うことができたら、ヴァレンウッドの海岸で定住地を見つけることが許されることになった。
取引は決定し、英雄たちはすばやく賢く、樹の従士から盗み出した。ある者からは秘蔵の弓を。ある者からは「手に入るものの中で世界で一番価値のあるものだ」と騙して、価値のあるネックレスを交換させた。世界で一番大事なものというのは、皆も知っての通り、空気のことだ。なければ生きられないのだから。
約束の時間に、すべての樹の従士のものは盗まれていたが、ウッドエルフは杖を奪うことができなかった。そしてエルダマール、ヒルメ、メルーランの勇気、賢さ、洞察力のおかげで、海辺の聖域が出来上がったのだ。
双子月の道の物語 第3巻Tales of the Two Moons Path Vol. 3
タジアコは困惑して、周囲を見渡した。彼女の祖父は一瞬前までそこにいたのに、今彼女は子供の頃の寝室の中に立っていた。高価なタペストリーが壁にかかっていて、木製の羽根板を暖めていた。母親が料理をしていて、甘い匂いが空気の中に漂っていた。
タジーは扉に向かって走り、挨拶の声を上げるために口を開いた。そこで彼女は立ち止まり、自分が再び舞踏の聖堂の中にいることに気づいた。年老いた月の代弁者が彼女に向かって重々しくうなずき、呪文を唱えるような口調で言った。「ジョーンとジョーデがお前に見せたものは、お前のためだけのものである。このことをよく考え、いつも覚えているように」
大胆な錬金術師の告白Confessions of a Bold Alchemist
錬金術師アレート 著
告白する。私は錬金術師だ。色々と混ぜ合わせてどうなるか試すのが好きだ。錬金術の工程における謎と魔力に魅了されている。一方では、重さや分量などを忠実に細かく守る必要があるので、とても精密な作業だ。そして他方では、自発的かつ衝動的に行なう余地が多分にあり、即興的な要素が大きい。実際に錬金術における大発見の一部は、確信と論理を元に積極的な賭けをした結果であると言える。
さらに告白しよう。私は冒険が好きだ。洞窟や暗い沼地を探検して、錬金術の試料を探すのが好きだし、何かが爆発するまで混合物や調合薬で実験してみるのが好きだ。実は、リスクが高かったり予期できないものを作る方が、私は楽しめるのだ。そのような作業には…胸が躍る!
ここで列記した内容は、私が特別だということを意味するのだろうか?勇敢?単に変だということか?私は決してひ弱な大学教授ではなく、秘密の実験室に隠れて実験に精を出しているわけではないが、判断は任せよう。最近の冒険について話をしよう。それはこれから説明するとおりに起きた。だいたいだが。
イーストマーチの荒野の奥深くで、オールドソルド洞穴を探していた時、とある客が私の錬金術の店に入ってきた。
ああ!本当に客が来た!しまった。この手紙は後で終わらせるしかない…
追放生活からの追放 第7巻Exiled from Exile, Volume 7
ヤスラ・アルアシャバー 著
砂の石と湿地
リッチ王ギデオンが敗れた後、寒々とした湿地に住む人々とヒストに最後の別れを告げ、私はストームホールドを通り抜けて北へと向った。モロウウィンドの南で最初の夜が訪れ、巨大な菌類の森にキャンプを張った。
ニックスの新鮮な肉を焼いていたとき、キャンプの近くの岩場に何かがあることに気付いた。数世紀とは言わないまでも、数十年前に誰かの手によって立てられたと思われる巨石がいくつか遠くに見えた。一番近くにあった一番大きな岩を見て、私はこれを記すことにした。
子供の頃、一族の税金を納めるためと追放者に対する視線に慣れるため、父親にアスワラ王の馬屋に連れて行ってもらったことがある。そこへの道中で大きな砂嵐に襲われ、私達は洞窟に避難した。
「娘よ」と父は言った。「教えたとおりに洞窟の中で水を探すんだ」
「分かったわ、父さん」と言い、私は洞窟に入った。水はなかった。だが馬屋の地下深くの巨大な空洞に、何か重要なものがあると分かった。
その中心に置かれていた石には、奇妙な見慣れない文字が刻まれていた。まるで私を呼んでいるかのようだった。私は手を伸ばして石に触れた。すると私はいきなり口を塞がれた。私はくぐもった叫び声を上げたが、ついには呼吸困難に陥り気絶してしまった。
数時間後に目を覚すと、そこには真剣な目をした父親の顔があった。
「娘よ、ここから離れる必要がある。まだ追っ手が来るはずだ」。父は攻撃してきた者がどうなったのか最後まで教えてくれなかった。父の服に付いた染みから、悲惨な最期を迎えたことが想像できた。
「でも父さん、あの石は何?あの記号は?」
「ここは神を冒涜するための場所だ。悪魔崇拝者に取り囲まれている。見てごらん。これはデイドラの邪悪な言葉のひとつだ。”コールドハーバー”と書いてある」
読者は私の驚きを想像してみてほしい。ニックスの肉で腹を満たした私は、キャンプファイアの火に照らされたモロウウィンドの石を見上げた。するとそこに、その時と同じ邪悪な言葉が書かれていたのだ。子供の頃に見たものと同じ言葉が同じような石に刻まれていた。
「コールドハーバーが呼んでいる。ニルンよ従え」
「コールドハーバーが呼んでいる。ニルンよ従え」
笛吹きThe Piper
笛吹きが街にやって来て、バグパイプを唇に当てて演奏し始めた。街の住人は彼を笑い飛ばし彼は街を去ったが、その音楽はかすかに鳴り続けていた。
その後笛吹きを見たものはいなかったが、時が経ってもそのバグパイプの音楽は鳴り止まなかった。街の住人が床に就くときにも鳴り響き、目を覚ましてもまだ鳴り響いていた。街の住人は眠ることができず疲れだし、毎日笛吹きを探した。しかし何も見つからなかった。
そしてある夜、その鳴り止まない音楽がこれまでにないほどの音量で空気を切り裂いた。その夜、街の住人は奇妙な生物や虫の夢を見てほとんど眠ることができなかった。住人が目を覚ましたとき、子供達が心地よく眠っていたはずのその場所は虫やネズミで埋め尽くされていた。街中の家から次々に悲鳴が上がった。母親達は路上に飛び出し、父親達は街中を探し回った。街の住人は不運を嘆き悲しんでいて気付かなかった…あの音楽が鳴り止んだということに。
盗賊の隠れ家 パート2Den of Thieves, Part Two
斑岩の女人像 著
青いベルベットのチュニックを着た紳士は、木でできたペンキの塗られていない低い扉をそっと押し、その向こう側の薄暗がりに目を凝らした。「ここに何の用だ」すぐ近くから問いただす声がした。
「その…盗賊の街道に立ち寄ったのだが」紳士の声はほとんどいぶかしむような調子だった。
「だからどうした」
「そう…言えと言われた。それから「今夜フクロウの父が飛ぶ」と言えと」紳士の上品なくちびるがためらいがちな笑みを作った。「それで良いのだろう?違うか?」
近くの声はどっちとも取れるようなうなり声を上げてから、「用件は?」と尋ねた。
「赤きコブラと…話がしたい」
「いいとも。彼は裏にいる。醸造桶の後ろだ」煙の中の影がぼんやりと立ち込める蒸気をかき混ぜるような仕草をした。紳士は咳をして、薄暗い部屋を横切るように歩き出した。
部屋は一種の控室だった。テーブルが1ダースばかりと、不ぞろいな椅子が60脚あり、どこかはるか上方から真昼の日差しが砂漠の街ホーリンズ・スタンドを照らしているというのに、その椅子の一部は酔っ払いに占領されていた。天井は低く、紳士は背が高かった。そのため彼は低く垂れ下がったオイルランプをかいくぐって進まねばならなかったが、それこそが部屋の空気を重くしている煙の大半を排出していた。「甲虫オイルか」彼は臭いをかぎながら独り言を言った。「それもあり得る限り最も安い等級のものだ」
醸造桶の向こう側はいくらか空気の密度が低かったが、控室よりさらに暗かった。遠くの壁際に置かれたテーブルの上にランプが1つ灯っていて、その炎がカラフとフラゴンと、椅子に座って壁に寄り掛かっている誰かのベストの縁飾りの刺繍に反射していた。
紳士はテーブルに近付くと、礼儀をわきまえた距離で立ち止り、こう尋ねた。「お前が…赤きコブラか?」
椅子の前脚がどすんと音を立てて床に落ちた。「確かにそう呼ばれているな」ベストの上から低い声が答えた。「昔からホーリンズ・スタンドの盗賊ギルドの頭目に与えられてきた称号だ。あんたは?」
「私の名は…重要ではない」と紳士は言った。「だが私の用件は…重要だ」
「どれくらい?」
紳士はウエストバンドから袋を引っ張り出し、それをテーブルの上に落とした。袋はガツンと音を立てた。赤きコブラは1本の指でそれを開き、一瞬その中身をかき混ぜた。「これなら重要な仕事の報酬として認められるだろう。いずれにしても頭金だがな」と彼は言った。「標的は?」
「ホーリンズ・スタンドの総督だ」
「友よ、来るべき場所を間違えたな」赤きコブラはほんの少し残念そうに言った。「暗殺はうちの仕事じゃない。お探しの相手は闇の一党だ。でなきゃモラグ・トングかな。奴らは王殺しが専門だからな」
「いや、総督の命を奪ってほしいのではない」と紳士は言った。「彼の名誉を盗んでほしいのだ」
「彼の名誉?」と赤きコブラは言った。「どういう意味だ?」
「総督の印章付きの指輪を盗んでもらいたい。彼が任命を受けた時に、王の手でその指にはめられた指輪だ。あれは彼の統治権の象徴だ。それを奪ってほしいのだ」と紳士は言った。「総督の舞踏会の儀式の踊りの間に」
長い間があった。そして「交渉成立だ」と赤きコブラが言った。「もちろんこの件は俺が個人的に引き受けなきゃならないだろう。うちのスリ師や泥棒達にこの手の仕事は無理だからな」彼はカラフを持ち上げると香り高いザクロワインをフラゴンに注いだ。「飲むか?」
「2人一緒に」と紳士は言った。「同じ器から?」
「それがここのしきたりだ」
「そういうことならば」と青いベルベットのチュニックの紳士は言った。「喜んでいただこう」
不死の血 パート1Immortal Blood, Part 1
著者不明
月も星も姿を隠していた。特別静かな夜がいっそう沈んで感じた。街の衛兵は松明なしには巡回もままならなかった。だが、私の聖堂を訪ねてきた男は灯りを携えてはいなかった。やがて気づいた。モヴァルス・ピクインは夜でも昼と同じように見ることができる。素晴らしい才能だった。彼がことのほか夜行性であることを考えたら。
侍者のひとりに連れられてやってきた彼を見たときに、まず、すぐにでも治療しなければと感じた。青白いどころかオパールのような顔色をしていた。耐えがたき苦しみに襲われ、かつての男ぶりの良さが抜け落ちてしまったような顔だった。目のまわりにできたくまが疲労の激しさを伝えていたが、瞳そのものは鋭く、真剣であった。
私の懸念を感じ取ったかのように、彼はすぐさま自分は病気ではないと告げた。それ以上、突っ込んで話そうとはしなかったが。
「吸血症さ」と彼は言い、私がいぶかしげな顔をしたのを見て、一旦、言葉を切った。「こういうことで力になれるのはあんたしかいないと言われた」
「誰から聞いたのかね?」と、私は笑みを浮かべて訊いた。
「ティシナ・グレイだ」
すぐに彼女を思い出した。勇気と美貌を兼ね備えた騎士で、吸血鬼にまつわる虚構から真実をより分ける手助けをしてほしいと頼まれたことがあった。あれからもう二年になるが、音沙汰がなく、私の助言が役立ったのかどうかはわからずじまいだった。
「彼女に会ったのかな?元気にしてたかね?」と、私は訊いた。
「死んだ」と、モヴァルスは冷淡に言った。と、私がうろたえるのを見るや、緩衝材となるような言葉を継いだ。「あんたの助言はすこぶる効果があったと言ってたよ。少なくとも、ある吸血鬼に対しては。最後に話したとき、彼女は別の吸血鬼を追ってた。そいつに殺られたんだ」
「となると、私の助言は充分でなかったわけか」私はため息をついた。「なら、どうしてお前には効果的だと考えるのかね?」
「おれはかつて教師だった。昔の話だ」と、彼は言った。「大学とかじゃない。戦士ギルドの訓練師だった。が、生徒が正しい質問をしなかったのなら、失敗したとしても教師に非はないことくらいはわかってる。おれは正しい質問をしようと思う」
そして彼はそうした。何時間ものあいだ、質問を投げかけてきた。私はわかる範囲で答えてやった。が、彼が自分自身のことを率先して話すようなことはなかった。笑うことも。ひたすら鋭い目つきで私の顔をながめ、私が口にする一字一句を記憶にとどめようとしていた。
彼の質問が途切れ、ようやく私が質問する番がめぐってきた。「戦士ギルドの訓練師だったと言ったが、ギルドのためにやっていることなのかね?」
「いや」と、彼はぶっきらぼうに言った。そしてとうとう、私はその熱心な眼差しにいくばくかの疲れを見てとった。「この続きは明晩にしよう、あんたさえよければ。少し眠って知識を吸収しないといけない」
「昼間は寝るのか」私は笑った。
驚いたことに、彼が笑い返してきた。いかにもぎこちなかったが。「獲物を追うときは、獲物の習慣に合わせないといけないからな」
不死の血 パート2Immortal Blood, Part 2
著者不明 著
翌日、彼はさらなる質問を抱えて戻ってきた。その内容はかなり具体的だった。彼が知りたがっていたのは、東スカイリムの吸血鬼のことだった。私は最強の種族である執念深くて残虐なヴォルキハーのことを教えてやった。その息で獲物の血を凍りつかせるという吸血鬼のことを。彼らがどうやって辺ぴな呪われた湖の氷の下で、食事どき以外はあえて人間界に降り立つこともなく暮らしているのか話した。
モヴァルス・ピクインはじっくりと耳を傾けていた。夜にかけてさらに質問をぶつけ、ようやく引き揚げる気になったようだった。
「数日は会うこともないだろう」と、彼は言った。「が、おれは帰ってくる。情報がどれほど役に立ったかをあんたに伝えるために」
それから四日後の深夜を少し過ぎたころ、約束通り彼は聖堂に戻ってきた。頬にまだ新しい傷を負っていたが、あの不気味だが満足げな微笑みを浮かべた。
「あんたの助言はとても役立ったよ」と、そう言った。「けど、ヴォルキハーにはあんたが言わなかった能力が備わっていたことを知っておくといい。やつらは湖の氷を割ることなく水中へ引きずり込もうとしてくる。何の前触れもなく下からいきなりつかまれたもんで、嫌な汗をたっぷりかかされたよ」
「そいつはすごいな」と、私は笑いながら言った。「そして、恐ろしくもある。まだ生きてるとは運がいい」
「運など信じない。信じるのは知識と訓練だけだ。あんたの情報は役立った。そして、おれの接近戦の技術があの吸血鬼の運命に破滅をもたらしたんだ。おれはどんな武器も信用しない。どんなに腕のいい刀匠でも、傷のある刀を造ることくらいあるだろう。だが、自分の体ができることならよくわかる。体勢が崩れるまでに無数の打撃を浴びせられることはわかってる。先手をとれたらの話だが」
「先手をとれたら?」と、私はぼそっと言った。「つまり、虚を突かれるわけにはいかないのか」
「だからあんたに会った」と、モヴァルスは言った。「この世であんたほど、あの怪物のことをわかってる人はいない。各地のいまいましい変種のことにも詳しい。さてと、北ヴァレンウッドの吸血鬼のことを聞かせてくれないか」
私は希望をかなえてやった。今回もまた、彼の質問に私の知識は悲鳴を上げた。話しておくべき種族はいくつもあった。ろうそくの火で照らさないかぎり、ボズマーと見分けがつかないボンサムのこと。肉体を霧状にすることができるキーリルスのこと。人を丸呑みするイェケフのこと。子供を食らう恐ろしいテルボスのこと。彼らはやがてその子に成りすまして家庭に入り込み、何年も辛抱強く待ってから、尋常でない飢えを満たすために皆殺しにするという。
またもや彼は数週間で帰ってくると約束して別れを告げ、またもやその言葉どおり、数週間後の深夜過ぎに戻ってきた。このとき、モヴァルスは生傷こそ作ってはこなかったものの、やはり新たな情報を仕入れてきていた。
「キーリルスは、水に突き落とされると霧状に変化できないというのは誤りだった」と彼は言い、親愛の情を込めて私の肩をぽんと叩いた。「幸いにも、やつらは霧のままだと遠くへは行けないんだ。で、首尾よく追いつめることができた」
「吸血鬼もさぞかし驚いたことだろう。お前の実践的知識はますます磨きがかかっているな」と、私は言った。「数十年前にお前のような侍者がいてくれたらよかったが」
「さて、教えてもらおうか」と、彼は言った。「シロディールの吸血鬼のことを」
私はできるかぎりの知識を与えた。シロディールに生息する吸血鬼は一種族のみ。帝国がそうしてきたように、すべてのライバルを蹴散らしてきた強力な一族だと。やつらの本当の名前は歴史に埋もれてしまってわからないが、潜伏の達人であるらしい。満腹でいるかぎり生きている人間と見分けがつかない。属州の吸血鬼と比べると教養があり、文明化されていて、獲物が寝入っているところを闇討ちするという。
「不意を突くのは難しそうだな」モヴァルスは顔をしかめた。「だが、きっと見つけだして、わかったことをあんたに報告しよう。そしたら今度はハイロックの吸血鬼について教えてもらう。それからハンマーフェルとエルスウェアとブラックマーシュとモロウウィンドとサマーセット諸島の吸血鬼のことも。いいな?」
私はうなずいた。この男は終わりなき旅を続けているのだ。真実のひとかけらを手にしただけでは満足できない。そのすべてを手にしたいのだから。
ひと月たっても彼は戻ってこなかった。ようやく帰ってきたその夜、その顔は落胆と失望に満ちていた。聖堂に火は灯っていなかったが、私はそれを見てとることができた。
「しくじった」と彼は言った。私はろうそくに火をつけた。「あんたの言うとおりだった。どこにも見つからなかったよ」
私はろうそくを顔のあたりまで持っていき、微笑んだ。彼は驚いた。私の顔色の悪さに、私の永遠の瞳に浮かぶよこしまな渇望に、そして私の牙にぼう然としていた。そうだとも。虚を突かれることの許されない男でも、この牙にはすこぶる腰を抜かしたことだろう。
「七十二時間ほど食事をしてなくてね」私はそう言いながら襲いかかった。モヴァルスは先手を打つこともとどめを刺すこともなかった。
物乞い王子Beggar Prince
帝都の物乞いのなんとみすぼらしいことか。哀れで貧しい人生の落伍者たちはどの街でも目にすることができる。ほとんどは貧苦にあえぎ、着るものもままならず、捨てられた残飯を糧としている。人々はゴールドを1枚投げ与えることで、彼らの苦境をできるだけ考えないようにしているのだ。
それ故、物乞い王子の話には少なからず驚かされた。そもそも、物乞いの王子とはいかなるものか想像がつかなかった。ここでその話を紹介しよう。ときは第一紀。神が人のように歩き、デイドラが何のおとがめもなく荒野をさまよっていた時代のことだ。オブリビオンに縛られていた以前の物語である。
* * *
かつてウィードルという男がいた。あるいは、女であったかもしれない。性別をあえて曖昧にしている節がこの物語にはあるのだ。ウィードルはヴァレンウッドの王の第13子であったため、王位継承が望めないのはもちろん、相続が許された土地や財産も皆無に等しかった。
ウィードルは自らの財産と栄誉を手にすべく、宮殿をあとにした。何日もの間、終わりなき森の道やこぢんまりとした村を旅していると、3人の男が物乞いを取り囲んでいるところに出くわした。
ぼろ布で全身がすっぽりと覆われていたため、物乞いの素顔を外からうかがい知ることはできなかった。だが、男たちに殺されかけているのは明らかだった。
憤怒の雄たけびとともに、ウィードルは剣を抜いて3人に襲いかかった。彼らとて所詮は街の民。手にした熊手と草刈鎌ではきらめく剣で武装した鎧の男にはとうていかなわないと気づくや、脱兎のごとく逃げていった。
「ありがとう、助かりました」汚いぼろ布の陰から、物乞いがあえぐように言った。耐えがたいほどの悪臭がした。
「あなたの名前は?」と、ウィードルは訊いた。
「ナミラ」
先ほどの男たちとは違い、ウィードルには教養があった。彼らにとっては無意味な名前でも、ウィードルはそこにチャンスを見てとった。
「デイドラ公ではありませんか!」と、ウィードルは叫んだ。
「どうして奴らのされるがままになっていたのですか?あなたなら、ささやくだけで殺せたでしょうに」
「よくぞ気づいてくれました」と、ナミラはかすれた声で言った。
「街の民にはののしられてばかりです。私の名ではなく人となりで覚えられるのは誠に喜ばしい」
ウィードルにはわかっていた。ナミラはすべての忌み嫌われるものをつかさどるデイドラの主なのだ。
腐敗をもたらす病気はナミラが支配していた。他の者であれば危険を察知したかもしれない。が、ウィードルはそこに希望を見い出した。
「おお、偉大なるナミラ。私を弟子にしていただけませんか。どうか力を授けてください。財を成し、世代を超えて語られる名を挙げるための力を」
「それはできません。私は独りで世界を歩むゆえ、弟子はとらないのです」
ナミラはよろよろと道を歩いていった。ウィードルは引き下がらなかった。さっと身を躍らせるとナミラのかかとにすがりつき、弟子にしてはもらえまいかと乞うた。
この懇願は33日間、昼夜を問わず続けられた。ナミラは何も言わなかったが、ウィードルの口が休むことは一時もなかった。
そして33日目、ウィードルはついに喉が枯れてしまい、しゃべられなくなったのである。
ナミラは振り返り、いきなり静かになった彼を見た。ウィードルは泥まみれになってひざまずき、哀願するように両手を広げた。
「どうやら、弟子としての務めをまっとうしたようですね」ナミラはそう告げた。
「あなたの願いを聞き入れましょう」ウィードルは歓喜した。
「あなたに病の力を授けましょう。いかなる病気であれ、症状が目に見えるものであれば、思いのままに患うことができます。ただし、どんなときも最低ひとつの病に耐えなければいけません」
「哀れみの力を授けましょう。誰からも哀れみを受けられるようになります」
「最後に、無関心の力を授けましょう。誰もがあなたの存在に関心を持たなくなります」
ウィードルはあ然とした。どれもこれも財を成せるような恩恵ではなく、むしろ呪いだったからだ。どれひとつとっても、それはひどいものであり、すべてそろったらいったいどうなってしまうのやら。
「かようにいとわしい才能で、どのように財を成し名を挙げろとおっしゃるのですか?」
「33日間の昼と夜の間、私の足元で乞い願ったように、皆の街にて財産を乞い願うのです。物乞い王子ウィードルの物語は、時代を超えて語り継がれていくでしょう」
ナミラの予言どおり、ウィードルは抗いがたい物乞いとなった。そのみすぼらしい哀れな姿を目にすると、誰もが金を施さずにはいられなくなってしまうのだ。
だが、ウィードルは無関心の力が秘密を知るのにたいそう役立つことも学んでいた。ウィードルが耳をそばだてているとは夢にも思わず、人々は知らないうちに大切なことを洩らしてしまうのであった。
こうして、ウィードルは全市民の行き来を把握することとなった。
わからないことがあれば物乞いに聞け、と今日でも言われている。物乞いの目や耳は街のいたるところに存在する。市民の暮らしにまつわることなら、彼らはどんなちっぽけな秘密にも通じているのである。
放浪者の死Death of a Wanderer
私が最後に老齢のアルゴニアンと会った時、断末魔の苦しみを味わっている最中にも関わらず、元気そうな彼の姿に驚かされた。
「秘訣はな」と彼が言い始め「生きるための秘訣は…逃げるのではなく危険に対してそのまま泳いでいく。そして不意をつくんだ」
「そうやってこの爪を見つけた?」その小さな彫刻をさも武器かのように振り回しながら尋ねた。彼の所持品を受取人達に分配する手伝いをしていた時に見つけた物だ。「これもいとこにやるのか?底からの潜水って呼ばれている彼に?」
すると歯根を見せるほど口を広げた。今ほど長く彼を知っていなかったら唸っているのかと思っただろうが、それが笑いであることを私は知っていた。笑おうと何回かしゃがれた声を出したが、苦しそうの喘ぎと咳に変わってしまい、鼻を突く血液がベッドシーツに飛び散った。
「それが何か知ってるのか?」彼は咳の発作の合間に尋ねた。
「話は聞いたことがあるよ」と答え「あなたと同じようにね。古い地下室にある封印された扉を開くための爪に見える。本物はこれまで見たことないけど」
「それなら私がそれを敵にしか渡したくないのはわかっているだろう。それをいとこにやろうものなら墓地に突入して、ドラウグルの刀で真っ二つにされてしまうに違いない」
「じゃあ、私に持っててほしいとか?」私は冗談で言ってみた。「そもそも、どこでこれを手に入れたんだ?」
「私の種族はお前達がなくなってしまったと思った物を見つけることができるんだ。湖の底に何か落とせば、ノルドはその物には2度とお目にかかれないだろう。湖底で見つかる物には本当に驚かされる」
彼は天井を見つめていたが、ぼんやりとした目がそわそわ動く様子から、見ているのは頭上にあるひび割れた石ではなく、自分の思い出であることがわかった。
「実際に使おうとしたことは?」思い出に浸っている彼に聞こえるように祈りながら私は囁いた。
「もちろんだとも!」突然明快にピシャリと言った。彼の目は大きく開かれ、私を見据えていた。「これをどこで負ったと思う?」大声を上げてチュニックを引き裂いて開くと、右肩の下部分にある鱗にできた大きな星型のこぶ状の白い傷を見せた。「忌々しいドラウグルに出し抜かれたんだ。奴らの人数があまりにも多くてな」
彼は自分の参加した戦いについて話すのが嫌いだということを知っていたため、申し訳ない気持ちでいっぱいになった。彼にとっては生き延びられたことだけで十分で、どんな話も自慢話にしかならないという考えだったのだ。お互い静かに数分間座り続けた間、唯一の音は彼の苦しそうな呼吸音だった。
その静けさを破ったのは彼だった。「何が気になっていたかわかるか?」と聞いてきた。「彼らがシンボルに煩わされてた理由だ」
「何だって?」
「シンボルだよ、ばか者。爪を見てみろ」
手の中でそれをひっくり返した。案の定、表面に刻まれているのは3匹の動物だった。クマ、フクロウ、それと何かの昆虫だった。
「これらのシンボルにはどういう意味があるんだ、ディアカザ?」
「封印された扉だ。爪だけでは十分でない。扉は巨大な石の車輪でできていて、開ける前に爪のシンボルと合致させなければいけないんだ。何か鍵のような物だと思う。ただ彼らがなんでそれに煩わされたのかがわからない。爪を持ってるなら扉を開くドアを持ってたはずだ。それならなぜ…」
彼の話は咳き込んでしまったことで途切れてしまった。こんなに話しているのを聞くのはここ数ヶ月で初めてだが、どれだけ大変かは見て取れた。しかし、何を考えているがわかっていたので、話を進めるのを手伝った。
「鍵に書いてしまうなら、そもそもなぜ組み合わせを作ったのか?」
「その通り。だが床に倒れて血を流しながら見つけたんだよ。ドラウグルは残酷な連中だが、賢さとは程遠い。私が倒れても彼らは足を引きずって歩き回り続けていた。目的もなく。方向もバラバラ。お互いぶつかったり、壁にぶつかったりする者もいた」
「だから?」
「だからドアのシンボルは別の鍵としてあった訳ではなかったということだ。入ってくる人間が本当に生きていて、頭が働いているのかどうかを確かめる方法だったんだ」
「じゃあ、その扉は…」
「人々が立ち入らないようにするための物じゃなかった。ドラウグルを中に閉じ込めておくための物だったのだ」
そう言うと、彼はまた眠りについた。何日後かに目を覚ますとドラウグルについては一切話そうとせず、私が話題に出そうとするとビクッとし、肩を抱きかかえるだけだった。
勇敢なる小さなスクリブBrave Little Scrib
勇敢なる小さなスクリブは、クワマー・クィーンとワーカー、そしてウォリアーと一緒に住んでいました。彼らはダークエルフの鉱山にも、その他のどんな奴隷状態にも拘束されないクワマーの自由な植民団でした。しかし、勇敢なリトル・スクリブはうんざりしていました。目上のクワマーに指示されるのが気に入らなかったのです。
「あなたが私より賢いのはなぜ?」と、勇敢なる小さなスクリブはクワマー・ワーカーに訪ねました。
「君より年上だからだよ、スクリブ」と、クワマー・ワーカーはいら立って言いました。「それに私はいつもとても忙しいから、何が最適かわかっている。滝には近づいてはいけない。信用しなさい。川で遊ぶより忙しくしていたほうが幸せなんだよ」
その答えが気に食わなかった勇敢なる小さなスクリブは、クワマー・ウォリアーと話しに行きました。「なぜ滝で遊んではいけないの?」と彼女は聞きました。
いつも真剣なクワマー・ウォリアーは、話しながらスクリブを見ることはありませんでした。その代わりに彼は、戦う可能性のある脅威がいないか、常に洞窟を入念に調べていたのです。ウォリアーは戦うのが好きで、いつも戦いを探し求めていました。「滝だって?滝とは戦えないよ、小さなスクリブ。水は冷たくて早いし、溺れてしまう。私や他のウォリアーが君を見守ることのできる卵部屋へ戻って、他のスクリブと遊んでなさい」
勇敢なる小さなスクリブは、その答えにも満足しませんでした。「やれやれ。滝で遊んではいけないのはどうしてなのか本当に納得のいく理由を誰も教えてくれないのなら、滝に行って遊んでみよう」と、勇敢なる小さなスクリブは考えました。
流れ落ちる水に続く地下水路に近づくと、勇敢なる小さなスクリブは行く手に小さなホタルを見つけました。「小さなホタルさん、こんにちは」と、スクリブは呼びかけました。
「やあこんにちは、小さなスクリブ」ホタルは歌いました。その声は激しく情熱的で、燃える炎のようにパチパチという音がしました。「何のために洞窟のこんなところまで来たの?」
「滝で遊ぶために来たの」勇敢なる小さなスクリブは元気よく言いました。「私が通れるように、飛んで行ってくれない?」
「ああ、いいよ」とホタルは言いました。「喜んで飛んで行こう。誰かが滝に来るなんてかなり長い間見ていないから、その光景にはとても楽しませてもらえるよ。どうぞ、急いで。思う存分笑いたい」
勇敢なる小さなスクリブは、ホタルが言ったことが気に入りませんでした。「私が溺れるのを見たいの?」
「さあね。どちらにしたってあまり気にはしないけど、派手に溺れるのを見るのは楽しいよ。泳ぎ方は知ってるのかい、小さなスクリブ?」と歌いました。
勇敢なる小さなスクリブはホタルの歌について考えました。彼女は、「泳ぎ方は知ってるよ」と嘘をついたのです。「でも今日は滝で泳ぐ気分じゃないな。たぶん明日ね。またね、ホタルさん」
「君がそう言うなら、小さなスクリブ」とホタルは歌いました。「さようなら」
そうして、勇敢なる小さなスクリブは新たな冒険を探しながら、卵部屋へとぶらぶら戻っていきました。
予想外の守りAn Unexpected Defense
盗賊は控えの部屋の暗い隅で待ち、観察していた。彼に注意を払う者はほとんどいなかった。神経質な貴族が1人、少しの間彼を見つめていたが、盗賊が探しているのはこの男ではなかった。しばらく後、控えめな出で立ちの商人が盗賊に近づき、巻いた羊皮紙を彼の手に滑り込ませた。盗賊は鮮やかな手つきで羊皮紙をシャツの袖に滑り込ませ、男に軽くうなずいてみせてから酒場を出ていった。
セクンダの光の下で、盗賊は巻物を広げその上に目を走らせた。黄ばみがかったページには頑丈そうな塔の見取り図が描かれており、すべての入口と出口、さらに塔の最上階に隠された、彼の獲物である小さな宝箱の位置も印づけられていた。街外れをゆっくりと歩き回っている間、夜の女に声をかけられたが、彼の頭には別の宝物があった。
塔は暗く高くそびえ立ち、周囲の木々に不気味な影を投げかけていた。盗賊が塔の外側をよじ登り、入口に使うつもりの上窓にまでたどり着くのに長くはかからなかった。彼はあっさりと窓をすり抜けて中に入り、暗闇の中で一旦しゃがみこみ、耳を澄ませていた。すると突然、部屋全体が火によって輝いた。炎のボルトが彼目がけてまっすぐに放射される。「シェオゴラスの歯め!」 彼は呪いの言葉を叫びながら脇に避け、火のボルトを間一髪で回避した。魔術師がいるとは、予測していなかった。
立派なアルアザル、その行いThe Worthy Ar-Azal, His Deeds
「幼きファハラジャード王子に語られた歴史の歴史」より
王子よ、以下をお知りおきくださいますよう。この国が第二帝国の属州となった時も、ハンマーフェルではフィロシッド朝が支配をしていました。この王の家には賢い者も愚かな者もいたのですが、誰もが気高くありました。そして家の最後にあたる上級王アルアザルは中でも最も気高い王でした。というのは、一時クラウンとフォアベアーの兄弟同士の争いを終わらせたからです。
どうやって実現したかって?しっかり聞いてください、そうしたら物語を話してあげましょう。
優れたアルアザルの優れた父、ジャフルールの逝去にあたり、ヘガテの王子はその直後にヘガテの王座を引き継ぎ、ダイアグナの王冠をいただき、ハンマーフェルの上級王の称号を得ました。そしてハンマーフェルの貴族全員が、ヘガテに敬意を表して逗留したのです。しかし、新しい上級王はろくに髭も生えていない若さでしたが馬鹿ではなく、貴族が忠誠心を見せるのは雲に対するのと同じことで、見えてはいるが実質はないとよくわかっていました。というのは、アルアザルはクラウンだったので、フォアベアーの貴族は彼をあまり好きではなく、クラウンの貴族は彼の父親がフォアベアー家を潰さなかったので、彼をあまり信用していなかったからです。そしてアルアザルは板挟みでした。上級王としてハンマーフェルを支配しなければならないのに、得られる支持はお産を終えたばかりの女と同じくらい弱かったのです。
そこで立派なアルアザルは自分の高い塔から雲ひとつないアビシアンを眺め、多くの祈りを祈り、多くの思案を思案しました。そしてまもなく王の教師にして精神的指導者であり、サタカルの女司祭、そして高名な賢人でもある素晴らしきザキーブのことを思いつきました。それで聖堂へ行き、素晴らしきザキーブにクラウンとフォアベアーをどうやって和解させるか、謎を解くことができないと話したのです。すると素晴らしきザキーブは王に神酒を与えて言いました。「今晩それを飲みなさい。王様、そして夢を見なさい」と。神酒を貰って、立派なアルアザルは感謝しながら引き返し、言われたとおりにしました。
そしてその夜、立派なアルアザルは世界の蛇サタカルの夢を見ました。サタカルは蛇の頭の最高顧問の姿をしてやってきました。そして最高顧問は上級王に敬意を表しました。というのは、この謎を解けるのは立派なアルアザルだけだと言ったのです。そして2回、1枚の舌で1度ずつ語られた答えは、ターヴァ、フォアベアーからもクラウンからも敬意を受ける神の祠にあるというものでした。
その時、アルアザルはオオタカの鳴き声を聞きました。この鳥はターヴァの聖鳥です。そこで王は目覚めると、夜明けになっていました。ヘガテにあるターヴァの祠へ急いで赴くと、そこにはオオタカのフレスコ画があり、ターヴァがつがって巣にいる姿が描かれていました。そして、かつて巣には1匹の連れ合いが描かれていたのが今は2匹になっていて、2匹目は朝の光に輝いていました。そしてアルアザルは言いました。「本当に神は私に答を示してくださった。フォアベアー一の貴人、センチネルのエブラヒムには美しくしなやかな娘、フェレスターがいるではないか?そしてクラウン一の貴人、リハドのムラードには積極的で賢い娘、アーリマヘラがいるではないか?」
そしてこれでアルアザル、王子様の立派な大叔父様のお話はおしまいです。王子様は物わかりがよく、上級王がどうやって謎を解いたのか、ご自身で思いつかれるとわかっていますから。
埃まみれのページDusty Page
フョッキは彼の歌う刀剣、ラブメーカーをダンマーの頭の上に持ち上げた。彼女の銀髪は、まるで剣と同じ金属から作られたかのように月明かりに輝いた。一粒の涙が彼女の黒檀の頬を転がり落ちた。
「泣くな。私が留まれないことを、分かっているだろう」。フョッキは囁いた。そして彼は去ってしまった。