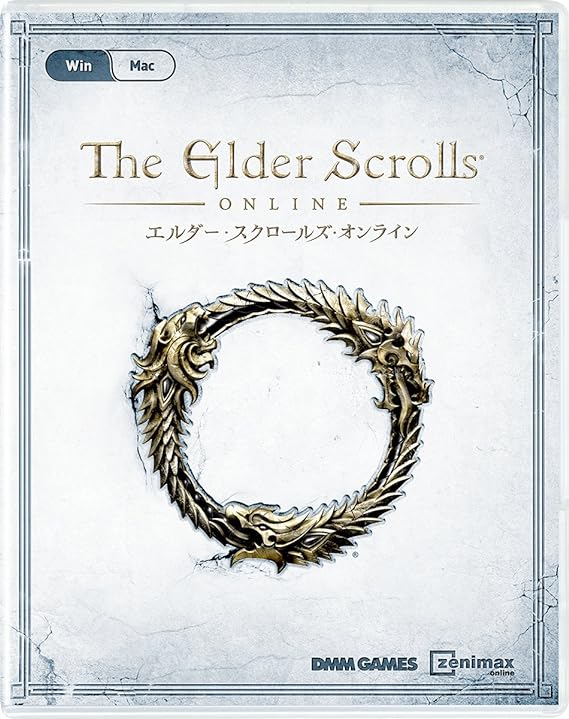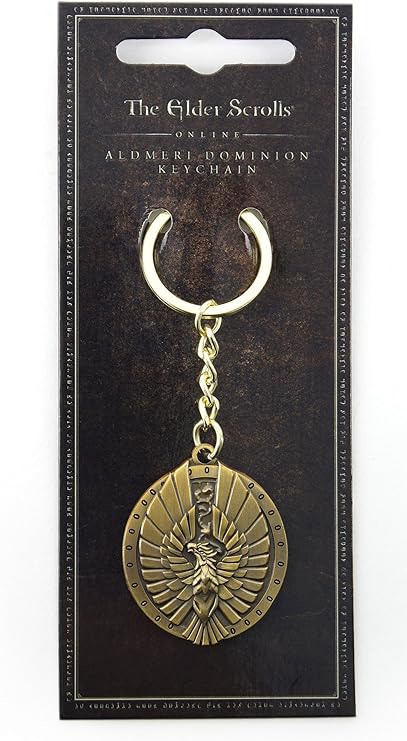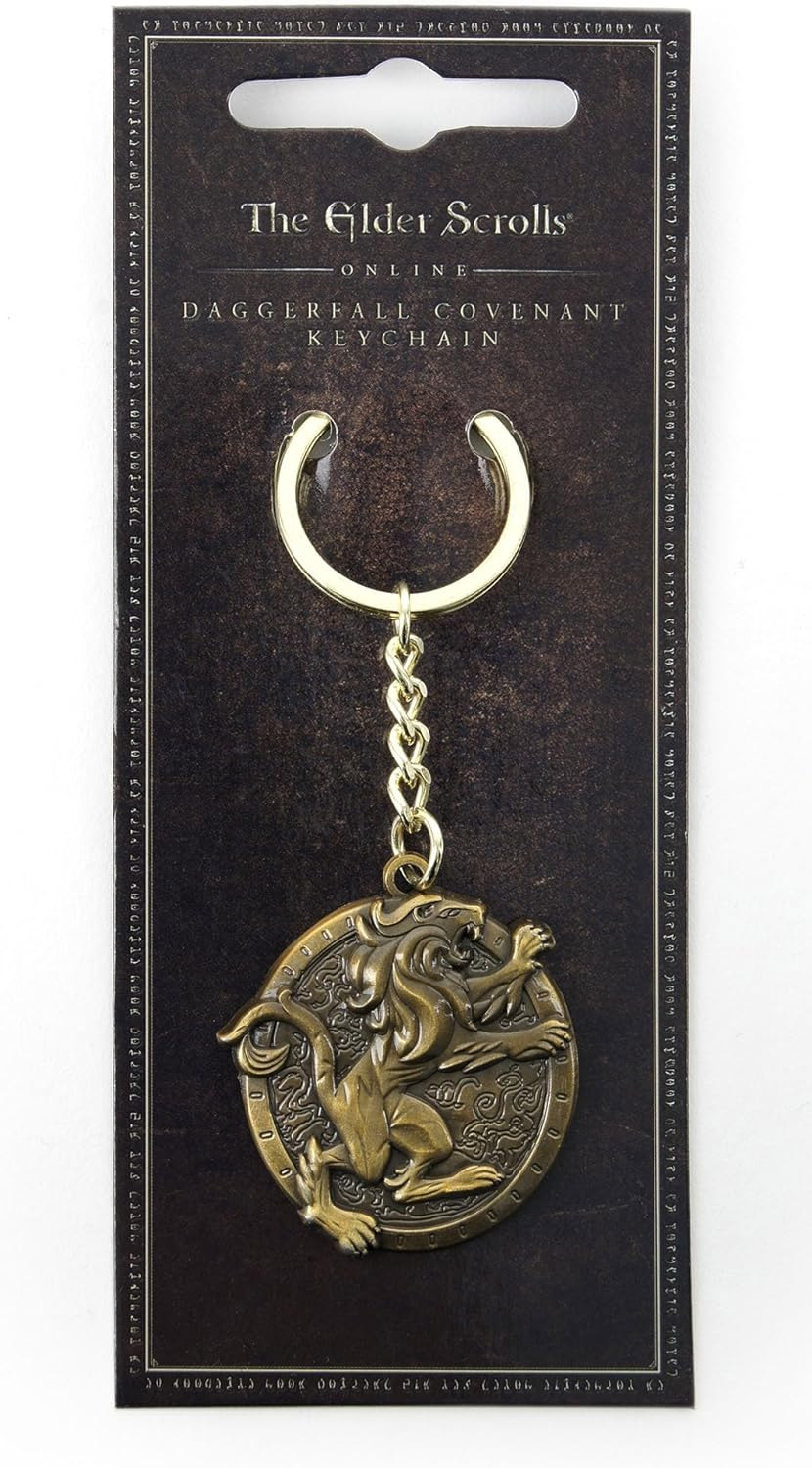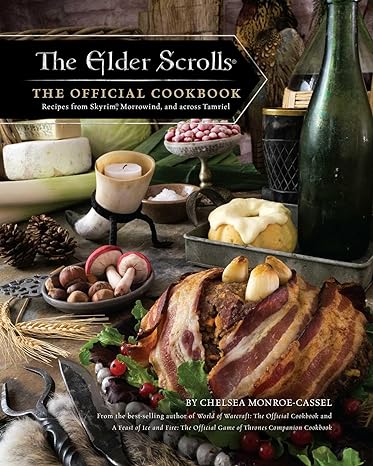デロディールの消失The Whithering of Delodiil
(著者不詳)
かつて、遥か昔、ハートランドにある街があった。デロディールという名だった。その街には素敵な散歩道があり、勤勉な学者たちがおり、技巧優れた職人たちがおり、踊り子たちがいた。そしてまた、デロディールには勇猛で誇り高い戦士たちがいて、散歩道を、学者たちを、職人たちを、そして踊り子たちを守っていた。戦士たちの数は少なかったが、彼らは屈強だった。
そしてデロディールの人々は多くの神々を崇拝していた。彼らは敬虔で、すべての神に敬意を払っていたからである。しかし彼らは他のどの神々にもまして光の淑女を崇めており、メリド・ヌンダのために色とりどりの光に満ちた教会を建てた。それは栄光のためであり、まるでエセリウスの一部分が定命の者たちの世界に降りてきたかのようだった。そしてデロディールの人々はそれに誇りを持っていた。
だが、谷を超えたところにアバガーラスというもう一つの街があり、デロディールが光を尊ぶのと同じように、闇を尊んでいた。そしてアバガーラスはデロディールと同じくらい多くの市民を有していたが、その中に踊り子や職人、学者の数は少なかった。なぜなら大部分は勇猛で誇り高き戦士だったから。その戦士たちは他の国や街に貸し出され、戦争での働きと引き換えに富を得ていた。そのようにしてアバガーラスは独自のやり方で繁栄を遂げた。
そしてアバガーラスの王はデロディールの誇りだった光の教会を見て、こう言った。「アバガーラスはデロディールと同じくらい偉大な街ではないのか?我々は自分たちの偉大な教会を持つべきだ」。そして王はアバガーラスの富の大部分が、彼自らの守護神、すなわちモラグ・バル王のための祠の建設に費やされることを命じた。そしてアバガーラスの人々はモラグ・バルのための広大な祠を打ちたてたが、彼らは職人ではなく粗暴な兵士たちにすぎなかったので、祠は作りが悪く、色合いもひどく、見るに堪えるものではなかった。しかし、それにもかかわらず、祠はデロディールの光の教会よりも大きかったので、アバガーラスの王は自分の街がそのためにデロディールよりも偉大だと自慢した。それでもデロディールの人々は嫌悪感を示すこともなく、今まで通り自分たちの仕事にいそしんでいた。
そしてデロディールのこうした無関心がアバガーラス王の心に穴を穿ち、彼は苦悩の末、狂気へと追いやられた。王は兵士たちを送り、アバガーラスにあったメリド・ヌンダの小さな祠を冒涜させ、それからモラグ・バルの広大な祠へ行き、大きな誓いを交わした。そうしてある家族をデロディールを訪問した罪で祭壇の前で殺し、王は軍を集結させ、谷を越えて進軍し、デロディールの民すべてを捕らえ、光の教会の中でモラグ・バルへの生け贄に捧げると誓った。
そしてアバガーラスの王は自分の兵士をすべて集め、激しく舞うオーロラによって空が輝いたある夜、谷を越えてデロディールに進軍した。だが王とその軍が到着した時、その地が空っぽであることを発見した。デロディールの街はなくなっていた、煉瓦のひとかけらに至るまで!
そして王は空の光の中から笑い声が聞こえてきたように思った。陽気な騒ぎ声は恐怖の悲鳴に変わった。それは上空からではなく、背後にある谷の向こうから来ていた。王は急いで兵士たちを進めて自らの街に戻ったが、彼らがアバガーラスに到着すると、そこに見出したのはまるで光に焼かれたかのように、すっかり破壊された街だった。兵士たちや王の家族の名残といえば、ただ街の壁に焼きつけられた影が見つかっただけだった。
これが、アバガーラスの物語である。だがデロディールの運命については、これ以上のことは何も知られていない。
ブラックフォージThe Black Forge
キンガルド・ナズクリクソーによる在庫目録の報告
グレート・シャックルのための原料:
黒檀合金の冷たい鉄の供給は17500トンで安定しているが、鋳造過程で発生する減量の一般的な割合を考慮すると、これではシャックルを鋳造するのにぎりぎり間に合う程度の量しかない。もう2000トンの採掘のために、鉄の巨像の巨大な死体の脇にある炭鉱の穴に人を送ったほうが賢明かもしれない。後で謝ることになるくらいなら、安全策を取ったほうがいい。
悔恨の木炭の物資における枯渇の原因を発見したと報告することができるのは喜ばしいことだ。灰インプどもが忘れ去られたプラズム菅を通って倉庫に入り込み、RのCを貪り食っていたんだ(このことがわかったのは、腹が膨れすぎて開いた管を通って戻れなくなった奴を1匹見つけたからだ)。我々は爆発するダクトワームを挿入し、それが巣を発見して灰インプどもをすべて粉砕した。悔恨の木炭における物資の不足は、コスリンギの魂なき者に対する拷問のノルマを上げることで作り出されたものだった。
こういうことを言うのは気が引けるが、私の義務として報告すると、たとえシャックルがスケジュール通りに鋳造されたとしても、1000人の無実の者の血の積み荷を受け取れなければ冷却できないだろう。我々は流血執行人サルタンティクスが繰り返し、積み荷はこちらに向かっており「今すぐにでも」届くだろうと請け合っているが、これまでのところ、受け取ったのは約束だけだ。このことをオーバーキンのレベルにまで持っていくのはためらわれるが、この問題の査察を依頼すべき時だと思う。
メリド・ヌンダの解釈Exegesis of Merid-Nunda
エリンヒルのファラスタス 著
率直に言って、メリド・ヌンダの冊子は第一紀初期から我々まで続いてきた神話史の作品の中でも最も奇妙で、最も理解されることの少ないものの一つだ。冊子は部分的な手稿の形でのみ存在しており、帝都の秘術大学蔵書庫に唯一の写しが保管されている(少なくともかつてはそうだった。しかし魔術師ギルドがヴァレン皇帝の失踪に関して非難を受け、シロディールから追放されて以来、かつては立派だったあの蔵書庫が現在どうなっているか私は知らない)。
幸運にも、私はギルドがまだ所持していた頃に注釈を施された冊子を細部にわたって研究する機会を与えられた。それで私は自分のために私用のコピーを作り、エリンヒルへ戻った際にその謎を解き明かす作業を続けられるようにしたのだった。
メリド・ヌンダの冊子を理解する際の問題は二重である。第一に、現存する文書は明らかにより大きな作品の一部であり、おそらくは真ん中あたりから始まっている。前後の部分がないために、残された部分に関する文脈がほとんど分からない。第二に、冊子はアイレイドの言葉をネードの構文で使用する特殊な隠語で書かれており、その中には他のいかなる文献にも見られない、起源不明の言葉が多く含まれている。
しかしながら、過去にウェネグラス・モンハナおよびヘルミニア・シンナによって翻訳された断片を元に作業することで、この謎の多い手稿における重要な部分のいくつかに関して、新しい光を投げかけられると思う。我々の形式は、各文の翻訳を提示し、次にその意味についての私の解釈を記すものである。
「…は九光輝として知られる、マグナスによって連れていかれる道を選んだ者たちである。メリド・ヌンダはこれら姉妹たちの出身であり、同時に、ニーモ・リーやゼロ・リグ、また…」
これは「デイドラ公」のメリディアといわゆる星の孤児たちに対応するようである。星の孤児とはマグナスがアービスの創造から身を退いた際に、マグナスから分かれたアヌイ=エルの原初存在である。これら星の孤児たちの中で最もよく知られているのはおそらく、青星のニーモリーであろう。ニーモリーは非時間的出来事と結びつけられ、ドラゴンブレイク時の昼間の空でさえ視認できると言われている。
「…それゆえ我々は光についてメリド・ヌンダに話しかけ、セネデリンを呼んで大地を拘束した。それは彼女が暗闇を恐れず、引力と回転の波を泳ぐことのできる稀有な存在だったからである…」
言うまでもなく、アイレイドにとって光は創造の4つの要素のうちの1つである。この文はメリディアが野生のエルフにとって光の化身であったことを確証していると思われる。この文の翻訳は間違っていないはずなのだが、正直に言って最後の文の意味は把握しかねる。
次の文はかなり難しかったが、この翻訳は深遠の暁紀についての我々の理解に対し、まったく新しい挿話を加えることになる。
「混沌領域の王たちはメリド・ヌンダの違反を叱責し、彼女のアービスへの帰還を命じ、その際に現存するすべての球は彼らのものだと主張した。しかしメリド・ヌンダは自らの実体から偉大なるドラグレンズを形作り、マグナスの光はそれによって屈折させられた。光線は新しい球を混沌から[削りだし?集中させ?]、メリド・ヌンダはそれを[笑いながら?きらめきながら?]自分のものと主張した」
これはどうやらメリディアのオブリビオン領域として知られる色彩の間の起源を、神聖な意志の行いによって混沌の物質から直接形成されたものとして詳述しているようである。
そして最後に:
「…それゆえメリド・ヌンダは虹の道を端から端まで[乗る?滑る?]。一方の端ではドラゴンを伸ばし、もう一方の端では縮めながら…」
実に不思議な文である。「ドラゴン」とはもちろん、伝統的に我々が時の神アカトシュとして知る神を指している。どうやらこれは「虹の道」(光の多色反射についての言及か)を旅することによって、メリディアが何らかの意味で時間の流れの進みかたを変化させられるということを示唆しているようである。
時間の「速度」を変える?これは後期アイレイドのソーサラー司祭たちの単なる馬鹿げた思いつきか、それとも、デイドラ公のうちでも最も理解されることの少ない存在の性質についての、真の洞察なのだろうか?
一体、誰に分かろう?
黄昏の蔵書庫:希少本The Library of Dusk: Rare Books
第12貯蔵庫:希少本コレクション
立ち入り禁止
品目:
ミモフォヌス著「アセドリクスの難問」
—9つの驚異的な問いと、読者を狂気へと追いやる解答の数々。
著者不明「ホシルの配置」(カリソスもしくはモラチェリス所有)
—シロディールのノルドにおけるアトモーラの民間伝承を記述した叙事詩の物語。
アーリエイト・サーペント著「グウィリム実践」
—知性を持つ怪物が死ぬ瞬間に、そのマジカを吸収する方法。
アルカン著「バーン・ダルの第3の巻物」
—偉大なる盗賊がいかにしてヴィベクから「第37の教え」を盗んだか——彼がそれを書き記すよりも前に。
「アレッシアとベルハルザの手紙」
—初代女帝と人牛との親密な往復書簡。
リンダイの異端者著「十祖先による十一のその他の勅令」
—古典「十一勅令」のパロディで、十祖先はデイドラよりもアーリエルを崇拝していたと仮定している。
技師カグレナク著「ヌミディウムの青写真」
—巻物がすべて行方不明——回収してくれば報酬あり
ペリナル・ホワイトストレーク著「ロルカーンの心臓との会話」
—アービスの本質についての考察。注意:創作の可能性大。
操舵手トパル著「南海岸は東の海ほどにも遠く」
—偉大なるアルドマー探検家の航海記。
アークメイジ・シャリドール著「考察」(初版本)
—ドラゴンの起源と性質に関する学術論文。
猿の預言者マルク著「アレッシアの教義:手稿原本」
—アカトシュの非エルフ的性質の教理を定義した長い論説。
モリアン・ゼナス著「アポクリファの研究」
—ゼナスが信じることを拒否したアポクリファから判明した真実の概説。全14巻。
透明なる者著「書簡的洞察」
—有害なデイドラの禁じられた祈祷。
コルヴス・ディレニ著「グリモア」
—強大な召喚師の呪文の秘訣。
匿名の作者著「メリド・ヌンダの冊子」(完全版)
—メリディアの本質と、彼女を星の孤児たちと同一視することの誤りを解明する作品。
伝統的な「好色なアルゴニアンの侍女」(完全収録)
—修復中——蔵書庫司書により誤って破損。
吟遊詩人のフョッキ著「愛と剣さばきの技法」
—信じがたく、かつ奇妙に説得力のある数々の功績を持つ遊び人のノルド、フョッキの有名な自伝。希少ではないが、本蔵書庫で年間を通しての人気作。
光なき土牢The Lightless Oubliette
光なき土牢に関するキン報告
過去に光なき土牢での勤務を経験したことがないのなら、よく注意を払うことだ。なぜなら、ここはミスを犯すべき場所ではないからだ。土牢はあの光の尻軽女の虜になったしもべたちのために特別に建設された拘留施設だ。我らがドレッドロードが彼女をどう思っているかは知っているだろう。もしあのオーロランやラストラントたちのどれか1人でも、お前の当番中に逃げ出してみろ。第2級の低速身体分解で済めば運がいいくらいだ。
さて、俺はお前が701の布告をよく知っているかどうかとか、強制追加条項の章や節をそらんじているかどうかとか、そういうことは気にしない。光なき土牢で大切なルールは次のものだけだ。
1.白や黄色に光るクリスタルを施設内に持ち込んではいけない。
陰気なのが好きだからじゃねえんだよ、馬鹿。囚人たちは光の特定の波長を捻じ曲げて、自分たちのために利用できるからなんだ。照明には青いクリスタルを使うか、あるいは剥き出しの炎ならもっといい。
2.囚人たちを拷問して遊んではいけない。
これにはエルフ王も含まれる。いや、俺はなぜかなんて知らん。ただそういうことになっているのだ。噂じゃドレッドロードはあの光の尻軽女のためにとんでもない驚きを企画していて、そのためには彼女のしもべたちの身体が無傷で残ってなくちゃならないんだと。本当かもしれんが、俺は知らんよ。
3.ちゃんと後始末をすること。
ここは最も警備が厳重な施設だ。だから魂なき者は誰も入ってはいけない。管理人でもだ。汚したら、ちゃんと洗うこと。これには実戦演習の時に飛び散った体液も含まれる。今度またフラグストーンに染みが付いてるのを見つけたら、次の勤務時間は痛みの輪の中でやらせるからな。
混沌のクリエイシア:アズール・プラズムChaotic Creatia: The Azure Plasm
ライザンディウス博士 著
境界間神話神秘学の博士として、私は長い間魂と身体の問題、すなわち消滅後のデイドラの身体の再形成、および「面影」として一般に知られるエキスの周囲での身体の形成に興味を抱いてきた。我々がコールドハーバーへの移転を強制されて以来、輝きの淑女の取り計らいにより、私はこの工程を直接観察する数多くの機会を得ることができたため、ムンダスにおいては単なる推測にすぎなかった多くの仮説を確証できる立場に身を置いている。
長い間理解されてきたところでは、デイドラは「魂」として知られるアヌイ=エルのアニムスを欠いており、その身体が破壊されても死ぬことはない。ムンダスにおいて殺されたデイドラは単に「消滅」してやって来た次元に帰るだけであり、そこにおいてデイドラの形態、あるいは「面影」が少しずつ新しい身体を形成し、いずれデイドラは復活する(これは自らの出身地であるオブリビオンで殺されたデイドラにも起きることである)。
さらに、我々がデイドラ自身から学んできたことによれば、デイドラの身体は混沌の物質そのものによって形成されており、これはオブリビオンの「クリエイシア」という、無形かつエネルギーを持つ素材としての面影の周囲に蓄積し、形態の遺伝パターンに順応する。
ムンダスにいた頃、私は単純にもこのクリエイシアを虚無のどこかに渦巻いている、霧状の無形物質のようなものだと考えていた。我々がコールドハーバーに到着して後、コールドハーバー全土に広がるこの青いスライムの液だまり、我々が今では「アズール・プラズム」と呼んでいる物質が、実はクリエイシアがこの次元において取る形態だと気づくまでしばらくかかった。その延長として、私は混沌のクリエイシアがオブリビオンのそれぞれの領域において、次元に対応した、互いに異なる形態を取るのではないかと推理した。この理論は後に、ソージュルナーという名の、無数の次元で存在することを直接経験していたズィヴィライの盗賊によって、私にとっては確証済みのものとなった。
実際、プラズム付着の過程が進行しているところを観察できる、秘密の洞穴の1つを初めて私に教えてくれたのはソージュルナーだった(デイドラが「生まれる」この類の洞穴を見つけるには、ただアズール・プラズムのゆったりした流れを観察し、その向かう先を追っていくだけでいい。プラズム付着は付近の源泉からの遅い吸収を引き起こすからである)。面影が少しづつアズール・プラズムを吸収し、それを一般的から特殊へと変化させていき、ゆっくりと巨大な爬虫類型のデイドロスの大きさと形になっていくのは、実に見事な光景だ。
そして魂なき者という名で知られる哀れな奴隷たちがいる。どれも死に際してムンダスから誘拐されてきた定命の者であり、その魂はモラグ・バルによって、何か想像もできないような目的のために盗まれ、その代わりとして面影がここコールドハーバーにおける紛い物の身体を形成しているのだ。しかし彼らはオブリビオンの生まれではないから、魂なき者の身体は人生に倦み疲れた身体の惨めな模造品でしかなく、急速な消耗と腐敗に苦しんで死ぬ。しかもその死は解放ではなく、面影は再び身体を形成し、それは無限に繰り返されるのだ…
以上が事実である。以下に続くのは、ソージュルナーの不定期かつ予期せぬ訪問の最中に彼と交わした会話から生まれた思弁である。彼の理論では、魂なき者の身体が不完全なのは、それがアヌイ=エルの魂の集中原理を失っているからであり、それゆえに彼らの身体の面影は不完全な模様になっている。それはあり得ると私は同意し、それから魂を失っておきながら、何か別のアヌイ=エルの内的姿を所有している魂なき者の存在という、理論的な可能性を提示した。この魂なき者の「パラゴン」とでも言うべき存在はコールドハーバーにおいて、ムンダスでまとわれていた身体の完璧な複製である無欠の身体を形成するだろう。実際、もしこのパラゴンが十分に高いアヌイ=エル原子価を帯びていれば、パドマーのクリエイシアとの接触によって、その身体はほとんど一瞬のうちに形成されるだろう。
ソージュルナーは私の理論を一笑に付したが、にもかかわらずその発想には興味をそそられたらしかった。彼はさらに思弁を進めて、もしそのようなものがあり得るとすれば、おそらくそれはムンダスが存在の危機に瀕している時に発生するだろうと言った。その場合、ニルンの心臓は自発的にそのような「パラゴン」個体を、破壊から自らを守る手段として生産するだろう。定命の者の身体が伝染病を撃退するのと似たようなものである。
ああ、ソージュルナー。君の刺激的な話が懐かしい。なんという空想の飛躍だろう!しかし、この次元での長期にわたる私の生活で見てきた驚異の数々を思えば、本当に不可能なことなどあるだろうか?
戦いと苦闘の人生A Life of Strife and Struggle
ラロリアラン・ダイナー王の私的な覚え書き「アイレイドの最後の王」への注釈
構成:慣習に則った10章立て。10人の祖先のそれぞれに1章ずつ
第1章:後期アイレイド時代の苦闘(263-331)
—我が父は女帝に辱められた
—ネナラータのシロディール帝国への隷属状態
—非奴隷経済への困難な移行
—強制されたアレッシア八大神の受容
—我、ネナラータの王冠を戴く
—高まる無力と絶望
第2章:アレッシア教団、アイレイドの無秩序(332-371)
—帝都の反乱
—我、皇帝に忠誠を誓う
—シロディールの神権政治
—アイレイドの迫害
—従属国家の縮小
—ネナラータの孤立
第3章:失われたネナラータへの涙(372-374)
—皇帝の最後通告
—頑固者たちとの協議
—ネナラータでの最後の時
—シロディールからの不穏な旅路
—頑固者たちの虐殺の知らせ
—ゴブリンに噛み殺される
第4章:ビョルサエの避難民たち(375-452)
—ディレニによる歓迎
—オークを追放し、街を設立
—湖のビスネンセル
—ブレトンとの緊急緩和、オークとの平和条約
—シロディールからの不快な知らせ
第5章:太古の探究者の驚異(453-460)
—ハルメアス・モラの邪悪な教団
—奇妙な儀式、消えない幻視
—大司祭ウルスキャントが権威を主張する
—夜の殺人
—王家の逃亡
第6章:ディレニの中の聖域(461-477)
—バルフィエラ島
—リャン、エイデン、レイヴン
—スカイリムとの戦争
—戦術家にして戦略家:我が天職の発見
—エルフ殺しのホアグ倒れる
第7章:アレッシア軍の接近(478-479)
—ハートランドから聞こえる不満
—アレッシア主義に転向するブレトンの発見
—宣教師たちの処罰
—アレッシア軍の西進
—クラグローンの陥落
第8章:ハイロックの集結(480-481)
—隷従王への使者
—エイデン、不承ながら権利章典に署名
—農場労働者たちを軍団兵に
—軍がハイロックへ接近
—アレッシアの虐殺
第9章:グレナンブリア湿原の戦い(482)
—開幕の小競り合い
—餌をまく
—ファオルチュ罠にかかる
—隠れていた騎士たちの突撃
—コルヴスとカラーニの召喚獣
—アレッシアの潰走
第10章:ネナラータへの帰還(482-484)
—アレッシア軍の追撃
—クラグローンでの抹殺
—マルーカティの殉教者たち
—ハートランドへの帰還
—ネナラータにおびき寄せられる
—モラグ・バルの狡猾な罠
—コールドハーバーの囚人
ここではたっぷりと時間がある。私の筆記用具が取り上げられなければいいのだが。いかにドレモラとはいえ、そこまで残酷になれるだろうか?
定命の者により召喚されたI was Summoned by a Mortal
デスブリンガー・クランのキンヴァル・ゼッデンカシク 著
私が記憶している限り——そしてドレモラなら誰でもそうであるように、私の記憶は、特に復讐に関する記憶は優れている——私は自分のクランの士官たちに忠実に仕えてきたし、それを通じて我が主、モラグ・バルに仕えてきた。しかしながら、常にというわけではなかった。恥ずべきことながら一度だけ、私は他の者に仕えることを強制されたからである。
私は終わりなき階段を警備する任務に就いていた。これはいつでも楽しい仕事だった。というのも、通りがかる魂なき者を馬鹿にしたり嫌がらせをしたりでき、しかも奴らのノルマ達成について責任を負わなくてもいいからだ。爪の柱のかげから飛び出し、「見つけたぞ、弱き者め!」と叫ぶのは、面白くてしょうがない。
私はダークアンカーの鎖の連結部の後ろに潜み、近づいてくる魂なき者をいきなり殴り倒し、「相手にならん」と嘲笑して、恐怖を与えてやろうと待ち構えていた。すると突然、角から足先まで体中にちくちくと痛みを感じた。目まいがして、危うく青いプラズムの池に倒れこんでしまうところだった。そして突然、終わりなき黒い虚無の中に自分が投げ込まれるのを感じたのだ。
最初は不安を感じなかった。終わりなき黒い虚無に投げ込まれたことのない者がいるだろうか?その場所で自分の体が具現化し始め、空気の味を感じて、初めて最初の不安を覚えた。「弱き者の臭いがする」と私はつぶやいた。私はまったく正しかった。
そこで初めて、私を召喚した者の声を聞いた。召喚者は「ああ、これはなかなか強そうだな」と言い、自分の置かれた恐ろしい状況が明らかになった。なにせ、私を召喚したのは…定命の者だったのだ。
私はぎょっとして振り向き、いったい誰がニルンとの無限の距離を超えて私を召喚したのか見ようとした。すると、目の前にいたのは背の高いサマーセットのエルフだった。こうした手合いは知っている。私はこれまで少なからぬ数のアルトマーの魂なき者をいたぶってやった。それも大いに楽しんで。こいつらは定命の者にはふさわしくない、偉ぶった傲慢さを隠そうともしない。このエルフは私に軽い、値踏みするような一瞥をくれた後、背を向けて「ついてきて戦え。虫の教団の信者どもを退治する」と言った。
虫の教団の信者。この屈辱を想像できるだろうか?憎たらしい定命のエルフによって自分の任務から引き離されただけでなく、そいつのためにマニマルコの、つまり我らがドレッド・ロードの副官にして副王となるべき存在のしもべを殺さなければならないのだ!私は抵抗しようとして我が不屈の意思を振り絞ったが、この定命の魔術師の拘束呪文はあまりにも強力だった。私にできることは「誰も逃さん!」と言ってこの者に従い、一対のたいまつを通り過ぎて地下のトンネル迷路へ向かうことだけだった。
「ドレモラよ、お前は偉大なるヴァヌス・ガレリオンに仕えるのだ」と私の召喚者は宣言した。誰もそんなことは聞いていない——自分を奴隷にしている主人の名前を知る必要がどこにあるというのか?しかし私は考え直し、その名を我々の誰もが持つ長いリストに心の中で付け足した。「復讐」という名のリストに。
私は付き従ったが、私の召喚者が身を隠すためにしゃがみ込んでも、ただこの召喚者をにらみつけて心の中で「お前の心臓を貪り食ってやる」と考えていた。しかし実際は、このヴァヌスとかいうエルフについていくしかなかった。というのもトンネルは数が多く入り組んでいた。我々ドレモラは恐れを知らず無慈悲で、オブリビオンのどこを探しても戦士としては右に出る者がいないとはいえ、方向感覚には優れていない。密使の任についていた時、私はムーンレスウォークのど真ん中で道に迷い、出発地の光なき土牢に戻ってきてしまうことで有名だった。
そのうち、ヴァヌスは頻繁に立ち止まり、耳を澄ませるようになった。これが私の怒りと苛立ちを一層あおった。結局、彼は足を止め、私に向かって「静かに!」と言った。まったくもって理不尽だ。私は一言も言葉を発していなかったのだから。しかし奥のトンネルから人間の話し声が聞こえてきた時、私はなぜ彼が止まったのかがわかった。一瞬もためらうことなく、私は自分のグレートソードを取り出して前方に突進していった。「近くに抗いし者がいる!」と叫びながら。エルフは悪態をついて後からついてきたが、自業自得だ——私は命令を忠実にこなしていたのだから。
その後の時間は、真のドレモラならば戦闘中に誰でも感じる、あの赤い憤怒の中で過ぎていった。しかし、普段は流血の殺戮が喜びをもたらすものの、自分が手にかけているのはドレッド・ロードが望まない相手なのだという意識にさいなまれ、喜びとは程遠い体験だった。私が虫の教団の信者たちの手足や頭を切り落としている間、エルフの強力な魔法のエネルギーが火花を散らしながら私を通り過ぎ、離れた場所にいる敵を焼き払っていたが、私は屈辱に打ちひしがれ、破壊の狂騒にひたれなかった。エルフは私が最後の虫の隠者を細切れにしているところにずかずかとやって来て「こいつらもこれで終わりだな。思い知ったか、マニマルコ!」と言ってほくそ笑んだ。
「相手になる者などいない」と私は不機嫌に応じた。すると、再びあの奇妙なちくちく感が襲ってきた。私をニルンへと誘った召喚術が弱まってきたのだ。拘束が解けると私はエルフに向かって威嚇の一歩を踏み出したが、そこで再び私の周囲の次元が回転し、また終わりなき黒い虚無の中に戻ってしまった。
感覚を取り戻すと、私はターコイズ色のスライムの池に横たわり、見上げると上司であるキンリーヴ・ザルゾルキグの笑顔が見えた。「さて、ゼッデンカシク」と彼はうなり声をあげた。「任務中に持ち場を離れたのか?こいつは痛みの輪ものだぞ!」
「しかし、キンリーヴ」と叫びながら、私はがばっと起き上がり言った。「仕方がなかったのです!私は召喚され、ニルンに向かわされてしまったのです——定命の者によって!」
ザルゾルキグはさらに口を広げて微笑んだ。「そんなくだらん嘘をつく奴には、痛みの輪をさらに追加してやろう。さあ歩くのだ、ゼッデンカシク」と彼は叫んだ。棍棒で私を叩きながら。「左、右、左、右、左、右…」
ザルゾルキグが笑うとロクなことがない。キンリーヴだろうが関係ない。彼の名前も私のリストに入れておこう。
侮辱の法廷の手続きProtocols of the Court of Contempt
ジャッジ・シベン 著
すべての手続きは厳密に記録されるべきものとする。ただし、その手続きが記録によって影響を被ると命ぜられた場合は例外とする。
罪ある者は本法廷に敬意を持ってあたるものとする。でなければ執政官ボグトロにより適切な処罰を受けるものとする。
罪ある者は適切なかつらを身に着けたスキャンプの格好で審議に参加する権利を持つものとする。ただしスキャンプは本質的に低俗であることから、侮辱の法廷で口をきくことは禁じられている。
罪ある者はこれらの手続きにおいて、自らの屈辱を時間をかけて、最も激しい言葉を用いて表現することが推奨されている。裁判官と執政官の余興のためである。
侮辱の法廷の公平性についての評判は、100パーセントの有罪率によって証明されている。
連れていけ!
名誉を失ったクランの誓いOath of a Dishonored Clan
ライランス 作
目的が達成されるまで、決して再び休むことはない。
誤りし者に報復する機会を探し続ける。
ヴァルキナズ・セリス:裏切りの代償を払わせよ。
オーバーキンに対する我々の義務でさえ、これには及ばない。
二度とフールキラーズ・クランの名を耳にすることなかれ。それは苦痛である。
我らは目的を助ける者に対しては寛大になるだろう。
デスブリンガー・クランの偽りの優位に終止符を打つ。