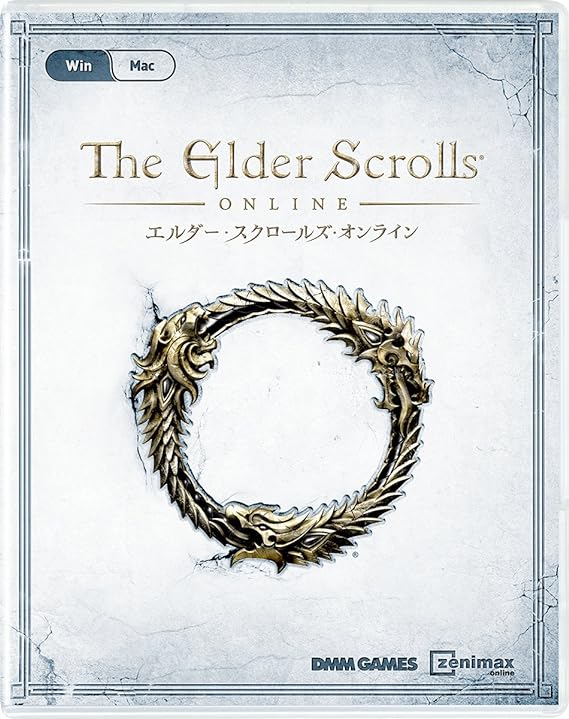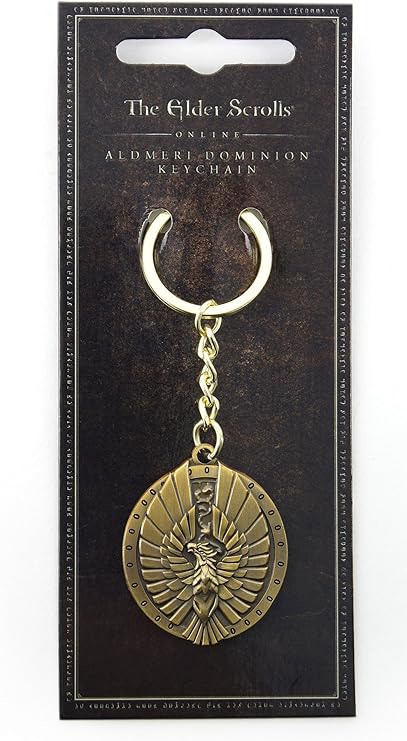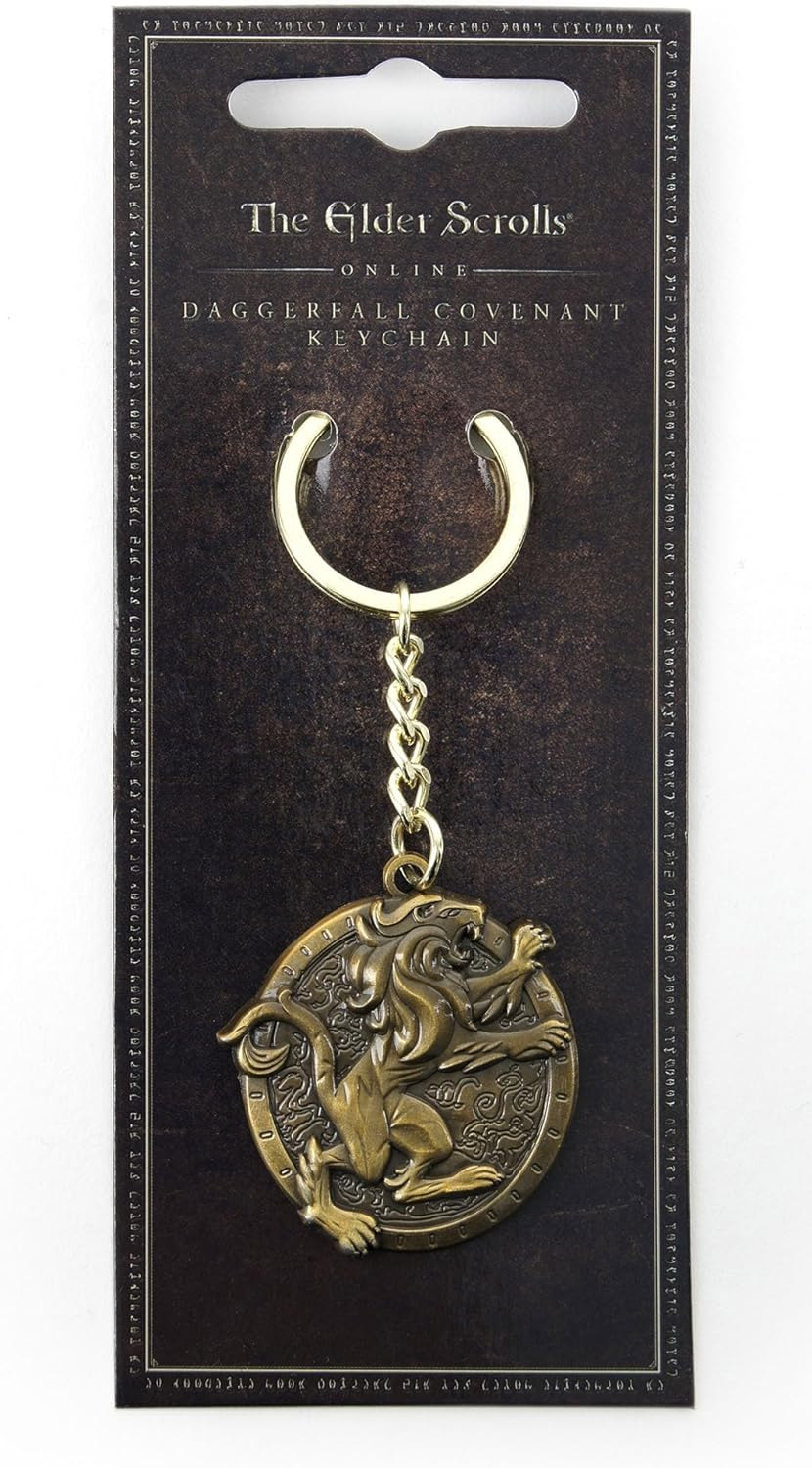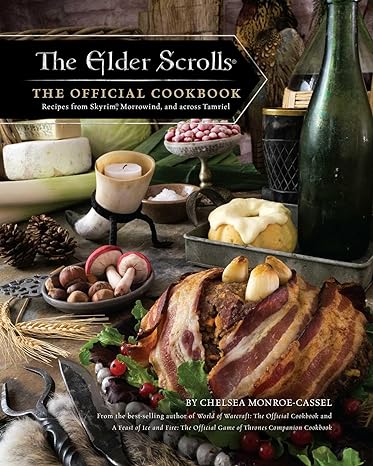エボンハート・パクトへの案内Guide to the Ebonheart Pact
エボンハート・パクトはモロウウィンド、スカイリム、ブラック・マーシュまでの広範囲に広がる各国に結ばれた予想外の同盟で、ダークエルフ、ノルド、自由アルゴニアンが共同防衛のためにまとまったものである。同盟国の大きさと距離のおかげで、パクトは内部の反目や不協和音とは比較的無縁な状態にある。ノルドとダークエルフには自国内で取り組むべき案件が非常に多く、お互い相手に干渉する時間がほとんどない。
エボンハート・パクトが生まれたのは第二紀572年、タムリエル北部への第二次アカヴィリ侵攻に対応するためだった。ノルド、ダークエルフ、自由アルゴニアンは、タムリエルの残りの地域を虐殺と隷属から救うために力を結集した。戦時中に結ばれたこの同盟は、大陸に急に登場した新興勢力となった。最初はダークエルフが昔からの宿敵および以前の奴隷との同盟を維持できると信じた者は少なかったが、色々なことがあった十年が過ぎたのちも、パクトは強力で無傷のままだった。
パクトは「グレートムート」が支配する。各国の種族代表が平等に扱われるこの評議会は、短期と大声で知られるだけでなく、相互の尊重と、どんなことがあろうとパクトを維持しようという驚くべき意志でも有名だ。平等でなければ、ノルドとダークエルフの誇りを満たし、以前は奴隷にされていたアルゴニアンの傷を癒すことができない。
不可欠、というより同盟の最も重要な一部であろうモロウウィンドのダークエルフは、よそよそしく誇り高く、そして非常に奇妙である。彼らは懸命に「劣等の」同盟国への軽蔑を隠そうとするが、現在の危機で競合する他同盟を寄せつけないためには、ノルドの強い武力とアルゴニアンの策略に富んだ機知が必要なのだ。ダークエルフは天才的な器用さと深い経験を武器にして、パクトに不可欠な反応と即応能力を提供している。アルドメリ¥ドミニオンにもダガーフォール・カバナントにもこれほどの力はない。パクトは優秀な戦士と妖術師を配置している。そして他の種族には匹敵するもののない財産がある。3人の生き神、アルマレクシア、ヴィベク、ソーサ・シルがその中にいることだ。
スカイリム東部のノルドは恐れを知らず攻撃的で、勤勉かつ進取の気性に富む。彼らは戦争に秀で、交易で栄え、探検家、開拓者として他に並ぶ者はいない。力強く、頑固で、たくましい彼らには戦いで問題解決を図る習慣がある。ノルドは陽気に戦闘になだれこみ、その獰猛さは敵を恐れ震撼させる。彼らはそれを認め、エボンハート・パクトのための突撃隊という役割を楽しんでさえいる。ノルドは率直で企むところがない。そのためグレートムートの会議では単純な解決法を支持するが、悪賢いアルゴニアンや抜け目のないダークエルフに投票で負けることもよくある。しかし戦場において彼らに勝る者はいない。パクトの将軍はノルドであることが多く、戦場の戦士のほとんどもまたノルドである。ノルドにはこだわりがない。これは戦利品を最初に獲得するという意味でもある。
アカヴィリに対して決然と武力介入したことにより、ブラック・マーシュのアルゴニアンはダークエルフの奴隷状態から自由を獲得し、その教訓から彼らはパクトの重要な一員となった。控え目かつ異質な彼らの無表情と抑揚のない話し方は他の種族に真の動機を理解させづらくしている。それでも彼らには冷静な知性がある。信頼するのは遅く、理解するのは難しいが、生得の敏捷性のおかげで、彼らは魔法も隠密活動も武器も同じように軽々と操ってみせる。長年国境を防衛してきたため、戦争において、より強力で昔ながらの組織化された軍隊に対しての専門家である。陸でも水中でも同じようにやすやすと動ける彼らは、パクト軍のために偵察隊、前衛隊の役割を果たしている。アルゴニアンの文化の他の側面は部外者にほとんど理解不能で、そこには彼らの社会的階級や集団意思決定も含まれる。彼らの代表が説明なしに奇妙な提案をすることがあるが、同盟国は彼らのやることにすべて必ず理由があることを学んだ。
今日、スカルド王の若きジョルンがムートの実質的上級王になっているが、必ずしも同盟全体の支持を得ているわけではない。パクトの一員として同盟を維持し結束させるために奮闘しながらも、各国は各々内部の脅威にも対応しなければならない。野戦でドミニオンやカバナントと対面する前に、未解決のこうした脅威のために自滅する可能性もある。
スカイリムのノルドNords of Skyrim
我が民、我が誇り
フロスムンド・ウルフハート 著
尊敬すべき読者よ。私はフロスムンド・ウルフハート、ノルド人だ。しかし何より重要なのは、私がスカイリムで育ったノルドである点だ。
本書は、タムリエルの人々に、知られるべき我が民について知ってもらい、この地方の真の姿、すなわち争う余地のないその美しさと文化の地である事を理解してほしいという切なる願いをもって書いている。
よく知られている点のいくつかは、間違いなく真実だ。身体的にも、ノルド人は印象的で人目を引く。身長が高く、骨は強く、筋肉は太い。髪は金髪で、先祖からの伝統に則って編んでいる。スカイリムは毛皮となる生物の宝庫であり、そのような有効な資源を利用しないのはもったいないので、我々はよく毛皮を身にまとっている。
ここまで読んだところで、私の言葉の強さと、北方の「野蛮人」としての教養に驚いただろう。そう、多くのノルド人は読み書きができる。子供の頃、父が書き方を教えてくれたのだ。その父も、またその父もそうだった。
スカイリムの子供達がたしなむのは、言語技術だけではない。私たちは職人でもあり、彫刻家が陶器を作るように、我々は代々、鋼の扱いを学んできた。
実際にハイロックとシロディールから来た旅人が、スカイフォージの火で鍛造され、グレイ・メーン家の神業ともいえる職人の手によって危険なまでに美しく磨き上げられた剣を見て、信じられないという様子で嘆くのを私は見た。
だがそんなことが可能なのか、と諸君らは疑問に思うかもしれない。雪と泥に覆われた地から出たことのない者たちに、そのような偉業を成し遂げることができるのだろうか?もう一度言うが、そうした地域的な偏見は真実を曇らせる。
スカイリムの街は、どれもノルドの創意力と職人芸の証だ。主要都市は以下のとおりである。ソリチュード—上級王の王座があるスカイリムの首都。ウィンドヘルム—古く名誉ある雪中の宝石。マルカルス—遥か昔から存在する、岩盤を削って造られた町。リフテン—秋の森の金色の影に位置し、極上の魚とハチミツ酒を生み出す街。そしてホワイトラン—ジョルバスクルを囲むように造られ、高貴なる同胞団や人々から崇拝されるスカイフォージの故郷。
尊敬すべき読者よ、以上が全体像だ。我々ノルドは諸君らの想像通りであり、また、それ以上でもある。
しかし、本書を真実への唯一の入口と捉えないでほしい。馬車または船を予約して、北方へ旅をしてみるといい。スカイリムを自分の目で確かめてみるのだ。神が最初に世界を形作ってから変わらぬスカイリムの姿を、ノルド人と同じ目線で見てもらいたい。
ダンマーの名家の格言Mottos of the Dunmeri Great Houses
ヴィリン・ジリス 著
息子よ、簡単な事実さえ覚えられないお前の無能さのせいで、ことあるごとに我が一族は恥をかく。これはヴァーデンフェルの名家に語り継がれる言葉と、各家が守護者として祀っている聖人たちをお前に伝えるための記録であり、もしお前がまた、我が家の取引相手であるフラール家とドーレス家の商人貴族たちを混同するようなことがあれば、今度こそお前を勘当する。これは改めて言う、お前への最後通告だ。
レドラン家:「レドランは戦士であり、その務めは第1にトリビュナルに、第2にレドラン家に、第3に家族と一族に対し果たされるものである」
—レドラン家の守護聖人は指揮官、聖ネレヴァルである。
インドリル家:「正義は眠らない。インドリルが命じ、聖堂が裁きを下す」
—インドリル家の守護聖人は公正なる聖オルムスである。
フラール家:「公正かつ自由な取引が三大神を称える」
—フラール家の守護聖人は巡礼者、聖ヴェロスである。
ドーレス家:「無知蒙昧の民に文化と真実を広めよ。これが我らの責任であり義務である」
—ドーレス家の守護聖人は、敬虔なる聖ロシスである。
テルヴァンニ家:「力強い意志を表現することが、真の栄誉を先人に与える」
—テルヴァンニ家の守護聖人は殉教者、聖ヴォリスである。
第6の名家、影の家、ダゴス家に伝わる格言が欠けているのにはきっと気づいていないだろう。これはあの家がレッドマウンテンの戦いで滅ぼされ、断絶したからである。そののち残った名家がトリビュナルに捧げる聖堂を建立した。もしダゴス家のことを気族仲間の前で口にしたら、私はお前を勘当する。
気付いただろうが私はここまでで2度、お前を勘当すると警告している。これは私がメファーラやヴィベク卿ほど冷酷ではないということだ。私の心は弱く、お前を家族から簡単に取り除けずにいる。
この文章を肌身離さず身に付けていなさい。そしてこの家訓を見ては我が身の行いを正し、貴族の立場に恥じることのないように。お前の愚かさで我が一族を汚すことのないように。2度とお前を人前で大ばか者と呼ばずにすむことを願っている。
私たちの中のアルゴニアンArgonians Among Us
シル・ロスリル 著
アルゴニアンは鱗に覆われ、知性に劣り、我々の日常生活の一部となっている。モロウウィンドとその周辺地域では、どの都市、どの街にもその姿が見られる。我々の食事を運び、子供たちに服を着せてくれる…しかし実際のところ彼らは何者なのだろう。
アルゴニアンは元々ブラック・マーシュとして知られる地域の出身だ。じめじめとした陰鬱な土地で、沼気を発し、虫がうじゃうじゃといる。その生まれ故郷でアルゴニアンは悪臭を放つ水溜りに住み、原始的な部族の神を信仰している。彼らの民間魔術と単純な部族の軍隊は、人間や勇敢なエルフに対してきちんと防御できたことはなかった。
沼地はシロディール軍により第一紀2811年に初めて制圧された。この残虐で気まぐれな人間たちは、人間の山賊王の支配を終わらせるためだけにその地域に侵入したのだった。籠手をつけた手の文明がアルゴニアンの元に入ってからは、彼らの故郷は主に流刑囚の土地の役目を果たした。無思慮で野蛮なシロディール人は無情にも最も暴力的で不安定な犯罪者たちを沼地に放った。
ほぼ600年前、この鱗のある召使の種族の生活にダークエルフが介入した。第二紀の黎明期に我々は本格的にアルゴニアンと共に働き始めた。部族全体がヴァーデンフェル、ストンフォール、デシャーンの安全で乾いた気候の土地に移住した。我々は彼らのかなり恥ずかしい外見を隠すために衣類を作り、世界に送りこんだ。彼らが新しい環境で学び仕えるためだ。我々の気前のよい行為に対して、アルゴニアンには見返りをほとんど求めなかった!それでもあの悪臭放つ地の住民全員が本当に感謝しているわけではない。
事実、我々の時代の密接な協力関係は数年前に終わりを告げた。ナハテン風邪の名で知られる恐ろしい病気が沼地の奥深くの瘴気から生まれ、地域一帯に広がった。アルゴニアンの呪術師の手による産物と噂された病は、爬虫類を先祖に持つ者以外を襲い、数えきれないほどの犠牲者を出した。最も悲劇的だったのは、他の種族がアルゴニアンを疫病を広めた者として恐れるようになったことだ。我々がアルゴニアンを発見の旅に送りこもうとするたびに、拒絶されてしまった。
現在、もちろんアルゴニアンはエボンハート・パクトにおいて共に立ち並んでいる。かつては単なる召使だったが、今はこの単純な爬虫類の評価が高まった。彼らは我々の軍事同盟において強力で誇り高い貢献者であり、家庭においては家族の面倒もよく見てくれる。
私たちの中のアルゴニアンは、生活を豊かにしてくれる存在だ。
先人とダンマー(要約)Ancestors and the Dunmer (Abridged)
彼らと共に歩む亡霊
ダンマーの死者の魂は、他の種族でも皆そうかもしれないが、死後も生き続ける。亡くなった先人達の知識や力はダンマーの家に恩恵をもたらす。生きている家族と先人を繋ぐものは血や儀式、そして意志である。結婚したことで新たにその家族に加わった者は、儀式と家に対する誓いを行うことによって家の先人と交流を図り、恩恵を受けられるようになる。とはいえ、結婚して家に加わった者は純潔の者と比べると先人との繋がりは薄く、自分自身の先人との繋がりも保ち続ける。
家の祠
それぞれの家にはその家の祠がある。貧しい家では、家族の遺品が置かれて崇拝するだけのただの暖炉棚程度の物かもしれない。裕福な家では、先人専用の部屋が用意されている。この祠は待機の扉と呼ばれ、オブリビオンへの扉を表している。
ここで家族の者は捧げものや祈り、責務の誓い、家族にあった出来事の報告を通して先人達に敬意を払うのである。その見返りとして家族は先人達から情報をもらったり、指導を受けたり、祝福を与えてもらう。このため、先人達は家、特に待機の扉との境界線における守護者なのである。
定命者の戦慄
霊魂は定命者の世界を訪れることを好まず、訪れるのは義務感や責任感によるものでしかない。向こうの世界の方が楽しく、少なくとも冷たくて厳しい、痛みと喪失感に溢れた現実世界より居心地が良いと魂は言う。
狂った霊魂
自分達の意思に反して我々の世界に留まることを余儀なくされた霊魂は、狂った霊魂や亡霊となる可能性がある。死ぬ際の状況が悲惨だったという理由や、人物や場所、物にとても強い感情的な結び付きがあるために留まっている魂もいる。これらを呪縛霊と呼ぶ。
ウィザードが魂を魔法のアイテムに縛りつける場合もある。もしそれが本人の望むものでなければ、その霊魂は狂ってしまう。望んでいた者の場合、正気を保てるか保てないかは、霊魂の強さと付呪師の知識次第である。
他にも、自分達の意思に反して家族の祠を守るために縛りつけられている魂もいる。この苦しい宿命は生きている間、家族にきちんと役目を果たさなかった者に待ち受けている。忠実で立派だった先人の魂は、言うことを聞かない魂を縛り付けるのに手を貸してくれることも多い。
こうした霊魂は通常狂ってしまい、恐ろしい守護者となる。儀式によって彼らは一族の者に害を与えないようになっているが、だからといって彼らの悪戯や気難しい態度を軽減させることはできない。彼らは侵入者にとって非常に危険な存在である。しかし侵入者が霊魂の怒りを見抜き、その霊魂の家に対する怒りをうまくかきたてることができたら、その怒った魂を操ることができてしまう。
オブリビオン
オブリビオンの存在はあらゆるタムリエル文化で認識されているものの、その別世界の性質については様々な説がある。皆が同意しているのはエドラとデイドラが住んでいる場所であり、この世界とオブリビオンは魔法と儀式を通じて交流や行き来ができるということくらいである。
ダンマーはこの世界とオブリビオンの違いについてタムリエルの人間文化ほどは重要視していない。彼らは我々の世界ともう一方の世界を違う性質を持った明確な境界で分割された別々の世界と考えるのではなく、双方を行き来することのできるいくつもの道で繋がった1つの世界として捉えている。この哲学的な視点があるからこそ、エルフは魔法やその実践に高い親和性を持っているのかもしれない。
他の種族から見たダンメリの先人崇拝と霊魂の魔法
アルトメリとボスメリ文化にも先祖を敬う風習があるが、こちらの世界から別の世界に通じる秩序だった幸福な道を大事にするだけである。ウッドエルフとハイエルフは我々の世界に霊魂を引き止めようとすることは残酷かつ自然に反することだと信じているのだ。さらに彼らにとってゴーストフェンスやアッシュピットに先祖の死体の一部を使用することは、奇怪かつ不快な行為と言える。例えば、家族の祠に指節骨を飾っておくことはボズマー(死体を食す種族)にとって冒とく的な行為であり、アルトマー(死者の灰を埋める種族)にとっては野蛮なことなのだ。
タムリエルの人間はダークエルフを教養はあるがオークやアルゴニアンと同じ邪悪な存在と見なしているため、彼らとその文化については無知で、恐れる傾向がある。タムリエルの人間は、ダンマーの先人崇拝と霊魂の魔法は死霊術と関連があると考えている。実際、このダークエルフと死霊術との関連性は、タムリエル中に広まっているダンマーにまつわる黒い噂と少なからず関係しているだろう。しかし、認められた種族以外の儀式で死霊術を行うことはダンマーが最も忌み嫌う行為であるため、これは無知による誤解と言える。
ダークエルフはどんなダークエルフにも、またどんなエルフの死体にも死霊術の魔法を施そうなどとは絶対に思わない。しかし彼らは人間やオークといった種族は動物と大差ないと考えている。そのような種族の死体、または動物や鳥や昆虫の死骸に対する死霊術は禁じていない。
闘争家の兄弟The Brothers of Strife
ニリ・オマヴェル 著
アッシュランドのエルフたちは無敵だと、私の仲間の学者たちに信じこませられただろうか。彼らはレッドマウンテンやその他の勝利、例えばドゥエマーに対する激戦を証拠として挙げる。しかし遠い昔、我らが民はスカイリムの山腹のように広がっていた。その遠い昔、我々はぎりぎりのところまで追いこまれた。
レッドマウンテンの前の時代、我々はチャイマーと呼ばれていた。我々は内海のほとりで何とか食いつなぐエルフの一種族に過ぎなかった。
それからネードがやってきた。今日のノルドは同盟だが、ネードは闇の性質を持つ敵だった。彼らは我々の土地だけを狙い、征服し、略奪した。我々は外交の手を差し伸べたが、撥ねつけられた。移動する集団においてはどんなエルフも格好の的だった。男も女も子供も。
当時の最も偉大な将軍は兄弟だった。バルレスとサダルは敵軍に対する意気盛んな戦士を率いた。最初は敵をアッシュから追い払おうという試みだった。戦争が続くにつれて、彼らの行動は純粋に防御と方向転換に変わった。チャイマーの部隊が血をもって村の民を避難させられるのであれば、その血は流す価値があったとみなされた。
ネードは数年後、我々が今ストンフォールと呼ぶ地のほとんどを支配した。チャイマーの軍隊は内海から追放され、援軍はヴァーデンフェルから切り離された。兄弟は撤退を重ね、最後には選りすぐりの妖術師と部隊からなる小さな集団だけが残った。この集団はその後、古代のデイドラの遺跡に避難した。
遺跡で起きたできごとは歴史の中に埋もれてしまったが、現在、その地を特徴づける大量の像が無言の証人として残っている。チャイマーの将軍たちの死により戦争は終わった。だが、その代償は?
この遺跡でいわゆる闘争家の兄弟が生まれた。私の研究によればヴァーデンフェル出身のチャイマーの魔術師がどうやら獣を支配したらしいが、それまでには兄弟が何百人もの人間とエルフの命を奪っていた。我々の民の最も暗い歴史がその後に続いた。止まらなくなった獣がアッシュを駆け回り血で染まらせたのだ。チャイマーもネードも同じように。
兄弟がどうやってニルンに持ち込まれたかは推測するしかない。デイドラ公が彼らを遺跡へ召喚したのかもしれない。笑うシェオゴラスか、ボエシアからの厳しい生き残りの試験かもしれない。
二匹の野獣は最終的にストンフォールの双子の尖塔に突き立てられ、爪で汚した血の歴史と共に休息についた。我々は彼らのような者が二度とアッシュランドに現れないよう希望し、トリビュナルに祈らなければならない。
名家とその特権The Great Houses and Their Uses
テル・ヴェラノ 著
アッシュランドに住めば厳しい暮らしに慣れるだろう。怒れるクワマー、毒キノコ、部族の襲撃者。どれも相手を殺そうと狙っている。みすみす殺されることのないように。
ここにダークエルフの名家に関する覚書をまとめる。使うもよし、使わぬもよし。判断は任せる。ただドーレス家の奴隷キャラバンにいる自分に気づいたとしても、テル・ヴェラノに忍び寄るのは勘弁してほしい。
インドリル家
内海の南岸近くのどこかにいるなら、インドリル家が采配を振るっていることだろう。アルマレクシアの犬たちはストンフォールとデシャーンの有力な家のほとんどの主導権を握っているし、ドーレス家には金があり、レドラン家には武力がある。だが騙されてはならない。青い帽子がアッシュランドの精神的中心を握っているのだ。
彼らの紋章を見たことがあるだろうか?翼があって、我々の頭上を高く飛べる。彼らは我々をそんな風に見ている。自分たちの下に。自分たちよりも遥か下に。ストンフォールの軍隊は地域で最も強力な軍隊のひとつで、インドリル家の戦争の英雄、タンバルがその頂点にいる。
ヒント:誰よりも先にインドリル家の軍隊に賄賂を渡すべし。彼らは最も顔が利く。聖堂に侵入しようとしないこと。砦のようなものだから。インドリル家の服を着た者はストンフォールとデシャーンに重要な影響力がある。もっと簡単な目標を探せ。
レドラン家
義務。名誉。愚行。一般の民はレドラン家をパクトの強力な利き腕と考えている。野外でパクトの士官の集団を見かけると、彼らは最も印象的な帽子がこの誇り高き一族に属しているように見せかける。
現実は少し違っている。赤い帽子の部隊は確かにパクトの軍隊を動かしてはいるが、下から支えているのであって、上から支配しているのではない。アルゴニアンの偵察部隊とノルドの狂戦士たちもまた多くの部隊の指揮を執っている。この話を隠そうとする理由?高潔なレドラン家はそもそもパクトが組織されたことをいまだに快く思っていないのだ。彼らの軍人らしい大胆さはアルゴニアンの隠密ぶりとノルドの勇気に比較するとやや薄っぺらく見える。
彼らの諺からひとつ引用しよう。「人生は厳しい。判断し、我慢し、熟考せよ。軽率な人生は生きる価値がない」それですべてうまくいっていたのは、外見の異なる民が来るまでのことだった。その後は、嘘をつき気取って歩く庶民の時代となった。
ヒント:レドランの部隊はユーモアのセンスはないが、強欲だ。充分なものを提供すれば、自分の母親でさえ売り飛ばすだろう。レドランは絶対に面と向かって侮辱してはならない。いや、どんな状況であれ侮辱してはならない。彼らは訓練場で噂話をする傾向がある。スリを働く気なら、レドランは格好の標的だ。逃げ道だけは確保しておくように。さもないと思っているより早くトリビュナルに合う羽目になるだろう。
フラール家
フラール家は称賛しないわけにはいかない。パクトの連帯に関して有言実行してみせたのだから。だが古くからの敵や奴隷を急に愛するようになったというわけではない。いや、フラール家の大師範はただ他のほとんどよりも賢いというだけのことだ。手を広げてみせれば、背中に隠した短剣には気づかれにくいというものだ。違うだろうか?
最も有力な地位はインドリル家が権利を持つ一方で、フラール家はデシャーンを狡猾に支配している。配下の最大の都市はナルシスで、モーンホールドにさえかなりの影響力を持っている。フラール家の宿屋と大農園はストンフォール南部のここかしこに見られる。その設計図をよく学ぶといい。建築業者の多くは同じ設計図を繰り返し使っている。フラールの宿屋の隠れ場所を一つ知ったら、すべての宿屋について知ったことになる。
ヒント:フラールの部隊はデシャーンのクワマー・クイーンのようだ。彼らに対抗するにはそれを使え。デシャーンの外に出ると、フラール家の者は自分が灰嵐に立っているような気持ちがするらしい。彼らにどこで会おうとも黄色い帽子がよい目印になる。とことん活用するとよい。
ドーレス家
ドーレス家のことは知っていると思っているのではないだろうか。階級の役割に厳格な、血も涙もない奴隷商人。庶民を見るやいなや売り飛ばす傲慢な上流階級。
かなりのところは当たっている。「ドーレスに関わるな」と頭の中にぐるぐる浮かぶことだろう。ただこういう声も聞こえる。「テル、彼らは使い道もわからないほど多くの金を持っている」それもまた正しい。平均的なドーレスの一員は、最も熟練したスリでさえその気にさせるほどの宝石を見せびらかしている。
友よ、その敏捷な指は抑えておくことだ。ドーレスの正義はオーディネーターや地元の衛兵を悩ませることはない。ドーレスに関われば、消えるのみ。死ぬかどこかの上流階級の大農園の奴隷になる。
ヒント:硬貨はすべて奴隷商人の財布に結びつけられている。ドーレスには関わるな。
テルヴァンニ家
この魔術師の家で良い点はひとつだけだ。パクトに関して文句を言わない。彼らが気にかけているのはテルヴァンニの海岸沿いの聖域だけだ。パクトが作られたとき、彼らは予想外の方法でロープを手に入れ、見つけられる限りの室内履きを吐き出した。彼らはトカゲともノルドとも仲良くはない。別の家の大師範を助けるために道を渡ることもしない。簡単に言えば、彼らは古典的な象牙の塔の魔法使いだ。
それ以外の茶色の帽子に関する話は悪いものばかりだ。彼らはドーレス家と同じくらいの奴隷を動かしている。テルヴァンニ家の貴族であるためには、かなりの力が必要だ。きちんとした身なりの茶色の帽子を間違ったやり方で見てしまったら、彼らは相手の顔を溶かしてしまうだろう。彼らは素晴らしい魔法の宝と、干からびた一斤のパンでも取り替えられないような本に同じ価値を見出している。
ヒント:暴れまわるデイドラは私に魔術師の塔を攻撃させることはできなかったが、どうしてもニルンを出たいのならば、炎と霜に対する防御効果を魔法で付与された鎧を勧める。それからできるだけ長く塔を観察すること。そこに魔法の防御の印が見られれば、たぶん修復のために外に出なければならないだろう。路上で幸運に恵まれることがあるかもしれない。新しい略奪品はじっくり観察するといい。宝の中には防御の力が既に備わっているものがある。
様々な宗派:アルゴニアンVarieties of Faith: The Argonians
帝国大学 ミカエル・カルクソル修道士 著
最も同化した少数を除いて、アルゴニアンはエドラもデイドラも崇拝しない。彼らにはタムリエルの他の地域で「宗教」として知られるものが存在しない。彼らがブラック・マーシュのヒストの木を崇めているのは知られているが、祈祷や聖職者や聖堂といったものはないようだ。
アルゴニアンはシシスも崇拝している。神々が生まれるまえに存在した原始的な影と混沌である。タムリエルの民のほとんどとは異なり、彼らはシシスを「悪」とは捉えない。実際、アルゴニアンで影座のもとに生まれた者は誕生時に連れ去られ、闇の一党に捧げられる。闇の一党は社会に不可欠な一部と考えられている。
様々な宗派:ダークエルフVarieties of Faith: The Dark Elves
帝国大学 ミカエル・カルクソル修道士 著
ダンマーは、エドラを崇拝するアルドメリから異端とみなされるチャイマーの子孫である。アレッシア改革はモロウウィンドで起こらなかったため、神殿はタムリエルの他の地とは類似していない。ダークエルフの元々の宗教は「善きデイドラ」と呼ばれるデイドラ公の崇拝だったが、ほとんどの者が「生ける神」トリビュナルを崇拝するようになった。
トリビュナル
アルマレクシア(モロウウィンドの母):
古代チャイマーの伝説からは、彼らが「大脱出」と呼ぶ一件の間にアーリエルの痕跡のほとんどが消えてしまっている。これはアルトマーとの繋がりが強く、彼らに人気があったことが主因だとされている。しかし、定命の各種族が重要視するアーリエルの要素の大半、すなわち不死性、歴史性、そして系統は、モロウウィンドの神聖なるトリビュナルの中でも最も人気のあるアルマレクシアに都合よく反映されている。
ヴィベク(モロウウィンドの主):
ダンマーの詩吟を詠む戦神であるヴィベクは聖なる地の目に見える管理人で、火山の邪神たち相手に警戒を続け、第二紀572年に1日だけ水中で呼吸する方法を教え、モロウウィンドを冠水させてアカヴィリの侵略者たちを排除した件を初め、ダンマーの民を何度も滅亡から救っている。
ソーサ・シル(モロウウィンドの謎):
ダンマーの神、ソーサ・シルは神聖なるトリビュナルの中でも最も知名度が低く、機械仕掛けの秘密都市から世界を作り変えつつあると言われている。
「善き」デイドラ
ボエシア(策略のデイドラ公):
預言者ヴェロスによって代弁されたボエシアは、ダークエルフの神にして開祖である。ボエシアがもたらした光により、やがて「チャイマー」、もしくは変容せし者と呼ばれる一族はアルドマーとの縁をすべて切り、デイドラの理念に基づいた新しい国家を設立したのだった。哲学、魔術、そして「責任ある」建築など、ダークエルフのあらゆる文化的な「進歩」はボエシア由来のものとされている。ヴェロスが古代に説いた説話はいずれもボエシアがあらゆる種類の敵に対し英雄的な成功を収める展開となっており、チャイマーの先駆者ゆえの苦労を反映したものとなっている。ボエシアはアルマレクシアの守護者としても知られている。
メファーラ(両性をもつ者):
メファーラは糸を紡ぐ者、すなわち蜘蛛の神である。モロウウィンドではチャイマーに敵から逃れ、殺す術を教えた先人とされている。チャイマーは小規模の集団だったため、敵は無数にいた。メファーラはボエシアと共に、やがて名家となる部族のシステムを生み出した。また、モラグ・トングも設立している。ヴィベクの守護神とも呼ばれる。
アズラ(黄昏と暁の女神):
アズラはチャイマーらに、自分たちがアルトマーとは別の存在たりえることを教えた先人である。その教えは時にボエシア由来とされることもある。伝説ではアズラは1人の先祖というよりも、一族共通の開祖として登場することが多い。ソーサ・シルの守護者としても知られている。
不在の神
ロルカーン(不在の神):
この創造者、詐欺師にして試練を与える神は、タムリエルに存在するどの神話にも登場する。彼の最も一般的に知られる名前はアルドメリの「ロルカーン」か破滅の太鼓である。彼は父親であるパドメイが始まりの場所に不安定さをもたらして現状を乱したのと同じように、原初の魂を説得、もしくはけしかけて定命の者の次元を生み出させた。その世界が実現すると、ロルカーンは神の中心地から離れ、伝承によっては不本意ながらという説もあるが、原初の神々の創造地をさまよう。彼と彼の「計画」については文化によって大きく違う。例えばモロウウィンドではサイジックの企て、すなわち定命の者たちが創造主である神々を超越する試みに関与しているとされている。
災厄の四柱神「試練の神」
崇拝ではなく、宥め、和らげる対象の敵対する神
モラグ・バル(企みの神、残虐の王):
モロウウィンドで重要な地位を占めるデイドラ。同地ではどこへ行っても策略のデイドラ公ボエシアの宿敵とされている。ダンマー(およびその先達であるチャイマー)の直面する苦境の主な出どころである。伝説では、モラグ・バルは常に名家の血統を壊そうと試み、ダンマーの純血を台無しにしようと試みている。モラグ・アムールに住んでいたと言われる怪物の種族は、前紀に行われたヴィベクの誘惑の結果であるという。
マラキャス(呪いの神):
ダンマーの神話では、ボエシアがアルドマーの英雄神トリニマクを飲み込み、排出したものがマラキャスとされる。弱いが復讐心に燃えた神である。ダークエルフは彼がオークの神王マラクだと言う。彼はダンマーの身体的な弱さを試す。
シェオゴラス(狂神):
シェオゴラスに対する恐怖は広く普及しており、タムリエルのほとんどの地域に見られる。最近の知見では由来がアルドマーの創世話にあるようで、ロルカーンの神性が失われたときに「誕生」したものとされている。重要な神話の一つではシェオゴラスを「シシスの形をしたこの世の穴」と称している。彼はダンマーの心の弱さを試し、名家を互いに裏切らせようとする。
メエルーンズ・デイゴン(破壊の神):
人気のあるデイドラ。火炎、地震、洪水などの自然の脅威に関連づけられている。一部の文化集団で、デイゴンは単に流血と裏切りの神となっている。モロウウィンドではとりわけ重要な神であり、その地の限りなく不毛に近い地形の象徴とされている。
様々な宗派:ノルドVarieties of Faith: The Nords
帝国大学 ミカエル・カルクソル修道士 著
八大神
カイネ(終末の口づけ):
ノルドの嵐の女神。ショールと死に別れている。戦士たちが好んで信仰する。しばしば人類の母と呼ばれる。嵐の声を意味するスゥームを初期のノルドたちに教えたのはカイネの娘たちだとされている。
マーラ(愛の女神):
ノルドの神話で、マーラはカイネの侍女にしてショールの愛人とされている。多産と農業の女神として、マーラは時にアヌアドのニール、すなわち宇宙の女性的基盤であり、創造を生み出した存在と関連づけられている。
ディベラ(美の女神):
八大神の一員で人気のある女神。シロディールでは様々な分派が存在し、女性を尊ぶもの、芸術家や美学を尊ぶもの、性愛の指導を身上とするものなどがある。
ストゥーン(身代金の神):
ツンとは兄弟であるノルドの神で、ステンダールの原型と言える。ショールの盾の従士であったストゥーンはアルドマーの神々と戦った戦神であり、人間たちに敵を捕虜にとる方法と、そうすることの利点を伝授している。
ジュナール(ルーンの神):
知識と秘密を司るノルドの神にして、ジュリアノスの先駆者。気まぐれで戦いを好むノルドの間では人気がなく、崇拝は消えようとしている。
ショール(死の国の神):
ロルカーンのノルド版であり、世界の創世後に人間たちに味方するものの異国の神(すなわちエルフのものなど)の共謀により倒され、ソブンガルデへと送られてしまう。アトモーラの神話では抑圧側のアルドマーに対しノルドらを何度も何度も勝利へと導く血に飢えた武将として描かれている。転落する以前のショールは主神であった。子供たちに神の異名で呼ばれることがある(オーキー参照)。「死んだ神」と考えられるショールには司祭がおらず、積極的に崇拝されている訳ではないが、誓いに使われることは多い。
オーキー(叩く者):
定命の神。オーキーはモーロッチとアーケイの側面を組み合わせている。ノルドの「借り物の神」で、アルドマーがアトモーラを支配していた時期に信仰が始まったようだ。ノルドは自分たちがかつて、オーキーが現れるまではエルフに匹敵する長寿であったと信じている。野蛮な策略により騙されて取引をし、冬を数える運命に縛られたのだとされている。伝説では一時オーキーの邪悪な魔術により、ノルドの寿命がわずか6年間まで落ち込んでいたことがあったそうだが、ショールが現れ、何らかの方法で呪いを解き、その大部分を近くにいたオークに肩代わりさせたものとされている。
アルドゥイン(世界を喰らう者):
アルドゥインはアカトシュのノルド版というべき存在だが、帝国の八大神との類似点は表層的なものにとどまっている。例えばアルドゥインの二つ名である「世界を喰らう者」は、この世を生み出すために前の世界を破壊した恐ろしく強大な炎の嵐としてアルドゥインを描く神話に由来している。ノルドらはすなわち、時の神を創造主でもあり、終末を伝える者でもあると認識している。アルドゥインはノルドの主神ではなく(主神はいない。ショールの項参照)、その恐ろしく、暗い水源的存在と見なされている。
アルドゥインは以前の世界を破壊し、この世界の作成を可能にしている。この世界も破壊し、次の世界の作成を可能にするだろう。アルドゥインは、以前竜教団に崇拝されていた。しかし、竜教団が非合法化されてから長いため、アルドゥインを公然と崇拝する者はいない。
ハルマ・モラ(ウッドランドの男):
古代アトモーラの魔族、「知識の悪魔」で、ノルドたちを誘惑してアルドマーに変える寸前までいったことがある。イスグラモルの神話の大半はハルマ・モラの企みをかわす話がほとんどとなっている。ボズマーとは異なり、ノルドはデイドラであることを否定していない。
モーロッチ(オークの神、山の屁):
ノルドにはデイドラ公マラキャスと同一視されているモーロッチは、戦いを通して試練を与える。モーロッチはハラルド王の世継ぎたちを長きに渡り苦しめた。第一紀660年に竜の壁の戦いでの敗北後、東方に敗走したという。その憤怒は空を憎しみで満たし、後に「夏中の冬の年」と呼ばれるようになったという。
死せる神
ツン:
今では消滅してしまっている、逆境に対する挑戦を司るノルドの神。ショールを異国の神々から守ろうとして命を落とした。