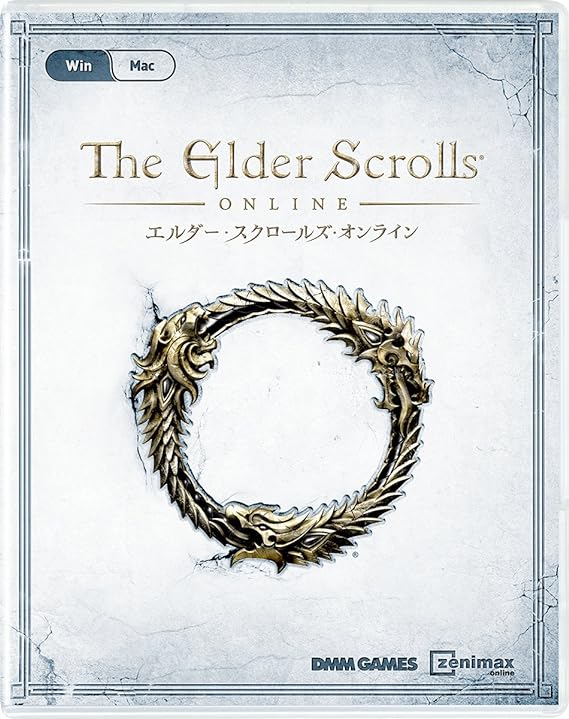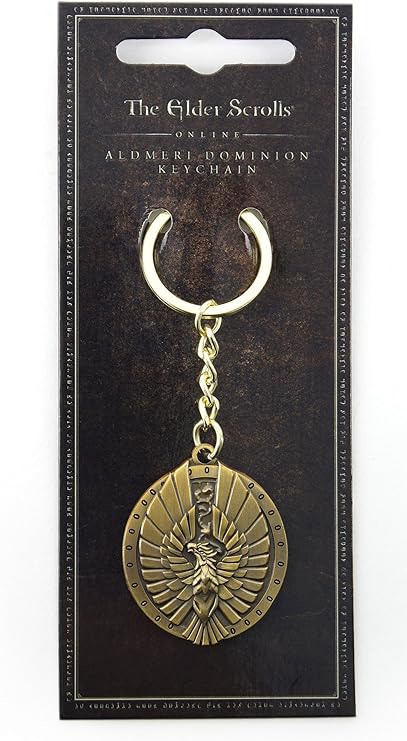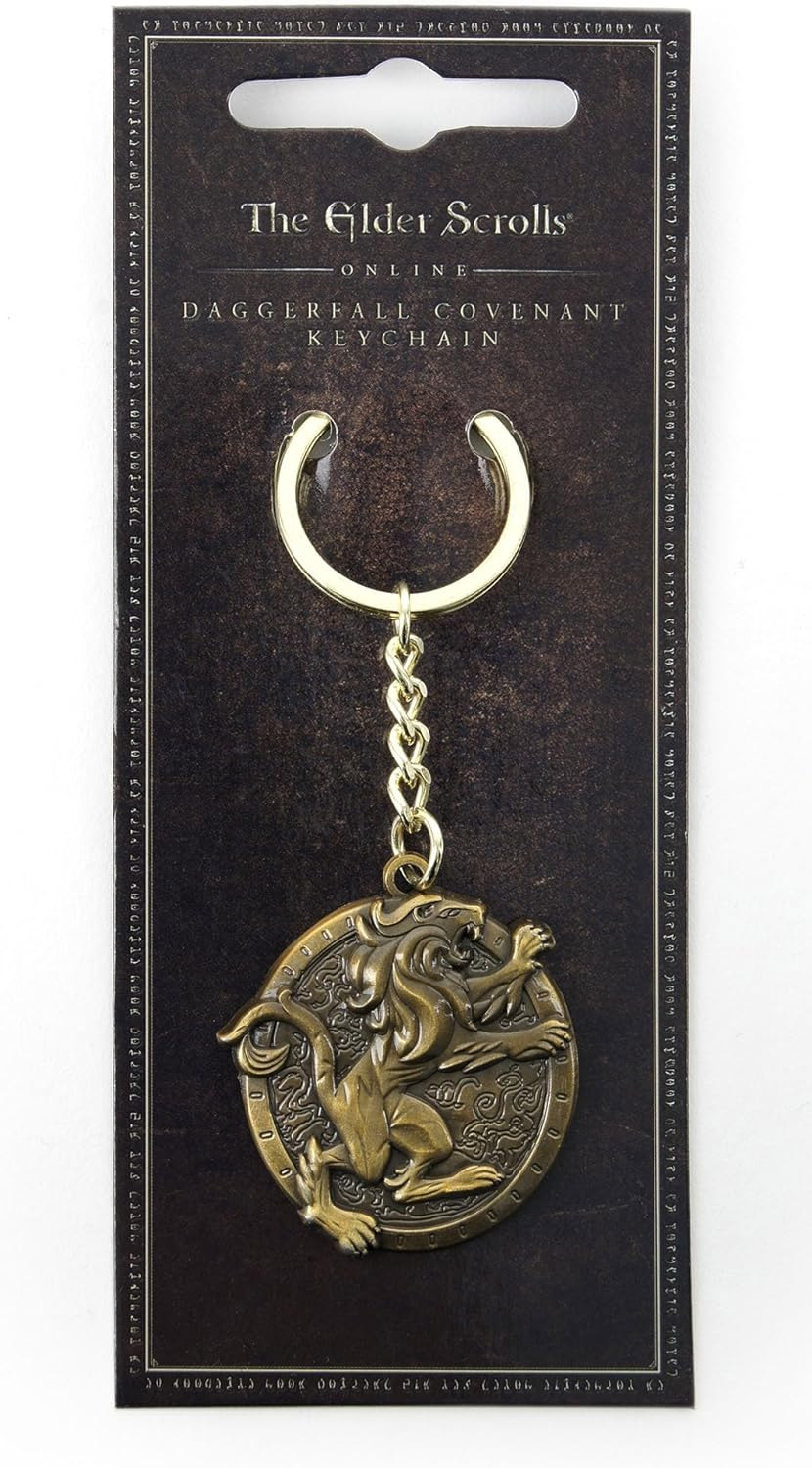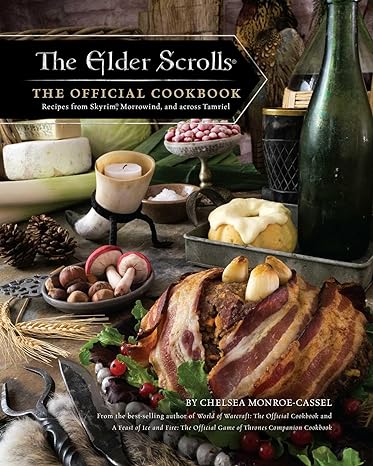アダマントの塔Tower of Adamant
ソリチュード、吟遊詩人の大学、住宅建築家フレーム 著
ハイ・フロスガーを除いて、スカイリムのどこを見てもディレニの塔のようなものはない。自然のものである大きな山とは違って、その塔は建造物である。しかし伝説が真実であるなら、建てたのは人やエルフではなく、エドラ達ということになる。
イリアック湾にあるバルフィエラの島の中心高く、切り立つ荒涼とした場所にそれはあり、時の始まりから建っている。建物を構成する物質が未知で不朽なことからアダマンチンの塔と呼ばれており、それと第零の塔はムンダスに存在するどの建物よりも古い建造物である。
ディレニのハイエルフは第一紀の始まりからバルフィエラを支配している。彼らは塔を取り囲むごく最近の砦しか所有権を主張できないにもかかわらず、その塔に自身の名を付けている(塔の地下墓地を調査する権利者は誰かという話は、答えのない議論である)。
私はアリノールのハイエルフと協議をしなかったが(する人なんているのか?)、ディレニのエルデン古物研究家である高貴なコロイデンは質問に答えてくれた。彼によれば、塔は神々がムンダスの運命を決めるために集まった深遠の暁紀に建てられたようだ。その頂点で、アルドマーの偉大な神アーリエルが詐欺師ロルカーンを殺して彼の心臓に矢を突き刺し、それを世界に向けて撃ち放ったという。心臓はただ笑い声に似た音を出して生き続けた。
その後、エドラはムンダスの事情から手を引き、ディレニが自身の物としているその塔を去っていった。彼らがそこで見つけた秘密とは何だったのか?今日まで何を隠しているのか?その秘密が何であろうと、ディレニはこんな程度の低いノルドの建築家には秘密を明かさなかった。
しかし、その周囲の8地点からディレニの塔の測量を行った結果、そこに秘密があるのは間違いないことが分かった。周知の建材を利用している前提で計算を行うと、あの規模の建造物を建てることは不可能なのである。
ウェイレスト、湾の宝Wayrest, Jewel of the Bay
(カンバーランド版)
長老サシル・ロングリート 著
ウェイレストはタムリエル西部にある最も輝かしい街の1つである。現代の美しさ、そしてその歴史の輝かしさ。ハイロックにある他のどの街よりも価値がある。ブレトンの文化にこれほど寄与した街はない。その街の賢き者達の魂は通りを見ればすぐに分かる。切り妻造りの屋根、雄大な並木道、香り漂う市場。ウェイレストの人々には、ダガーフォールの人々のように歴史に囚われるのではなく、その真価を見抜く力がある。ウェイレストを訪れた人は皆、近代的な街だと感じるのだが、そこには何世紀にもわたる文明こそが織り成せる魔法が存在しているのだ。
歴史家にとって、ウェイレストが創立された日を断言するのは困難なことである。ビョルサエ川がイリアック湾に注ぐ場所には、少なくとも第一紀800年からいくつかの集落が存在していた。ウェイレストの商人と漁師を取り囲むのは非友好的な集団ばかりであった。オークの首都オルシニウムはどんどん北の方向に勢力を伸ばし、西の島々には海賊や襲撃者が群がった。ウェイレストという名に何ら不思議はない。イリアック湾の東の端まで耐え抜いてきた多くの旅人にとって、ビョルサエにある小さな漁村は願ってもいない宿泊所だったのである。
スカイリム占領時代の自慢気な調査にウェイレストのことは一切言及されていない。ダガーフォールの年代記において、第一紀948年にジョイル王がガイデン・シンジに送った手紙には次のような言及がなされている。「オークはウェイレストの人々をずっと苦しめ、今にも大陸の中心に迫る勢いである」
ウェイレストが実際に栄えたのは、第一紀980年のオルシニウム崩壊の後である。勤勉な商人達が貿易同盟を結成する際の助けとなり、それにより湾での海賊の活動も衰退していった。商人として成功を収めたガードナー家は、街の中に城壁を巡らせた宮殿を建てると、そこで銀行やその他の商売を始めるに至った。ガードナー家のファランゲルは、第一紀1100年にウェイレストが王国と名乗ることを認められた際、王に任命された者である。
ウェイレストは一族によって支配されることになったが、商人が持つ偉大な力は相変わらずであった。多くの経済学者がこう主張する。苦境の中でもウェイレストが無限の富を得られるのは、商人と王のこの奇妙な関係に因るものだと。ガードナー王家の跡はカンバーランド王家が継いだが、ウェイレストの王が革命や暗殺によって退位させられることは決してなかった。ウェイレストの商人としての心を忘れる王は1人もいない。商人と王は互いに尊敬し合い、その関係は互いを強くしているのだ。
ウェイレストは荒廃、干ばつ、天災、海賊行為、侵略、そして戦争をその素晴らしい気質と実行力で乗り越えてきた。第一紀2702年、海賊や襲撃者、そしてスラシアの疫病からの保護を理由に、街の人口の大部分は強制的にガードナーの城壁の中へ移された。より愚かな人々には耐えられなかったかもしれないが、ウェイレストの人々は何世代にもわたって生き延び、タムリエルを豊かにしている。
オーク:我々の中の害獣Orcs: The Vermin Among Us
アブソロン・ソリック 著
奴らは穴をねぐらにして寝る。奴らは大量に繁殖し、腐った肉の臭いがする。賢い読者の諸君、これはスキーヴァーのことではない。オークのことだ。差し迫る脅威、無慈悲な大軍。「待て、ソリック。今や彼らとは同盟の仲ではないのか?」と諸君が言っているのが聞こえてくる。エメリック王の指揮を信じたいのならそれもいい。私達をオルシニウムの獣人に縛りつけている、このカバナントを信じたいのであれば。
しかし、実際諸君の信念は間違っている。王への信頼は間違いだ。この不完全な人間どもには残忍で邪悪な狡猾さが備わっているからだ。狩りをする狼の群れのように、オークは今でも草原に潜んでいる。私達の警戒が緩むのをじっと待っているのだ。陛下のような偉大な方々も、この単純な戦略によって誤りへ導かれるかも知れない。
奴らは今や私達の身近な存在だ。名誉ある獅子の守護団に仕えている。裕福な商人の護衛をしながら、傭兵として働いている。聖堂で聖職者の護衛としても働いている。賢い読者の諸君、分からないか?私達がこの獣達に贅沢を与えれば付け上がるだけだということを?あの粗削りの刃を、私達の鎧に突き刺す機会を与えているだけだ!
ブレトンがやるべき仕事を、奴らはその異常な力で奪っている。奴らの臭く厚い皮は、どんなレッドガードも太刀打ちできない防御を与えている。カバナント領域内の様々な都市で、オークが女性を強姦して異常な混血児を発生させているという話も増えている!
読者の諸君、これをどれだけ放っておくつもりか?この不潔な獣にどれだけ屈服するつもりか?私はもううんざりだ!今日、自身の村で志を同じくする者同士団結しよう。そして、この獣どもに対して反乱を起こすのだ!このくずどもに。この…オークどもに。
かつてOnce
〈告げ示す者〉ベレダルモ 著
かつて、我々は偉大であった。
かつて、バトルリーブは戦争の達人であり、サピアルチは賢く教養があった。かつて、我々はエルセリック海からロスガーの山々までハイロックのすべてを支配した。そしてネードは我らの奴隷であり、道具であった。
かつて、ティリゲルの白鳥ことディレニ・シグナスはバルフィエラとその塔を発見し、自身のものだと主張し、後から来た彼女のクラン全員に彼女の名を冠するように命じた。
かつて、錬金術は、アルテウムの初期のサイジックに入会依頼を受けたアスリエル・ディレニが「試料簡略年鑑」を編集するまでほぼ不明瞭であった。
かつて、レイヴン・ディレニの「エルドリッチ結合の法則」の確立以前は、付呪すべてが大変珍しいものであり、その試行のほぼすべてが失敗に終わるようなものであった。
かつて、アレッシア改革の間、リャン・ディレニは帝国に耐え忍んだ。彼のブレトン軍はディレニのエルフから武器の供給と指示を受け、東はマルカルスとエリンヒルまでを支配するに至った。オルシニウムのオークの要塞は何度も略奪を受けたが、そこを最初に略奪したのは我々ディレニである。
かつて、グレナンブリア湿原の戦いで、エイデン・ディレニの無数の軍勢はアレッシアの大軍に圧勝し、彼らをシロディールに追い返した。
かつて、下級デイドラの召喚でさえも恐れられ避けられていた頃に、コルヴス・ディレニは召喚の法則を体系化した。
かつて、ペレグリン・ディレニは自身の真なる意志をイリアック湾の波に変え、ラ・ガーダの船隊をセンチネルへ追い返した。
かつて、ペラディル・ディレニは石の精霊の軍団を召喚することで、リルモシート遺跡に散らばった瓦礫からたった1日でブラックローズ監獄を建設した。
そう、我々はかつて偉大だった。しかし、個人の功績が何であろうと、シグナス以来ディレニは皆、成功に恵まれることはなくなってしまったのだ。
なぜなら我々はゼロストーンの謎を解き明かせず、それによって守られたアージャント・アパーチャーを開くことができないからである。
成人すると、高潔な血筋のディレニは皆、塔の地下宝物庫へ案内され、ゼロストーンを見せられる。我々はそれに触ることができる。我々が決して使うことができない力、そこに流動する神秘的で並外れた力を肌で感じるのだ。そして隣接する金属製の壁にあるアージェント・アパーチャーを見せられる。その扉にはゆっくりと逆回転する13の輪の錠が付いている。決して開くことができない扉だ。
我々ディレニがストーンから力を吸収するか、アパーチャーを開くことができなければ、間違いなく他にできる者はいないだろう。我々は世界の高みへ戻り、壮大なことを成し遂げる。自身の失敗を受け止めずに済むように。
しかし、我々は死の間際に一度、それぞれの知識、功績を集結させ、もう一度地下宝物庫へと続く階段を作る。清算するために。ただ一度だけ。
大半は1日か2日以内に、死んだ状態か体がひどく捻じれた状態で発見される。私の最愛の人であるヘロンのように、中には生き延びる者もいるが、怪我がひどく、混乱状態で自分達に起きたことを理解できない。
私?私はトルマリン尖塔にある自分の部屋に留まり、昼間はヘロンの世話をして、夜は蔵書庫でアイレイドの書物の翻訳をしている。この生活にも十分満足している。
しかし、古代のグリモアやリブラスの魔術師のことを調べていると、長らく行方不明だった一族のアルケインの書物は秘密にしておくべきなのかどうか、時に疑問に思うこともある。
そこでこう考える。何の役にも立たない知識は存在するのか?そしてこう考える。この知識は何の役に立つのだろうか?
そして私は階下への長い道のりに足を踏み出す。
ただ一度だけ。
ハイロックの騎士団The Knightly Orders of High Rock
タネスのレディ・シンナバー 著
封建的な階級制度へのブレトンの愛着は、最も身分の低い小自作農民からウェイレストの上級王に至るまでハイロックのすべての側面に浸透している。ブレトンの騎士社会の興味深い現象においてこれほど明確なものは他にはない。
ここハンマーフェルで、私達レッドガードは剣の握り方を知る男女すべてに平等な市民権を与えている。そう、私達にも支配階級がある。もちろん文明には指示と管理がつきものだ。しかし、この貴族政治と比べると差はほとんどない。
ハイロックでは事情が異なり、皆が自身の階級の高さがどれくらいかを自覚している。それは、ディレニのエルフの大君主達から領土を解放したブレトンの一族にまで遡る。ハイロック文化の歴史の基盤には、エルフの支配を振り払った気高き勇敢な「ブレトンの騎士」の物語が存在している。この騎士達がディレニをバルフィエラの島に追い払った後、貴族の伝統を守るため、そして有事の際にハイロックができるだけ守り手を持てるように騎士社会を築き上げたのである。
少なくとも話ではそうなっている。今日、ハイロックにあるすべての王国と公爵領は独自の騎士社会を築いており、ブレトン解放の全盛期まで遡ると言われるほどの伝統も備えている。ダガーフォールの竜騎士団、アルカイアのフレイム騎士団、エバーモアの聖ペリン騎士団など、例を挙げればきりがない。
これらの騎士団は、その輝きを放つ大剣と鎖かたびらを正当化するために近頃どんな任務をこなしているのか?彼らの旗と豪華な式典の先を見越せば、騎士団はハイロックの社会において主に2つの目的を達成していることが分かる。
まず彼らは、多過ぎる貴族の息子や娘が満足できるほど「高貴な」職業を与えている。貿易によりハイロックが栄えたように、長い時間をかけて商人という職業は、貴族の子供達にとって君主に代わる職業として受け入れられてきた。しかし、実際には男爵の子供すべてに数字と交渉の才能があるわけではない。これらの数多いる後継者候補にとって、地元の騎士社会には常に自分のものにできる地位が存在する。
2つ目に、下層階級の人々に騎士爵を与えることは、社会(や、成り上がって行く君主)に対する顕著な貢献に対して報いる手軽な手段である。彼らはブレトンの社会において重要な階級を得ることになる。騎士のほとんどはこのケースだが、平民が戦闘以外の功績で騎士爵を受ける場合、その騎士団への在籍は名ばかりだ。そうした「卿」は有事に剣と盾を掲げることを期待されていない。しかし、彼らの功績が貿易において極めて重要なものであれば、新たな「商人騎士」は、騎士団の財政維持に対して、重要かつ持続的な貢献を期待される。
外交や貿易の仕事でウェイレストやエバーモアに来て、輸送会社の頭としてドリック卿が紹介されたり、宿泊所を束ねる経営者としてリザベッテ卿が呼ばれたりしても驚かないでほしい。目の前にいるのは、ハイロックの伝説的なブレトンの騎士の1人に過ぎない。
ブレトン:雑種か上位種か?The Bretons: Mongrels or Paragons?
エリンヒルのファラスタス 著
人間とエルフが交配できることは、神話紀の中期に最初の人間がタムリエルの海岸に辿り着いた頃から知られている。しかし、エルフと人間の交配が広まったのは大陸のごく限られた北西地域のみであり、そこでブレトンという人種が発生したのである。タムリエルの他の地域における人間とアルドマーの子孫との紛争の歴史を考えれば、このような交配がいかにして、またどうしてハイロックで発生したのであろうか?
その答えは、かつてタムリエルの北西部を支配していたエルフのクラン・ディレニの(エルフにとっては)独特な文化の中にある。出会った人間をすべて容赦なく奴隷にするシロディールのアイレイドとは対照的に、ディレニは征服した地元のネードを、単に貴族社会のカーストに組み込んだだけだった。上流階級のエルフは人間を臣下として支配する封建制度を敷き、その権利や特権には望んだ人間を誰でも相手にできる「性交の特典」が含まれた。魅力的なネードとの性交はちょっとした娯楽として考えられ、ディレニの貴族達は、極めて魅力的な人間の臣下をどれだけ抱えられるかを競ったのである。
このような性的関係から必然的に生まれた半エルフの子供は亜エルフと考えられ、ディレニの親の家族に引き取られることはなかったが、ネードの臣下の中でも特権を与えられることがよくあった。これにより、長い時間を経て、「ブレトン」(エルノフェクスの「ベラトゥ」もしくは「ハーフ」から)という名を与えられた混血の人間のカーストがはっきりと形成されるようになった。ブレトンは人間とだけ結婚することを許され、長い時間をかけて彼らのエルフの血はより薄くなり、ネードの外見が濃く出るようになった。
第一紀の頃は彼らも偉大な力を備えていたが、その頃でもクラン・ディレニのエルフは決して数が多くなかった。支配地域の拡大とともに、管理と支配は少しずつブレトンのカーストへと移っていった。第一紀482年に侵攻してきたアレッシアの大軍を打ち負かした後、クラン・ディレニは散り散りになり力を失ってしまった。エルフがハイロックの中央、最終的にはバルフィエラの島に逃れる一方、ブレトンは易々と彼らの跡を継いだ。ディレニが敷いた封建制度をそのまま受け継ぎ、彼らの地位に自分達の貴族を就かせたのである。
ディレニの伝統と自身を区別することを強要されてきたブレトンの貴族は、エルフやエルフに関するすべてを自分達から遠ざけることで新たな即位を正当化した。皮肉にも、古い貴族の家ほどエルフの血が強く残っていたのは言うまでもないが。ディレニは以前の臣下にますます中傷されるようになり、島のクランはさらに隔離されて孤立していった。しかし、彼らは今でも偉大な魔術師として知られており、第一紀907年に起きたレッドガードの侵攻を追い払うほどの力を持っていたことは間違いない。
ブレトンは自身を再定義し続けた。ディレニの支配に抵抗した気高い歴史の神話を創作し、タムリエルの沿岸地方で貿易を行う商人階級を育て続けた。女帝ヘストラとその軍団が第一紀1029年にバンコライ峠に到着した頃には、人間の帝国に加わり、八大神に帰依する態勢が整っていたほどである。レマンの支配下において、ハイロックは第二帝国の中ではおそらく最も安定して栄えた場所であっただろう。
そして、題目の(わざと挑発的にした)質問に戻ってくる。ブレトンは雑種か上位種か?その答えはもちろん両方である(もしブレトンを雑種と呼べば、少しばかりの鋼鉄が飛んできそうだが)。ブレトンという情熱的な人種を見れば、人間とエルフ両方の強さ、そして欠点も同様に体現していることが分かるだろう。
わが使命、わが誓いOur Calling, Our Pledge
ドゥラク修道院長 著
この一団に入ってきた新人はほとんどが私に「霊魂の守人になることの意味とは?」と尋ねてくる。この戸惑いは当然のことだと思う。アズラは道を示して下さるが、それがいつも我々が考えている方法で示されるとは限らない。彼女は私に話しかけてきたが、それも人生で2度である。それも夜に辛うじて聞き取れる穏やかな囁きのみであった。
ドリームシャードとはアズラの贈り物だ。我々が毎晩飲む夢見ずのの薬も同様である。アズラが予見するのは、悪夢の女王ヴァルミーナがこの地にいつ狂気の災いをもたらすのかということだ。我々がそれを止めない限り、数え切れない罪のない命が失われるだろう。
夢見ずの薬を飲めば我々はヴァルミーナの狂気から守られる。そうすれば他の人々を、夢で気を狂わされた魂や犠牲者を助けられるかも知れない。災いの時、我々は立ち向かう。これはアズラ、そして誓いによって示された…我が使命なのだ。
石喰いの聖なる儀式Sacred Rites of the Stonechewers
ネリック・ステロン 著
私は長期間にわたって石喰いゴブリンの部族を観察している。彼らの日々の活動を記録してきて、その習慣や日課に随分詳しくなってきた。ゆっくり時間をかけて、少しずつ彼らのキャンプの境界近くまで近付いた。時々姿を見せて相手に自分の接近を慣れさせるようにも仕向けた。ある時、木の後ろで用を足そうとしていた1人の戦士が私の監視所を見つけ、不平を言いつつ不格好でありながらも使いやすそうな短剣を取り出した時は、私の仕事もここまでかと思った。幸運なことに、部族の呪術師が私の近くへやって来ると、戦士に声を荒げて、彼の剣を振り払ったのだ。呪術師は私を指差して、自分の頭の側でゆっくりと手を回転させた。私が思うに、それはゴブリンの意思表現の1つで、格上の知性を認識したことを意味するのだろう。いわゆるこのような原始生物にそんな学識の一面があるとは誰が考えただろうか?
それ以降、敵対行動は一切なく、彼らの女子供とそれなりの距離を保っていれば、ゴブリン達は私の存在を許容してくれたのだ。時折、戦士が吠えてくることはあったが、私はただ自分の頭の横で手を回転させて「知性的存在」の意思表示を行った。すると、戦士は肩をすくめて自分の仕事に戻っていくのだ。
ゴブリンの宗教的な習慣について知られていることはほとんどないため、私は部族の呪術師を詳細に調べることにした。彼の仕事場のシンボルは骨の棒、おそらく大腿骨だが、その先端に小さな頭蓋骨を取り付けた物であった。その頭蓋骨もおそらくは幼児の物であろう。この頭蓋骨は様々な羽、とげ、そして動物の爪で飾られている。中は木の実の外皮のような物で満たされているため、振るとガラガラと大きな音を立てる。呪術師は、聖なる儀式の招集をかける際や女の食事の給仕が遅い際に、この神聖なシンボルを振り鳴らすのだ。
特に重要な儀式では、呪術師はそのシンボルを胸に当て、それから頭に当てた後、それを空に向けて「モロク!」と叫ぶ。最初私はこれに戸惑った。彼らがヅラゾグや子供を折檻する際に使う言葉「モールク」や糞便に対応する言葉「ムロコー」に類似していたからだ。しかし、少しずつその差異を学び、呪術師が叫ぶ「モロク!」にはゴブリンの神を呼び起こす意味があると、ある日私は気付いたのである。
その言葉がとても印象的だ。「モロク」は「モーロッチ」とそれほど違いがない。まさかゴブリンの神とオークの神は同一のものなのか?
このほどの発見ならウェイレストの大学で終身在職権を得られる!そのためにはこの発見を第三者が確認することが必要だ。だがどうやって?
夢から夢へTo Dream Beyond Dreams
百の預言の予兆 著
メネヴィア、緑多き愛しきメネヴィア、そこにある若いブレトンが住んでいた。彼は歴史的遺産を受け継いでおり、身の周りの世話は人を雇っていたため自分は何もする必要がなかった。間仕切り窓のところに座り、ひし形窓の外で田舎の風景が日の光とともに変化する様子をじっと眺めた。その日彼は、辺りが暗くなり就寝の時間になるまでずっとうとうとと過ごしていた。その後床に入った彼は夢を見たのである。
彼はどんな夢を見たのか?それは自身の所有地の夢だった。しかし日中のものよりも色が濃く、実物以上、さらに汚れのない清らかなものであった。夢のメネヴィアは現実のメネヴィアよりも現実味があり、起きている時よりも寝ている時の方が生を実感できたのだ。毎日彼は間仕切りのところで、夢を越える夢を見る方法を模索した。夢見のメネヴィア、レヴァリメネヴィアで永遠に暮らす方法を。
彼は「レヴァリメネヴィア」と言う。それは祈りの言葉であった。「レヴァリメネヴィア、レヴァリメネヴィア」。彼は何千回もこの祈りの言葉を口にした。すると、その言葉はみるみる「ヴァーメネヴィア、ヴァーメネヴィア」に変化していき、さらに回数を重ねて短くなっていった。そして最後には「ヴァルミーナ」となり、彼は何度もそれを繰り返す。「ヴァルミーナ、ヴァルミーナ」
そこで夢の形でヴァルミーナが現れ、彼のことを天上の夢見人、最初のナイトコーラーと呼ぶと、百の預言の予兆と名付けたのである。目覚めた後も、まだ夢の中にいるようで夢うつつで言葉を発し、彼は他の夢見人を彼のもとへ、レヴァリメネヴィアへ呼ぶのであった。
あなたもすぐに彼のようになれる。ナイトコーラーはそれを夢見てきた。ある夜夢を見たら、そこでその名前を言うのだ。そうすれば彼女が現れる。
霊魂の守人の創設Founding of the Spirit Wardens
信者のサークルの第三の番人、ジャニス・ムリック 著
第1章:ドゥラクの若年時代
ドゥラク修道院長は我々の崇高な指導者であるが、彼がその肩書に満足することはない。巨匠ウグバクがかつて言ったように、その理由はオルシニウムの廃墟での彼の幼少時代に関係しているようだ。オークにしては小柄なドゥラクが、オークにとっては馴染みの薄い神秘主義の道へ進んだのは、兄弟のいじめのせいだというのは誰もが考え得ることである。
ウグバクが言うように、ドゥラクの物語はオルシニウムから始まる。そこでの彼の運命は辛く寂しいものであった。ドゥラクの生活が一変したのは、デイドラ公アズラが囁きかけてきた夜からである。アズラは、ドゥラクが偉大な任務を完遂すると語ったのだ。彼はストームヘヴンへ行き、そこで彼女の名のもとに崇拝者の一団を築き上げる。この一団「霊魂の守人」が混沌の時、ストームヘヴンの人々が悪夢の狂気に苦しめられる時に向けて備えるであろうと。
ドゥラクはこの囁きを兄弟に教えるつもりはなかった。魔法の知識と身体能力が乏しいせいで、すでに嘲笑されていたからだ。彼は杖以外何も持たずにオルシニウムの家を出発し、ストームヘヴンへの長い旅を始めたのであった。
ドゥラクはストームヘヴンへ辿り着くが、「霊魂の守人」の一団をどのようにして築いて、どこで暮らせばいいのか見当もつかなかった。途端に彼は絶望した。ある夜、彼が嘆きの巨人の下で宿りをしていると、再び囁きが聞こえてきた。穏やかなアズラの声が語った内容はムーンリット・モーの西にある丘に隠された道についてであった。その行き着く先で、ドゥラクは草に覆われて見捨てられた古代の大修道院を見つけた。ここが霊魂の守人の本拠地なのだと彼は悟ったのだ。そして、そこがアズラへ通ずる我らが聖堂となったのである。
ドゥラクの指導の下、我々はヴァルミーナによる夢の災いに備えている。我々はストームヘヴンを悪夢から守るために築かれた。命尽きるまでそれを遂行しよう。